No, mother. Let me be and let me live.
(ℓ279、強調筆者。スティーヴンが母親をmotherと呼ぶこの挿話唯一の箇所。他はすべてshe。)
※邦語の引用は柳瀬尚紀訳(河出書房新社)を使用し、ページ数を「p.○○」で表記する。あわせて、原文の箇所を指定するため、/の後にガブラー版の行数を「ℓ○○」で併記する。(ちなみに、ここで使用しているのはPenguin Modern Classicsの1986年版である。)
1. 偽神父マリガン
第1挿話をクリアするために、最後から始めよう。
簒奪者め。(Usurper.)
後に「テレマコス」と題されることになる、本挿話の最後の文だ。この「usurper」という語は、英国史ではヘンリー4世(在位1399-1413)やジェームズ2世(在位1685-1688)等、盤石でない正統性で王位に就いた王を反対派が呼ぶ時、そして19世紀以降の英文学ではしばしばナポレオン・ボナパルトを指す時に用いられた。では、ここの「簒奪者」は誰を・何を指しているのだろうか? 今回はこの問いに答えられればクリア! 頑張りましょう。
第1挿話の舞台となるマーテロ塔は、usurperことボナパルトがヨーロッパを席巻していたナポレオン戦争時代、大英帝国が植民地防衛のために各地沿岸に建造した塔の総称である。本作に登場するのは、ダブリン南東約11キロメートルのサンディコーヴ海岸に建つマーテロ塔だ(現在はジェイムズ・ジョイス博物館になっているとのこと)。スティーヴンと友人のマリガンは、なぜかこの塔を間借りして生活している。この6月16日木曜日朝、マリガンの友人でイングランド人のヘインズも共に宿泊している。
ヘインズが訊く。
―この塔は賃借りしてるのかい?
―十二ポンド、バック・マリガンが言った。
―陸軍大臣に、スティーヴンが振り向いて付け足す。
三人は足をとめ、ヘインズが塔をしげしげ眺め回してから言った。
―冬はそうとうに冷え込むだろうね。海岸砲塔(マーテロウ)って言うんだっけ?
―ビリー・ピットがあちこちに造らせたんだ、バック・マリガンが言った。フランス軍が海にありの頃さ。でもここのが中心なる臍(オムパロス)だ。
p.35/ ℓ541-、原文は( )内ルビ
マリガンが愛称で呼ぶウィリアム・ピット(「小ピット」、首相在職1804-06)が建造した大英帝国の要塞を、年12ポンド(つまり月あたり1ポンドの計算)支払っているとはいえ大学生くずれ(?)だけで占領しているのだから、スティーヴンやマリガンもusurperである。
しかし、マリガンが「簒奪」しているのは塔だけではない。『ユリシーズ』において最初に名指されセリフが与えられるのは共にマリガンなのだが、彼に注目しながら、冒頭に戻って読んでいくとしよう。時刻は朝の8時。
ふんぞり返って、ふくらかなバック・マリガンが階段のてっぺんへ現れた。捧げ持つ石鹸の泡立つ丸い器にのせて、手鏡と剃刀が十文字にねかせてある(lay crossed)。黄色のガウンが、紐のほどけたまま、穏やかな朝風に吹かれて後ろでふんわり持ち上がった。器を高く掲げて誦える。
―われは神の祭壇に昇らん(イントロイボー・アド・アルタレ・ディー)。(中略)
ぐるっと見渡し、塔と周囲の地と目覚めかけた丘陵を、三度、重々しく祝福する。それから、スティーヴン・デッダラスの現れたのが目に入ると、そっちへ向って一礼し、喉をがらがらいわせて首をゆすりながら、虚空にすばやく十字(crosses)を切った。
p.11/ ℓ1-、強調筆者、原文は( )内ルビ
反復されるcrossは、マリガンが朝の用意にかこつけてキリスト教の儀式を「簒奪」しようとしていることを示している。カトリックの神父ならミサでガウンを「紐のほどけたまま(ungirdled)」着ることなどもっての他だから、言わば彼は、黒ミサを執り行っていると言ってよい。とすれば説教も法外なものになる。
—なんとなれば、よろしいかな、皆様方、これぞ真のキリメト(christine)、肉体にして霊魂にして鮮血にして槍満創痍。ゆるやかな音楽をお願いしますぞ。目をつむって、旦那方。ちょいとお待ちを。この白血球どもが少々ざわついておりましてな。静粛に、皆さん。
p.12/ ℓ21-
Christでなく女性形のchristineを讃える黒ミサ(柳瀬訳は「女」の漢字を響かせて「キリメト」としている?)。そこでは、”body and soul and blood and wounds(傷)”とあるべき説教の最後が、音が近いだけの”ouns(女性器)”となってしまっている。白血球に言及があるのは、パンが肉体になりワインが血になるというイエスの奇跡を疑似科学で皮肉っている。出ましたtransformation!(→本連載「第0回」第2節を参照) transformationの作用がいきなりピックアップされるのは『ユリシーズ』全体を告知している…、でもそれもさしずめ、髭を剃る時の泡を見て思いついた出まかせではなかろうか。
この黒ミサで「召喚」されるように(「—上って来い、キンチ!」)登場するのが主人公1ことスティーヴン。スティーヴンとマリガン、アイルランド人2人が揃うと、話題は自然とアイルランドの文学運動に向かう。もちろん1904年当時、アイルランドは大英帝国の一領域でしかなく、「国」としては存在していなかった。
―ちょいと鼻拭いをお借りして剃刀を拭くよ。
スティーヴンが逆らいもせずにいると、汚いしわくちゃのハンカチをひっぱり出し、これ見よがしに端をつまみあげる。バック・マリガンは剃刀の刃を器用に拭った。それからハンカチをしげしげ眺め、口を開く。
―歌人の鼻拭い!われらがアイルランドの詩人諸君にふさわしき新しき芸術の色だ。青っ洟緑(snotgreen)。味もするんじゃなかろうか、え?
今度は胸壁にのっかると、ダブリン湾を見渡した。淡褐色の金髪がほのかになびく。
—ふふーん! と、静かにうなずく。海ってのはアルジーの称した通りだ。大いなる慈母か。
p.14/ ℓ69-
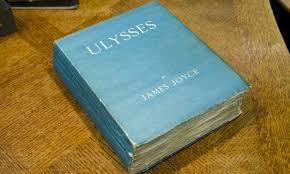
自分の鼻水の色をアイルランド芸術の興隆と重ねるマリガンのあっけらかんさ(現在もアイルランドのナショナル・カラーは緑、そして『ユリシーズ』初版は青緑色の表紙で出版された)。しかし支配者の語である英語を使用するアイルランドの文学者達は、英文学を「簒奪」して自らの伝統を立ち上げていく他ない。望むと、望まないとにかかわらず。マリガンがまたも愛称で呼ぶ「アルジー」とは英国詩人Algernon Charles Swinburne、「大いなる慈母(the great sweet mother)」1 もスウィンバーンの詩からの引用である。「usurper」は、アイルランドの若き文学者達でもある。次の引用に出てくるオスカー・ワイルド(1900年没)も、英文学を「簒奪」して戦ったアイルランド文学者だ。「簒奪」元は、ウィリアム・シェイクスピア『テンペスト』。
—鏡に己の顔の見えぬキャリバンの激怒、と、言った。ワイルドが生きているうちにきみと会ってたらなあ!
上体を起して指差しながら、スティーヴンは苦々しく言った。
―それ、アイルランド芸術の象徴だよ。僕(しもべ)のひび割れた鏡だ。
p.17/ ℓ143-、原文( )内はルビ
「鏡に己の顔の見えぬキャリバンの激怒」(マリガンのセリフ)は『ドリアン・グレイの肖像』(1891)序文からの
―ぼくは二人の主人に仕える僕(しもべ)でね、スティーヴンは言った。イギリス人とイタリア人の。
p.40/ℓ638、原文( )内はルビ
大英帝国とローマカトリック教会という二人の主人。新しいアイルランド文学を立ち上げようとするスティーヴンたちは、「僕(しもべ)」であることを自覚しながら「主」の言葉を簒奪し、ずらし、異なる価値を立ち上げていく。メタ的に言えば、第14挿話で英文学史を・第17挿話で教理問答をパロディーの対象とした『ユリシーズ』全編が、その価値創出の試みだった。
2. ゲール語研究者ヘインズ
さて、「偽神父」マリガンは朝食のベーコンエッグを切り分けながら「父と子と精霊」(p.26)の三位一体に触れる。「三」で溢れる第1挿話には、まず主要人物が三人いる。この時代、すなわち19世紀末から20世紀初頭にかけてのアイルランド文芸復興運動はゲール語の復興運動(後に初代大統領となるダグラス・ハイドがゲール語連名を設立したのが1893年)を伴ったが、この矛盾を生きているのが「第三の男」ヘインズの存在である。ヘインズはオックスフォード大学からダブリンに来たイングランド人(「オックス公」the oxy chapとマリガンに呼ばれている。Oxford+Saxonのこと)で、ゲール語を研究している。
支配者側の文化に加担している帝国の学生が、被支配者のオリジンをなす周縁言語を保存しようとする、どこまでもねじくれた構造。ヘインズの熱意は、アイルランドの民衆代表と言うべき牛乳売りの老婆には、残念ながら届かない。ヘインズの研究対象には現代を生きている庶民は入っておらず、マリガンがからかうように、古代にばかり関心を割いているからだ。
—そういう庶民をだな、と、大真面目な口ぶりで、きみの本に書いてくれなくちゃ、ヘインズ。五行の本文に十頁の注釈をつける。ダドラムの土地っ子と魚神様たちのことをさ。大風の年に魔女らの手にて印刷。
p.27/ ℓ365-
以上を踏まえて、老婆がマーテロ塔に牛乳を売りに来る場面の会話を読んでみよう。
―この人の言うこと分る? スティーヴンは老女に尋ねた。
—フランス語をしゃべっていなさるんで? 老女はヘインズに言った。
ヘインズはまたしても老婆相手に長々と偉そうに一席ぶつ。
—アイルランド語だ、バック・マリガンが言った。お婆ちゃん、ゲール語分る?
—やっぱしアイルランド語でごぜえますか、老女は言った。そんなふうに聞えますもんな。西のお人でごぜえますかい?
—ぼくはイギリス人だ、ヘインズが答えた。
—こいつはイギリス人、バック・マリガンが言った。だからアイルランドではアイルランド語をしゃべれってという考えでね。
―そりゃそうですわな、老女は言った。そんでわたしゃ恥かしいんですよ。自分がしゃべれねえもんでさ。
p.30/ ℓ424-
アイルランドの象徴のような老婆が、日頃英語を使っているためアイルランド土着のゲール語を解さない(しかも聴いてもフランス語と間違えた)という皮肉。ゲール語というアイルランドの伝統は、ここではヘインズすなわちイングランドによって「簒奪」されてしまっている。老婆が最も習熟しぺらぺらと話すのは、「七の二は一シリングと二ペンスで」(p.30/ℓ443)のように牛乳の勘定計算であり、「近代や資本主義に侵されていない、純粋なアイルランド」の保存・復興なんて、ともすれば、被支配者側の事情をわきまえない支配者側の身勝手な幻想にすぎなくなるのだ。
3. マザコン者スティーヴン
そんなマーテロ塔での朝の情景に、主人公であるはずのスティーヴンはあまり関わっていない。もちろん同じ場には存在しているのだが、マリガンのミサ/英文学簒奪とヘインズのゲール語簒奪が本質的であるようには、ストーリーの流れに属していない。にもかかわらず、読者が最も読むことになるのはスティーヴンの独白だ。そう、スティーヴン自身が、何よりもテクストと読者を「簒奪」している「簒奪者」なのだ。
彼はマリガンのミサにも、続く文学談義にも、ヘインズと老婆との会話にも、内心では同じ一つのモチーフしか思い浮かべていない。最近亡くなった母のことである。本挿話のタイトル「テレマコス」は、『オデュッセイア』ではオデュッセウスの息子の名であり、スティーヴンが「子」であり続けていることを強調している。スティーヴンはマリガンからグレーのズボンを譲ろうかと言われ、「グレーならはけないね」(p.16/ ℓ120)と言っており、この日も喪に服して黒を着用しているほどなのだ。これから『ユリシーズ』というゲームをプレイしていくにあたって、主人公1の設定は当然重要なので、プレイヤーの皆さんは必ず覚えておいてください。
―叔母がね、きみがおふくろさんを殺したと思ってる、と、切り出した。だからきみとかかわりをもたせまいとするんだ。
―誰かさんが殺したんだろ、スティーヴンはくぐもり声で言った。
—どへっ、せめて膝をつくくらいはできたろ、キンチ、死にかけてるおふくろさんの願いじゃないか、バック・マリガンが言った。おれもきみと同じくらい冷感人種さ。それにしたっておふくろさんが今わの際に、どうか膝をついて祈ってほしいと頼んでるんだぜ。それを聞き入れないってんだから、きみはどこか拗けたところがある……。
p.14-15/ ℓ88-
「誰かさんが殺した」の「誰かさん」=「神」とすれば、神と祈りのテーマでマリガンの黒ミサとスティーヴンのトラウマとはつながってくる。スティーヴンは、母の死が近づくのを認められないあまり、神への祈りを拒否したのだろうか?
スティーヴンは「音もなく、夢の中で近づいてくる息を引き取った母(Silently, in a dream she had to come to him after her death)」(p.15/ℓ102)という現実でない情景をオブセッションとして思い浮かべる(このオブセッションは「夢の中、音もなく近づいてくる母(In a dream, silently, she had come to him)」p.23/ℓ270と少し先でもほぼ同じ語彙で反復されている)。そして、マリガンがあっけらかんと提示した新しいアイルランド文学のシンボルとしての「青っ洟緑」は、スティーヴンの心内では、母の死の床にあった器の中の「緑のどろっとした胆汁」(p.15/ℓ109。強調筆者)のイメージに吸収されてしまう。英国詩人スウィンバーンを引用して「大いなる慈母」と呼びかけた海が、「湾と水平線の輪が鈍い緑の液体のかたまりを抱える」(p.15/ℓ107)ように見え、同じ器の中の胆汁に重ねられていく。(この点に関しては、webあかし上の論考、小林広直「海を眺めるスティーヴン・デダラスーー『ユリシーズ』のはじまり」が詳しい。必読です。)
マリガンと軽快に話しているように見えても、スティーヴンはマリガンが自分を家族に紹介した「おふくろが畜生みたいに死んでしまったやつ」(p.19/ℓ198)という発言を許すことが出来ていない。原語はbeastly deadであり、ニヒリストであるマリガンにとっては死は物質的現象であり、スティーヴン母の死体が解剖されるのを見ても”It’s a beastly thing and nothing else.”(ℓ206)と感じるのみである。しかし、スティーヴンにとってはそうではない。何気なくマリガンが「こけ犬わんちゃん(poor dogsbody)」(p.16/ℓ112)と呼ぶようには、優しい母がdogsbody=犬の死体になることこそが死だとは達観できないでいる。英語圏では馴染み深い語呂合わせが示すように、GODを逆さまにするとdogになるのだが。
ヘインズとの間でも、母へのオブセッションは発動している。先ほど述べたように、ヘインズが老婆にゲール語で話している間、スティーヴンは老婆から連想して内面で母のことを考えている(そのため、「ヘインズはゲール語で話した」という記述が飛ばされて何かを「聞いていた」ことしかわからず、初読の読者を混乱させる結果になった)。
スティーヴンは侮蔑の無言で聞いていた。(中略)おれをこの女は軽んずる。告解を聴いてやり、女の不浄の腰を除く全身に、男の肉体から神に似せずに造られた肉体に、蛇の餌食に、終油を塗ってやろうという声にも。
p.29/ ℓ418-
このような母へのオブセッション、海岸の塔に立つ悩める若者、と来れば、英文学史からまず挙がる作品は1つ、シェイクスピア『ハムレット』(1601?)である。そんな連想を先回りして裏書きするように、イングランド人ヘインズが「この塔とこのへんの崖がなんとなくエルシノアを思わせるんだ」(p.36/ℓ567)と言い始める。エルシノアは、『ハムレット』の舞台となる、デンマークに建つとされる架空の城の名前。
亡くなった父の亡霊から暗示を受け、母へのオブセッションから叔父クローディアスを「簒奪者usurper」として排斥しようとするハムレット。対照的にスティーヴンは、亡くなった母へのオブセッションに、自己が「簒奪」されていると言える。彼と過ごす長い長い24時間のうちに、このオブセッションは何度も顔を出す。彼は国立図書館で聴衆を前に『ハムレット』論を述べることにもなるのだが、それはまた別の話。
しかし、自国の秩序を回復しようとする悩めるハムレットと異なり、一平民にすぎぬスティーヴンは身軽だ。「その鍵よこしてよ、キンチ」(p.43/ℓ721)と水浴中のマリガンに言われてマーテロ塔の鍵を渡し、「今夜は寝に帰るもんか」(p.44/ℓ739)と決意する。鍵を取ったマリガンのことを「簒奪者め。」と、思わないでもないけれど。それでも今日は16日、「月一の浸り日」(p.32/ℓ473)こと給料日(兼、泳げるほど飲む日)だ。マリガンとは「シップ」という酒場で昼に落ち合う約束もした(だが、結局は行かないことにしたようだ。それもまた別の話)。なにせまだ、一日は始まったばかりだし。
ということで、第1挿話の最後を飾る「簒奪者」という語には、ここまで述べた全ての意味が透かし模様のように入っていることがわかっていただけただろうか? それならば、第1挿話はクリアできたと言える。すなわち、①フランスとヨーロッパを簒奪したナポレオンのように、マーテロ塔を簒奪したスティーヴンたち、②キリスト教儀式を簒奪したマリガン、③英文学を簒奪したアイルランドの文学者、④アイルランドとアイルランド文化を簒奪した大英帝国、⑤スティーヴンの意識を簒奪した母に対するオブセッション、⑥テクストと読者の意識を簒奪したスティーヴン、⑦エルシノアと母を簒奪したクローディアス、⑧マーテロ塔の鍵を簒奪したマリガン。そして『オデュッセイア』との対応から、⑨オデュッセウスの不在中にペネロペイアを簒奪しようとした求婚者たち、という意味の層も加わるようだ(ギフォードの注に言及あり)。ジョイスが『ユリシーズ』で狙った意味の重層性とはこういうことであり、本挿話で視点人物に起用されているスティーヴンの象徴的思考が何事にも意味を見い出すせいで、それに拍車がかかっている。まあ1語だけでもこんな調子ですが、付き合っていってあげましょう。
最後の1文に注意を向けて始めた本稿を、冒頭の1文に注意を向けることで締めるとしよう。冒頭は英語だとこんな感じ。
Stately, plump Buck Mulligan came from the stairhead,~
ゆっくり『ユリシーズ』を読む読者は、ここに仕掛けられたジョイスのたくらみに気づくことができる。まず、“Stately”などというあまり見慣れない副詞から大長編が幕を開けているのはあまりにも変で、ジョイスの特徴となっている。私は「動詞はヘミングウェイ、形容詞はフィッツジェラルド、副詞はジョイス、代名詞はフォークナー、現在分詞はウルフ」と勝手に思っている者だが(なんじゃそら)、ここで”Stately”を使ってくるのは世界広しと言えどジョイスだけなのは間違いない。Statelyのstateには姿勢の意味ももちろんあるが、「国」という意味がまず第一に浮かぶだろう。ジョイスは『ユリシーズ』がアイルランドという「国」になれていない国の問題を語っていくことを、実は冒頭から宣言していたのではないか。
しかし、それだけではない。『ユリシーズ』は小説としての醍醐味を備えた大長編であると同時に、多種多様な語を含んだ散文詩としても読むことができる。よく見ると、”Stately”は後ろの”stairhead(階段の上)”と頭韻を踏んでいる!
Stately, plump Buck Mulligan came from the stairhead,~
さらによく見ていくと、『ユリシーズ』の主要登場人物の人名、特に主人公2ことブルームにまつわる人物名は、この文に含まれる音から生まれてきていることがわかる。まず1番目の語Statelyは、この挿話に初登場するStephenと韻を踏んでいる。その後に続く語を1文字目だけ取るとp、b、mである(これらの文字は、音に直すと全て唇を合わせないと発音できない、音韻論的にも語の弁別に重要な音素となっている)。Bは男性キャラクター、Mは女性キャラクターの頭文字に使われている。
Stately, plump Buck Mulligan came from the stairhead,~
B→ Bloom(主人公2)、Boylan(モリーの不倫相手)、Bannon(ミリーの恋人?)
M→ Molly(ブルームの妻)、Milly(ブルームの娘)、Martha(ブルームの文通相手)
有害男性が並ぶ(笑)「B」のカテゴリーから、ブルームはモリーからの呼び名によって柔和化され、半身抜け出ている。ここが、ブルームのキャラクターとしての愛らしさと重なっているのではないか。
P→ Poldy(「無害男性」化されたBloom)
(以上の着想を、私は「2022年の『ユリシーズ』」読書会初回(2019年)の場で第4挿話を読んだ時に得て、意見として発表したことがある。あれから6年になるが、改めてこの読書会に関わっていた全ての皆様に感謝したい。)
そして、冒頭1文に限った話ではない。『ユリシーズ』はストーリーにも、象徴性にも、文や語や音にも着目して、いくらでもゆっくり読むことができる。ここから第18挿話まで共に、ゆっくりしずかに読んでいきましょう。私も読んで考えたことを書けてすっきりしますし。
うーさっぱり。
【ジョイスの計画表・第1挿話】
表題=テレマコス 場面=塔 時刻=午前8時 学芸=神学 象徴=相続人
(脚注)
- スウィンバーンの詩「時の勝利」(1866)よりの引用。”I will go back to the great sweet mother, / Mother and lover of men, the sea.”↩
- 「十九世紀におけるリアリズムにたいする嫌悪は、キャリバンが鏡に映った自分の顔を見る時の怒りと異なるところがない。」(福田恆存訳、新潮文庫版『ドリアン・グレイの肖像』p.9) ↩





