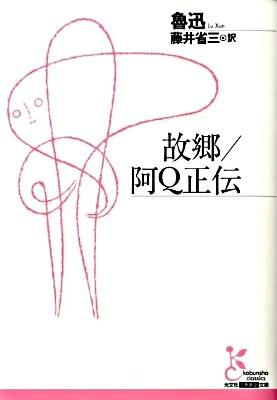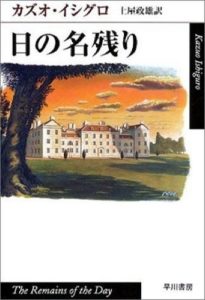概要
『故郷』は、1921年5月に『新青年』に発表された魯迅の短編小説。のちに魯迅の最初の短編小説集である『吶喊』(1923年)に収録された。日本では国語の教科書に採用されて有名になった。
20年ぶりに故郷を訪れた主人公が、社会の価値観に染まった旧友を発見し、どのように生きるべきか考えを巡らす物語。
国語の教科書に掲載されている小説はほかに、ワイルド「幸福な王子」、ヘルマン・ヘッセ「少年の日の思い出」、中島敦「山月記」、宮沢賢治「注文の多い料理店」、辻村深月『ツナグ』などがある。
また「海外小説のおすすめ有名文学」で、海外文学のおすすめを紹介している。
登場人物
僕:主人公。20年ぶりに故郷に帰ってくる。
閏土(ルントウ):「僕」の家の雇い人の息子。少年時代には「僕」と仲良しであった。
楊(ヤン)おばさん:「僕」が子供の頃、筋向かいで豆腐屋をしていたおばさん。
水生(シュイション):閏土の息子。
宏児(ホンアル):「僕」の甥。8歳。
あらすじ・ネタバレ・内容
主人公の僕は、20年ぶりに故郷に帰ってくる。しかし故郷は全く生気がない。かつての故郷ははるかに美しかった。僕はしかたなく故郷とはこんなものだと自分に言い聞かせる。
僕が故郷に帰ってきたのは、昔住んでいた生家を引き払うためだ。そして母たちとともに、今自分が住んでいる異郷の地へと引っ越さなければならない。故郷には別れを告げるために帰ってきたのである。
生家に住んでいた親戚らは皆すでに引っ越しを終えており、残っているのは母と8歳になる甥の宏児だけであった。家に着くと母が出迎えてくれた。お茶を飲みながら話をしていると、閏土の話になった。閏土がじきに僕に会いにやってくるという。その話を聞いて、僕には幼少の頃の記憶が鮮やかに蘇ってきた。
閏土は雇い人の息子だったのだが、僕の家が大祭の当番だった年に、あまりに忙しいので手伝いとしてやってきたのである。閏土の噂は前々から聞いており、歳も近かった僕は会うのを楽しみにしていた。閏土は自分には知らないたくさんのことを知っていた。猹という動物がいること、それがスイカを齧ってしまうこと、海には五色の貝殻があること・・・、閏土の心は自分が知らない不思議なことで満ちていた。
閏土と再会できると知って喜んでいると、外では数人の女の声がする。そのなかに向かいで豆腐屋をやっていた楊おばさんがいた。見ると足がかなり痩せていて僕はびっくりしたのだが、この楊おばさんは、執拗に僕を金持ちだとしてぶつぶつ文句言いながら、母の手袋をお金も払わず取っていってしまった。
その後は近所の一族や親戚も訪ねてきたが、ある日の午後に閏土が来た。僕は一目で閏土だと分かったが、僕の記憶の中の閏土とは違っていた。皺が大分深くなっていた。僕は再会の嬉しさのあまり一言こういった。「わあ!閏兄ちゃんーーいらっしゃい」。閏土は喜びと寂しさが入り混じった表情をしていたが、やがて態度が恭しくなりはっきりとこう言った。「旦那様・・・・・」。僕は閏土と悲しく分厚い壁で隔てられていることに気づき、言葉が出なかった。閏土が水生という五男坊を連れてきていたので、宏児と遊びに行かせた。彼に暮らしぶりを聞いてみると、かなり苦しいということが分かった。僕と母は、不用品はなるべく閏土にあげるということにした。翌日朝には閏土は水生を連れて帰っていった。
僕らの出発の日、閏土は来たが水生を連れてこなかった。船に乗ってお別れすると、宏児がいつ帰ってくるのかと聞く。水生に家に遊びに来てと言われたのである。宏児はそのことに夢中になっている。閏土には灰もあげたのが、その灰の中に食器類を隠していたのを楊おばさんが発見して得意になっている。
故郷はどんどん離れていくが、僕は少しも名残惜しいとは思わなかった。というよりひどく落ち込んでいた。僕は考えた。宏児や水生の世代は僕らが味わったことのない新しい人生をいきるべきだと。しかし僕の希望は遥か遠い。僕は考えた。希望とは本来道のようなのもので、歩く人が多くなると、そこに道ができるのだと。
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
解説・批評文
いくつかの邦訳:晦渋な魯迅の文体
中国文学の代表作の一つとして、魯迅の『故郷』は多くの日本人読者に親しまれてきた。それは本作が国語の教科書に掲載されていたからだ。ただし、魯迅の『故郷』と言っても、翻訳によって印象がかなり異なるので注意が必要である。
一般的に、国語の教科書に掲載されているのは、竹内好の訳である。竹内の翻訳は、歯切れの良い文体を特徴にしており、適度に原文にない句点を挿入することで、読みやすい文章に仕上がっている。多くが親しんできたのもこちらの訳である。
それに対して、光文社古典新訳文庫版での藤井訳は、なるべく直訳になるよう心がけている。したがって、句読点の位置をできる限り忠実に訳しているのだが、原作は一文一文がとても長く読点でそれらを繋げているので、藤井訳も非常に読みにくい。知人の国語教師に藤井が自分の訳を見せたところ「これでは教科書には採用されませんね」(訳者あとがき)と言われてしまった。それぐらい訳によって印象が変わってくるのである。
他の訳では、これまでは「私」としていた一人称を「僕」と訳してみたり、より口語的に訳してみたり、さまざまな工夫がなされている。異なる翻訳を読むことで、新たな『故郷』に出会えるかもしれない。
テーマは階級と貧富の問題
本書のテーマを理解するうえでまず注目すべきは、登場する4種類の人物たちである。各々は所属する社会や集団を代表していると考えて良い。つまり、中国社会を大まかに分ける4種類の集団を、エリート集団に属する「僕」という視点から眺め、閉塞感が漂うこの国に新たな希望を見出すというのが、物語の大まかな流れである。
一種類目が「僕」。「僕」はその頃の中国知識人の原像であり、また魯迅自身でもある。1916年の袁世凱による帝政復活とその頓挫から中国はますます混乱の時代へと突入していた。1920年代には国民党と共産党、アナーキストが三つ巴で革命の主導権を争っていた。そんな中で魯迅ら知識人は態度を迫られ、貧しく疲弊しながらも戦っていた。
二種類目が「楊おばさん」。彼らは貧しく、もはや魯迅たちの家財を金を払わずに奪っていく盗人みたいになっている。
三種類目が「閏土」。むかしはあんなに感情豊かだったのに、今では飢饉や税金からくる貧しさのあまりだめになっている。もはやただただ生きることしか頭にない。
四種類目が「水生と宏児」。彼らは昔の僕と閏土との関係に似ている。その間には上下関係など存在しておらず、遊ぶことに夢中になっている。
これら登場人物の間には、階級と貧富の問題が横たわっている。「僕」と楊おばさんの間には貧富の差が、「僕」と閏土の間には階級の違いがある。楊おばさんや閏土は低い階級であるが故に、盗みを働き感情が乏しくなっている。低い階級に人間性が順応してしまったのだ。ところが「僕」も知識人として疲弊しているという意味で、楊おばさんや閏土とさして変わらない。彼/彼女らの精神は身分や環境によって、擦り切れてしまったのである。
苦しみと貧しさは人をダメにする
魯迅は前者三種類の生き方を否定する。そして「水生と宏児」の世代に、別の生き方を期待するのである。
だがそのいっぽうで彼らが仲間同士でありたいがために、僕のように苦しみのあまりのたうちまわって生きることを望まないし、彼らが閏土のように苦しみのあまり無感覚になって生きることも望まず、そして彼らがほかの人のように苦しみのあまり身勝手に生きることも望まない。彼らは新しい人生を生きるべきだ、僕らが味わったことのない人生を。
『故郷/阿Q正伝』光文社古典新訳文庫、2009年、68頁。
しかしなぜ「僕」も「閏土」も「ほかの人(楊おばさんたち)」も苦しんでいるのだろうか。その苦しみの原因は何だろうか。根底にあるのは「貧しさ」である。僕も貧しく、閏土も貧しく、楊おばさんも貧しい。閏土の畑は不作であり、楊おばさんは貧しさという苦しみを理由にして身勝手に物を取っていってしまう。そこに税金や役人や盗賊など、人間社会の腐敗が重くのしかかる。これらから被る苦しみが皆をダメにしてしまったのだ。
重要なのは、「僕」がこれを個人の問題だと全く考えてないことだ。例えば、物を盗む楊おばさんに対して、「僕」は彼女の道徳性の欠如を非難しない。閏土がダメになった理由を彼の心の弱さのせいにはしない。自分を含めた大人たちが貧しい人間になってしまったのは、個人の問題に還元できないほどに根深い社会構造の問題と苦しみが存在するからだ。だが「僕」は、この問題を社会の腐敗に求めることもしない。個人が悪いわけではない、だからと言って、社会を糾弾しても解決できない。そのことを魯迅は重々承知している。この深い現状認識をまず理解すべきであろう。そして魯迅は、この苦しみの取り除く道を、つまりわずかに光る未来への希望を模索することになる。
\Kindle Unlimitedで読める!30日間無料!/
→Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
考察・感想文
若者がただいるだけでは、希望ではない
この「苦しみ」の外部に「水生と宏児」がいる。「僕」は彼らが僕と閏土の関係にようにならないことを希望する。だがここでも「僕」の洞察は鋭い。水生と宏児が変わらないことを望みそこに希望を託すだけでは、実現できないことを直感しているのだ。
事実、「僕」と閏土は変わってしまった。貧しさの中で生きる長い年月は、人間を慣習に順応させてしまう。身分や貧富を考えることなく純粋に遊んでいた「僕」と閏土ですら、その強制力に抗うことはできない。いや、その強制力を意識することすらできない。貧しさという外的要因は道徳心の欠如として現れ、気づいた時にはすでに主従の関係を内面化してしまう。
だから「僕」は、希望について考えたとき「突然恐ろしく」なる。というのも自分の希望、つまり新しい人生を生きて欲しいという希望が途方もない希望に思えたからだ。今は確かに「水生と宏児」の間に、貧富も身分の差も存在しない。だが、それを喜ぶだけでは「僕」と閏土のような関係に変化してしまう。では、どうすれば「水生と宏児」は、いつまでも変わらずにいられるのだろうか。一体希望はどこにあるのだろうか。
伝えたいことは、希望が道であるということ
最後に「僕」はもう一度、「希望」について考え直す。ここが本書のハイライトであり、作者の伝えたいことである。
ぼくは考えたーー希望とは本来あるとも言えないし、ないとも言えない。これはちょうど地上の道のようなもの、実は地上に本来道はないが、歩く人が多くなると、道ができるのだ。
同書、68−69頁。
どういうことだろうか。まず重要なのは、希望とは期待された未来や物事ではないということである。そうだとしたら、希望は道ではなく道の先にあるものになってしまう。それでは希望が道であるということの含蓄は何なのだろうか。
まず「僕」が希望について考え、そしてその希望について考えが恐ろしくなり、再度考えた結果、道としての希望という考え方が生まれたという思考の流れが重要だ。「僕」が考えているのは確かに途方もないことである。達成できる見通しはないし、どうやったら良いのかもわからない。そんな実効性のないものを希望として立てても良いのだろうか。良いのである。なぜならそのように考え行動すること、そのこと自体が希望であるからだ。
ここに一つの逆転した真理がある。遠くに希望という名の目的があるから、人間はそこに向かうのではない。人間は歩くからその先に希望が現れるのだ。だから遡及的に現れた希望は「本来あるとも言えないし、ないとも言えない」。確かに希望は元々存在しなかった。しかし歩いているうちに、人間は希望の存在を見つけてしまう。歩くことが希望を作るのだ。
この「道」の比喩には、能動性が含意されている。既に存在する「希望」に期待させられるという受動性ではなく、道を造るという能動性がここにある。この能動性は、すぐさま責任を呼び起こす。若者たちに希望を見るのではない。階級や貧富の差のない世界に向けて行動することの大人の責任。「僕」が考え行動したら、今度は僕たちがその足跡に続いてくれるかもしれない。その足跡が重なれば、いずれ地は固まり道になるだろう。そしたら既に希望が生まれている。そう、希望とは皆が考え行動することなのだ。
→小説家、シナリオライターを目指すならこちら|アミューズメントメディア総合学院
関連作品
Audible・Kindle Unlimitedでの配信状況
| Kindle Unlimited | Audible | |
|---|---|---|
| 配信状況 | ○ | ○ |
| 無料期間 | 30日間 | 30日間 |
| 月額料金 | 980円 | 1,500円 |
文学作品を読む方法は紙の本だけではない。邪魔になったり重かったりする紙の本とは違い、電子書籍や朗読のサービスは、いつでもどこでも持っていけるため、近年多くの人に人気を博している。現在日本では、電子書籍や朗読が読み・聴き放題になるサブスクリプションサービスが多数存在している。ここでは、その中でも最も利用されているAudibleとKindle Unlimitedを紹介する。
AudibleはKindleと同じくAmazonが運営する書籍の聴き放題サービス。プロの声優や俳優の朗読で、多くの文学作品を聴くことができる。意外なサービスだと思われるが、聴き心地が良く多くの人が愛用している。無料お試しはこちら。
関連記事:Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
関連記事:【2023年最新版】Audible(オーディブル)のおすすめ本!ジャンル別に作品紹介
Kindle UnlimitedはAmazonが運営する電子書籍の読み放題サービス。様々なジャンルの電子書籍が200万冊以上も読めるため、多くの人に愛用されている。30日間の無料期間があるので、試し読みしたい本を無料で読むことができる。無料お試しはこちら。
関連記事:Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
関連記事:【2023年最新版】Kindle Unlimitedのおすすめ本!ジャンル別に作品紹介
参考文献
魯迅『故郷/阿Q正伝』藤井省三訳、光文社古典新訳文庫、2009年。