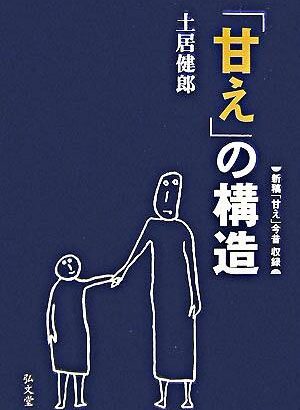日本と「甘え」について
つらつらと読んで思ったことを書き連ねたい。
「甘え」の構造とは何か
甘えという語が日本語に特有のものでありながら、本来人間一般に共通な心理的現象を現わしているという事実は、日本人にとってこの心理が非常に身近なものであるということを示すとともに、日本の社会構造もまたこのような心理を許容するようにできあがっていることを示している。いいかえれば甘えは日本人の精神構造を理解するための鍵概念となるばかりではなく、日本の社会構造を理解するための鍵概念とものなるということができる。
『「甘え」の構造(新装版)』33頁。
甘え・・・・。一般には「AがBに甘えている」などのように対人関係で使用される場合が多いが、日本の場合この「甘え」が社会全体を覆っている。一億総甘え社会。甘えすぎたよ、全く本当に。
「甘え」という状態はごく普通に考えて良い。赤ちゃんが母親に甘えている。これは親へと密着しようとする行為だ。ここから精神分析的に、原初的な分離からの回復が求められているんだ、と土居は解釈するわけであるが、それはともかくとして大事なのは、甘えの世界では、甘える人と甘えられる(甘えさせる)人の二人一組が必要だということである。
どれが甘えだというのか。例えば義理人情である。人情は「甘えを肯定すること」であり、義理は「甘えによって結ばれた人間関係の維持を称揚すること」であるが、こういった日本的感情は全て「甘え」を土台として生じると解釈できるのである。
他に社会構造にも、その「甘え」を見ることができる。例えば天皇制である。これは〈甘えのイデオロギー〉だという。
依存度からすれば天皇はまさに赤ん坊と同じ状態にありながら、身分からすれば日本最高であるということは、日本において幼児的依存が尊重されていることを示す証拠とはいえないであろうか。
同書、78頁
戦時中、権力だけは絶対的であったが絶対王政だったわけではない。やることなすことは実質的に天皇が決めることはできず、内閣その他諸々で決められていた。そんなわけで「輔弼」というものが存在したのである。戦後天皇は日本国家の象徴になったが、まさに象徴でしかないということが「甘え」を体現している。
甘えているのが身分の高い人である、というのが面白い。ここで甘えているのは天皇なのだ。国民は天皇を甘えさせている。もちろんこのような分離、絶対的権力と幼児的依存というところに、丸山眞男がいうところの「無責任の体系」が隠されているのは言うまでもない。
しかし天皇だけではない。日本では上に立つもの全てが甘えている(というか日本文化がそれを許容している)。そこで展開されるのが斬新な敬語論である。敬語も「甘え」に由来している。こういった敬語論はあまり見たことがないが、かなりピンとくる。
天皇に限らず日本の社会ではすべて上に立つ者は、周囲からいわば盛り立てられなければならないという事実が存するが、これも同じような原則を暗示するものである。いいかえれば、幼児的依存を純粋に体現できる者こそ日本の社会で上に立つ資格があることになる。
78頁。
天皇はイメージしづらいが、それを上司だとか先輩とかすれば誰でもイメージが沸く。彼ら彼女らはなぜか敬語を使ってもらいながら甘えたがる。おだてられ盛り立てられることで彼らはある種の独特なアイデンティティを形成する。問題は、甘えている彼らはそれほどの能力をおだてられなければいけないほどの能力を持ち合わせていない場合である。いやこれに関しては周りを見回してもらいたい。自らの上に立つもので、敬ってもよいほどの能力を兼ね備えた、つまり尊敬できる人間はどの程度存在しているか。ここで中井久夫の有名な言葉を思い出しておこう。「日本では有名な人はたいしたことがない。無名の人が偉いのだ」。すべてに当てはまるわけではないが、もしそうだとしたら有名な人が大したことがないのは何故なのか。おわかりだろう。甘えているからである。
上のものが甘えていると同時に下のものは甘えさせている。それによってますます「おだてれば木に登る」かのような人間が出来上がる。もっと通俗的な言い方でいうとかっこ悪い大人というものが出来上がる。内弁慶、下っ端にはいろいろ言うが上には頭が上がらない。というのもさらに上の立場の人も甘えているからである。
もうちょっと色々考察してみよう。「あいさつ」という儀礼を一つ例にとってみよう。ある運動部に属していると、なぜかあいさつの声の大きさや方法を強要される。基本形は「ちわっ」である。「こんにちは」の省略形なのだと思うが、定かではない。とりあえず、いわゆる顧問という存在に、この全力の「ちわっ」を行うのが一般的なしきたりである。というのもこの全力の「ちわっ」ではなく、なめくさった「こんにちは〜」を行うとまずい展開になる可能性があるからである。
彼ら(上の者)の言い分としては「挨拶は人間関係の基本だ」ということだろう。だから全力でやらなければやらないし、(表面的には)すごく重要なことだという主張なのだろう。しかしこれを横で見ていると、ここに「甘えの構造」が潜んでいるのを見逃さないわけにはいかない。
「あいさつが重要」という考えは極々自然だろう。しかし、いわゆる生徒が全力の「ちわっ」をやっているのにもかかわらず、そこで繰り出される上の者の返答はなんなのか。「おうぅ」。これは挨拶ではない。とりあえず二度言ってみる。これはあいさつではない。加えて思い浮かぶ感想は、なぜあなたは全力の「ちわっ」をしないのかということである。一応重要なこととして下の者に教えているわけだから。それではなぜしないのか。甘えきっているからである。
こういった構造を生み出す最大の要因は敬語である。だから、敬語は「甘えの構造」なわけである。とにかく敬語を使われる人間は基本的に能力値がだんだんと下がってくる。というのも周りの者が全部やってくれるからである。もちろん上には上がいるわけだから、そこに対しては幾分対応する能力を残しておかなければならないが。
また敬語を使われまくっているというか、敬語を使われたいと甘えている人や甘えさせたい人は、ほとんど対等関係のコミュニケーションができなくなる。彼らは距離の縮め方を知らない。というのも敬語の世界しか知らないからである。敬語的な関係の中では距離はなかなか縮まることはない。日本では大人になるにつれて(特に男性は)友達のいない率が他の国と比べて圧倒的に上がっていくというデータを見たことがあるが、同年代の人としか敬語外のコミュニケーションが取れないのでそりゃそうだという感じである。そもそも敬語的コミュニケーションしかしてこなかった人は、友達になれる人の母数が少ないのである。
もちろん甘えていない上司もいる。『相棒』の杉下右京さんなんかはそんな感じのイメージとなるだろう。一匹狼的存在であるが身分は高くない。ただし甘えの世界ではそういうポジションの人がカッコよく見え、受けが良い。他にも『ハケンの品格』の大前春子や『ドクターX』の大門未知子もそうであった。他の国でも(例えばアメリカでも)このような作品は好んで制作されるのであろうか(「シャカイ系とは何か」に詳しい解説がある)。
「甘え」と母性・父性について
甘えというの母性的だ、という主張も本書ではなされている。そして現代は父の不在の時代だと。母性優位というのは『母性のディストピア』(宇野常寛)が思い出されるし、父の不在というのもジジェクを彷彿とさせる。土居も精神分析科なので、やはり背景にはフロイトの理論がある。彼らよりも前に土居がすでにこういった主張をしていたのは先見の明があったということだろう。
今日の世代間の問題はもともとは古い世代の自信欠乏に発していると考えられる節がある。このことは家庭のレベルでいえば、父親の影が薄いことに、したがってほとんど父親不在といってよい状態が今日ふつうになっていることに現れている。
239頁。
父の不在になると価値観が揺らぐ。そういうわけなので「各自思い思いの行動をしても誰もあえて咎めようとしない。あらゆるタブーは取り払われ、社会全体は何かお祭り気分のように浮き浮きした気分にある」(同書、248−249頁)とある。しかしその「お祭り気分」が2020年代まで続いた感じは全くしない。
本書の初版が1971年だから、現代というのは〈政治の時代〉における政治闘争などが念頭にあるだろう。その闘争が終わり、社会運動をしていた人たちは家族に帰っていく。そしてそれを吉本隆明が肯定するという流れがあるわけだ。だとするとそこで一旦お祭り騒ぎが終わり、カオスは閉じて祭りの後として何らかの秩序化(制度化)がはじまったと考えるのが自然だろう。例えばそれは「母性のディストピア 」的秩序かもしれないし、「甘え」的秩序かもしれない。
甘えの発生について
これは土居が考察していないことだが少し考えてみよう。仮に同年代同士が複数人集まったとしてそのうちの一人に何か重大な事柄を任せるとしよう。そのとき私たちはどういう行動をとるか。敬語を使って、「できればお願いしたい」とか言うのではないだろうか。つまり「甘える」わけである。日本語の敬語には尊敬語と謙譲語があるというのがこういうところからも理解できる。「甘え」というのは、自分が何らかの意味において下になる行為だ。そうやって「甘えの構造」の中で上下の身分が生じてくる。先程の天皇の例にもあったように「甘える」方が下になるとは限らない。上になるのは「甘え」ているかどうかというより、「もてはやされている」かどうかが鍵となってくる。天皇も上司も重要な役割を任された同僚も皆、わっしょいされることで上の立場となる。天皇クラスになると自分が「甘えており」、周りが「甘やかしている」ということになるが、もとをたどれば、周りの者が最初「甘えて」おり、その中で骨抜きにされた天皇が最終的には「甘えている」という構造になるのではないか。
上に立つ者の能力がないというのは日本社会ではよくいわれることだが、もとを辿ればそういった人たちが甘えているからなのではなく、下の者たちが「甘えた」結果、いつのまにか骨抜きにされてしまったということも可能性としてはありうるだろう。
無限責任との関係について
ところでこのような被害者意識は、二重に屈折した甘えの心理を秘めていると見ることができる。というのはもともと被害的心理が先にのべたように甘えの不満に由来していることに加えて、この場合は、それが意図的に連帯故に選び取られているからである。被害的心理自体は苦痛なものであるが、連帯故に主体的に選び取られた被害者意識は苦痛を感じさせることが少ない。かくしてかかる被害者意識の持ち主は、被害的心理にも拘らずあるいはむしろそれ故に他に危害を及ぼすことが平気になり、サディスチックな自己満足すら覚えるほどになる。
同書、255頁。
面白い指摘である。先に説明しておくと、ここではフロイトの理論が念頭に置かれている。
それではなぜ被害者意識に耐えられなくなるのだろうか。それは日本が恥を道徳の基礎においているからだろう。たとえば親族が罪を犯したときに、自分も一緒に恥を感じるが、罪を感じることはないだろう。自分が何かを犯したわけではないからである。しかし道徳の基礎が恥なので、罪を犯していなくても自分も悪いのである。被害者を見て見ぬ振りすることは恥である。それゆえ見て見ぬ振りすることはできない。ではどうするのか、自分も心理的に被害者になるのである。そうすることによって、見て見ぬ振りをしたい自分という罪悪感を止揚し、なんとか精神を保つ。
これは丸山眞男の「無限責任の体系」とつながりそうである。丸山はそのようには主張していないので筆者の解釈になってしまうが、「無責任の体系」にはその基礎に「無限責任」があると考えられる。つまり、無責任になってしまうのは、何か起こると無限責任で無限に責任が広がっていくことになり、責任の所在がいまいち掴めなくなるのだ。責任というのは確かに恣意的で、ある問題が起こったときに誰に責任があるのかと問われたときに、考えようによっては誰しもが責任者になってしまう。そんなこんなで無責任と無限責任というのは共犯関係にあるのではないかと考えたりしている。
そしてこの無限責任についてであるが、これがなぜ発生するのかというと、それはつまり「無限責任の体系」なのは根本的に道徳の基礎に恥をおいているからである。それゆえ、無限に責任が広がってしまうのである。そしてこの恥というは「甘え」につながっている。というのも恥というのは「じぶんが属している人たちの信頼を裏切る」ということであり、そこにもう一度戻りたいというのが甘えであるからである。
甘えと一体化について
甘えと一体化
甘えについて色々見てきたが、自分が問いたいのは、そもそも甘えが肯定されるのかということである。つまり「甘え」の構造になってしまうのはなぜかということである。実のところここに日本社会をより深く迫っていく上での鍵があるはずである。
土居が〈甘えの心理的原型〉について述べている箇所を引用しよう。彼はその心理的原型について、木村敏の批判に応答するなかで次のように述べている。
「甘え」を定義した際、それは本来「乳児が母親に密着することを求めること」であり、もっと一般的には、「人間存在に本来つきものの分離の事実を否定し、分離の痛みを止揚しようとすることである」とのべたのである。
同書、274頁。
つまり、甘えの構造を支えているのは、土居の考えによれば「分離の痛みを止揚しよう」とする運動であり、言い換えれば一体化の肯定であるということである。「甘え」は一体化、一体感、くっつくことの肯定ということに根差している。さてどうであろうか。
日本社会の全体主義的な傾向を考えれば確かにという気もする。
もっと深く考えてみることもできる。この一体化するというのはどういうことだろうか。全体主義というのはもちろん日本だけで生じたものではないからである。むしろ一体化みたいなものはヨーロッパ哲学にも見られるもので、それとどう違うのかが根本的に重要なこととなってくるであろう。つまり全体と言ったときのその全体とは一体何なのか、という問いである。
「みじめさ」というのは一つの鍵になる。土居はラフカディオ・ハーンの「停車場で」という随筆の中で述べているエピソードを紹介しているが、これが面白い。この話は強盗をして一旦捕まった後、巡査を殺して脱走した男の話なのであるが、この犯人が再び捕まって護送されるときに殺された巡査の未亡人とその子供と対面する。そこで犯人は「いかにも見物人の胸を震わせるような、悔悛の情きわまった声」で「堪忍しておくんなせえ」云々かんぬんと述べる。するとそれを聞いていた群衆が「俄かにしくしく啜り泣きを始め、」そればかりか附添いの警部も泣いたという話である。
なぜ群衆も泣いたのだろうか。それは子供と同じくこの犯人も「可哀想」「みじめ」であることを悟ったからではないかと土居は考えている。そうすると全体の肯定が現れてくる。罪は確かに存在する。しかし、それさえも水に溶けてしまうかのような共感という情(一体化)の出現がある。
ある種の一体化には西洋哲学だったら理性を持ってきそうなものだが、ここで出てくるのは「可哀想」「みじめ」といった情動である。それを取り出すための行動が「申し訳ない」といったことであり、これが「甘え」(甘えられた義理ではないが、しかし許してほしい)ということである。なにか全てが調和する場面においてはある種の子供じみた芸が必要となるということでもあろう。そこで必要なのは幼児である。天皇もそういえば幼児であった。つまり祭りたてられる人であり、このとき大事だったのは犯人と子供が同一化したということであり、そこで祭りたてられる人がいるということが重要な気もしなくもない。
つまり全体の肯定といったときに、そこにあるイメージは「平等」などとはちょっと違う。何か犠牲となるものが必要なのだ。おそらくそれはイメージの中でも隠されている部分ではあると思うが、この意味での「平和」とは「尊敬された」「甘えさせられた」「盛り立てられた」他者であり、私たちはその人に甘えると同時にその人も甘えている。もしかしたらこういったものが「甘え」のイメージの原型となるのかもしれない。
甘えの現在
翻って現代の「甘え」はどうであろうか。この本の初版は1971年だからそれからもう50年以上もたっているわけである。土居は『続「甘え」の構造』も書いており、それが2001年の出版である。今は『続』と比較しても20年以上経っている。『続』に関しては、甘えが肯定的に受けとられなくなっており、それはどうなのかというような論調になっていたが、これは『「甘え」の構造』』の主張とは真逆である。『「甘え」の構造』では、「甘え」を乗り越えて他者を他者と認めることが重要だ、というような主張がなされていた。土居自身も心境の変化があったのだろう。ただどちらにせよ、あまりピンとこない。
というわけで現代について自分なりに考えてみたいのだが、「甘え」という観点からして、感覚的には次のようなことが言えるのではないかと思う。「甘え」の構造は消えておらず、依然としてある。そして薄く広く日本社会に浸透しており、むしろ常識となった観さえある。
「甘え」でまず想起せずにはいられないのが「母性のディストピア」における「ネット社会」の到来だ。宇野は母性というは、今は「インターネット」における「SNS」などが担っているのではないかと主張する。「甘え」と「母性」というのはかなり近しい面もある。義理人情というような時代ではもはやなく、「広大なネットワーク」に現代人は薄っぺらく甘えている。
またなんというか「「甘え」の構造」があまりに常態化しすぎて常識となってしまったのではないかという観もある。一つの例だが、いわゆるサービス残業というものを例にとってみよう。思うのは、日本ではずっとこのサービス残業とかそういったものがありきで労働システムが成り立っていたということである。そういう論評があったら教えてほしいのだが、日本社会はあまりシステムというものを信用していないように思える。システムで効率よくやってもどうしたって綻びは出てくるじゃないか、どこかで埋め合わせしないといけないに決まっているじゃないかという考え方である。「職人気質」と呼べば良いのかなんと言ったら良いのかわからないが、そういう感じがする。すると埋め合わせは隙間や余白でするしかない。それがサービスである。それでであるが、こういった構造自体は、あまりに変わらなすぎてむしろそれこそが自然という感じになってきているというように思える。とりわけ若い世代は全体としてはそうなのではないか。
サービス精神こそ本質だというような考え方が根強いというか、むしろ常識として一般化してしまっているのである。これも「甘え」と何かしら関連があるような気がする。
とにもかくにも現代において「甘え」は浸透しきっている。それが日本古来のものなのかというと、やはり明治になってから強くなったのではないかというような気もする。『「甘え」の構造』で登場するのも明治以降の話が多い。甘えはどこまで行くのだろうか。おそらく際限がないのであるが、甘えの構造の中では「甘える」方も「甘えられる」方も、自らの首を締めながらもある種の快楽を得ているというところではある。互いの承認は得られているので。だとすると「甘え」の肯定と、私たちが向かっている方向性というのは、ある意味で死の欲動みたいなものを本源的に保持しており、そういったマゾヒズム的な志向性を持っているのではないかという気さえしてくるのである。
参考文献
土居健郎『「甘え」の構造(新装版)』弘文堂、2001年。