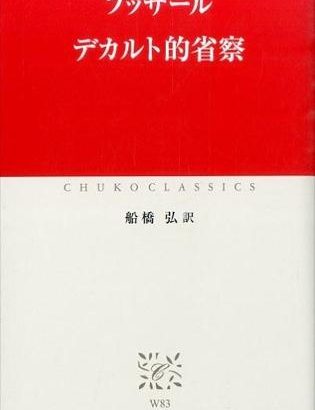まえおき
「間主観性(intersubjectivity)」という言葉を日常生活で使う機会はほとんどないだろう。ごはんを食べているときに、いきなり「このトマトは間主観的なのかなあ」などと言い出す人がいたら、怪訝な顔をされるにちがいない。しかしこの言葉は、学問の世界ではそれなりに定着しており、現代では心理学、教育学、言語学などの諸分野において用いられている。したがって、間主観性とは何かについて知っておくことは――食卓での会話を盛り上げるためにはあまり役立たないかもしれないけど――世界や人間のあり方について考えるための手掛かりになるかもしれない。
ところで、「間主観性」という言葉が浸透することになった一つのきっかけは、ドイツの哲学者エトムント・フッサール(1859-1938)の確立した現象学である。というのも、フッサールが『デカルト的省察』(1931)という著作において提示した「間主観性」概念が、あとにつづく現象学者たちによって批判的に継承され、さらにそれが現象学の枠を超えて波及していくことになったからだ。
ではそもそもフッサールは、「間主観性」について何を述べていたのだろうか?
トマトはどこにどんなふうにあるのか
せっかくなので、先ほど言及したトマトを具体例としながら考えてみよう。私はトマトを食べようと思い、冷蔵庫からそれを取りだし、包丁で一口サイズに切って皿に盛りつけた。さて、このときトマトはどこにあるのだろうか――当然のことながら、お皿の上に存在している。しかもその存在は、私にとっては、すごくありありとしている。お皿の上のトマトは赤く見えて、ひんやりした手触りで、口に入れれば甘酸っぱい香りや味が広がる。それらの経験を通じて、トマトはいろいろな仕方で、ありありと現れてくる。その結果として私は、トマトがこの世界に(もっと詳しく言えば、お皿の上に)存在しているのだと確信せざるをえなくなる。フッサールは、こんなふうに経験を通じて対象の存在が確かめられることを、私の経験における対象の「構成(constitution)」と呼んだ。
では、私の経験を通じてトマトがお皿の上に存在するものとして構成されたとして、そのトマトは客観的に存在していると言えるのだろうか? こんなふうに問うことは、奇妙な感じがするかもしれない。対象の存在はすでに私の経験を通じて確かめられたのだから、そんなふうに確かな存在は、一見すると、すでに「客観的」と言っても差し支えないように思われるかもしれない。しかしフッサールによれば、あるものが私にとって経験されているだけでは、まだそれが「客観的」であるとはかぎらない。なぜなら、私にとって経験されているものが、みんなにとって経験されうるとはかぎらないからだ。例えば、私はトマトが食べたいと強く念じるあまりに、ほかの人には経験できないトマトを経験できてしまっているのかもしれない。このとき、私にとってそのトマトがどれほどありありと現れているとしても、それが客観的であるとは言いがたいだろう。ここからフッサールは、あるものが客観的(objective)であるということは、それがみんなにとって経験可能である(experienceable by everyone)ということにほかならないと主張した(『デカルト的省察』42~44節)。客観性=みんなにとっての経験可能性、というわけである。
※ここで客観性を担保するのが、みんなの実際の経験ではなく、あくまで経験の可能性であるというのがポイントである。お皿の上のこのトマトが客観的かどうかを確かめるために、ありとあらゆる人びとにそれを実際に経験してもらわねばならないというのは余りにも大きすぎる要求だからだ。ここで要求されているのは、あくまで、「もしこの場所に他の人がいれば、その人も同じように経験してくれるはずだ」という可能性なのである。ちなみに、「みんなにとって経験可能」という語句は、『デカルト的省察』44節などに見いだされる。
複数の主観のあいだで成り立っていること
客観性=みんなにとっての経験可能性。この定式を踏まえれば、間主観性という言葉の意味も理解しやすくなるだろう。間主観性(intersubjectivity)というのは、読んで字のごとく、複数の主観(subject)のあいだ(inter)で成り立っているということである。このときの主観の数は、最小では2名、最大では存在しうるありとあらゆる者たち、すなわち「みんな」である。これから地球上に生まれてくる人間や、地球の外にいる(かもしれない)生命体まで含めるならば、経験の主体のすべてを数え上げることは実質的には不可能だろう。このように、想定される数には2~無限大までの幅があるにせよ、とにかく複数の主観のあいだで何かが成り立っているとき、それは「間主観的」なのである。
すると客観性(みんなにとっての経験可能性)は、間主観性(複数の主観のあいだで成り立っているということ)における「複数の主観」を、「みんな」という極限にまで大きくしたときに成立すると考えられる。
2名の主観のあいだで成り立っている=2名の主観にとって経験可能である
3名の主観のあいだで成り立っている=3名の主観にとって経験可能である
・
・
・
みんなのあいだで成り立っている=みんなにとって経験可能である=客観的である
作りかけの客観性
こんなふうに間主観性を広げていくことで客観性に至るという発想は、客観性を主観性から切り離すような素朴な見方と対立する。なんとなく私たちは、客観的な世界というものが主観を離れてそれ自体で存在していると考えているかもしれない。これに対してフッサールは、そのように客観性を初めから前提することをやめて、主観のあいだで成り立っていることを地道に押し広げていくことによって客観性を目指すことを勧める。ただし押し広げは順調に進むとはかぎらず、従来とは別の意見や理論を持った新たな主観の登場によって覆されるかもしれない。したがって私たちにとっての客観性は、いつも作りかけの状態にとどまっている。完成した客観性というのは、間主観性を無限に拡張した先にあるという意味で、あくまで理想的なものなのである(『デカルト的省察』49節)。
間主観性の二つの意味
上では、間主観性を「複数の主観のあいだで成り立っているということ」として、客観性との関連において説明してきた。しかし実は、フッサールの言う間主観性には、もう一つの意味がある。それはすなわち、主観どうしの「共同体(community)」という意味である(『デカルト的省察』49、56節など)。ちなみに「共同体」は、もともとのドイツ語では「ゲマインシャフト(Gemeinschaft)」と言う。
まとめておこう。
| 間主観性(フッサール) ①何らかのものごとが、複数の主観のあいだで成り立っているということ ②主観どうしの共同体 |
どうしてこんなふうに多義的な言葉づかいをしちゃうの……とフッサールに不平を述べたくなるが、よくよく見ると、①と②は関連している。①は、経験されるものごと(対象)の性質であり、②は、経験している主観どうしのつながりである。すると、①は②のおかげで成り立っているのだと考えられる。このように同じ事態を対象の側と主観の側の双方から記述して、それらの相関関係について考察するというのが、フッサールの思考のスタイルだった。
すると間主観性をめぐる議論は、さまざまな方向に開かれていることが分かる。例えば、①の側面に注目すると、「間主観性」という概念は、対象の「客観性」がどのように知られるかという問題へとつながる。これは哲学において、伝統的に、認識論(知識の哲学)の文脈において論じられてきた問題だ。他方で②の側面に注目すると、「間主観性」という概念は、主観どうしの「共同体」がどのように形成されるかという問題につながる。これは、いわゆる共同体論(社会の哲学)の問題であると言えよう。もちろん、知識の哲学と社会の哲学は密接に結びついている。なぜそれが密接に結びついているのかを考えるためにも、やはり「間主観性」という概念に注目することは重要かもしれない。
※ちなみに、intersubjectivityには、「間主観性」だけでなく「相互主観性」という訳語が当てられることもある。上記の①と②の意味のうち、「間主観性」は①、「相互主観性」は②の意味をうまく反映できているが、どちらも完璧な訳語ではないかもしれない。
フッサール以降の現象学における展開
フッサール以降の現象学者たちも、複数の主観のあいだで成り立っていることや、主観どうしの共同体について独自の思索を展開した。例えばハイデガーの『存在と時間』においては、「間主観性」という言葉は使われていないものの、「共同現存在(Mitdasein)」という概念を用いて独自の共同体論が提示されている。またメルロ゠ポンティは、フッサールについての論考「哲学者とその影」において、主観が生身の身体を介して関係し合っていることを示すために、「間身体性(intercorporéité)」という語を用いている(メルロ゠ポンティ「哲学者とその影」、『精選 シーニュ』所収、廣瀬浩司編訳、ちくま学芸文庫、2020年、256-257頁)。さらに『デカルト的省察』の仏語訳者の一人であったレヴィナスは、『全体性と無限』において、客観性や社会についての独自の見解を述べている。フッサールが「間主観性」という概念を通じて引き入れた「他者」の問題は、彼自身にも思いもよらなかった仕方で、あとにつづく現象学者たちによって展開されていったのである。