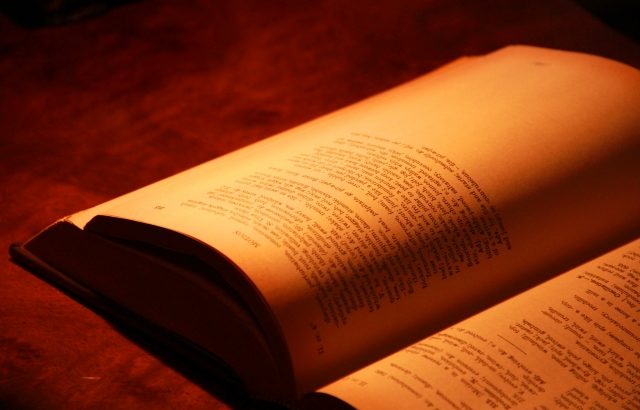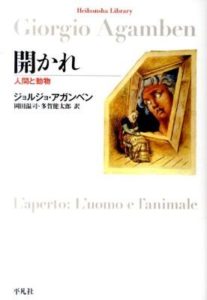受容理論の概要と「内包された読者」
文芸批評理論は1960年代までに世界各地で様々に考案されてきた。ロシア(ソ連)ではロシア・フォルマリズム、アメリカでは新批評(新批評とは何か – 文芸批評理論*なるほう堂)から神話批評、フランスではフッサール由来の現象学、ドイツではハイデガー由来の解釈学。これらの理論は批評の仕方は違うとはいえ、作品を批評するにあたり作者か作品に注目するという点では一致していた。
だが文学作品を取り巻く環境を考えてみると、作者と作品だけでは足りないことがわかる。そう、読者が足りていないのだ。作者が文学作品を執筆してもそれが読まれなければ作品の価値がない。文学作品において読者は非常に重要なのである。
この観点から、1967年にドイツのコンスタンツ大学に勤務していたヴォルフガング・イーザーとロベルト・ヤウスは受容理論(受容美学)を提唱した。受容理論は名前の通り受け手側(読者)に注目した理論なのだが、かといって作品や作者に注目した文芸批評理論から理論的にかけ離れたものというわけではない。むしろ理論的な土台はロシア・フォルマリズムや現象学、解釈学におうところが多い。
イーザーとヤウスは同じコンスタンツ学派に属しともに受容理論を発展させるのだが、それぞれ重点を置くところが異なるので受容理論の内容も人によって異なる。イーザーとヤウスのそれぞれの受容理論にはいる前に、受容理論が前提としてる「読者」について考えてみよう。
偏に「読者」といっても様々である。批評家、同時代の読者、未来の読者、意味を解さない子供、作者が想定している読者、超越者、意図された読者など。考えられる「読者」を列挙するだけで容易に分かることは、これらの「読者」には共通点がないことである。しかしこれでは想定する読者像が定まらず受容理論を構築することができない。
ここでイーザーは「内包された読者」(想定された読者)という読者のモデルを提唱する。内包された読者は、性格、時代、年齢、教養、その他諸々を一切問わない。それどころか内包された読者はこの世に存在する必要すらない。文学作品はそれ自体に反応を引き出そうとする性質があり、それによって理想的な反応をしながら作品を理解していく、そのような読者が(作品に)内包された読者である。受容理論は基本的にこの内包された読者を想定して理論を構築していくことになる。
インガルデンの受容理論とその問題点
受容理論といっても一枚岩ではない。まずは、フッサールの弟子でポーランドの哲学者ローマン・インガルデンの受容理論からみていこう。インガルデンの主張は至極簡単である。文学作品には不確定箇所があり、読者はその不確定箇所を埋めながら小説を受容(=反応)するというのである。
例えば梶井基次郎の『檸檬』という小説の一節をインガルデンの見方で読解してみよう。「その日私は何時になくその店で買い物をした。というのはその店には珍しい檸檬が出ていたのだ」。この文章だけで事態を過不足なく表現できていると考えたら大間違い、脳が勝手に行った補正を意識できていないでいる。例えば、「珍しい檸檬」というところを抜き出してみても、一風変わった檸檬という意味なのか、檸檬自体が珍しいという意味なのか判別つかない。前後の文脈を読みそこから類推して後者と判断するのである。
このように文学作品には不確定箇所が多数存在し、それを読者が埋め合わせることで文学作品は美的価値が生まれるということになる。インガルデンはこのことを、文学作品は単に「図式」を集めたものであり、読者が作品を「具体化している」と表現している。
しかしこのインガルデンの受容理論は大変窮屈なもののように感じないだろうか。不確定箇所があってそこを埋め合わせるのは、まるで小学校のテストにでてくる穴埋め問題のようである。読者は結局のところ決まった解を発見することしかできない。
イーザーはインガルデンとは違って、読者の読解に自由と柔軟性を与える。文学作品が「図式」の寄せ集めという点はインガルデンと変わらないのだが、間にある「不確定箇所」を「空所」と言い換え、この「空所」を埋める作業に読者の創造性をみる。「図式」の断片を繋ぐ部分が「空所」であって、「空所」を埋められないときは、戻ったり読み進めたりしながら、つまり全体から部分へ、部分から全体へと読み進めながら「空所」を埋めていく。このように作品と読者の共同作業によって「空所」が消滅したとき、文学作品から首尾一貫した意味が組み立てられるというわけである。
イーザーの受容理論のポテンシャルと問題点
イーザーは「図式」「空所」「具体化」に加えて「準拠枠」「否定作用」という概念を提案する。「準拠枠」は文学作品に取り入れられた共通の慣習や知識、過去の文学作品の引用のことである。文学作品は何かしらの規範あるいは過去作品を吸収することなくして、文学的な作品たることはあり得ない。結局のところ文学作品は、その時代の慣習と過去の作品をどれくらいの割合で取り入れるかで、作品の性質が決まってくるのである。
社会の慣習や規範、過去の文学作品を取り込むことで作られた「準拠枠」は、しかしながら、元々の規範とは異なるものになっている。「準拠枠」という規範を引用し書かれるとき、まるっきり純粋にそのままのものを取り入れることはできない。したがって、文学作品は取り入れた「準拠枠」とは異なる「準拠枠」を作品のなかに作り出すことになる。
この社会とは異なる「準拠枠」をもとに作られた「空所」を読者が「具体化」するとき、読者はこれまでの自分とは別の見え方ができたりする。このように社会の「準拠枠」に違和感をもつようになることを「否定作用」という。イーザーによれば、文学作品は「空所」を埋め合わせる想像力と「否定作用」によって美的価値が生じるのである(「否定作用」はこれまでと違うものの見方ができるという意味で「異化作用」に近い概念である。詳しくはこちらを参照 : 異化とは何か – シクロフスキー、ブレヒト)。
「否定作用」とはつまり規範に対して疑問の目を向けるということに他ならない。イーザーは、文学作品には現在の制度に疑問を投げかけ批判意識を向けさせる力があり、それが文学の美的価値であると主張する。
ところが、この考えはイーザーの受容理論の理論的な問題点を明るみにだす。この命題を反転させると、既存の慣習に批判意識を向けさせない文学さらには読者には価値がないということになってしまうのだ。いいかえると、凝り固まった思想をもつような読者はよろしくない、むしろ認識が変化しやすい読者が理想的なのだ、ということになる。結局イーザーの受容理論は、寛容なリベラル知識人が理想的な読者ということで読者を限定してしまうのである。
ヤウスの「期待の地平」と、フィッシュの洗練された読者反応理論
受容理論にイーザーとは別のアプローチをしたのがハンス・ロベルト・ヤウスである。ヤウスは現象学、マルクス主義、フォルマリズムの理論を取り入れながら受容理論を確立していく。
ヤウスはマルクス主義の歴史理論とロシアフォルマリズムの非歴史的テクスト理論を融合させて、さらに、ハンス=ゲオルク・ガダマーの解釈学(ハイデガーを理論的支柱にした文芸理論)から発展させた「期待の地平」という概念を提唱する。「期待の地平」とは解釈者が前提とする慣習や知識のことであり、解釈者は読書の都度「期待の地平」を生成する。「ヤウスは、この共時的な期待の地平が生成されては破壊され、通時的な軸に展開していくという、読者による受容を基礎にした文学史を構想した」のである(「受容理論」、p26)。
イーザーやヤウスの議論を突き詰めていくとどうなるのか。それを実行し「読者反応理論」をもってアメリカの文学研究に挑発をしたのがスタンリー・フィッシュである。
「空所」を埋めることによって文学作品の一貫した意味を作り出し、その一連の行為によって作品に美的価値が生じるということのなら、文学作品の意味は読者が作っているとも言えてしまう。作品の中には意味などない、真の作者は読者であるということになってしまう。
解釈ごとに意味が異なる作品ができてしまうと、一つの文学作品にもかかわらず無数の作品が氾濫してしまうことになる。そこでフィッシュが提案するのが「解釈共同体」という概念だ。「テクストの意味の権威は、テクスト内部ではなく、ある読者が属する解釈共同体に存するというわけだ」(「受容理論」、p27)。
しかしこの概念を用いたフィッシュも、結局はイーザーが陥ってしまったように限定された読者像を打ち立てることになる。解釈共同体に属することができるのは、作品を上手に解釈できる人だけだ。つまり、文学的教養のある読者だけが解釈共同体に属して、文学的教養のない読者はそこから省かれるのである。
\30日間無料!解約も簡単!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
他の文芸批評理論
こちらは「批評理論をわかりやすく解説」で紹介してています。また「批評理論のおすすめ本」も参考にしてみてください。
参考文献
河野慎太郎「受容理論」(大橋洋一編『現代批評理論のすべて』新書館、2006年、26-29頁)
筒井康隆『文学部唯野教授』岩波書店、同時代ライブラリー97、1992年