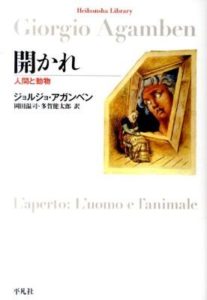現代的なカルチュラル・スタディーズとは
カルチュラル・スタディーズ(Cultural studies : CS)は日本語に訳すと文化研究になり、この「文化」という単語がどこまでを含めるかによって研究の対象が大きく変わる。現代では「文化」を広義の意味にとることで、広大な領域を研究対象としている。例えば、写真、ファッション、髪型、アニメ、漫画。アカデミックな世界では研究の対象にならないような俗物的なものにまで研究の手を広げられることは、カルチュラル・スタディーズの大きな魅力の一つに繋がっているのだが、一方で何でもかんでも手をつけてしまう節操のなさに嫌な印象を抱いている人も少なくない。
数多くある文芸批評理論の中でもカルチュラル・スタディーズは他にはない大きな特徴がある(例えば、印象批評や新歴史主義を参照)。上記の概略からも分かるように、文芸批評理論が文字通りの「理論」であるのとは違って、カルチュラル・スタディーズが意味するのは「研究」であり、制約となるのは「文化」という対象だけである。カルチュラル・スタディーズの始まりは後述するようにイギリスの文芸批評であるのだが、研究の対象が文芸を超えて文化一般にまで拡張できたという事実は他に類を見ないため、文芸批評理論との違いが気になる人も多いのではないか。
文芸から文化への研究対象の拡張。カルチュラル・スタディーズに対するこのような見方は正しいのだが他の説明もできるように思われる。ここでは対象の問題から一歩離れて、受容の観点から問題を眺めてみよう。すると、文芸と文化は内容は異なるにしろ、それらを享受する受け手は変わらないことが分かる。一般的に文芸を論じるにあたって批評理論は「社会-作者-作品-読者」の4項から成る関係を想定し、どこを重視するかによって理論の形式を決定してきた。作品なら構造主義、社会ならマルクス主義批評といった具合に。この中で「読者」に注目したのが受容理論である。
カルチュラル・スタディーズの系譜の一つは受容理論にある。受容理論を社会に接続したときカルチュラル・スタディーズが生まれる。だからカルチュラル・スタディーズの本質は文芸から文化への研究対象の拡張という見方は一面的だ。むしろ受容(=消費)の観点から対象を批評しようとした結果として、対象が拡張されたのである。
労働階級の民衆文化の見直し(レイモンド・ウィリアムズとリチャード・ホガート)
カルチュラル・スタディーズは、1960年代にバーミンガム大学のレイモンド・ウィリアムズとリチャード・ホガートによって発展した。当時のイギリス文学界は、保守的で国民国家文学主義者であるF・R・リーヴィスの影響力が強かった(この時代の解説はこちら : 文学史 – 文芸批評成立の前史*なるほう堂)。レイモンド・ウィリアムズとリチャード・ホガートは労働者階級の出身というこもあり、彼らの主張は主流社会に抵抗を示す意味合いの反リーヴィス主義という側面があった。ウィリアムズとホガートの研究対象は被抑圧者性やマイノリティーへと向かうのだが、その傾向はスチュアート・ホールが人種問題を扱い始める1969年以降に決定的となる。
マイノリティーを研究するというカルチュラル・スタディーズのイメージはこの頃に形成され、それは現在まで続いている。だが初期のカルチュラル・スタディーズのモチベーションは少し違う場所にあった。初期のカルチュラル・スタディーズは「ナショナリスティックな中産階級的バイアスに気づかない「教養」と対立し、高級文化と大衆文化を峻別する政治への批判を「民衆文化研究」の形で結実させた」(143)。高級と大衆を差別化し前者を持ち上げ後者を蔑むアカデミズムに抵抗する思想であったのだ。
カルチュラル・スタディーズの方向性を決定づけたウィリアムズ、ホガート、ホールについて簡単にみておこう。まずはウィリアムズとホガートから。
ウィリアムズは労働者階級出身でマルクス主義的な立場の批評家、大学人。イギリスだけで75万部を売り上げた『文学と政治』が有名。旧来の共産党や社会党を権力にしがみつく既成左翼とみなし批判した新左翼(ニューレフト)から支持を集める。文学に限らず、政治、メディア、文化などを批評しており活動は多岐にわたる。ウィリアムの功績は「文化」の概念を高級文化から大衆文化まで拡張したことにある。労働者階級であったウィリアムズならではの視点と言えるかもしれない。
ホガートはバーミンガム大学に設立された現代文化研究所の初代所長で、現代文化研究所はカルチュラル・スタディーズの学問的発展の拠点となる。ホガートの『読み書き能力の効用』(1957年)では、「労働者が独自の習俗により受け継いできた民衆文化」(144)に力点が置かれる。ただし『読み書き能力の効用』で言われるのは、その民衆文化を汚染する大衆メディアへの批判である。特にアメリカのマスメディアが発信する通俗的なテレビ番組が、民衆文化を大衆文化へと変容させたと主張し、「受動的な大衆消費者に堕した人々を非難したのである。」(144)
ウィリアムズとホガートの問題点は明らかだ。高級文化と対比させて民衆(=大衆)文化にも価値を見出すその手法は、しかしながら、グローバル社会で生まれた大量消費的大衆文化を退け国民文化のみを扱うものなのである。言い換えれば、民衆文化を退けることで高級文化を称揚した従来の研究のように、グローバルな大量消費的大衆文化を退けることで民衆(=大衆)文化を持ち上げているのだ。
\30日間無料!解約も簡単!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
グローバルな視点へ(スチュアート・ホール)
これらの問題点を克服したのが、ホガートの次に現代文化研究所の所長になったスチュアート・ホールである。もう一度ホガートの主張を確認しよう。ホガートは労働階級の生き生きとした生活に価値ある民衆文化を見ようとするあまり、大量に発生していた大衆消費者を評価することができなかった。アメリカ的マスメディアによって与えられる大量の情報を消費するだけの大衆消費者は、受動的であるとしてむしろ否定的に評価されたのである。
ホールはメディア研究から出発し「コード化 / 脱コード化」という概念を提唱する。コード化とは、マスメディアが「生産—流通—配分」によって意味を創出することを指す。メディアはある種のイデオロギーに則って情報をコード化して流すのだ。では大衆はコード化された情報を受動的に受け取るだけかというとそうではない。大衆はコード化された情報を能動的に脱コード化して消費しているのである。このように大衆消費のなかに能動性をみることで大衆消費文化を肯定的に評価することに成功する。
さらにもう一つ重要な仕事は、現代文化研究所(バーミンガム学派)のプロジェクト『危機を取り締まること』(1978年)である。これは少年によるひったくりなどの犯罪がメディアに取り上げられ、黒人や移民の犯罪と結び付けられる様子を分析したものである。
この仕事によってカルチュラル・スタディーズは人種の問題にまで応用できることが示された。こののちホールやヘイゼル・ガービーは、「人種の分析枠組みを使い、他者化された主体のアイデンティティ・ポリティクスを」(145)カルチュラル・スタディーズで扱うようになる。その後カルチュラル・スタディーズは研究の幅を広げ、植民地主義や奴隷制の分析、さらには「国民国家批判とも結びつき、空間論やポストモダン批判とも連携し、進行中である。」(145)
現代のカルチュラル・スタディーズの骨組みはここまでで完成したとみて良い。カルチュラル・スタディーズの歴史を辿ると、研究の対象が大きく変化していることが分かる。それによって当初の目的である「文化的立場への批判意識はむしろ甘くなってしまった」かもしれなず、見直していく必要があるだろう。が、時代を経るごとに研究の対象を拡張していくカルチュラル・スタディーズのダイナミックさが織りなす魅力は色褪せることはない。
\30日間無料!解約も簡単!/
→Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
ほかの文芸批評理論
こちらは「批評理論をわかりやすく解説」で紹介しています。また「批評理論のおすすめ本」も参考にしてみてください。
参考文献
新田啓子「カルチュラル・スタディーズ」(大橋洋一編『現代批評理論のすべて』新書館、2006年、142-145頁)