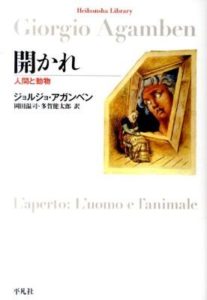異化(остранение, Verfremdungseffekt, defamiliarization)
基本的な意味は「ふだん慣れ親しんでいる事物や当たり前だと思っているものの見方を刷新する(異なるものにする)こと」。噛み砕いていえば、「物事をいつもと違った角度から、違った仕方で見せること」。
ロシア・フォルマリズムの批評家ヴィクトル・シクロフスキーによって1910年代に、ドイツの劇作家ベルトルト・ブレヒトによって1930年代から40年代に提唱され、今日でもしばしば参照される手法、考え方。一見したところのわかりやすさとは裏腹に、その意味合いは論者によっても解釈によってもばらつきが大きい。ここではシクロフスキーおよびブレヒトの「異化」を、以下の三つに分類して説明する。
(1)事物のそのものらしさの知覚を回復する——シクロフスキー
(2)知覚のプロセスを体験する——シクロフスキー
(3)感情移入の抑制により社会的批判を可能にする——ブレヒト
(1)事物のそのものらしさの知覚を回復する——シクロフスキー
シクロフスキーが異化を論じた代表的論文「手法としての芸術」(1917年)の、以下の一節がよく参照される。
そこで生の感覚を戻し,事物を感じ取るために,石を石らしくせんがために,芸術と呼ばれるものが存在しているのだ。芸術の目的は,わかることとしてではなく見ることとして,事物の感覚を与えることである。(……)芸術においては知覚のプロセスが目的そのものであり,長引かされねばならないからである。芸術は,事物=作品の制作を体験するための手段であり,芸術において,完成しているものは重要でないのだ。(八木、18頁、太字引用者)
シクロフスキーが「異化」と対立するネガティヴな現象としてあげるのが「自動化」である。「自動化」され、日常的な習慣と化してしまった知覚には、「石の石らしさ」を鮮烈に感じとることはできない。「自動化」は、〈事物のそのもの性〉から人びとを遠ざけ疎外してしまうのである。
「異化」はこうした「自動化」を解除し、事物をふたたび見慣れない様相のもとに描きだすことで、鑑賞者が、事物のそのものらしさ、さらには「生の感覚」を取り戻すことを可能にする。具体例として、シクロフスキーはトルストイから多く例をとっている(馬の視点を通して見た世界の記述(「ある馬の物語」)や、オペラ経験のない人の視点を通して見るオペラの舞台(『戦争と平和』)など)。
有り体に言えば、当たり前に知っていると思っていたひまわりや星空の見え方がゴッホの絵画によって刷新されるとか、あるいは直接芸術に関係なくとも、悩み事について自分とは違う考えの友人の意見を聞いたら一気にこれまで気づかなかった解決策が見えてきたとかといったことだろう。
(2)知覚のプロセスを体験する——シクロフスキー
しかし、ロシア文学者の八木君人によれば、(1)のような解釈だと、上記引用の「わかることとしてではなく見ることとして」という部分がうまく理解できない。(1)の「異化」によっていかに鮮烈な〈石の石性〉を掴んだとしても、それはあくまで「石」という対象・事物を「わかること」(=認識すること)でしかない。「事物の感覚」を〈物のその物らしさの体験〉だと捉えている限りは、結局「完成しているもの」を重視していることになってしまう。
これに対して、「完成しているもの」の認識にたどりつく以前の「プロセス」に重点を置くという立場がある。シクロフスキーは造形芸術論において、物の「肌理・質感」の意義を強調しているらしく、これを敷衍すれば、物の「肌理」をすこしずつ触って感じ確かめていくプロセス、知覚の触覚的なプロセスが大切だということになる。
たとえばりんごの絵を見たとして、「深紅で熟した、小ぶりでまん丸の、みずみずしくていかにも美味しそうなりんごだ!」ということが重要なのではなくて、「画布の左上から右下へ、赤い球状の物体の中心から輪郭へ、そしてまた中心へ……」というように視線を動かすそのプロセスだけが問題なのだ。これこそ「わかること」(=認識すること)に至らないまま「見ること」の内容である。「体験する」とはあくまでこのプロセスの「体験」なのであり、そう考えれば「完成しているもの」は重要ではないという点も納得できる。
こうしてシクロフスキーの同じ一節から、
(1)「物の物らしさへの認識」 vs (2)「物を知覚するプロセス」
という対立を取り出すことができる。これは言語的にいえば、「意味」vs「非意味(意味生成のプロセス)」という風に捉えることもできるかもしれない。
(3)感情移入の抑制により社会的批判を可能にする——ブレヒト
シクロフスキーが文芸批評家だったのに対し、ブレヒトは劇作家、演劇理論家である。シクロフスキーの「異化」論を参考にしてはいるものの、ブレヒトのそれはシクロフスキーのものとは大きく性格を異にする。従来の「戯曲的演劇」に対して「叙事的演劇」を提唱していたブレヒトは、後者の中心をなす手法として「異化」という概念を使うようになった(それは「中国の俳優術の異化的効果」(1937)、「実験的演劇について」(1939)など)。
両者の違いを一言でいえば、ブレヒトの「異化効果」(V効果とも呼ばれる)は、社会的、政治的である。自明なもの、日常的なものを、驚くべきものにすることによって(ここまではシクロフスキーの「自動化」批判と同じ)、観客に能動的、積極的な批判的態度や思考をうながすのである。
ブレヒトが何よりも批判のやり玉にあげるのが、アリストテレス以来、あるいはディドロ以来の、感情移入、没入を至上とする演劇観である。
ここで問題になっているのは、観客が脚本の人物にすっかり感情を同化するのを妨げるような仕方で演技をしようとする試みである。作中人物の表白や行動を受け入れたり拒んだりすることが、これまでのように、観客の意識下の領域で行われずに、意識の領域で行われるようにするわけだ。(「中国の俳優術の異化的効果」、140頁)
西洋の伝統的な演劇においては、役者が演じる人物に同一化し、さらにそれに観客も同一化することがよしとされる(例えばハムレットが悲しむ場面では、役者はいかにも悲しそうにし、観客もその悲しみを経験するべきである)。そこでは本物の感情が、あたかも「演じられ」ていないかのように感情が経験されることが望ましい。
これに対して、ブレヒトは役者と役、役者と観客のあいだに「距離」を作ることを求める。役者はそれが演技であることを積極的に示すべきであり、観客もそのことを意識すべきだ。なぜなら感情の同一化は、思考能力や批判能力を奪うからである。同一化を防ぐことではじめて、観客に思考の余地が生まれ、登場人物の行動や判断に対して自分独自の批判的な判断をすることが、さらには社会的行動や変革を起こすことが可能になる。
同一化を防ぐ方法には、以下のものが挙げられる。
- 第四の壁を取り払う(第四の壁は、舞台と客席の間にも壁がある=舞台上の出来事は誰にも見られていないという約束事。これを取り払って、役者が観客に語りかけるなどのアクションを取れば、おのずと物語への没入は妨げられる。)
- スクリーンに各場面のタイトルを映し出すなど、テクスト化。
- 台詞に三人称、過去時制を用いる(ふつうなら「わたしは……だ」と言うところを、あえて「かれは……だった」と言う。)
- 照明の光源を見せる。客席まで明るくする。
- 「社会的身振り」(「ある一定の時代の人間が互いにおかれている社会的関係の表層的身振り的表現のこと」(156頁))
- 演劇のなかで登場人物がとらなかった選択肢を示すこと(「……ではなく……である」)。これによって別の可能性があったことを示す。
この「過去時制」や「社会的身振り」ととくに関連する「異化」の効果として、「歴史化」がある。舞台上で起きる出来事が、普遍的な出来事ではなく、「一定の時代と結びついた、一回限りの、絶えず動いている出来事」(156頁)であることを示すのである。これによって「進歩」的な時間を想定すること、つまり、後からみれば以前のことはあの時代特有のことであった、と考えることが可能になる。
「異化」の魅力と不思議
このように一口に異化といっても、力点の置き方によって、また書き手やジャンルによって、その意味合いはさまざまだが、それ以上に異化にはほかの文学的技法にはない捉えがたさがある。
そもそも、異化は「技法」なのだろうか。「信用できない語り手」や「内的独白」には、巧拙はともかく明確な「やり方」があるが、「異化」する(見慣れたものを見慣れないものにする)手法はほとんど無限にある。そうだとすると異化はむしろ「理論」なのだろうか。しかし「精神分析」や「フェミニズム」といったいわゆる体系的「理論」とくらべると、異化はあまりにもシンプルである。むしろ「理想」や「目標」(「異化しましょう」)、「価値判断」(「異化的でよいですね」)に近い。
別の観点からいえば、「異化」はあまりにも一般的である。「常識を疑いましょう」も異化だし、「科学」だって異化である(顕微鏡で日常的に使う物体のふだん目にしない微細な構造を覗きこんだら驚きが得られるだろう)。小学生だって「異化せよ」と言われているし実際している。あまりの当たり前さに、異化を異化した方がよいのではないかと不安になるほどだ。
シクロフスキーやブレヒトの名前を知らない人は多いだろうが、事実上「異化すべし」という命題に頷かない人はほとんどいないだろう。こうなると、異化の意義は明白でありながら、まさにそのことによって疑わしいようにも思えてくる。こういう立ち位置にある芸術「技法」はほかにあまり見当たらず、それが「異化」概念の不思議な捉えがたさになっている。
「異化」について改めて考えるとき、一般的な「異化」のイメージからシクロフスキーやブレヒトに遡ってその具体的な方法や内容を検討してみるのは刺激的だし、そこから再び一般化した「異化」に戻って、今日におけるそのステータスを考え直してみるのもおもしろいだろう。
参考文献
八木君人「シクロフスキイの「異化」における視覚」『ロシア語ロシア文学研究』43、2011年、17-26頁。
ヴィクトル・シクロフスキー『散文の理論』水野忠夫訳、せりか書房、1971年。
ベルトルト・ブレヒト『今日の世界は演劇によって再現できるか』千田是也訳、白水社、1962年
ほかの文芸批評理論
こちらは「批評理論をわかりやすく解説」で紹介されています。また「批評理論のおすすめ本」も参考にしてみてください。