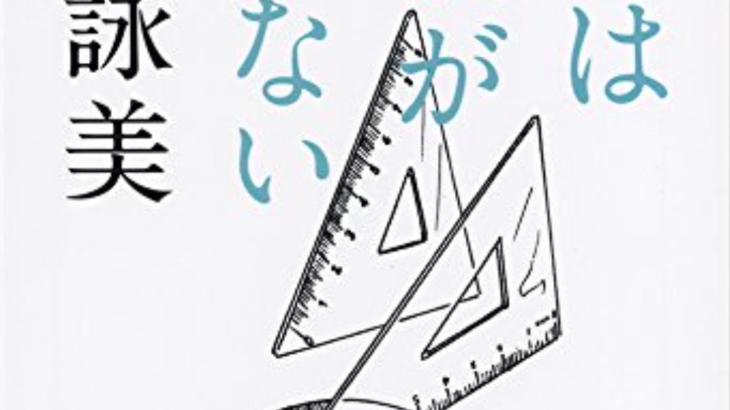「そういう抽象的な言い方って、ちっとも役に立たねえや」
「ほんとね。じゃ、後で、私の部屋でセックスでもしましょう」
「こんな時に?」
「具体的でしょ?」(p.176)
*本文の引用とページ数は、すべて文春文庫版に基づく。
1. 十八世紀作家?としての山田詠美
作家自身の奔放なイメージとは真逆に、山田詠美の小説はいつも論理的だ。論理的すぎて、『アニマル・ロジック』(1996)という名の作品すら生まれてしまった。
今回は、文庫版の巻末解説で綿矢りさが「私にとって他の科目と並ぶ『美学』という科目の教科書」(p.267-268)だったとすら語った、『ぼくは勉強ができない』の魅力について語りたい。強いて分けるならば青春小説のジャンルに入るのだろうか。勉強はできないが頭の回転が速く女の子にはよくモテる、今風に言えば「地頭」の良い時田秀美(男子である)が語り手。父はおらず、派手好みの母と祖父とで暮らしている。年上の恋人・桃子さんとはセックスも致す中。やる気はあまりないがサッカー部に所属し、担任で顧問の桜井先生の影響で哲学書などにも手を伸ばし、堅物の教師やガリ勉同級生の不自然な硬直ぶりをおちょくることもしばしば。こうした秀美の語り口に、読者が痛快さを覚えながらもその刃が自分に向かない「甘さ」をそろそろ感じ始める第7章、告白してあえなくフラれたばかりの山野舞子は、秀美に強烈な長台詞を浴びせる。
「何よ、あんただって、私と一緒じゃない。自然体だって演技してるわよ。本当は、自分だって、他の人とは違う何か特別なものを持ってるって思ってるくせに。優越感をいっぱい抱えてるくせに、ぼんやりしてる振りをして。あんたの方が、ずっと演技してるわよ。[…]でもね、自由をよしとしてるのなんて、本当に自由ではないからよ。私も同じ。」(p.167、強調引用者)
最初にこの一節を読んだ時、うれしくなって思わず立ち上がってしまった。今まで「見る」主体として教師やクラスメイトの自意識をさんざん諷刺してきた秀美が、彼女の台詞一発によって「見られる」側へ急激に転落し他の登場人物と同じ地平に立ってしまう、このスリリングさ。
山田詠美作品では、相手を「見る」者は極めて論理的に相手から「見られる」者へと変貌していき、そこに人物同士の関係性が浮き上がってくる。人物をというより人物同士の関係性を、一体感に昇華・解消せず、違いは違いとして冷徹に描写するのは、バンジャマン・コンスタン『アドルフ』(1816)やスタンダール『赤と黒』(1830)・『パルムの僧院』(1839)など、十八世紀生まれのフランス「心理小説」作家が得意とした手法だ。原点には、ラクロ『危険な関係』(1782)が聳え立っている。これらの作品で、登場人物は互いを分析し、見通そうとし、論理的に裏切り合う。
山野舞子の「私は、人に愛される自分てのが好み」と言いきってしまう啖呵も、十八世紀ピカレスク小説(悪漢小説)によく出てくる「悪の魅力」を漂わせている。登場人物の輪郭がくっきりと立ち現れていて、内面を見通せる雰囲気。この「明晰さ」を現代日本の小説で感じられるとは思わなかった。私が立ち上がってしまったのはそういう理由だったのだ。
2. 文体と感性、痛みと成長
続いて、『ぼくは勉強ができない』を構成する文体について見てみよう。
「朝、目覚めたら、風邪を引いていた。不思議だ、と思った。昨夜まで、なんともなかったのに、何故、突然、発病するのか。眠りが、病気を呼び寄せたように、ぼくには、思えたのだった。そういえば、ぼくが風邪を引く時は、いつも、こうだ。ある朝、病人になっているのだ。」(p.128)
これは第6章「時差ぼけ回復」の冒頭で、読点のリズムが非常に独特である。若い男子学生を語り手に据えた小説を書くうえで、山田詠美が参照したと思われる、庄司薫『赤頭巾ちゃん気をつけて』の有名な冒頭、
「ぼくは時々、世界中の電話という電話は、みんな母親という女性たちのお膝の上かなんかにのっているのじゃないかと思うことがある。特に女友達にかける時なんかがそうで、どういうわけか、必ず「ママ」が出てくるのだ。もちろんぼくには(どなるわけじゃないが)やましいところはないし、出てくる母親たちに悪気があるわけでもない。それどころか彼女たちは、(キャラメルはくれないまでも)まるで巨大なシャンパンのびんみたいに好意に溢れていて、まごまごしているとぼくを頭から泡だらけにしてしまうほどだ。特に最近はいけない。」
の現代口語性とも似ていない。私には、より前の時代の、ある日本のモラリストが連想されてならない。
「太宰は、M・C、マイ・コメジアン、を自称しながら、どうしても、コメジアンに、なりきることが、できなかった。[…]『父』だの『桜桃』だの、苦しいよ。あれを人に見せちゃア、いけないんだ。あれはフツカヨイの中だけにあり、フツカヨイの中で処理してしまわなければいけない性質のものだ。フツカヨイの、もしくは、フツカヨイ的の、自責や追懐の苦しさ、切なさを、文学の問題にしてもいけないし、人生の問題にしてもいけない。」
引用したのは、坂口安吾が太宰治の自死に際し書いた「不良少年とキリスト」である。「生活」をキータームに、現実から乖離した戦中戦後の政治や文化を撃った安吾の徹底した散文精神は、『ぼくは勉強ができない』にも受け継がれている。いわば、山田詠美は「いい顔」という感性をキータームに硬直した「勉強」という制度を撃っている、というべきか。
作品の前半部に注目してみよう。最初の3章では、対象を変えながら、実感に基づかない概念や思考が批判されている。第1章「ぼくは勉強ができない」では、批判されるのは小学校担任の形式的な民主主義と、級友・脇山の成績を上げるためだけに勉強し秀美を見下す姿勢だ。第2章「あなたの高尚な悩み」では、サッカー部・植草の「高尚」な哲学の実態が、彼をフッた礼子から「何も考えてないのよ」(p.46)と暴露される。第3章「雑音の順位」では、「飛行機の音がうるさい」ことから基地撤廃を目指して政治家になろうとしたはずの後藤が、ごみ捨て場の惨状を目にしてエコロジー研究へと自分の「順位」を簡単に変えてしまうさまが滑稽に描かれる。「真善美」という価値の古典的な三分法になぞらえれば、第2章で植草が追究する「真」、第3章で後藤が実現しようとする「善」は、いずれも感性に基づく「美」に敗北する形になっている。山田詠「美」の描く時田秀「美」の思想と行動を、綿矢りさが「美学の教科書」として読んでいたという先ほどの引用は、正鵠を射抜いていると言うべきか。(そう考えると、秀美の女友達の中で最も逸脱行動を取り停学を食らう登場人物が「真理」と命名されているのも意義深く感じられる。)
上に紹介したいずれのエピソードも、抽象的な概念や思想が具体的な感覚に比較されて敗北する、という構成になっている所に、作品を貫く散文的精神が表れている。以下、類似の箇所を引用する。(下線は引用者)
「脇山、恋って知ってるか。勉強よか、ずっと楽しいんだぜ。」(p.33)
「気分が悪くなってる間ってね、なんにも考えられなくなるの。すごく利己的な自分に気付くのよ。優しさとか思いやりとか、まったく役に立たないのよ。世界情勢がどうなるとか、環境保護が叫ばれてるとか、そういうことが、意味をなさなくなっちゃう。あー、気持ち悪い、吐きそう。それが自分のすべてになっちゃうの。」(P.49)
「空腹と虚無という二つの言葉には、同じような意味合いを持ちながら、象と蟻くらいの隔りがある。後者は常に前者に踏みつぶされる可能性を持っているのだ。」(p.53)
「体がなきゃ、頭だってなくなっちゃうのよ。」(p.55)
「あんな痛みすら、こらえられなくて、何が、虚無だ、傷心だ。」(p.60)
「ぼくは、腕組みをして、宿酔に苦しむ彼女を見詰めた。うーん、やっぱり。頭痛は高尚な悩みは凌駕する。」(p.60)
「『どうして、このクラスって、こうなんだろ。おれが政治家になるって宣言したことが、なんだって、隣のセックスの話になっちゃうんだよ』/『だって、おれにとっちゃ、隣のセックスの方がうるせえんだもん。』」(p.68)
さて、感覚を重んじるこの作品の中でも繰り返し登場するのが、「痛み」のモチーフだ。植山はふだんカミュの不条理哲学に傾倒し虚無を気取っているが、踝の骨を折った痛みのせいですべてをかなぐり捨てて「足が痛いんだよお!!」(p.59)と叫ぶほかなくなる。(この点でも、「もう十日、歯がいたい。」と書き出して「学問は、限度の発見だ。私は、そのために戦う。」と結ぶ「不良少年とキリスト」の坂口安吾と共振を見せている!)
ウィトゲンシュタインは『哲学探究』(1953)のある箇所で、
「この男は痛みを感じているという私の確信が、2×2=4であるという確信よりも確実性において劣るであろうか。―それでは最初のも数学的な確かさだというのか。―『数学的な確かさ』は心理学的な概念ではない。確かさの種類は言語ゲームの種類である。」(『哲学探究』第二部十一章)
と書いている。「痛み」はここで、「自分が自分である」ことを確信する根拠として重要な位置を与えられている。そして、最初は脇山が傷つき植草が痛がるさまを諷刺的に見ていた秀美は、真理の爪の手入れを見て自分も痛みを感じ(「ぼくは、自分の爪にまで痛みが伝わるように感じる。」p.91)、自ら脳震盪を起こし(p.100)、片山の飛び降り自殺、祖父の昏倒、などを契機に、他者の痛みを感じながら自分のこれからの人生に思いを馳せるようになる。
そして最後には、再び痛みをありありと感じながら、一瞬一瞬を心に刻み付けるように走るのだ。
「ぼくは、ここで、確かに勉強をしていた、と今になって思う。[…]汗が目に入って痛い。しかし、それが痛みだけではないことを、今、ぼくは、走りながら悟って行く。」(p.189、下線引用者)
ここで『ぼくは勉強ができない』は、通過儀礼と成長の物語としての姿を見せる。
3. 秀美と外界との「隙間」、そして女たちの「ひらがな」的認識
『ぼくは勉強ができない』は、「ぼくは、ぼくなりの価値判断の基準を作っていかなくてはならない」(p.125)とある時目覚めた秀美が、それを自分の手で完成するために「勉強」をやり直そうとする話、と要約できる。
しかし、上の決意にはすぐ後に「その基準に、世間一般の定義を持ち込むようなちゃちなことを、ぼくは、決してしたくない」(p.126)と留保を付けなくてはならないほど、秀美と「世間」=外界とのギャップは深刻だ。本論第1節で指摘したように、山田詠美は主人公や語り手を他者の目から見た姿を描くのに長けた作家だが、そのことは当人の認識と外界とのギャップを読者に意識させる。デビュー作『ベッドタイムアイズ』(1985)冒頭から、山田詠美の作家性は一貫している。
「スプーンは私をかわいがるのがとてもうまい。ただし、それは私の体を、であって、心では決して、ない。私もスプーンに抱かれる事は出来るのに抱いてあげる事が出来ない。何度も試みたにもかかわらず。他の人は、どのようにして、この隙間を埋めているのか私は知りたかった。」(強調引用者)
『ぼくは勉強ができない』第6章「時差ぼけ回復」では、この「隙間」が「時差ぼけ」として描かれている。「時差の調整が出来ない一生を送った」と想像の中で語れる片山。風邪から回復することで「健全な身体」に復帰し、自分の時差を調整した秀美だったが、続く第7章「賢者の皮むき」で、今度は自意識という「皮」(「人に対する媚ではなく、自分自身に対する媚」(p.168))の存在を意識してしまう。
「考えてみれば、世の中のすべてのものには皮がある。まわりから覆われ、内側から押し上げられて出来上がる澱のような皮だ。その存在に気づかない人もいる。ぼくは、今、自分のそれに気付いて慌てている。皮剥き器をくれ。けれども、ぼくは、それを手にすることが、まだ、出来ない。山野舞子を嫌いだと口にしなくなった時、ぼくは、それを手にすることが出来るのかもしれない。」(p.169-170、強調引用者)
遅ればせて、読者は第5章「〇をつけよ」で、秀美が「コンドーム」を落として佐藤先生に怒られる、というエピソードの意味に気づく。自らの「皮」=自意識を指摘されて逆上してしまった秀美は、まだ外界との調整が済んでいなかったのだ。第7章は、連作短編形式を取るこの作品には珍しく問題が何も解決しないまま終わり、そして第8章「ぼくは勉強ができる」の冒頭での秀美は、進路選択の問題もあり「焦燥」に陥っている。恋人の桃子は、「大きな服を着せられた子供がむずかるようなもの」(p.175)と、的確に秀美の様子を形容している。端的に言えば、秀美は自分に合った「ファッション」を着られていない、不調和な状態にいる。
一人称小説の語り手としての秀美は、読者に植え付けようとしている颯爽たるイメージとは異なり、実はじくじくと不調和に苦しむ奴なのだ。しかし彼の周りにはいつも女たちが現れ、外界との調和を取り戻してくれる。十八世紀文学の正統な後継者として、山田詠美の小説では女性の方が世界を「即物的に」捉えられる傾向が強い。例えば、初期作品の一つ「ジェシーの背骨」(1986)のラスト、
「バルコニーから部屋に戻る時、今度はココが後ろからジェシーの背中を押してやる。彼の体は痩せていて、小さな骨で組まれた背骨が彼女の手の平に当たる。それは、憎しみでもなければ、愛でもない、ただの人間の骨である事を、ココは今度こそ感じ取っていた。」(p.314、下線引用者)
など、ココが観念抜きに背骨をただの背骨として、ジェシーをただの少年として認識できた時に、この小説は一応のハッピーエンドを迎えることになる。(『ぼくは勉強ができない』に「真理」という名の女性がいたことをもう一度思い出してほしい。)
そして、『僕は勉強ができない』における女性たちの認識は、小説内では「漢字優位的な世界」をぶち壊す「ひらがな優位的な論理」として、秀美の前に立ち現れる。
「『私、勉強しか取り得のない男の人って、やっぱ苦手みたい。つまんないんだもん。』
こんなにも呆気なく自分を否定されたら、どういう気分だろう。しかも、こんなに軽い言葉で。だって、つまんないんだもん。その上に、どのような讃辞を付け加えても補うことは不可能である。」(p.37、強調引用者)
下線部にあるように、秀美が真理の言葉を再引用して(しかも一部改変して)なくもがなの解説を付け加えているさまは、秀美がこの「つまんないんだもん。」の破壊力を知っていることの証である。そして、真理と自分を同化させつつも、この「ひらがな優位的な論理」を心の底では恐れ、震撼していることの。他の例も見てみよう。次の話者は黒川礼子である。言わずもがなのことだが、漢字は表意文字であるが、表意文字のひらがなは一切を音に還元し「意味」をはぎ取る暴力性を持つ。
「ねえ、黒川さん、虚無なんて言葉を普通に使ったことある?」
「きょむ?」
「虚無だよ。からっぽのことだよ。」
「ああ。時田くんの口から出ると、食べ物の種類みたいに聞こえるわね。使わないわ。それは、日常語じゃないわ。」(p.46、下線引用者)
「あいつ意味をなさない哲学的なことばっか言ってさ、自分だって、物も食べれば、くそもするのに」
「くそ?!」(略)
「じゃ、なんて言えばいいのよ」
「排泄物とか、さ」
「ふん。げろのことを吐瀉物とか呼ぶタイプよ。」(p.50、下線引用者)
そして恋人の桃子。ノックに返事がなかった日のことを、秀美は彼の語彙の中でできるだけ「即物的」に聞くが、彼女の返答はそれを超えている。二人の感覚の違いが、表記の違いで見事に表現されている。
「『ごめんね、秀美くん。あの晩、私、男の人といた』
『寝てたの?』
何という即物的な質問だろう。ぼくは、他の言葉が見つからずに、そんなことを尋ねた。けれど、彼女は、もっと、即物的に言葉を返した。
『してたの』」(p.78、下線引用者)
しかし桃子は後に、山野舞子とのやり取りを経て「ぼくのおかしな自意識も削り取ることができたら良いのに」とまた小難しいことを考え始めた秀美を、「いいじゃないの、そんなに、じたばたしなくたって」とひらがなで受け容れる人物だ。つまり、秀美は「ひらがな」によって「あるがままの外界」を認識させられ、「ひらがな」によって「あるがままの自分」を受容される。そのプロセスを通して、外界との調和を取り戻していく。
それでは、秀美自身の言語使用はどうか。第2章では、骨折した植草をからかうために「きょむとたいはいとあいでんてぃてぃとしょうしんふじょうりなんでも来いだ」(p.59)などとひらがなで並べるが、これには漢語を振り回す植草への諷刺的な意図しかない。むしろ秀美は、佐藤先生を激昂させことになる「それは、ぼくのプライバシーです」(p.118)のカタカナに見られるように、抽象的な語を使いたがる側にいると読むこともできる。第1章でやたら言う「いい顔」も、そのような無理解な人によって振り回される傾向のある、一見具体性を装っただけの語ではないのか(80年代に一世を風靡したコピーライターの「おいしい生活。」というコピーが、現在では最も陳腐に響くように!)。秀美の本質は、真理との会話で「いいけどさ、あんたと寝るのは絶対嫌よ」への返事が「何故、そんなにまで吝嗇なんだ」(p.34)であることに、しかも「けち」ではなくわざわざ「りんしょく」と音読みのルビまで振られていることに、表現されている。(パフォーマンスを離れるとつい古い言い回しを使ってしまうような理屈っぽさは、秀美が『赤頭巾ちゃん気をつけて』の薫くんから継承したものだろうか。)
そんな秀美がありありと外界を認識するのは、冒頭に紹介した山野舞子とのやりとり以降のことだ。実際この時、秀美は「今の、こたえた」(p.167)と平易な語で感想を返しており、自分自身と外界との間の「皮」を意識するというストーリー展開と対応している。
しかし、秀美が物語が終わっても外界との調和にもがき続けるだろうことは、タイトルと本文との「隙間」として暗示されている。タイトル『ぼくは勉強ができない』や1章・8章の章題がひらがな表記なのに対し、秀美の語りを通した本文では、勉強が「できる/できない」は「ぼくは勉強が出来ない」(p.38)「勉強が出来るようになりたい」(p.191)と、常に漢字で表記されているのだ!小説の見事なデザインに、舌を巻かざるを得ない。
4. まとめ 時田秀美の「勉強」
「哲学を軽蔑することこそ、真に哲学することである。」 ―ブレーズ・パスカル『パンセ』
社会学者の土井隆義は、1980年代中曽根政権下における教育の「個性重視の原則」への方針転換について、「教師と生徒の間の役割演技の関係が崩壊し、また両者のヒエラルキカルな関係も解体されることで、『先生はそう考えるかもしれないが、自分はこう考える』といった発想が受容されるようになっていく。その結果、個々の生徒の立ち振る舞いも、教師との役割関係によってではなく、親疎関係によって規定されるものへと変質していく。生徒にとって『好きな先生』とは、『教え方がうまい先生』である以前に、まずは『自分と気が合う先生』となった」と指摘している(「個性化教育のアイロニー」、斎藤美奈子+成田龍一編著『1980年代』河出ブックス、2016年.)。
『ぼくは勉強ができない』の中の桜井先生と佐藤先生に対する秀美の評価の差を見ると、いかにこの小説が(結果的に)時代の変化を捉えているかわかる。また土井氏は、この時代に端を発した個性化教育が現代にも及ぼしている影響として、生徒間の人間関係もフラット化したため、「今日、ほぼすべての子どもから同意を得られやすい評価軸は、いわゆるコミュニケーション能力だけだろう。しかし、その能力の有無は、学校の中ではまさに友だちの数が多いか少ないかで測られることになる」(同上)とも述べている。
『ぼくは勉強ができない』は一見、秀美の視点から従来の「勉強」概念を否定してこの「コミュニケーション能力」(および、今日の「生きる力」)に軍配を上げているかに見える。しかし、そうではない。引用したパスカルの言葉が哲学の否定ではなく可能性の示唆であるように、秀美も「勉強」という愚直な営みを、第8章「ぼくは勉強ができる」では肯定していくことになる。真理の口からも、秀美が「人とは違う勉強家になる」(p.187)ことが予告される。秀美にとって「勉強」とは、外界と自分の「隙間」を調整することで、人生をより生きていくためのメディアなのだ。
ピーコとの対談『ファッション・ファッショ』シリーズを読むと、作家山田詠美の「ファッション」概念は秀美の「勉強」と相同的なものであることがわかる。最後にグラウンドを走っている秀美の身体には、サッカー部のユニフォームが気持ちよくフィットしていた(p.189)。高校を卒業することで制服(=ユニフォーム)を脱がなければならない秀美は、どんな勉強をし、どんなファッションを着こなしていくのだろうか。