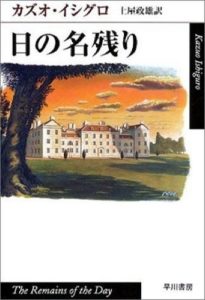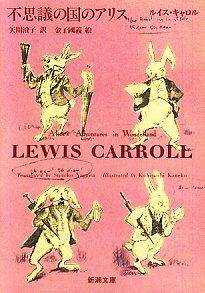概要
『オメラスから歩み去る人々』は、1973年に発表されアーシュラ・クローバー・ル=グウィンのSF短編小説。ル=グウィンは『闇の左手』、『所有せざる人々』、『ゲド戦記』などで有名なアメリカのSFファンタジー作家。ハヤカワ文庫の『風の十二方位』に収録されている。
1974年、世界的なSF作品賞のヒューゴ賞を受賞。オメラスとは、本作に登場する架空の理想郷のことである。
オメラスの住人がその理想郷の成立にひとりの犠牲が必要と知って、そこから歩み去る人々を描いた物語。
哲学的な小説はほかにミラン・クンデラ『存在の耐えられない軽さ』、カミュ『異邦人』、カフカ『変身』、サルトル『嘔吐』がある。
海外文学はほかにサン=テグジュペリ『星の王子さま』、フロベール『ボヴァリー夫人』などがある。
本作は「海外小説のおすすめ有名文学」で紹介している。
あらすじ・ネタバレ・内容
あるところにオメラスという、平和で豊かで幸せなユートピアがあった。オメラスには飢えも差別も苦しみもない、誰もが羨むとても素晴らしい国なのである。
だが、オメラスには一つだけ汚点となるような秘密があった。オメラスの地下牢には、痩せ細り汚物に塗れた一人の子供が、鎖につながれ監禁されているというのだ。そしてこの子供の犠牲こそが、オメラスの平穏を成り立たせているという。この子供を監禁から解放することはおろか、気をかける、綺麗にするという些細な行為だけで、オメラスという理想郷は終焉を迎えてしまう。
驚くべきことに、オメラスの住人は誰もがこの事実を知っている。成長し犠牲の意味を理解できると判断されたとき、オメラスの若者は監禁されている子供のことを知らされるのである。
この公然の秘密を打ち明けられると、オメラスの住人は誰もが苦しみときに憤慨する。だが、オメラスの住人は何もすることができない。この子供を助けることでオメラスを危機に陥ることは、絶対に避けねばならないからだ。
したがってオメラスの住人は、囚われの子は知能指数が劣っているため状況を理解していない、あるいは解放してもすぐ死んでしまう、ましてや解放しても幸せになることはない、と自分に言い聞かせ犠牲を容認するのである。
だが稀にこの犠牲の存在を知らされた後に、オメラスから姿を消す人々がいる。その人たちはこの事実を知った直後に、あるいは何年も経ったある日に、周囲に何も告げずオメラスから静かに去っていく。この人たちがどこに向かったかは誰も知らない。
だが人々は、西かあるいは北へと進む。その人たちはまるで行くべき場所を知っているかのように、しっかりとした足取りで歩み去っていくのである。
\30日間無料!解約も簡単!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
解説
オメラスとは、犠牲によって成り立つユートピア
オメラスとは、飢饉や争いが存在しない美しさや優雅さに溢れる架空の理想郷のことである。本作で語られるのは、そんな理想郷オメラスに住まう人々の罪と決断の物語である。
大っぴらには語られることのないある秘密がオメラスには存在している。盲目で痩せ細り汚物にまみれた少年が、オメラスの地下牢に監禁されているのだ。オメラスに飾る優雅さと美しさは、この少年の犠牲によって成り立っている。言い換えると、理想郷の存在は犠牲無くしてはあり得ない。理想郷の表層を覆う美しさは、オメラスの地下牢にいる醜い犠牲を下層に隠している。
サンデル著『これからの「正義」の話をしよう』でも取り上げられた道徳の問題
したがって本作のテーマは、「すべての人々の利益のためにひとりの犠牲は許されるのか」と言える。これは現代においても道徳哲学の分野で議論にあがり、ベストセラーのマイケル・サンデル著『これからの「正義」の話をしよう』でも本作が取り上げられている(p.56)。
サンデルは最大多数の最大幸福を目指す功利主義の立場から、この問題に取り掛かる。功利主義に従えば、1人の犠牲による不利益と住民の幸福の総和が比較され、幸福が最大になるような状況を是とすることになる。驚くべきことに、本作ではオメラスの地下牢の犠牲者は自らの不幸を認知できないと述べられている。そうであるならば、功利主義は犠牲者の存在は容認するべきと判断するだろう。
だが、功利主義の立場から犠牲者を容認することは、道徳的・倫理的に許されることだろうか。犠牲者の存在は人の心をざわつかせないだろうか。本書で問われているのは、道徳と倫理の普遍的な問題なのだ。
オメラスの地下牢とは?犠牲を受けいれた極限の状態で何をすべきか
物語の途中で明かされるのは、オメラスの地下牢に囚われた少年を救うことはできないということだ。どういうことだろうか。
まず先ほど言及したように、少年は知性が弱く不幸を把握していない。汚物にまみれていようと痩せ細っていようと、少年はそのことを認識していない。第二に、少年を救いだしたところでずっと地下にいたために死んでしまう可能性があるという。彼を救いだすことは、本当の意味での救済に繋がらないかもしれないのだ。最後に、もし子供を救いだすとするとオメラスという理想郷は崩壊するということが再確認される。しかもこれで犠牲になるのはオメラスの住人だけではない。救いだしたはずの犠牲者も含めて不幸が訪れるのである。
したがって『オメラスから歩み去る人々』は、「ユートピアの存在の条件である犠牲者の存在を知り、さらに助けることができないと知ったとき、あなたは何をするのか?」という極限の問いも提起している。
本書の回答は「何もすることはできない」だ。だが、それにもかかわらず「オメラスから歩み去る人々」がいるという。それは自分の無力を知ったとき、あるいは、社会を変えることができないと悟ったとき、犠牲をただ受け入れるということをしない人々のことである。
これは倫理的な行動である。去るということは、諦めではなく、無言の抵抗であり、犠牲のシステムをもつオメラスには属さないという意思表示である。さらに、去る人々は「行くべき先を知っている」という。もしかしたら、オメラスの外部から犠牲を救済するすべを考えだすかもしれないのだ。
この問題は最後に「天皇」にひきつけて考えてみることにしよう。
\30日間無料!解約も簡単!/
→Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
考察
犠牲と理想郷ー「オメラス」システムの作り方
政治哲学者のカール・シュミットは著書『政治的なものの概念』で、「政治的なもの」という概念を規定するのは友敵理論だと提唱した。「政治的なもの」は友と敵を分別し敵を滅ぼすことを目的とする。同じ考えを持つ友から成る集団は、敵を認定することで結束することができるのだ。例をあげれば、クラス対抗リレー、右翼vs左翼、フェミニズムvsアンチフィミニズムと枚挙に遑がない。
この理論を極限まで推し進めてみよう。敵の数を一人また一人と減らしてみるのだ。そして敵と認定できる最小単位、つまり一人まで減らしたとき、一人の犠牲から成り立つユートピアとしてのオメラスが誕生する。
したがって地下牢に繋がれた子供を助けると、理想郷が崩壊するという設定は論理的にも正しい。敵や外部のないところに平安はありえない。オメラスの国民はそのことがわかっているからこそ、子供を救うことはできないのである。だからここで問われているのは善意や憐みといった倫理や感情ではない。変えることも救うこともできない強固な構造を前にしたときどのように行動すべきか、それが問われているのだ。
オメラスから歩み去る人々と日本の天皇
犠牲者によって理想郷が成り立つという「オメラス」システムは、実は普遍的にみられる現象ではないだろうか。古のイエス・キリストから現代のいじめられっ子まで、共同体の安定のために犠牲が強いられてきた。国民的アニメ作家で『秒速5センチメートル』や『君の名は。』で有名な新海誠の『天気の子』でも、ある意味で「オメラス」システムを主軸に置いている。『天気の子』の設定では、日本が存続できているのは陽菜という犠牲があるからで、帆高が陽菜を救おうとすると東京は水没してしまう。
これを日本固有の問題にひきつけて考えれば、そこには「天皇」が浮かび上がる。何故なら天皇は象徴とされていて、自由も人権も存在しないからだ。天皇はオメラスの地下牢に繋がれた子供であり、天皇の犠牲のもとに日本という国家が成り立っている。
小説家の三島由紀夫は、天皇は国民の犠牲になるべきだと主張した。天皇はオメラスの地下牢に閉じ込められた犠牲者のように耐え忍べというのである。この意見に私が賛成することはないが、天皇の問題を真摯に考えた三島なりの回答なのだろう。
オメラスと違って日本では天皇について語ることは禁止されていない。それだからか、人権の観点から天皇制をなくすべきと主張する人も多い。しかし何千年も天皇制が廃止されていないことからもわかるように、天皇制の即時撤廃は現実的には非常に難しいだろう。そうであるならば、人権の観点からなどと主張する天皇制廃止論者は、地下牢に繋がれた子供から目を背けたオメラスの住人たちとなんら変わるところはない。
『オメラスから歩み去る人々』が問いかけるのは犠牲を知りながら理想郷に留まり続ける人々に対してだ。「オメラス」システムは壊れることはない。犠牲者は救われないし理想郷は崩壊しない。そのことを知ってなお君達は何も行動しないのか、と。
果たしてこの国に、オメラスから歩み去った人々のように、何も言わず行く先を見据えながら歩み去る人々はどれだけいるのだろうか。
→小説家、シナリオライターになりたいならこちら|アミューズメントメディア総合学院
関連作品
参考文献
アーシュラ・K・ル=グウィン『風の十二方位』小尾芙佐共訳、ハヤカワ文庫SF、1980
マイケル・サンデル『これからの「正義」の話をしよう』鬼澤忍訳、早川書房、2010