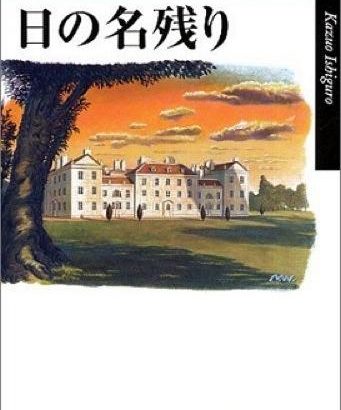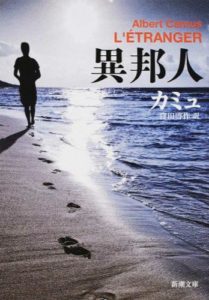概要
『日の名残り』は、1989年に刊行されたカズオ・イシグロの長編小説。原題はThe Remains of the Day。ブッカー賞を受賞。2017年にイシグロはノーベル文学賞を受賞した。1993年、ジェームズ・アイヴォリー監督が実写映画化。
語り手であるスティーブンスは、嘘や記憶違いがあるまま事実のように過去を回想するので、「信用できない語り手」と言われている。
執事のスティーブンスが第二次世界大戦前の主人ダーリントン卿に仕えいてた過去を回想しながら、当時の同僚であった女中頭ミス・ケントンに会いに行く物語。
文学はほかにクンデラ『存在の耐えられない軽さ』、サルトル『嘔吐』、キャロル『不思議の国のアリス』、デフォー『ロビンソン・クルーソー』、ポー『黒猫』、チャペック『白い病』などがおすすめである。
本作は「イギリス文学のおすすめ小説」と「海外小説のおすすめ有名文学」で紹介している。
\映画はU-NEXTで観れる!31日間無料!/
→U-NEXT(ユーネクスト)とは?料金・サービス内容・注意点を解説
登場人物
スティーブンス:ダーリントンホールで奉仕する執事。第二次世界大戦前はダーリントン卿に、1956年現在は新たな主人であるファラディ氏に仕えている。
ダーリントン卿:ダーリントンホールの前主人。第一次世界大戦後のドイツに対するイギリスの対応に不満を抱き、ドイツ宥和政策のために尽力する。そのためナチスに接近し、第二次世界大戦後は汚名を被ることになる。
ミス・ケントン:女中頭。優秀。スティーブンスに物怖じせず意見をする。スティーブンスに好意を持つも、1936年に退職しベンと結婚をする。
ファラディ:現主人。アメリカ人。ジョーク好き。
名言
私にとりましては、あの夜は極めて厳しい試練でした。しかし、あの夜のどの一時点をとりましても、私はみずからの「地位にふさわしい品格」を保ちつづけたと、これは自信をもって申し上げられます。おそらく、あの夜の私なら、父も誇りに思ってくれたことでしょう。そして、私が注視しつづけた、ホールの向こうのドアの内側では——私がたったいま任務を遂行してきた部屋の中では——ヨーロッパで最も大きな影響力を持つ方々が、大陸の運命について意見を交わしておられたのです。あの瞬間、私がこの世界という「車輪」の中心にいたことを誰が疑いえましょう。そして、あの夜の私をうらやまぬ執事がどこにおりましょうか。(p.329)
人生、楽しまなくっちゃ。夕方が一日でいちばんいい時間なんだ。脚を伸ばして、のんびりするのさ。夕方がいちばんいい。わしはそう思う。みんなにも尋ねてごらんよ。夕方が一日で一番いい時間だって言うよ(p.350)
あらすじ
1956年、ダーリントンホールでアメリカ人の主人ファラディ氏に仕える執事スティーブンスは、深刻な人手不足に悩んでいた。ダーリントン卿の死後、優秀なスタッフが辞めてしまったためである。
ある日、第二次世界大戦以前に同僚であったミス・ケントンから手紙をもらう。その手紙からは夫との関係が良好ではないこと、元の職場であるダーリントンホールに戻りたがっていることとが読み取れた。ミス・ケントンに信頼を置くスティーブンスは、新たなスタッフに彼女を迎えるべく、イギリス西岸のクリーヴトンへと彼女に会うために旅にでる。
旅先で現地の住人と交流しながら、1920年代から1930年代の当時を回想する。ダーリントン卿は第一次世界大戦の敗戦国であるドイツに対するイギリスの対応に不満を持ち、ドイツにたいして救済をすべきだと考えていた。ダーリントン卿に協力的な各国の重要人物がダーリントンホールに集まり、国際的な会合が繰り返されるようになる。
要人の奉仕に精を尽くすスティーブンスと、人員補充のために雇われた女中頭のミス・ケントンは、互いに信頼をえて仕事における良きパートナーとなる。同じく執事であるスティーブンスの父の死、イギリスの将来を決するような重要な会議、新たな女中の教育など、数多くの出来事をともに経験する。
1956年の道中、このようなことを回想しながら旅を続ける。1956年においてはダーリントン卿は既に亡くなっており、世間からはナチに親和的な悪名高い紳士と噂されていた。車の故障や紳士と間違われるといったハプニングに見舞われる。
ダーリントン卿は紳士であるが故に、ナチスドイツの策略に巻き込まれていく。イギリスとドイツの首相の秘密裏の会合が行われた夜、スティーブンスはダーリントン卿の名付け子であるカーディナルに、今何が起こっているか知らないのかと問い詰められる。知らないと答えたスティーブンスは、次第に執事として職務を全うしたことで満足を感じる。
再び1956年。ミス・ケントンと再開したスティーブンスは、昔話に花を咲かせ、愉快な時間を過ごす。しかしミス・ケントンにはダーリントンホールに戻る意思は全くなかった。亡くなったダーリントン卿、失われたイギリスの伝統、違う未来のあり得たミス・ケントンとの関係に想いを馳せ涙を流す。
やがて前向きに生きることを決意し、手始めに主人のファラディ氏を笑わせるために、ジョークを本格的に練習しようと思うのだった。
\30日間無料!解約も簡単!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
解説
信用できない語り手と物語構成
『日の名残り』は、『遠い山なみの光』(1982年)と『浮世の画家』(1986年)の次に発表された、カズオ・イシグロの三作目にあたる長編小説である。彼は本作で弱冠35歳にしてイギリスで最も名誉のあるブッカー賞を受賞し、作家としての地位を盤石なものにした。その勢いは止まることを知らず『わたしを離さないで』(2005年)や『忘れられた巨人』(2015年)などの名作を世に送り出したあと、2017年にはノーベル文学賞を受賞し歴史に名を刻むことになった。
本作は、第二次世界大戦後の1956年の地点から、第一世界大戦と第二次世界大戦前の間の1920ー1930年代を回想するという物語である。アメリカ人の主人ファラディ氏に仕えていた執事スティーブンスは、元同僚のミス・ケントンから手紙を受け取ることで、彼女に会いに短い旅に出かける、というのが1956年の現在における物語の筋で、その旅の先々で過去の回想がスティーブンスから語られる。
語り手のスティーブンスは、俗にいう「信用できない語り手」で、彼の回想は時に一貫性がなく無意識に記憶を改ざんしている節がある。特に、ミス・ケントンとの関係においては、スティーブンスの都合が良いように記憶が変更されている。例えば、記憶されていたはずのミス・ケントンの涙という印象的な情景は、二回ほど思い出されるのだが、その都度異なった理由づけがなされている。一度目は叔母の死、二度目はスティーブンスのせいといった具合に。このような「語り」は、今村夏子の『星の子』やフィリップス監督の『ジョーカー』など、他の作品にも時々登場する。
1956年の「現在」と、ダーリントン卿に仕えた1920年代から1930年代という「過去」、それを繋ぐ執事スティーブンスによる「回想」が、本作の大雑把な構成になっている。加えて、舞台が20年隔たっていること、その間に世界規模で価値観を揺るがす大事件である第二次世界大戦が横たわっていることは、本作にとって重要であることも押さえておこう。
現在のモチーフ——旅、風景、品格、ジョーク、コミュニケーション
構成は単純なのだが、いくつもの要素が重層的に絡み合うことで、物語に独特の深さと哀愁が漂っている。「現在」に注目すれば、「旅」というテーマが物語を貫いていることがわかる。スティーブンスは執事であると同時にその副産物として「留まる人」でもあった。ダーリントンホールで働いていた彼は、街に出掛ける以外に外の世界に触れることがない。それでいて彼が世界を知っていると満足できたのは、ダーリントンホールに世界各国の要人が日夜重要な会合を開いていたからである。「あの瞬間、私がこの世界という「車輪」の中心にいたことを誰が疑い得ましょう。そして、あの夜の私をうらやまぬ執事がどこにおりましょうか」(329)。ダーリントン卿の失墜によって、世界の中心であることという確信が失われた。彼は世界を知るために本来の「旅」にでるのである。
そこからいくつものテーマを読み込むことができる。イギリスの「風景」、貴族ではなく「庶民」との交流、執事としての「品格」、読者には示されないミス・ケントンからの手紙の「誤読」。さらに「旅」が「西部」に向かっていたことから、東部=ドイツからの逃避と西部=夕暮れの渇望を読み込むこともできるかもしれない。
あるいは、三箇所にあまりにも綺麗に配置された「ジョーク」に注目することもできよう。「旅」の前に諦めかけていた「ジョーク」は、中盤では恥ずかしさに、そして終盤では練習するものへと変化していた。スティーブンスの「旅」の終わりに見出されたのは、旅=人生の疲れと後悔であると同時に「ジョーク」に対する態度の変更でもある。「ジョーク」は「コミュニケーション」の問題とも結びついている。ダーリントン卿との繋がりはお互いの「信頼」であったのだが、アメリカ人のファラディ氏に対しては「信頼」はおろか「忠誠心」すらない。だからこそ、繋がるために求められているのは「コミュニケーション」であり、それはスティーブンスが最も苦手とするものでもある。
回想の場面で明らかになるように、スティーブンスとミス・ケントンとの「コミュニケーション」はお世辞にも上手くいっているとは言い難い。それもそのはず、彼の人との関わり方は「信頼」であり、裏返していえば、言わなくても通じるという、ある種の相互依存であった。スティーブンスは「コミュニケーション」とどう向き合うのか、それも一つの主題である。
\30日間無料!解約も簡単!/
→Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
考察・感想
執事における品格と内面
「過去」に目を向ければ、ダーリントン卿とミス・ケントンとの関係が焦点化される。スティーブンスは、何を誇り、何を守りたかったのか。「忠誠心」と「品格」は特に重要である。貴族や紳士の価値の評価軸は存在する一方で、執事の価値の判断基準は存在しない。この価値不定の存在である「執事」という立場に、スティーブンスは「品格」と「忠誠心」という、曖昧で決断的で相対的な価値基準を導入する。
これは分別に裏付けられた忠誠心です。そのように忠誠を誓うことのどこに、品格に欠けるところがありましょうか?それは、不可避の真実を真実として受け止めることにほかなりますまい。私どもが世界の大問題を理解できる立場に立つことは、絶対にありえないのです。とすれば、私どもがたどりうる最善の道は、賢く高潔であるとみずからが判断した雇主に全幅の信頼を寄せ、能力のかぎりその雇主に尽くすことではありますまいか。(290)
雇主の善悪を判断することを中止して「信頼」し「尽くすこと」、そのあまりに行為の次元を重視したこの態度こそが、執事=内面を持つべきでない存在の評価基準=「品格」を担保するものである。しかし「内面を持つべきでない存在」ということは、「内面がない」ということを意味しない。スティーブンスが抑圧するのは、まさにその「内面」そのものである。そして内面が抑圧されることで、むしろ行為の次元に内面が前景化してくる。結婚を申し込まれた相手に会うというミス・ケントンに、スティーブンスは平静を取り繕うも、ミス・ケントンの指摘「台所で派手な物音をたててみたり、私の部屋の前を何度もばたばたと行き来してみたり、そんなことで私の気持ちを変えようとしておられますの?」(310)によって、スティーブンスの内面が透けて見える、いや、内面が行為に現れているのだ。抑圧の対象と内面の、このあまりのわかりやすさは注目に値する。この小説の読みどころの全てが、「信用できない語り手」の隠れた本心を探偵のように緻密な調査によって暴くことだとしたら、捻りのないこの直線的な答えは何を意味するのだろうか。だが最後まで本心を隠し通したスティーブンスに敬意を払い、彼の本心を明らかにすることはひとまず控えることにしよう。
過去と現在を繋ぐ記憶と老い
そして「回想」という「現在」と「過去」を繋ぐ縦の軸によって、さらにいくつもの重要なモチーフが現れる。その一つが「記憶」であり、それはカズオ・イシグロが小説家人生をかけて探求している深淵の一つでもある。20年間という期間は、記憶を風化させそして美化するのに十分な長さだ。今から20年前のことを思い出してみよう。何もかもがおぼろげで、そして強烈な印象を与えた出来事だけが、都合のいいように作り替えられているはずだ。この現実的な視点から、スティーブンスの「視点」を想像してみると「信用できない語り手」が自然と導かれる。「信用できない語り手」は探偵的視点を促す装置であるというより、平凡な「語り手」が「記憶」と結びついたときに登場する自然な語り手である。「信用できない語り手」は嘘をつくのではない。スティーブンスには見栄は存在しても、騙そうという意図は存在しない。そしてその見栄すらちっぽけに見えるような、「記憶」の不確かさと創造性がここにはある。
もう一つは「老い」の問題がある。偉大な執事であり父でもあるスティーブンス・シニアは、威厳を保ちながらも執事に求められる行動を取れなくなっていった。スティーブンスは回想にあった父の姿に、自らを投影しているのである。「回想」の間に横たわるのは、第二次世界大戦という出来事だと先ほど指摘したのだが、これが意味することは徹底的な「価値の転倒」である。ダーリントン卿は紳士であるが故に、ナチに利用され汚名を被ることになった。1956年現在、ダーリントン卿の名は忘れ去られるどころか嫌悪されるべき相手である。
だがダーリントン卿に奉仕したスティーブンスは、そのことを恥じていることはない。「卿の一生とそのお仕事が、今日、壮大な愚行としか見なされなくなったとしても、それを私の落ち度と呼ぶことは誰にもできますまい。私がみずからの仕事に後悔や恥辱を感じたりしたら、それはまったく非論理的なことのように思われます」(291)。信じていたものが間違った行いをしたとして、信じて尽くした行為を後悔することは非論理的である。そしてこのことはスティーブンスの「品格」の問題に一直線に繋がっている。付け加えると、元主人のダーリントン卿がイギリス人紳士であることと、現主人のファラディ氏がジョーク好きのアメリカ人であることの対立を重視し、回想が古き良きイギリス紳士に向かっていることに重きを置けば、「ノスタルジー」という問題が浮かび上がる。「ノスタルジー」を感じる「旅」の結末が、「アメリカンジョーク」の練習であることは、彼の人生にたいする肯定とみるべきだろうか。
この三つの層、「現在」「過去」「回想」に見られるモチーフや主題に、想いを巡らせることはとてもワクワクすることだ。例えば、「旅」を過去の精算と読み、否定したいダーリントン卿の事実を受け入れる、成長の物語といえるかもしれないし、ダーリントン卿の罪はとっくに受け入れていてそれでもノスタルジーに浸りミス・ケントンにも本心を語ることのできない非成長の物語と主張する場合もあるかもしれない。そもそも「記憶」と「老い」が主題であって、「成長」は問題にすらなっていない、という見方もある。『日の名残り』は未知の部分、いくら読んでも解明できない部分——例えばミス・ケントンに問い質されて思わず隠した恋愛小説は一体何であったのだろうか(237)——を残している。
「The Remains of the Day」の四重の意味
どの解釈も楽しい。だが謎解きや解釈をする前に、『日の名残り』の「名残り」に浸ることをお勧めしたい。「The Remains of the Day」は、1日の終わり、つまり夕方を意味していた。
人生、楽しまなくっちゃ。夕方が一日でいちばんいい時間なんだ。脚を伸ばして、のんびりするのさ。夕方がいちばんいい。わしはそう思う。みんなにも尋ねてごらんよ。夕方が一日で一番いい時間だって言うよ(350)
一日の終わり、それはスティーブンスの残りの人生のことでもある。「老い」を迎えたスティーブンスの残りの日々は、見方を変えれば、人生で「いちばんいい時間だ」。「一日」と「人生」そして「旅」の三重の意味がかけられた「名残り」の場面が、『日の名残り』の終盤つまり小説の「名残り」において登場することで、「The Remains of the Day」の「the Day」は四重の意味になる。作品に浸るところから無理に這い出すことはない。「脚を伸ばして、のんびりするのさ」。時間はある。さあ、「ジョーク」の練習でもして一息つこうではないか。
内面と品格で二重に引き裂かれた執事
スティーブンスに内面はあるのだろうか。ある、が、抑圧されている。それは執事という職業が要請する、一つの規範でもある。
執事の任務は、ご主人様によいサービスを提供することであって、国家の大問題に首を突っ込むことではありません。この基本を忘れてはなりますまい。国家の大問題は、常に私どもの理解を超えたところにあります。(288)
スティーブンスは意見を持つことを放棄する。何か発言するにしても、あくまで主人に仕えるという職務においてであり、考えを持つどころか内面すら否定しようと努力しているようにもみえる。ミス・ケントンがスティーブンスが一人で読書をしている部屋を訪れ、何を読んでいるのかを質問してきたあと、彼が思い描くあるべき理想の執事像を明確に示す。
執事であることは、パントマイムの衣装とは違います。ある瞬間に脱ぎ捨て、またつぎの瞬間に身につける。そんなところを、他人に見られてよいものではありません。執事が、執事としての役割を離れてよい状況はただ一つ、自分が完全に一人だけでいるときしかありえません。(239)
彼が内面を見せるのは「完全に一人だけ」になれる個室にいるときだけだった。スティーブンスの語りは、彼の理想の執事像をふまえて読まれなくはならない。つまり、スティーブンスは語り手であるが故に、つねにすでに執事(=内面を見せない)なのである。したがってスティーブンスは回想のなかでも、一人の時間を描くことはない。寝る前に一人の部屋で彼は何を思ったのか、そのことが明らかにされることはない。人である前に執事でなのだ。しかしこの命題は当然ながら、執事である前に人である、という有無を言わせぬ前提によって常に侵食されている。この二つの命題によって彼は二つに、内面と行為の主体に引き裂かれている。内面の次元は、抑圧の対象であり恋と結びつき「威厳」と関わる。行為の次元は、執事の領分であり描かれるものであり「品格」と関わる。
この二重の位相のズレは何をもたらすのか。スティーブンスは行為の水準で執事としての評価を求めた。扉を隔てた向こう側で、ダーリントン卿とイギリス首相とドイツ大使の歴史的な会合が開かれているとき、ダーリントン卿の名付け子で国際情勢を専門とするコラムニストであるカーディナルは、この歴史的談合で何が行われているのかをダスティーブンスに問いかける。「卿がなぜこの三人を集めたか、わかるかい、スティーブンス?いま何が起ころうとしているのか、君にはわかっているのかい?」(319)。スティーブンスはダーリントン卿に絶大な信頼を寄せられていた。真実を述べるなら、答えはイエスだ。しかし彼は執事としてこう答える。「残念ながら、私にはわかりかねます」(320)。スティーブンスとカーディナルのこのやりとりは、手を替え品を替えて繰り出されるカーディナルの問いと、わからないというスティーブンスの答えに終始する。彼は知らないのではない、わからないのだ。別の言い方をすれば、「ダーリントン卿が崖から転げ落ちようとしているのを」(323)止めるという倫理の問題ではなく、行為の次元にある「品格」を守ったのである。カーディナルの猛追を逃げ切り、会合が行われている扉の外で一時間も待ち続けるとき、スティーブンスは「心の奥底から次第に大きな勝利感が湧き上がってきたの」(328)を感じる。
私にとりましては、あの夜は極めて厳しい試練でした。しかし、あの夜のどの一時点をとりましても、私はみずからの「地位にふさわしい品格」を保ちつづけたと、これは自信をもって申し上げられます。おそらく、あの夜の私なら、父も誇りに思ってくれたことでしょう。そして、私が注視しつづけた、ホールの向こうのドアの内側では——私がたったいま任務を遂行してきた部屋の中では——ヨーロッパで最も大きな影響力を持つ方々が、大陸の運命について意見を交わしておられたのです。あの瞬間、私がこの世界という「車輪」の中心にいたことを誰が疑いえましょう。そして、あの夜の私をうらやまぬ執事がどこにおりましょうか。(329)
歴史的で国際的な会合の夜に現れた最大の敵カーディナルは、質問責めという「極めて厳しい試練」を課してきた。だが、それに勝利した。世界の片隅にあるダーリントンホールはあの瞬間、「大陸の運命」が決定されるという事実において、まさに「世界という「車輪」の中心」でであり、スティーブンスは「父も誇りに思」ってくれるような執事として「地位にふさわしい品格」を示したのである。
旅の果て、スティーブンスは泣いているのだ……と。
しかしこれは、信用できない語り手スティーブンスの嘘である。スティーブンスは「極めて厳しい試練」から、このとき同時に進行していたミス・ケントンとの出来事を忘却している。ドアの向こうで行われていたのは会合だけはなかった。もう一つのドアの向こうで「ミス・ケントンが泣いているのだ……と」「確信」(327)したのはスティーブンスであった。「執事人生で成し遂げたこの集大成のように感じられた」(328)のは、ミス・ケントンにも執事の姿を全うして対応できたからだ。カーディナルの質問攻めに耐えただけでなく、ミス・ケントンに内面を悟られることもなかった。そのことが彼に「集大成」と呼びたくなるほどの高揚感をもたらしている。
したがってカーディナルの質問は、スティーブンスにとって二重の意味を持つ。「君は好奇心を刺激されるということがないのかい」(320)。「それなのに少しも好奇心が湧かない?」(320)。「ぼくの言っていることに興味すら覚えないのかい?」(325)。カーディナルは、スティーブンスが壁の向こうで行われている会合の秘密を知りたくないのかと問いかけると同時に、ミス・ケントンと結婚相手の会合に興味がないのかと問いかけている。正確にはカーディナルはそのことを問いかけてはいないのだが、スティーブンスはそう感じている。執事か人間か、スティーブンスは選択を迫られているのだ。その誘惑に打ち勝ちスティーブンスが選び取るのは、人間としての欲求ではなく執事としての品格で、それによって彼は「執事人生で成し遂げたこの集大成」を感じる。スティーブンスはミス・ケントンを失う代わりに、執事としての人生に価値を見出したのだ。
旅の果て、執事としての振る舞いを強いてくるダーリントンホールの磁場から遠く離れた西部のとあるバス停で、スティーブンスはミス・ケントンのあまりにも悲しい言葉を聞いて、「その瞬間、私の心は張り裂けんばかりに痛」(343)む。それでも何も言いだせず、「いまさら時計をあともどりさせることはできません」(344)と続けるスティーブンスに、読者の心も「張り裂けんばかりに痛」い。偶然知り合った見知らぬ男性に手渡されるハンカチは、スティーブンスが壁の向こうにいるミス・ケントンに感じた「確信めいたもの」と同様のざわめきを、読者にも感じさせる。ページの向こう側で、スティーブンスが泣いているのだ……と。スティーブンスと読者は、一日の夕暮れ時に、旅の終わりに、人生のくたびれ時に、読書の終着点に、ようやくあの扉の向こうに感じた確信のありかを発見したのだ。
関連作品

参考文献
カズオ・イシグロ『日の名残り』 土屋政雄訳、ハヤカワepi文庫、2001年