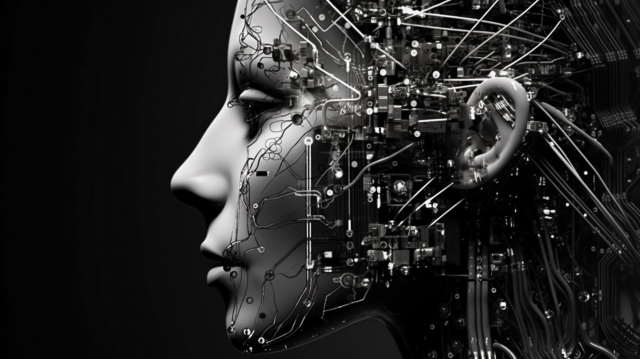概要
「ボッコちゃん」は、1958年に発表された星新一のショートショート。星の代表作の一つであり、最初の短編集の表題でもある。
1963年に英訳され、1977年にはインドやユーゴスラビアにも紹介された。
完全な美人として作られたロボット”ボッコちゃん”と彼女に悲劇的な恋をする男性の物語。
文学はほかに、梨木香歩『西の魔女が死んだ』、森絵都『カラフル』、宮沢賢治「注文の多い料理店」「やまなし」、谷崎潤一郎『春琴抄』、志賀直哉「小僧の神様」、リチャード・バック『かもめのジョナサン』、森見登美彦『夜は短し歩けよ乙女』『四畳半神話大系』、辻村深月『ツナグ』などがある。
おすすめの小説は「日本純文学のおすすめ」で紹介している。
登場人物
ボッコちゃん:マスターによって作られたロボット。完全な美人として作られる。頭は空っぽで、飲む動作しかできない。
マスター:バーの店長。道楽でボッコちゃんを作った。客がボッコちゃんに答えられない質問をすると止めに入る。
青年:ボッコちゃんに恋心を抱く。恋心に応えてくれないボッコちゃんに、毒が入った酒を飲ませようとする。
あらすじ・内容
あるバーのマスターが、完全な美人のロボットを作った。彼は人間のように働くロボットを作ろうとはせず、客を相手してくれるロボットを作り出した。名前はボッコちゃん。
ボッコちゃんはお酒で酔うことはなく、飲んだお酒は回収することができるため儲かった。多くの客がボッコちゃんを気に入り、彼女に話しかけた。
ボッコちゃんは客の言ったことをオウム返しするしかできないが、それでもロボットだとバレることはなかった。客はボッコちゃん相手におしゃべりを続け、答えられない質問の時はマスターが止めに入った。
そんなある日、一人の青年がボッコちゃんに恋をしてしまった。支払いに困り家の金を持ち出そうとして、父親に叱られてしまった。二度と行くなという条件でお金を持たされてボッコちゃんに会いに来た青年は、会話の流れで「殺してやろうか」と質問し、ボッコちゃんは「殺してちょうだい」と答えた。
青年はお酒に毒を入れて、ボッコちゃんに飲ませたあと立ち去った。マスターはその毒入りの酒を回収して、残っていた客に振る舞った。
その夜、バーに明かりが灯っていたが、客の声は聞こえてこなかった。ラジオも「おやすみなさい」と言って終わってしまった。ボッコちゃんもおやすみなさいと呟いて、次に喋りかけてくる人を待つのだった。
解説
ショートショートの神様
本書は1958年に発表された星新一の初期短編にして代表作。海外にも翻訳されており、現在も幅広い読者に愛読されている。
星新一は「ショートショートの神様」という異名を持つSF作家。小松左京や筒井康隆と並んで「SF御三家」と呼ばれ、戦後のSF界の基礎を築き後世のSF作家に多大な影響を与えた。
ショートショートとは小説の一ジャンルで、特に短い小説のことを指す。星のショートショートはその短さにもかかわらず、質が高いことに定評があり、さらには大量の作品を世に送り出したことで、先の異名を持つこととなった。そんなショートショートの神様によるショートショートの傑作が本書である。
ボッコちゃんのどこに惹かれるのか
ボッコちゃんはあるバーのマスターが道楽で作ったロボットである。「完全な美人」として作られた彼女は、「つんとしている」という「美人の条件」(p.14)も兼ね備えていた。彼女の存在理由はただ一つ、バーに来た客を喜ばせてお酒をたくさん飲ませることである。
この目的を達成するために、「頭はからっぽ」で「動作のほうも、酒を飲むことだけ」(p.15)で事足りるのがポイントである。バーのマスターが作ったのは「人間と同じに働くロボット」ではなく、人間に好かれるロボットであった。そのためには、人間のような表情も、複雑な動作や思考も必要ない。相手の言葉をただただ繰り返す、ここに人間を喜ばせる秘訣がある。
「きれいな服だね」
「きれいな服でしょ」
「なにが好きなんだい」
「なにが好きなのかしら」(p.16)
人間は自分の発言を繰り返されると、話を聞いてくれていると認識して、その相手に好感を持つらしい。ボコっちゃんはその動作のエッセンスを凝縮したようなロボットで、その繰り返しも機械的であるが、それゆえ客から好かれてしまう。
だが、お客は気がつかなかった。若いのにしっかりした子だ。べたべたおせじを言わないし、飲んでも乱れない。そんなわけで、ますます人気げ出て、立ち寄るものがふえていった。(p.17)
実は、人間は「べたべたおせじを言」う人間らしい存在を好まない。客はボッコちゃんの繰り返し話術だけでなく、非人間的な側面にも惹かれているのだ。
考察
人間の本質——この質問には罠がある
気になる相手を前にして話しかける言葉には、肯定的と否定的の二種類がある。
ボッコちゃんを前にして客が発する「ぼくを好きかい」とか「こんど映画へでも行こう」は肯定的な言葉である。この時、客はボッコちゃんに好かれようと期待していて、彼女に嫌われているなどといった疑いがない。
ボッコちゃんは相手の言葉を鸚鵡返しするロボットである。客が肯定的な言葉をかけるなら、それと同等の言葉を返す。するとその先にあるのは、ボッコちゃんへの行き過ぎたお誘いになる。
「こんど映画へでも行こう」
(p.16-17)
「映画へでも行きましょうか」
「いつにしよう」
これが肯定の会話の行き着く先だとすれば、否定的な言葉が導く結末とは何か。
「きみぐらい冷たい人はいないね」
(p.18)
「あたしぐらい冷たい人はいないの」
「殺してやろうか」
「殺してちょうだい」
ボッコちゃんは向けられた否定の言葉を否定することはしない。否定や疑惑、悪意といった負の感情は、訂正されることなく発した本人に返されてしまう。負の感情は否定されることなく増大し、最後には殺意へと変換される。
とするならば、ボッコちゃんは返答をするただのロボットではなく、相手の感情を写す鏡のような役割を果たしていることがわかる。話しかける人はロボットを媒介した自分の言葉に癒され、あるいは傷つき、最悪の場合、死を決断する。反復するだけのロボットとの会話に隠れていた鏡のような効果は、このような恐ろしい結末を招いてしまうのだ。
人間不在の世界という悲劇
客もマスターも亡くなってしまった結末をどうみるべきだろうか。
試しにここで描かれていない物語を想像してみよう。青年はロボットの「殺してちょうだい」という声を聞いて殺害を決意する。お酒に毒を盛り、一つは彼女の元へ、もう一つは自分の手元に持っていく。「一緒に死のう」と言ってお酒を飲んだ青年は、薄れていく意識の中で「一緒に死ぬわ」と言うロボットの声を聞いた。彼女の愛の深さに打たれた青年は、深い後悔を胸に息を引き取る。ロボットは喋らなくなった青年の前で何食わぬ顔をしているのだった。
これは悲劇である。だが本書はこのような結末にならなかった。青年の愛がもたらす悲劇は、個人の死を超え人類の滅亡へと導く。この悲劇の飛躍が、AIと人類の未来を予見しているようでもあり恐ろしい。好かれたいという単純な欲求が、相手への懐疑を生み、他人を死にまで追いやる。このような可能性を否定できないのがAIと人間の関わりでもある。
人間はロボットを欲する。だがロボットは人間を必要としない。人間とロボットのこの非対称性を見事に描いているのが、最後の場面である。
そのうち、ラジオも「おやすみなさい」と言って、音を出すのをやめた。ボッコちゃんは「おやすみなさい」とつぶやいて、つぎはだれが話しかけてくれるかしらと、つんとした顔で待っていた。(p.19)
ボッコちゃんは人間ではなくラジオの言葉を繰り返す。彼女にとって人間とラジオは等価な存在だ。人間によって作られたボッコちゃんは、人間を必要としないという不可解な現象によって、人類滅亡後も生き残る可能性がある。そこはラジオとボッコちゃんが、見せかけの会話を続けている世界かもしれない。そこにはこれまで人間がしてきた人間らしい会話がなされている。しかしそこに人間はいない。人間が作り出したロボットによって作られた人間不在の世界。それはこの世界に起こりうる悲劇の本質を鋭く抉り出している。