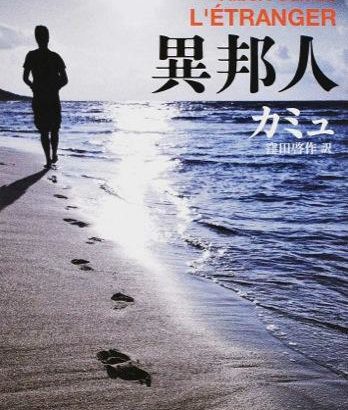概要
『異邦人』は、1942年に刊行されたアルベール・カミュの中編小説。原題は L’Étranger。
カミュの『ペスト』、カフカの『変身』、サルトルの『嘔吐』とともに不条理文学の傑作の一つに数え上げられる。
ママンが死んだという報を受け葬儀に出た主人公ムルソーが、数日後、太陽のせいで殺人を犯し死刑宣告を受けるまでの日々を描いた物語。
海外文学はほかに、キャロル『不思議の国のアリス』、フロベール『ボヴァリー夫人』、ポー『黒猫』『モルグ街の殺人』『ウィリアム・ウィルソン』、モーパッサン『脂肪の塊』などがある。
本作は「海外小説のおすすめ有名文学」と「フランス文学の最新おすすめ小説」で紹介している。
登場人物
ムルソー:母の死の報を受け葬儀に向かう。日曜日を不意にするのを嫌いこれまで母を訪問したことはなかった。葬儀の間も至って冷静で、周囲から不審がられる。葬儀の翌日マリイと再会し関係を持つ。
レエモン・サンテス:ムルソーの隣人。自称は倉庫係だが、裏では売春の仲介業。情婦に恨みを抱き、ムルソーに頼み手紙で呼び出して暴力を振るう。また情婦が不誠実だったとムルソーに証言してもらうよう頼む。情婦の兄たちアラビア人に付き纏われ、ムルソーと共に訪れた浜辺で喧嘩になる。
ママン:ムルソーの母。冒頭で亡くなったことが明かされる。ムルソーと同居していたが、三年前から養老院に入っていた。
御用司祭:ムルソーが神を信じていないことが受け入れられず、絶望に囚われていると思い込み祈ろうとするも拒絶され、彼の元から去る。
アラビア人:レエモンの情婦と兄とその仲間。
院長:ムルソーに対して悪い印象を持つ。ムルソーが母を一度も訪れなかったこと、葬儀のさいに冷静であったこと、年齢を知らなかったことなどを法廷で証言する。
門衛:母の棺の前でムルソーが煙草を吸い熟睡したことを証言する。
トマ・ペレーズ:葬儀でムルソーが涙を流さなかったことに苦痛を感じたと証言する。
マリイ・カルドナ:タイピスト。ムルソーの元同僚。葬儀のあと海水浴場でムルソーに出会い、映画を観賞したあと体の関係を持つ。その後ムルソーとの結婚を望み、逮捕後もムルソーを庇う。
マソン:レエモンの友人。アラビア人と乱闘になると、そのうちの一人を殴り倒し、匕首で切りつけられたレエモンを病院に連れていく。
名言
そのとき、すべてがゆらゆらした。海は重苦しく、激しい息吹を運んで来た。空は端から端まで裂けて、火を降らすかと思われた。私の全体がこわばり、ピストルの上で手がひきつった。引き金はしなやかだった。私は銃尾のすべっこい腹にさわった。乾いた、それでいて、耳を聾する轟音とともに、すべてが始まったのは、このときだった。私は汗と太陽とをふり払った。昼間の均衡と、私がそこに幸福を感じていた、その浜辺の特殊な沈黙とを、うちこわしたことを悟った。(p.64 – p.65)
自分の滑稽さを承知しつつ、それは太陽のせいだ(p.110)
あらすじ・内容・ネタバレ
第一部
「今日、ママンが死んだ」から始まる。ムルソーは母の死の電報を受け、アルジェリアから母が入院していた養老院に向かう。葬儀の前後で、母の姿を見ようとせず、煙草を吸い、うたた寝をする。焼けつく暑さと疲労で草臥れたムルソーは家に帰りゆっくり休む。
翌日、ムルソーは泳ぎに海に向かう。そこで元同僚でタイピストのマリイと出会い、意気投合したあと二人で映画を鑑賞する。その夜、ムルソーはマリイと体の関係を持つ。
ある日、隣人のレエモンから、情婦が家に居座り働かず金をせびりだしたと相談を受ける。ムルソーはレエモンに協力し情婦を誘き出す手紙を書く。現れた情婦にレエモンは暴力を振るい、情婦を追い出す。そのことがきっかけとなり、レエモンは情婦の兄を含めたアラビア人の集団に付き纏われるようになる。
ムルソーはレエモンから、海辺で開かれる友人との遊びに誘われる。ムルソーはマリイを誘い参加する。そこにはほかにマソン夫婦などがいて、みんなで大いに楽しむ。
ムルソーがレエモンとマソンと三人で散歩に出ると、アラビア人が目の前に現れ、喧嘩が勃発する。レエモンは首と腕に怪我をし、その後また喧嘩になりそうな場面でレエモンが発砲しそうだったので、ムルソーが拳銃を預かる。
ムルソーは一人で海辺を散歩に出掛けると、アラビア人の一人がそこにいた。ムルソーは激しい暑さを感じ、太陽の光から逃れようと一歩前に進む。そして拳銃の引き金を引きアラビア人を殺害した。
第二部
ムルソーは逮捕される。
アラビア人殺害に関する法廷が開かれると、ムルソーは数々の証言で不利に陥る。養老院に入院していた母を見舞いに来たことがない、葬儀のあいだ母の顔を見ようとせず涙も流さない、葬儀の翌日マリイとデートをしているなどなど。しかしムルソーは至って冷静で人ごとのように感じていた。
検事は犯行を計画的だと主張し、殺害動機を問い立てる。するとムルソーは「太陽のせいだ」(p.110)と言った。弁護士も証人も弁が立たず、最後には死刑が言い渡される。
死刑を言い渡されたあと牢屋にいたムルソーの元に、御用司祭が訪れる。御用司祭はムルソーが神を信じないことを驚き、いつかは神のもとに向かうと硬く信じ、ムルソーのために祈ろうとする。しかしムルソーは突然激怒し、御用司祭を追い出しています。
ひとりになったムルソーは夜空を見上げる。そして「世界の優しい無関心に、心をひら」き、「世界を自分に近いものと感じ」、「自分が幸福だったし、今なお幸福であることを悟った」(p.130)。残された望みは、処刑の日に大勢の人が憎悪の叫びをあげて自分を迎えることだけだった。
\30日間無料!解約も簡単!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
解説
カミュの第一作にして不条理文学の傑作
『異邦人』は、第二次世界大戦中の1942年に刊行された、アルベール・カミュの第一作にして代表作の一つである。1913年生まれのカミュは当時29歳、早熟の天才は第一作目にして人間の社会に存在する不条理を見事に描いた。1947年には伝染病のペストによって集団に降りかかる不条理を描いた『ペスト』を発表し、カフカの『変身』に並ぶ不条理文学の傑作を生み出した。そしてカミュは1957年に43歳の若さででノーベル文学賞を受賞する。
題名の「異邦人」は「外国人」や「よそ者」といった意味である。主人公のムルソーは母が入院していた養老院へ、80キロ離れたアルジェリアから向かうのだが、そこが初めての土地だから「異邦人」という題になったのではない。『異邦人』が主題に据えるのは、人間社会と人間の本質に備わる不条理であり、そしてムルソーはその人間社会から疎外されているのだ。
したがって「異邦人」とは、ムルソーが人間社会ののけ者であり、世界から弾かれていることを意味している。本作のラスト、夜空を見上げたムルソーが、「これほど世界を自分に近いものと感じ」(p.130)たのは、逆説的に彼が世界に対して「異邦人」であると感じていたことを示唆している。ムルソーは死刑を宣告され神を拒絶したとき、「異邦人」であることから脱却できるのである。
複合過去を用いた特徴的な文体
『異邦人』は二部構成である。一部は、ママンの葬儀からアルジェリア人の殺害まで。二部は、裁判の開始から死刑判決まで。
一部の冒頭は有名な名訳「きょう、ママンが死んだ。」(p.6)で始まる。これに続くのは、「もしかすると、昨日かもしれないが、私にはわからない」(p.6)だ。母の死が今日か、昨日かで迷っていることを初めに示しているあたりに、語り手ムルソーの母の死の無関心さが予見されている。
ところで、母の死に対して文章が醸し出す語り手の微妙な距離感は、フランス語で書かれた複合過去という用法に由来する。複合過去は英語の完了形に似ていて、一般的に小説で使われることはない。カミュは「不条理」という重いテーマを扱いながら、文法的にも実験的な手法を取り組んでいたのだ。ここに『異邦人』の独創性の一つがあるといえる。
この効果はいうまでもなく成功している。第一部、語り手と対象の距離が近い印象を受けるのは、このためだ。一部のラスト、アラビア人を殺害する場面、「それでも、一歩、ただひと足、わたしは前に踏み出した」(p.64)、という描写は、ムルソーの切迫した様子が見事に描かれている。彼は近視眼的に母の死に接しアラビア人を殺害するのである。
\30日間無料!解約も簡単!/
→Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
考察・感想
理性の外部、ムルソーの不条理
『異邦人』が不条理文学と言われる所以は、まずもってムルソーの論理性の破綻にある。レエモンと喧嘩をしたアラビア人をムルソーは拳銃で殺害するのだが、殺した動機については登場人物たちはおろか読者ですら理解することができない。裁判長に殺害の動機を問われたムルソーは、「自分の滑稽さを承知しつつ、それは太陽のせいだ」(p.110)と言い、思わず「延内に笑い声があが」る(p.110)。誰も太陽のせいで殺人を犯したなどという主張を信じることはないし、ムルソーですらそれが滑稽であることを承知している。
太陽のせいで人を殺害するなど論理が破綻している。太陽の日差しが強く暑かったことが原因で、結果として人を殺すのでは、命がいくつあっても足りることはない。では、殺害の場面では、ムルソーは実際どのように感じていたのだろうか。
そのとき、すべてがゆらゆらした。海は重苦しく、激しい息吹を運んで来た。空は端から端まで裂けて、火を降らすかと思われた。私の全体がこわばり、ピストルの上で手がひきつった。引き金はしなやかだった。私は銃尾のすべっこい腹にさわった。乾いた、それでいて、耳を聾する轟音とともに、すべてが始まったのは、このときだった。私は汗と太陽とをふり払った。昼間の均衡と、私がそこに幸福を感じていた、その浜辺の特殊な沈黙とを、うちこわしたことを悟った。(p.64 – p.65)
ムルソーはこのときアラビア人に対して殺意など抱いていなかった。それどころか、何かを考えていたということすら怪しい。「すべてがゆらゆらした」とは、涙によって視界がぼやけたということを意味しているだけではない。文字通り「すべてが」、思考や論理を含めたありとあらゆるものが、「ゆらゆら」しているのだ。彼は理性や思考の外部にいて、その状態で引き金を引いた。殺害動機が「太陽のせいだ」と聞いた人たちは笑ったが、しかしそれは嘘ではない。ムルソーは太陽によって論理性の外部へ、つまり不条理の世界に足を踏み入れているのである。
遡及的意味づけによる社会の不条理
裁判が始まると、ムルソーは非常に不利な状態に置かれることになる。弁護士も友人のレエモンも弁が立たず、むしろ好感度を下げる一方であった。そしてあれよあれよと言う間に、死刑判決が下されてしまう。
ムルソーに向けられていたのは、証言者たちの厳しい非難の目である。母を見舞いに来なかった、煙草を吸い居眠りをしていた、翌日にはマリイと関係を持っていたなど。それらの証言は、殺人事件と全く関係がないにも関わらず、ムルソーが非人間的で非道徳的な人物であるという印象を与えた。そしてこれらの証言が、間接的にムルソーの死刑宣告を導いてしまう。
だが、それらの証言が示す人物像は、偶然作りあげられた虚像である。例えば、養老院を訪れなかったのは、「数ヶ月たつと、今後はもしママンを養老院から連れ戻したなら、泣いたろう。これもやっぱり習慣のせいだ。最初私がほとんど養老院へ出掛けずにいたというのも、こうしたわけからだ。」(p.8)という理由である。また、亡くなった母の顔を見なかった場面では、門衛は「不思議だという様子で、別に非難の色はなかった」(p.10)どころか、「わかるよ」と同意すらしていたのである。煙草も同様で、「ママンの前でそんなことをしていいかどうかわからなかったので、躊躇した」(p.12)が、勧められたミルク・コーヒーはすでに飲んでいるので、「どうでもいいこと」と考えなおし、門衛とともに吸ったのだった。
それらの行為は当初何事も意味していなかった。多くの人が母の死に直面したムルソーに同情し、共感さえしてくれていたのだ。だが、殺害を犯したあと、それらは否定的な意味を持ち始める。ムルソーは非人道的で非道徳的だから、養老院を訪れず、母の顔を見ず、母の前で煙草を吸ったのだ、と。そしてこのような行為を臆面もなくできるからこそ、彼は非道徳的であり、アラビア人を計画的に残虐に殺害できたのだ。
いうまでもなく、これらは順序が逆転しており、なおかつ、トートロジーに陥っている。すなわち否定的評価が先にあって、それにより殺人事件を評価するのではなくて、殺人事件によって過去の行為が否定的に評価され、その否定的な評価によって殺人事件の罪を証明しようとしているのである。これは「あなたは悪い人だから、悪い人なのだ」と言っているに過ぎない。ムルソーの印象が行為に先行し、それにより罪の重さが決定され、重すぎる刑罰が与えられる。ここに論理や一貫性など存在しない。彼は社会の不条理によって、弁解の甲斐なく不当に、死刑に処されてしまうのである。
法廷、そして、自分自身からの疎外
ムルソーはこの社会から疏外されている。二部の裁判の場面、ムルソーは被告でありながら、その場に必要ないかのような印象を受ける。法廷では目撃者の証言が集められ、彼なしに罪の重さが決定されていくのである。
私は十分注意はしていたものの、時には口を入れたくなった。すると、弁護士は「黙っていなさい。その方があなたの事件のためにいいのです」といった。いわばこの事件を私抜きで、扱っているような風だった。私の参加なしにすべてが運んで行った。私の意見を徴することなしに、私の運命が決められていた。(p.105)
私の事件に関する、私抜きの法廷。そこには私は必要なく、私がいなくてもすべてが順調に進行し、「私の運命」ですら勝手に決められていく。そもそもこの法廷は、ムルソーの殺人事件に関して開かれたものでありながら、犯罪よりもムルソーについて主に語られた。「検事と私の弁護士の弁論の間、大いに私について語られた、おそらく私の犯罪よりも、私自身について語られた、ということができる」(p.105)。事件そのものではなくムルソーの人格を検証することが、罪の重さを決定する。
このときムルソーは法廷から疎外され、他人の視線に晒される。そしてその他人の視線はムルソー自身を射抜くことはなく、ムルソーの虚像を見つめつつ形作る。ムルソーは見られる対象として他者の視線にさらされながら、またムルソー自身も客観的に作られたムルソーの虚像を眺めている。言い換えれば、ムルソーは法廷から疎外されるのと同時に、自分自身からも疎外されているのだ。つまり彼は自分自身に対しても「異邦人」なのである。
二部の法廷に対するムルソーの距離感は、このことに起因している。彼は法廷の証言をときに熱心に、ときに飽き飽きと聞く。これが彼の運命を決めるにもかかわらず、彼に発言権はない。疎外されたムルソーは、まるで他人事のように、法廷の結論を待つしかできないのだ。
世界の優しい無関心に、心をひらいた
彼はまた、母の埋葬の時も、アラビア人を殺害するときも、太陽の焼けつくような光を感じている。
焼けつくような光に耐えかねて、私は一歩前に踏み出した。私はそれがばかげたことだと知っていたし、一歩体をうつしたところで、太陽からのがれられないことも、わかっていた。それでも、一歩、ただ一足、わたしは前に踏み出した。
万人に無条件に降り注ぐ太陽の恵み。その光ですらムルソーには耐えがたい。彼は馬鹿げたことと知りながら、太陽の光から逃れるために一歩進む。しかし等しく降り注ぐ太陽の光から逃れることはできない。つまりムルソーは世界からも疎外されていると感じているのだ。これにより彼は銃の引き金を引き、昼間の均衡を破り、不幸な世界に突き進むことになる。
神を信じないムルソーに、御用司祭は「あなたが信じられない」(p.127)と言う。彼はムルソーのために祈ろうとする。そこで初めてムルソーは感情をあらわに激怒する。御用司祭の信念など「女の髪の毛一本の重さにも値しない」(p.128)、「何ものも何ものも重要ではなかった」(p.129)、と。
そして平静を取り戻し独りになった牢の中で、彼はもう一度世界との関係を取り戻す。死を受け入れたムルソーは、星々の光を感じながら、「今や私とは無関係になった一つの世界への出発を、告げ」(p.130)るサイレンを聞く。死を悟り世界から無関係になったこの瞬間、ムルソーは疎外し続けた世界と和解するのだ。
そして、私もまた、全く生き返ったような思いがしている。あの大きな憤怒が、私の罪を洗い清め、希望をすべて空にしてしまったかのように、このしるしと星々とに満ちた夜を前にして、私ははじめて、世界の優しい無関心に、心をひらいた。これほど世界を自分に近いものと感じ、自分の兄弟のように感じると、私は、自分が幸福だったし、今もなお幸福であることを悟った。(p.130 – p.131)
「世界の優しい無関心」。それはこれまで暴力的で不条理なものだった。だが、彼は世界から無関係になったとき、逆説的に「世界を自分に近いものと感じ」、「世界の優しい無関心に、心をひら」く。ムルソーは銃弾によってもたらされた不幸と均衡の崩壊の後で、ようやく、不条理な世界との調和を得るのである。
関連作品

参考文献
カミュ『異邦人』窪田圭介訳、新潮文庫、昭和29年