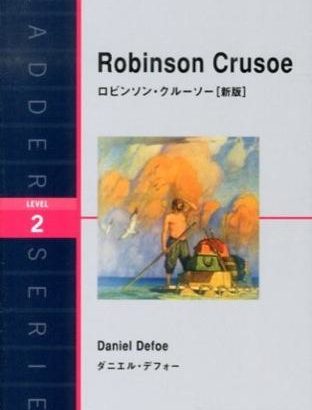概要
『ロビンソン・クルーソー』は、1719年に刊行されたダニエル・デフォーの小説。続編は『ロビンソン・クルーソーのさらなる冒険』、第三部は1720年に刊行された『ロビンソン・クルーソーの真面目な省察』。
イングランドで生まれたロビンソン・クルーソーが、父の教えに反対して船乗りになり、無人島に漂着したのちひとりで生き抜いていく物語。
文学作品はほかに、谷崎潤一郎『春琴抄』、村上春樹『街とその不確かな壁』、モーパッサン『脂肪の塊』、星新一「ボッコちゃん」、プリーストリー『夜の来訪者』などがある。
登場人物
ロビンソン・クルーソー:イングランドのヨーク市に生まれた三男。船乗りになって海に出るも、不運なことに無人島に漂流する。
父:ブレーメン生まれ。商売で財を成した。中庸、節度を重んじ、クルーソーに家業を継がせようとする。
ジューリー:クルーソーがムーア人から逃れるときに同行する。
フライデー:奴隷。無人島に捕虜として連れてこられたところをクルーソーに助けられる。それからクルーソーに仕えるようになる。
あらすじ・ネタバレ
ロビンソン・クルーソーはイングランドのヨーク市で、謹厳で思慮深い父のもとに三男として誕生した。
父は中庸、平穏の生活を息子に望むものの、クルーソーは船乗りとして海に出ようとする。止める父を振り切って出発するも、嵐に巻き込まれる。それでも旅を諦めずアフリカ行きの船に乗るも、海賊に襲われ奴隷になる。
二年後、脱走に成功し、ブラジルに向かう。そこで四年間過ごし、農園経営を成功させる。また航海したくなったクルーソーは、経営を他に任せ海にでる。しかしまた難破し、無人島に漂流する。
この無人島で家を建てたり、畑を耕したりして、徐々に生活を快適にする。そのまま28年間もこの島で生活する。
この島を訪れた蛮族の一団に食べられそうになっていたフライデーという若者を助け奴隷にする。言語や信仰を教え、信頼関係を築く。
無人島にイギリス船が到着する。その船は船員の反乱に遭い、反逆者に乗っ取られていた。船長を助けたクルーソーたちは、船を奪還し生まれ育ったヨーク市に帰還する。
資産を処理し、家庭をもつが、また旅に出るのだった。
解説
始まりの小説は航海記だった!?
この小説が書かれたのは1719年のこと。はるか昔の300年前に書かれたにもかかわらず、現代に生きる我々が本作を面白く読めるのは、作者であるダニエル・デフォーがロビンソン・クルーソーの生き様を軽妙にかつユーモアをもって描いているからであろう。
デフォーは1660年にロンドンで生まれたイギリスの著作家、ジャーナリストである。パンフレット作者やジャーナリストとして活躍したデフォーが小説を執筆したのは、59歳にのとき。その記念すべき一作目が『ロビンソン・クルーソー』であった。
本書はイギリス文学史において、1726年に出版されたスウィフトの『ガリヴァー旅行記』と共に、最初の小説の一つとされる。したがってデフォーは自らを小説家だと自認しておらず、読者も本書を小説だと思って読むことはなかった。本書はロビンソン・クルーソーの実体験を基にした旅行記という体裁をとっている。
世界をまたにかけた個人の冒険物語に、かりにも刊行に値するもの、刊行されたさいに広く受け入れられるものがあるとすれば、この記録こそがそれであると編者は考える。(19頁)
本書は「序」をこの一文で始まる。「個人の冒険物語」の「記録」と銘打たれて出版されたこの書物は、事実、一部でそのように受け取られたようだ。ロビンソン・クルーソーとは作者であるデフォーのことであり、彼が経験した実話なのだと。ところが本書に記された出来事は、二十八年も孤島で一人寂しく過ごしたというものであり、俄には信じ難いものであった。普通に考えればフィクションだと分かりそうなものだが、一部の人が本書を実話だと真に受けたのにはワケがある。
諸説あるものの、アレキサンダー・セルカークという船乗りの航海誌がこの本の元ネタとされている。15世紀半ばから17世紀半ばまで続いた大航海時代のあと、船乗りたちの航海誌が巷に出回っていて、その一つにセルカークの無人島に漂流したという航海誌があったのだ。本書が執筆された当時、未だ発見されざる無人島に唯一人取り残されるというこの物語は、十分あり得る現実の出来事として受容されたのである。
中流階級と上流庶民の思想——ここではないどこかへ
時代が時代なので、無人島での一人生活のほかに、キリスト教の信仰が主題の一つになっている。デフォーはイングランド国教会ではなくプロテスタントに属していたため、ある種の疎外感があり作品に反映されている。
神と人間の関係は、冒頭で、父と私の関係として立ち現れる。
おまえがその愚かな道へもし本当に踏み出したら、神はおまえを祝福ならさらないはずだから、おまえは将来きっと、この父の忠告に耳を貸さなかったのを悔やむことになる。けれどもそのときにはもう、助けてくれる人はだれもいないかもしれないぞ。(19頁)
この地で成り上がった父は、長男を戦争で次男を理由不明で失い、三男のクルーソーに家を出るなと諭す。父は禁止を与える神としてクルーソーの前に立ちはだかるものの、彼は船乗りになる夢を捨て去ることはできない。しかしそうなることも宜なるかな、父の理想はあまりに平凡なのだ。
中ぐらいの成功には安らぎと豊かさがかしずいてくれるし、中ぐらいの暮らしには、節度、中庸、平穏、健康、社交のほか、好ましい気晴らしと望ましい娯楽のすべてが、恩恵としてもたらされる。こうして人は穏やかにつつがなく世を渡り、安らかに安らかに世をさることができる。(17-18頁)
18歳の若者が広大な世界の入り口を前にして、「安らかに安らかに世をさること」を望むはずがない。クルーソーは安心、安全、平穏の「ここ」を抜け出し、「ここではないどこか」を目指して船に乗る。
この感情は、例えば、新海誠の『雲のむこう、約束の場所』や『秒速5センチメートル』で描かれる主人公の「ここではないどこか」への欲望とは質を異にしている。クルーソーが望む「ここではないどこか」は否定や欠落がもたらす欲望ではなく、もっとあっけらかんとしたものだ。それは十分に豊かだが『華麗なるギャツビー』のギャツビーほどの金持ちではない、中流階級に特有のものであるように思われる。足りないからでもなく、ありすぎるからでもない、中間から生まれるあっけらかんとした欲望。それは先進国の一般的な生活水準で生活している現代の人々にも接続されうる感情である。
考察
ダメダメな性格が心を温かくしてくれる
本書が現代において面白く読める理由はこれだけではない。私たちはクルーソーの欲望に普遍性を認ると同時に、彼の性格に個性的な豊かさを発見する。彼は外部を目指す強い心性と、災難に遭遇するとその決意を容易に破棄する弱い心性の、二面性を保持している。この二極を行き来するブレブレの態度は、主題であるキリスト教に対しても一貫していて、それが読者を笑いへと誘う。
彼は無人島に漂流する前に、海賊に捕まり奴隷にされた。そのとき「わたしはすっかり打ちのめされ」(39頁)て父の忠告を聞かなかったことを後悔する。その後悔は父の元へ戻ることを思い付かせるが、逃亡しブラジルで一財産を築くと後悔を忘却し、故郷を飛び出した当時の衝動を呼び戻してしまう。
そう、わたしはまさに父に勧められた中ぐらいの身分、すなわち上流の庶民になりかけていたのであり、この暮らしを続けるつもりなら、このように外国で苦労せずとも、家にいればよかったのである。(65頁)
ここにあるのは、一種のリセット願望である。困難に見舞われれば自らの決断を後悔し、時が経てばその後悔を忘却する。その繰り返しが、クルーソーを外部へと連れ出し、ついには無人島へと連れ出してしまう。神への感謝、父への懺悔、そして忘却。この三位一体の円環は、決してクルーソーをその場に留まらせることはしない。彼はこの円環に駆動されて、いわば外部への欲望に導かれて、無人島での生活を快適なものへと改変させていく。
マインクラフト文学と制作の快楽
この外部への欲望に、西欧の植民地主義を認めるのは容易い。また、終盤に登場するフライデーに対する奴隷扱いもそれを強固なものとして提示しているが、そのことは指摘するだけに留めるとして、ここで注目したいのは本書の独特な快楽についてだ。
無人島生活の描写において、本書は徹底して会話文を極力排している。これは実に妙なことだ。我々はふつう一人でいても言葉を発してしまう。「はあ」とか「いやだな〜」とか思わず口に出てもおかしくない。それにもかかわらず本書で示される彼が発した言葉は、聖書と格闘したあとの「そんな偽善者になれるものか」(182頁)といった独り言と、主人の言葉を繰り返す鸚鵡によってかろうじて知ることのできる「ロビン、ロビン、ロビン・クルーソー、憐れなロビン・クルーソー、おまえはどこにいる、ロビン・クルーソー?おまえはどこにいる?どこへ行っていた?」(225頁)という嘆き節だけなのだ。
聖書や神との対峙でのみ言葉が発せられるということは、この孤島における他者が神しかいないということを示している。だが、注目したいのはキリスト教との関わりではなく、会話文を排したことで生まれる、家を造り土地を開拓していく地の文の豊かさについてだ。私はそれを「制作の快楽」と呼び、本書を「マインクラフト文学」と位置づけたい。
マインクラフトとは、ブロックを配置し建築をしながらサバイバル生活をするといったコンセプトの単調かつ地味な作業ゲーでありながら、多くの人々に愛され続けている現代のゲームである。マインクラフトがつまらない(単調かつ地味)にもかかわらず楽しい(愛されている)のは、課題を見つけてはコツコツと改善し次第に大きいものを積み上げていく「制作の快楽」があるからだ。そのマインクラフトの魅力は、おそらく本書に共通するものである。例えば次のような一文。
生垣を作りはじめてたしか五十ヤードほど進んだところで、それに気づいた。そこですぐに計画を変更して、とりあえず長さ百五十ヤード、幅百ヤードほどの土地を囲うことにした。(232頁)
クルーソーは羊を飼育するために制作しようとしていた柵が、大きすぎることに気づき計画を変更する。本書は基本的にこの試行錯誤の繰り返しである。パンを欲すれば「だがまずは、畑を広げる必要があった」(190頁)となり、船を欲すれば「このあたりの原住民が造るようなカヌーをこしらえられないだろうかと考えるようにな」(200頁)る。
家を建て、畑を耕し、土器を作り、羊を飼い、カヌーを拵える。その度に困難に直面し、試行錯誤して乗り越える。この試みが読者に心地よく感じるのは、本書を流れる時間が異常にゆったり流れているからかもしれない。「骨を惜しまずこの不毛な重労働にはげみ、三、四週間を費やしたと思う」(200頁)なんていうのは序の口で、海賊に捕まって奴隷として働いたのは丸二年、そして無人島生活が二十八年間も続いていたのだ。現代人にとってこの時間スケールは、恐ろしくもあり羨ましくもある。我々が本来欲していたのは、このような試行錯誤の時間ではなかったか。あまりに速いスピードを求められる余裕のない現代に、本書はゆったり流れる時間を与えてくれている。