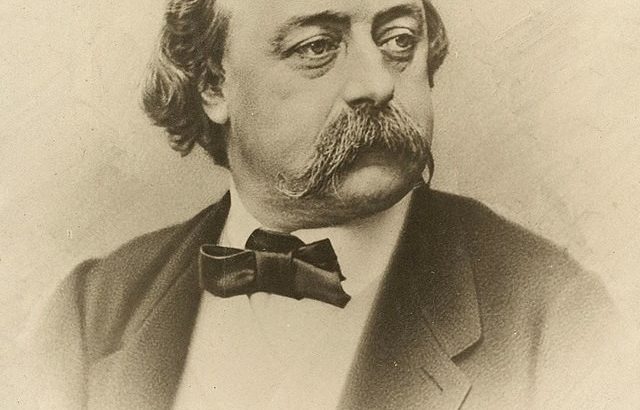はじめに
アルベール・チボーデが『フロベール論』の中でフロベールの人生について述べることを、例えば彼の恋について「この時期まで恋は、フロベールの実生活というより、彼の夢想の世界をしめていた」(46)と書かれているのを読むとき、フロベールの実人生においてひじょうに重要であった現実と虚構をめぐる問題が、そのままエンマの直面する事態と関連していることが分かる。彼女は、自分の読んだ小説をもとに理想の恋を作り上げ、その実現を目指しながら破滅にいたった。この理想はどのように作られ、彼女はなぜ破滅しなければならなかったのか。本記事ではこの点を、登場人物が口にする「紋切型」との絡みで考えながら、『ボヴァリー夫人』の核心に迫ってみたい。
あらすじ
小説との出会い
エンマは十三歳で尼僧院に入りここで小説と本格的に出会う。母が死んだのち信仰心が薄れて寄宿舎を出た頃、シャルルと知り合い彼との間に理想の恋を見て結婚する。後の展開を決定することになるエンマの傾向性は、すでに早い段階からあらわれている。
しかし彼女は田舎を知りすぎていた。羊の群れの鳴き声も、乳のしぼり方も、鋤の使い方も知っていた。のどかな田園風景を見慣れた彼女は、逆に常ならぬものに心ひかれた。海が好きなのは暴風雨があったればこそだったし、緑の草木が好きというのも、それが廃墟のなかにちらほらと萌え出るときに限られていた。彼女は物事からいわば自分の得になるものが引き出せねば気に入らなかった。自分の心がそのまま直接に摂取する足しにならないものは、すべて無用のものとして捨てる。———けだしエンマの素質は芸術家のそれよりは感傷家のそれであり、風景自体ではなく感動を求めていたのである。(58)
これは尼僧院で宗教書を読むエンマについて書かれた箇所である。「作家の筆」による「大自然の叙情的な呼びかけ」に彼女は応じない。なぜなら、それは彼女にとって「常ならぬもの」でないからである。「海」も「草木」も、それが「常ならぬ」状態にあるからこそ彼女の心を引く。そのように他とは違う、唯一無二であることから得られる感動を彼女は求める。このことは対象が「自然」から「恋愛」に移っても全く変わらない。
\Kindle Unlimitedで読める!30日間無料!/
→Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
解説
ヴェビエサール荘の舞踏会
やがてウォルター・スコットを中心とするロマン主義的な恋愛小説に憧れるようになると、彼女は夢想の中で小説の虚構世界の内に自分の身をおいて恍惚感に浸るが、次にはその虚構世界を現実世界に持ち込むことを目指すようになる。この成り行きを決定的にするのが、第一部八章で描かれるヴェビエサール荘で行われた舞踏会の場面である。
エンマはシャルルとの新婚生活が思い描いたもの(すなわち過去に読んだ小説に描かれたような生活)とは違うことに失望し、田舎育ちの自分からはかけ離れた世界である舞踏会に招かれて、大きな希望をもって出かける。館に入ってから、室内の装飾、出された料理、集まった人びとなどが描写されるのだが、興味深いのは、ここで書かれていることが、エンマが本の中に見いだしたであろう貴族の華やかな社交の場面をなぞった、ある種の紋切型のイメージで構成されていることである。この場面の描写がほぼ一貫してエンマの目を通して行われていることに注意する必要があるだろう。つまりここでは、館の様子について語りながら、それを必死に目で追っているエンマの視線こそが描かれている。このときエンマは、小説を読みその世界の中に自分を置くことによって蓄えてきた理想のイメージを、今度は現実の舞踏会に託そうとしているのではないか。それゆえこの舞踏会が、エンマが見た(と思い込んだ)通りに理想的なものであったかどうかは分からない。急に差し挟まれたいささかグロテスクな植物の描写は、エンマが作り上げた理想的な舞踏会の様子に不吉な影を投げかけているようにも思える。「そこでは天井に吊り下げた植木鉢の縁から、蛇の巣から蛇がはみ出たように、緑のひもが長くもつれてたれているかと思うと、その下には毛むくじゃらの異様な植物がピラミッド型に重なり合っていた。」(85)
エンマの欲望の形成においておもしろいのは、その実現の可能性を見せられることによって、欲望がかき立てられるというパターンがあちこちに見られることである。これはレオンやロドルフとの関係も含めて作品全体に見られるパターンであるが、その最初でもっとも大がかりなものがおそらくこの舞踏会の場面であろう。彼女はここで自分の抱いてきた理想が現実に実現しうるということを見ることに成功した。これ以降彼女はその理想の現実化を強く願うようになり、レオンやロドルフを求める。先に指摘したように、このとき彼女がみた「実現」は彼女が読んだ小説から作り出された虚構の枠内にあった。ここまで来て、小説の中に見た恋を現実に求める準備が、ロマン主義的な紋切型の愛の形を求め紋切型の愛の言葉を繰り返し口にする準備が完了したことになり、このことを緑の葉巻入れを拾うことが象徴する。
エンマの恋と不自由な言葉
しかしこのエンマの欲望は、原理的に叶えられることの不可能なものであった。最初に確認したように彼女が求めるのは唯一無二の恋である。彼女が読んだ小説の恋する登場人物たちは皆、自分たちだけの、他とは違う恋を体験しているように描かれていただろう。しかし彼女が恋人に語る言葉は、それを小説から引用してしまっている以上、どこまでも紋切型に陥らざるを得ない。「エンマは慣習的な考えにすがりつき、慣習的なことをあれこれと慣習的に破るだけだ。」(ナボコフ 321)とナボコフは言っているが、ここで問題なのは、「慣習的に破」っているだけのことを、エンマ自身は唯一無二の仕方で破っていると信じて疑わないことである。確かにドン・キホーテと違って、エンマはレオンともロドルフとも一度は恋を成就させたかに見える。しかし、先の引用に続く箇所でナボコフが「姦通くらい慣習的なものを越えようとして、それ自体、慣習的なものもまたないのである」(同上)と指摘する通り、その成就自体がまた紋切型なものであり、結局彼女の理想は、他の誰とも違う自分だけの恋をするというその一点においてどうしても実現することができない。
「小説のような唯一無二の恋をする」という欲望自体に解きがたい矛盾がある。チボーデは、
われわれは、外面に姿をあらわしていなくとも、以前のある状況のもとですでに実現されていたものを宿命的と呼ぶ。われわれが宿命観を抱くのは、われわれが生をまっとうする以前にあらかじめわれわれのものと定められている地点に正確にもどって行くのだから、所詮生はむなしいと感じるときであり、発見に至るものと信じていた道が、じっさいには、われわれが閉じこめられている円の周りをまわっているにすぎないと知るときである(115)
と述べているが、この意味で言えば、エンマはヴェビエサール館を訪ねた時点ですでに破滅を宿命とされていたということになる。
考察
紋切り型を眺めて生きる——ロドルフ
このエンマの状況の特徴を示すのに、ロドルフという人物が一役買っている。もちろん彼は第一にはエンマの理想に合致する男として登場し彼女の欲望を一時的に満たす相手となるが、一方で彼は、紋切型の言葉に対してエンマとは対照的な態度を示す人物でもある。エンマに別れの手紙を書く場面で、彼は「あなたが美しくいらっしゃったのが私の罪でしょうか。いやいや、それは運命のいたすところです、ただ運命を責めてください」(324)などと紋切型に紋切型を書き連ねつつ、次のように言う。「この文句はきくぞ、経験ずみだ」(同上)つまりロドルフは紋切型表現を、そうと分かった上で意識的に用いている。チボーデは彼について「ロドルフは『紋切型辞典』の別の一ページ、それも自覚した一ページである。」(132)と述べているが、これは正確な評言であろう。言葉から一歩引いたところに構えて大局を把握し、女心を巧みに操って悦楽を得る。これに対してエンマの言葉に対する態度は正反対であると言えよう。彼女は自分の紋切型の言葉にどっぷり浸かっていて、言葉との距離が限りなくゼロに近い。彼女は自分の言葉の中を生きているのである。この二人の差はやがて離れて行くロドルフと彼の情熱の欠如に不満を覚えるエンマとの距離にそのまま繋がることになるが、ロドルフの存在はエンマの紋切型な言葉とのこうした特徴的な関係を浮き立たせる効果を持っているだろう。
エンマから一旦離れて付け加えると、現実を自在に操っているように見えながら、しかし単純に幸福であるとはいかないところに、ロドルフという人物の悲哀がある。彼と言葉との関係を描写した箇所に、次のような一節がある。
さすが経験豊富なロドルフも、この同じ表現の下に隠された感情の真偽を見わけることはできなかった。淫奔な唇、または金で買える唇がそれと同じ台詞をささやくのを聞かされてきたために、彼はエンマの言葉の正直さをろくすっぽ信用しなかった。どうせありきたりの愛情をたいそうらしい言葉のあやでいろどったものだ、掛け値をさっ引いて聞くぐらいでちょうどいいのだと考えた。(304)
紋切型に陥る言葉を遠くから見つめるロドルフは、エンマのような破壊的な結末に突き進むことはないかわりに、言葉から離れてそれを退けてしまうことで、その下にもしかしたらあるのかもしれない、そしてロドルフ自身も本当は求めているように見える、相手の真の感情を信じる悦楽にいたることができない。ここでエンマとロドルフのどちらが幸福かと考えることにはあまり意味がないだろう。大切なのは、二人がそれぞれに紋切型に縛られてそこから自由になれずに苦しんでいることであり、この点にロドルフの登場人物としての魅力もあるように思われる。
エンマの破滅、あるいは救い?
さて、エンマの破滅がすでに第一部で運命づけられていたことを思いだすと、ロドルフを訪ねて「金の問題をまるっきり忘れてしまっていた」エンマに、「自分の境遇の真相が深淵のように脳裏によみがえ」る場面は悲痛である(512)。彼女の自殺は金銭問題が直接の原因であった。恋に破れての自殺も恋愛小説の紋切型には違いない。しかし彼女には、それすらも不可能なのである。恋の紋切型に取り憑かれ不幸を味わいながらそれでも叶えられない欲望を生き続けて、最後にはその紋切型の中に残ることすら許されない。死に際のエンマの笑いは、自身の皮肉な人生に対する自虐的な嘲笑と読めるだろう。
真実の愛は、結局言葉として表に現れてくることはできないのだろうか。そうなのかもしれない。『ボヴァリー夫人』では、エンマと恋人とが最大の幸福を感じる場面で、しばしばそれと同時に静寂が訪れる。エンマが求めていたような愛情を実のところ抱いていたのではないかと思われるシャルルとジュスタン(この二人は、ロドルフもレオンも眠った夜の静けさの中で、それぞれにエンマのことを思っている)の想いは、結局誰にも気づかれることがない。「感傷家」(58)としてのエンマと対比される「芸術家」(117)としてのビネーが「しきりとにたつき」ながら「あの絶対の恍惚境」にいたる(497-8)のは、一人轆轤の低い音を鳴らしながら制作に向かっているときである。
しかし、それでもエンマに救いがあるとすれば、それはロドルフに資金の融通を断られたあとの長台詞ではないだろうか(509-11)。この小説では会話の場面が少なくないが、その割に一人の台詞を長く引用する箇所は珍しい。ここでエンマが二ページ以上に渡って自分の思いを口にすることはそれまでのことを考えるといささか意外で、エンマが詰まりつつも真の想いを解放しようとしているような印象を受ける。台詞の内容を具体的に見ると、ロドルフの金がないという言葉に対してエンマは「思わず本音を吐」き、「取りとめがなく」なる。ロドルフが自分のものを売って金を得ようとしないことを咎め、自分だったら「道ばたで乞食でもなんでも」するという。「よくって? あなたさえいなかったら、わたしは幸福に暮らせたのよ! なぜわたしなんかに言い寄ったの? だれかと賭でもしたんですか?」というように、自分の理想と、ロドルフとを否定するような言葉を口にしたのち、「でも、あなたはわたしを愛していらしった」から再び過去の愛を認めようとする言葉を続けるが、「私にはその持ち合わせがないのです!」とロドルフにきっぱり断られて、二人の面会は終わりを迎える。
もちろん、この彼女の台詞全体に依然として恋愛小説の紋切型表現が並んでいることは事実である。しかし、「わたしだったら」から、ある意味でここまでのエンマの追ってきた夢全体を否定するような発言に至る過程で、エンマの心情がこれまでよりは幾分か自由に、言葉の上にあらわれてきていると言えないだろうか。さらにここでさりげなく口にされる「乞食」という語は、最後まで読むとエンマの死に際に再登場するあの強烈なイメージを伴った乞食を想起させる。この小説では、先に引用した舞踏会の場面における植物の描写がそうであったように、醜いもの、ぞっとするものの方により真実がある書かれ方が見られるように思われるが、ここでエンマが乞食になってでもと語ることは、その覚悟の真実味をいささかなりとも表現しないだろうか。
しかし、一時的に足枷をはずしつつあったように見えたエンマの言葉は、またすぐに過去の愛を語りはじめ、結局ただの紋切型に戻ってしまう。彼女はやはり、逃れられない宿命にしたがって破滅するしかなかった。
おまけ——収税吏ビネーについて
ビネーという脇役は、登場回数が少ないながらもひじょうに魅力的な人物だ。彼は轆轤と強く結びつけられて読者の前に現れ、「道楽とはいえこの環作りには芸術家の執念とブルジョアの思いあがりがこめられているのだった」(117)と語り手が述べる通り、フロベールの目からすればおそらく好ましいものと憎むべきものというように矛盾する性質を併せ持っている。
前者の性質についてはチボーデが「この叙情の清算において(……)あたかも芸術家の局限の像を象徴するかのように、収税吏ビネの姿がある。彼は、小説にむかうフロベールさながらにナプキン・リングを回転させ、フロベールと同じように一室にこもって人生をすり減らしてゆくのだ。」(104)と指摘しており、エンマが金策のため訪ねていったときの彼の姿につながる。「仕上げること自体に満足感があるだけで、その先にはなんの夢もないような、そういった仕事だけがどうやらわれわれにもたらしてくれるらしいあの絶対の恍惚境にひたっているところと見えた」(498)という彼の幸福感は、その先に夢を求めてやまないエンマの幸福とは対照的なものであり、ここにエンマが芸術家ではなくむしろ感傷家であると評されていたことも重なる。彼の作るナプキン・リングの量や象牙細工の模造の形は、シャルルの帽子の描写がもつ異常さと関連するようにも思われる。
関連記事:「フランス文学のおすすめ本」、「海外小説のおすすめ有名文学」
関連作品
Audible・Kindle Unlimitedでの配信状況
| Kindle Unlimited | Audible | |
|---|---|---|
| 配信状況 | ○ | ✖️ |
| 無料期間 | 30日間 | 30日間 |
| 月額料金 | 980円 | 1,500円 |
文学作品を読む方法は紙の本だけではない。邪魔になったり重かったりする紙の本とは違い、電子書籍や朗読のサービスは、いつでもどこでも持っていけるため、近年多くの人に人気を博している。現在日本では、電子書籍や朗読が読み・聴き放題になるサブスクリプションサービスが多数存在している。ここでは、その中でも最も利用されているAudibleとKindle Unlimitedを紹介する。
AudibleはKindleと同じくAmazonが運営する書籍の聴き放題サービス。プロの声優や俳優の朗読で、多くの文学作品を聴くことができる。意外なサービスだと思われるが、聴き心地が良く多くの人が愛用している。無料お試しはこちら。
関連記事:Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
関連記事:【2023年最新版】Audible(オーディブル)のおすすめ本!ジャンル別に作品紹介
Kindle UnlimitedはAmazonが運営する電子書籍の読み放題サービス。様々なジャンルの電子書籍が200万冊以上も読めるため、多くの人に愛用されている。30日間の無料期間があるので、試し読みしたい本を無料で読むことができる。無料お試しはこちら。
関連記事:Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
関連記事:【2023年最新版】Kindle Unlimitedのおすすめ本!ジャンル別に作品紹介
参考文献
アルベール・チボーデ『フロベール論』戸田吉信訳、冬樹社、1966年。
ウラジミール・ナボコフ『ナボコフの文学講義 上』野島秀勝訳、河出文庫、2013年。
ギュスターヴ・フロベール『紋切型辞典』小倉孝誠訳、岩波文庫、2000年。
———『ボヴァリー夫人』山田𣝣訳河出文庫、2009年。
バルガス・リョサ『果てしなき饗宴』工藤庸子訳、筑摩叢書、1988年。