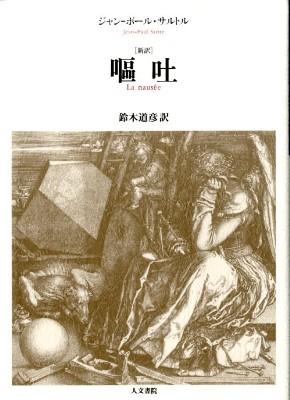概要
『嘔吐』は、1938年に出版されたサルトルの哲学小説。この作品でサルトルは一躍有名になった。1964年、『嘔吐』などの小説によってノーベル文学賞に選出されたが受賞を拒否・辞退している。
アルベール・カミュの『異邦人』『ペスト』、カフカの『変身』と共に不条理文学の傑作の一つに数え上げられる。
内容は主人公ロカンタンの日記という体裁を取っており、最初の短い部分を除くと1932年1月25日から約1ヶ月間、ロカンタンの身に起こった出来事や思想を記している。
海外文学はほかに、ポー『黒猫』、ヘッセ『少年の日の思い出』、カズオ・イシグロ『日の名残り』、サン=テグジュペリ『星の王子さま』などがある。
本作は「海外小説のおすすめ有名文学」と「フランス文学の最新おすすめ小説」で紹介している。
登場人物
アントワーヌ・ロカンタン:主人公であり日記の作者。高等遊民的な生活を送っている。ある日を境に吐き気に苛まれている。
アニー:ロカンタンの元恋人。「完璧な瞬間」を追い求めている。
独学者:いつも図書館で本を読んでいる人物。ヒューマニストであり、ロカンタンの冒険の話を熱心に聞きたがる。
あらすじ
30歳の独身男性アントワーヌ・ロカンタンはブーヴィル(架空の都市)の安ホテルに一人で暮らしている。彼は何年かにわたる旅行から帰ってきて、そこで18世紀の貴族であるロルボン氏の生涯についての歴史の本を書こうとしていた。
彼はある日、海辺で小石を手に持ったときに不愉快な感じを抱いて以来、吐き気を感じるようになった。彼はそれ以来この吐き気の正体は何かを突き止めようとしていたが、わからないまま孤独に生きていた。
そのときには彼は、図書館で独学者と頻繁に出会うことと、「鉄道員の溜まり場」というバーでマダムと性的関係を持つ以外に人付き合いのほとんどなくなっていた。この度もセックスをするために、そのバーへとやってきたロカンタンだったが、不意に吐き気を感じる。ここでも感じるようになったか、と思うロカンタンであったが、あるレコードが流れると突然吐き気が消えてなくなった。
その後もロルボン氏に関する歴史の本を書くために図書館に行き、独学者に出会い、バーではアシル氏について考察したりするなどして過ごしていたが、吐き気は増すばかりである。そうこうしているうちに、元恋人のアニーから手紙を受け取り、5年ぶりに再開することになる。彼女は「完璧な瞬間」を追い求めて、演劇を行うような人間であった。しかし会ってみると、もう「完璧な瞬間」は追い求めなくなっていた。彼女は「完璧な瞬間」はあきらめ、パトロンから金を貰いながらすでに「余生」を過ごしているという。彼も「冒険」を求めていたが、それが冒険とならないことに気づいており、アニーと同じ発見をしていたことを悟り、彼女と別れる。
彼はロルボン氏に関する歴史の本を書くこともやめ、ついにブーヴィルという街からでていくことを決意する。彼は最後に「鉄道員の溜まり場」に寄り、あのレコードをかけてもらうように頼む。彼はそれを聞きながらその存在を超えたものを感じる。ロカンタンは「私も試みることができないだろうか」と考え、「起こり得ないような物語、一つの冒険」の小説を描きたいと思う。そう考えながらこの日記は終わる。
\30日間無料!解約も簡単!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
解説・考察
本格哲学小説
サルトルはノーベル文学賞にも選考された(しかし辞退)実存主義の哲学者であり作家である。彼は小説も哲学的著作もどちらも多く残しているが、サルトルを一躍有名にしたのがこの『嘔吐』である。
もともとの題名が『偶然性にかんする弁駁書』であり、それから『メランコリア』『アントワーヌ・ロカンタンの驚異の冒険』を経て、この『嘔吐』に落ち着いた。最初の題名が示しているように、偶然性という哲学的テーマについて考察を深めた小説であり、本格哲学的小説と読んでも差し支えないだろう。
『嘔吐』は1931年から執筆を開始し、最終的に1938年に出版された。サルトルの哲学的主著である『存在と無』は1943年の著作であり、あまり『存在と無』との繋がりは見出せない。それよりも『想像力の問題』や『自我の超越』との繋がりの方が多く見出される。しかし発想の源泉である「偶然性の問題」は、それらの著作を書いた時よりももっと前からあった発想だろう。そういうわけで、哲学という観点からすると、最初期のサルトルの思想をここでみることができる。『嘔吐』を下敷きにして『想像力の問題』や『自我の超越』が生まれ、またそれらを下敷きにして『存在と無』が誕生したのである。
題名『嘔吐』について
日本語に訳すと、本当は「吐き気」が正しい。つまりこの題名は嘔吐したことを意味しているのはなくて、嘔吐する前の気持ち悪い状態のことを指しているのである。「嘔吐」という言葉を使うなら「嘔吐感」と訳した方が適切である。もちろんこのことは訳者も気づいており、旧訳では語感などの理由であえて「嘔吐」という訳語を選定していた。新訳でも、それを踏襲して「嘔吐」というタイトルにしている。
どうして吐き気を催すのか(マロニエの根)
話の内容としては、ある日物に吐き気を感じたロカンタンがその意味がなんなのかを探究し始める。そこで彼が気づいたのは、吐き気とは存在そのものの偶然性のことだったということである。それゆえ実生活での「冒険」も「完璧な瞬間」も実現しないことになり、彼の歴史の本を書くことが中断される。しかし、ロカンタンはあるレコードでは吐き気が失われることに気づいており、それが存在を超えていることを発見する。そこで自分も最後にそれを実行してみようと欲するという日記物語である。
問題は哲学用語が登場していることだろう。それが「存在」だ。これが何度も言及されることによって理解を難しくしている。最もこの小説自体が存在=吐き気の正体は何かを暴こうとするロカンタンの執念を描いているので、そこまで哲学的知識がなくても理解することができる。
さて、『嘔吐』の中で最も有名な場面の一つが「マロニエの木(根)」の場面である。そこで彼は吐き気の正体、すなわち存在の正体を理解することになる。
本質的なことは偶然性なのだ。つまり定義すれば、存在は必然ではない。存在するとは単に、そこにあるということなのだ。存在者は出現し、出会いに身を委ねるが、人は絶対にこれを演繹できない。
『嘔吐』鈴木道彦訳、218頁
存在(あるということ)が偶然性というのは比較的わかりやすいのではないだろうか。例えば目の前に石ころが二つ並んでいる。赤い石が左側に青い石が右側に置かれているとする。しかし、それはなぜそのような配置なのだろうか、と考えると特に理由はない。「偶然だ」ということは、それがあることに特に理由がないということだ。自分で考えてみよう。自分はこの世に生まれてきたが、先ほどの「理由なし!」という存在の本質に従うとすると、生まれてきたことには特に意味がない。例えば使命があったわけではない。また例えば自分だけが病気にかかって友達は病気にかからなかったとしても、それは悪い行いをしたからではない。逆もまた然りで自分だけうまくいったとしても、それは良い行いをしていたからではない。
彼はその存在を「不条理」とも読んでいる。偶然であり不条理である、これこそが存在なのだ。
しかしこれはひょっとすると当たり前じゃないかと思われるかもしれない。そんなことは常識だと。しかし、ここに哲学が絡んでくるとちょっと突拍子もないことを言っていることになる。伝統的に存在は理性的で必然で条理があるとして見られてきたからだ。それが19世紀後半ごろから一変する。反理性の時代である。そのころから理性的ではなかったもの、例えば感性であったり情動であったりといったものが注目されるようになってきた。世界は表面的にはごちゃごちゃしているけれども、本当は条理に満ちているというのがそれまでの価値観だったが、ここでは逆転する。世界はごちゃごちゃしていてその基礎は条理に満ちていると思っていたけれども、本当はさらにその基礎は不条理に満ちていると。サルトルはそのことを吐き気で表現したのだ。
この魅せられた状態は、どれだけ続いたのか?私はマロニエの根だった。と言うよりもむしろ、完全に根の存在の意識になりきっていた。とはいえーーそれを意識している以上ーー私は依然としてその存在からは切り離されているのだが、にもかかわらずそのなかに埋没し、その存在以外の何ものでもなくなっていた。
219頁
少し後の文章であるが、ここには現象学者フッサールの志向性理論の影響が見られる。ここで何が言いたいのかというと、私は存在から切り離すことが原理的にできないということである。つまり永遠に存在に囲まれていなければならないのだ。フッサールの志向性理論は、そのことを明確化した理論である。いつだって人は物のもとにある。つまり絶対的な独我に陥ることはない。これも大したこと言ってないな、と思われるかもしれないが、哲学的には結構斬新な考え方だった。そんなわけで、私はいつも不条理に囲まれているし、私も存在している以上不条理である。要するに、全部不条理である。これは哲学的にはつらいことである。だからこそ感じるのが「吐き気」なのである。
しかし、不条理だとか偶然性で吐き気を感じるのはおかしい、と感じる人もいるだろう。ごもっともである。世界が偶然性に満ちているからといって吐き気を催すなんて現実にありうるのか。実はサルトル自身、このことで吐き気を感じたりしたことはないと述べているのだ。先にこの小説は「本格哲学小説」だと述べておいたが、それはこういう意味においてだ。この小説はまず哲学的な思想があって、それを小説という形に当てはめている。つまり「吐き気」というのは、西洋哲学の伝統を引き継いで考えると、偶然性の発見というのは、現実生活における吐き気にも匹敵する、ということである。これはひとつ押さえておくべきポイントである。
《存在》と《完璧な瞬間/冒険》と《ただある》
しかしこの小説は、「吐き気」を感じたロカンタンが憂鬱なまま一生を過ごすといったような小説ではない。「吐き気」が消える瞬間もあるのだ。
三つのカテゴリーを取り上げて図にしてみるとわかりやすい。それをみれば、この小説の構図が理解できるはずだ。
| 真善美 | 芸術その他 | 情動 | |
|---|---|---|---|
| 存在(そこにある) | 偶然性、不条理性 | 物(日常生活) | 吐き気 |
| 完璧な瞬間、冒険 | 倫理(道徳) | 演劇、歴史 | |
| 存在を超えて(ただある) | 美(非現実) | 音楽、小説(起こり得ないような物語) | 苦しみ |
一つ目が、先ほど説明した「存在」である。これは偶然性であり不条理性である。この「ある」には理由がなく、ただそこにある。それと鋭く対をなすのが二つ目、アニーの「完璧な瞬間」とロカンタンの「冒険」である。これは存在ではない。例えばアニーの演劇について考えてみよう。アニーは演劇で「完璧な瞬間」を求めたりしていたが、演劇では全てが最初から決められている。また舞台演出にしても意味のないものは存在しない。つまり、そこではあらゆるものに条理があるのだ。「冒険」もそれに準ずる。というのも、「冒険」することができるのはある物語の登場人物にしか無理だからである。試しに『ロード・オブ・ザ・リング』でも思い浮かべてもらえばよい。あのようになにがしかの意味を与えられ、その目的を達するために旅出ることが「冒険」なのだ。目的には必然性があり、つまり条理がある。ロカンタンはロルボン氏を蘇らせるために歴史の本を書こうとしていた。これもこの部類に入るだろう。というのも歴史には全て意味があるからである(逆に歴史的記述において意味のないものは全て忘れ去られてしまう)。これらは全て存在に抵抗する試みであった。
しかし、ご存知の通りこれらは全て失敗している。ロカンタンはそもそも「冒険」を途中で止めて、ブーヴィルの街に帰ってくる。またロルボン氏に関する本を書くのも途中で止めてしまう。アニーも「完璧な瞬間」を諦め「余生」を送ることにしている。これらは存在に抵抗するが、しかし存在に負けてしまうものとして描かれる。
三つ目が「ただある」のカテゴリーだ。「そこにある(存在のカテゴリー)」と「ただある」はまったく別物なので注意が必要だ。実はロカンタンは何度か日記中で吐き気を忘れることに成功している。Some of these days, You’ll miss me honey. から始まるレコードを聴いている時である。ロカンタンにとって音楽は存在ではないのだ。
自分自身の死を内的必然性として誇らしげにおのれのうちに抱えているのは、音楽の調べのみだ。ただし音楽は存在ではない。すべての存在者は理由もなく生まれ、弱さによって生き延び、出会いによって死んでいく。
『嘔吐』、222頁。
もう一つ存在を超えているものがある。最後にロカンタンが書こうとした小説である。それは「起こり得ないような物語、一つの冒険」(296頁)である。音楽に関しては、先ほども述べたように始まりと終わりが決まっている。これは偶然なものではなく、決定されているものである。ロカンタンの小説は?というとちょっとカテゴリーが違うように感じるかもしれない。たしかに小説もある種の必然性の中で描かれるものだろう。しかしそれならロルボン氏に関する本でも、ノンフィクションの歴史小説でもよかったのではないか。
ここには芸術に関するサルトルの思想が反映されている。『嘔吐』執筆後に書かれた『想像力の問題』(1940)の最終章「芸術作品」の一節を見てみよう。
幻惑され、想像界の中へ閉じ込められていた意識が戯曲や交響曲の突然の停止のために解放せられて、突如として存在との接触を取り戻す。現実的意識の特徴をなす嘔吐をもよおす不快感を挑発するためにはこれで十分なのである。
『想像力の問題』人文書院、371頁。
以上に指摘した諸点によって、現実界とは絶対にうつくしいものではない、とすでに結論を下すことが出来よう。美とは想像界だけにしかあてはまり得ず、その本質的構造のうちにこの世界の空無化を蔵している価値である。これこそ倫理と審美性とを混同することが馬鹿げていることの所以である。
「嘔吐=吐き気」というキーワードも出てきてわかりやすい。 全体を補ってまとめると、芸術(=美)と現実世界(倫理)が鋭く対比させられていて、芸術は現実(=存在)を超えて別のところ(=非現実)へと連れて行ってくれる。しかし逆にいえば現実世界に美が入り込むことは絶対にあり得ない。だから戯曲や交響曲という美が停止するとすぐに現実世界に連れ戻され、「嘔吐をもよおす不快感」を感じてしまう。また倫理とは現実生活と関係することなので、美と混同することは「馬鹿げている」。最も大事なのは芸術は現実(存在)から非現実(非存在)へと連れ去ってくれることである。
ここに歴史に関する本がダメな理由があるだろう。歴史は現実の過去の出来事である。すでに現実と関わってしまっている。その意味でロルボン氏に関する本はどうしても存在に関わってしまうことになる。実は「冒険」もそうだ。これも現実世界での「冒険」だ。だから、そこには不条理が紛れ込んでしまう。これも「吐き気」を忘れさせることはできない。アニーの「完璧な瞬間」が訪れないにも、それを現実世界で求めたからだ(実際アニーはそれを道徳の問題、義務問題だったと主張している)。現実世界には「完璧な瞬間」はない。だからアニーは演劇にも満足しない。俳優は演じているだけであり、それを結局のところ生きているわけではない。このようにして、現実世界に存在の外側を求める行動は全て失敗する。
ロカンタンが希望を見出したのは小説だ。しかもそれは「起こり得ないような物語」だ。起こり得ないような物語とは一体なんだろうか。それは完全に非現実的な想像もつかないような物語となるだろう。つまり現実という存在が一切介入してこない物語のことだ。それまでの「冒険」や「完璧な瞬間」との違いは、これが美的な領域だということだけではない。そもそも現実世界においては何も期待していないということなのだ。かろうじて美の領域だけが、存在を超えていける。しかしそれは束の間にすぎないだろう。それでもロカンタンは書くことを欲する。これはアニーとの対比が鮮明である。現実には無理だと諦めたアニーと、現実には無理でもと希望を捨てなかったロカンタンである。
これは本当にささやかな希望である。実はそれを書いたからといって、自分の「存在」を感じなくなるわけではない。そのことをロカンタンは自覚している。それでもロカンタンは前を向くのである。
余計なものについて
本書では何度も「余計」という概念が登場する。これもサルトルが好んで語った哲学的概念だ。
『嘔吐』では次のように言われていたりする。
私たちは、自分自身を持てあましている多数の当惑した存在者だった。私たちの誰にも、そこにいる理由などこれっぱかりもなかった。存在者の一人ひとりが恐縮して、漠とした不安を抱えながら、他のものに対して自分を余計なものだと感じていた。余計だということ。これこそ私が、木々や鉄柵や砂利のあいだに確立することのできた唯一の関係だった。
『嘔吐』、214頁。
二つの意味で自分は「余計」である。第一に自分が偶然的な存在だという意味で「余計」である。引用最初で「そこにいる理由などない」と言われているが、『嘔吐』の哲学的なテーマである「偶然性」を指している。自らの生が偶然だということは、自分に生きる意味(目的)というものが生来から備わっていないことを意味している。その意味でまず「余計」である。世界に存在しなくてもいいというわけである。
第二に他の存在者との関係性という点において「余計」である。例えばあの木に対して、自分がある規定性を与えたとしよう。一本だとか、緑色だとか、枯れているとか。そうすることで、あの木は何なのかを特定しているようにみえる。しかしこういった規定(一本、緑色、枯れている)は、木の存在が偶然だとするならば、何一つ普遍的な規定とはならない。つまり相対的な規定となってしまう。別の人あるいは別の種族なら別の規定を施ほどこすからだ。だから、あの木との関係性において、自分は何一つ完璧な意味を示すことができない。そういうわけで「余計」なのだ。
この「余計」という発想は『存在と無』にも登場する。ながくサルトルを捉えた概念であるが、それの発想がすでに『嘔吐』の時期からあったことがここから分かるのである。
感想・名言
私たちのようにすべきだ、リズムに合わせて苦しむべきだ
ロカンタンがレコードを聞いたときに訴えかけてきたのがこの言葉である。「苦しむ」べきだ。ここには「吐き気」とは別の情動がある。
けれども歌を聴いて、これを作ったのはこの男だと考えるとき、私は彼の苦悩と汗を・・・・・・感動的だと思うのだ。
294頁。
この「苦しみ(苦悩)」は存在ではない、とロカンタンは言う。というのも、それは非存在なもの(この場合は音楽)が生まれる場だからだ。かつてメルロ=ポンティは、哲学をする作業も詩人が詩を作るように「不断の辛苦」であると言った。何かを創造するときにはそこに苦しみが伴う。しかも「リズムに合わせて」である。リズムに合う、というのは調和がとれているということである。いわば何かが舞い降りている状態、一切が必然的になったかのような状態だと考えられないだろうか。だとすれば、リズムに合わせてを強調したのもうなずける。
私も試みることができないだろうか……
ロカンタンがレコードを聞いたあとに思ったのが、この言葉である。
能動性といえばサルトルの代名詞みたいなものだ。「ここがロドスだ、ここで飛べ」よろしく、サルトルはしかもそれを現実に実践しようとした。ロカンタンは高等遊民的な生活(実際ほとんど高等遊民である)をしており、せいぜいやるにしても小説を書こうとしたぐらいだ。実際のサルトルとは乖離がみられるだろう。しかし、ロカンタンはアニーから「なんにもやろうとしない受動的な人」と呼ばれていた。たしかに、ブーヴィルでは日々をなんとなく過ごしているようにも見える。しかし、結末ではアニーの方が「受動的な人」になっている。逆にロカンタンは試みようとするのだ。サルトルの能動性は最初期の小説にも見出だせるのである。
関連作品
参考文献
J-P・サルトル『嘔吐[新訳]』鈴木道彦訳、人文書院、2010年。
J-P・サルトル『想像力の問題(サルトル全集第十二巻)』平井啓之訳、人文書院、1971年。