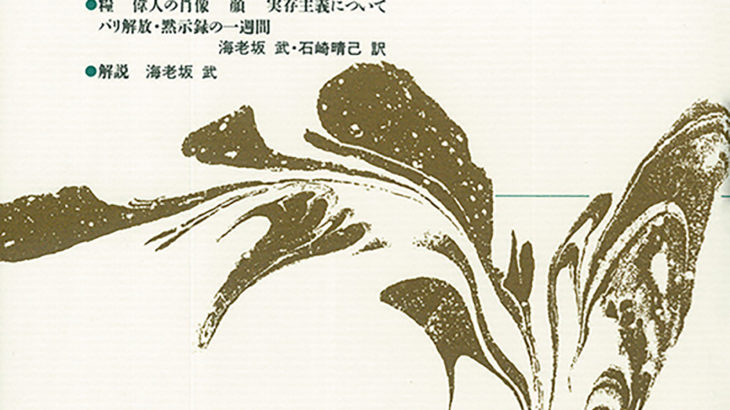意味
実存主義(existentialism)とは、人間主体を基礎とする考え方を主張した概念。
教科書的にはキルケゴールとかニーチェも実存主義の思想と言われているが、彼らはその言葉を一度も使用していない。実存主義が流行ったのはフランスの実存主義哲学(サルトル、ヴォーヴォワール、カミュ)からで、広い意味で言えば、人間的主体を基礎にした哲学のことを指す。その中でも実存主義者として一番有名なのが、ジャン=ポール・サルトルである。
しかし「実存」という言葉自体はサルトル以前から使用され、主張されてもいた。ヤスパースは『世界観の心理学』(1919年)で、人間の主体的な生を「実存」と呼んだ。また、ヤスパースは『現代の精神的状況』(1931年)で自らの哲学を実存哲学と呼んでもいる。
しかしながら実存主義とは名乗っていない。どうやら当時、実存主義という言葉はマイナスイメージを帯びていたことが原因らしい。というのも、実存主義者というのは「定住所を持たず、一日なにかわからぬ「仕事」を30分だけして、あとはカッフェとバーとキャバレーを行き来しているだけの寄生虫のような存在」(『実存主義とは何か』3頁)とみなされていたからである。そういった背景もあって、ヤスパースは自らの哲学を実存主義とは呼ばず実存(の)哲学と呼び、サルトルもまたそうであった。しかし、1945年の「実存主義はヒューマニズムか」という講演で、サルトルは本格的に実存主義という言葉を自らの哲学を指す用語として引き受けることになる。
関連記事:サルトル『嘔吐』なぜ吐き気を催すのか|あらすじ・解説・考察
著作読解
『実存主義はヒューマニズムである』における実存主義
実存主義という言葉の哲学における最初の使用はガブリエル・マルセル(1940年代中頃)だと言われている。サルトルはそのあと使用したわけだが、実存主義を哲学として広めたのはサルトルの力が大きく、その代表作が『実存主義はヒューマニズムである』(1946年)である。この著作は、1945年の講演「実存主義はヒューマニズムか」を本にしたものである。邦訳もあるが、邦訳の題名は『実存主義とは何か』となっているので、そこには注意が必要だ。それでは「実存主義はヒューマニズムである」から実存主義の意味を見ていくことにしよう(訳は適宜変更した)。
実存主義は人間的生の条件である
当時実存主義(者)というのは様々な意味で使用され非難されていた。そこであらゆる実存主義に対する非難(例えば、実存主義は人間の低劣な部分ばかり強調している!という非難)に対して、サルトルが実存主義を定義し直しているところからこの本は始まる。
われわれが意味する実存主義とは、人間的生を可能にする考え方であり、また他方で、あらゆる真理、あらゆる行動は環境と人間的主体性を含意しているということを宣言する考え方だということである。
『実存主義とは何か』37頁。
ちょっと難しいが、ここでまず読み取りたいのは、実存主義というのが哲学的概念であるということである。これが前半でいわれる「人間的生を可能にする」という意味だ。単に浮浪者みたいな人間が持つ思想のことを指すのではなく、そもそも人間全般の可能性を示す思想だということである。
後半はもっと重要だ。ここでは「環境と人間的主体性」という二つが含まれていることが重要である。サルトルが言いたいのは、デカルトの心身二元論みたいに、自我(主観)があって、その外側に環境(客観)があるのではないということ、両者が共に等根源的に成立していることが人間的生を可能にしているということである。これは非常に難しい文章で、というのも何でこんな発想を持っているのかといったら、ハイデガーの「世界ー内ー存在」という概念が下敷きにあるからである。だからここでは、実存主義はデカルト流の観念論ではなく、世界にいつもいるような存在を前提としているのですよ、と当時のハイデガーの存在論的実存論的哲学を取り入れながら主張していることになる。実存主義は、サルトルもそう述べているが、専門的・哲学的概念なのだ。
実存は本質に先立つ
その哲学的な実存主義という概念にしても、実は実存主義というのは二つに分かれるという。一つ目がキリスト教的実存主義でヤスパースやマルセルが入る。二つ目が無神論的実存主義でハイデガーや自分自身(サルトル)がそこに含まれるという(ここからもハイデガーの思想からかなりの影響を受けていることが分かる)。そして、サルトルはあの有名な言葉をここで述べることになる。
この両者に共通なことは「実存は本質に先立つ」と考えていたことである。あるいはこれを「主体性から出発せねばならぬ」と言い換えてもよかろう。
『実存主義とは何か』39頁
どういうことか。この後サルトルはペーパー・ナイフの例を持ち出して分かりやすく説明している。曰くペーパー・ナイフは本質が実存に先立っている。なぜならペーパー・ナイフは最初から「ある物体を切る」というある目的のために造られたものである。この最初から目的があるというのが、本質が実存に先立つという意味だ。これを過去の哲学者(ディドロやヴォルテール、カント)は人間にも当てはめていた。神が目的ありきで造ったかのように、人間には人間としての本性(本質)があるのである。例えば、人間は必然的に結婚して子供をつくらなければならないという価値観があるとしたら、これは本質が実存に先立っていることになる。というのも子作りという目的がまずあって、人間という概念が生じているからである。
しかし本質に先立つ存在が少なくとも一つはあるという。それが人間である。それではこの場合実存が本質に先立つとはどのような意味になるのか。
それは、人間はまず先に実存し、世界のうちで出会われ、世界のうちに不意に姿をあらわし、その後で定義されるものだということを意味するのである。実存主義者の考える人間が定義不可能であるのは、人間は最初は何ものでもないからである。人間はあとになってはじめて人間になるのであり、人間はみずからがつくったところのものになるのである。このように、人間の本性は存在しない。その本性を考える神が存在しないからである。人間は、みずからそう考えるところのものであるのみならず、自らが望むところのものであり、実存してのちに自ら考えるところのもの、実存への飛躍のうちにみずから望むところのもの、であるに過ぎない。人間は自らつくるところのもの以外の何ものでもない。以上が実存主義の第一原理なのである。
『実存主義とは何か』42頁
人間に本質はないということは、ペーパー・ナイフのようにある目的のために誕生したわけではないということである。目的は誕生した後に出てくる。自分はギターが得意で、ギタリストになる運命だったと考える人がいたにせよ、それは生まれた時からそうだったのではない。この地に誕生してから様々な経験をする中で、そう考えただけのことに過ぎない。そしてそう思うことによって、そう(ギタリスト)なっていくのである。しかし何者でもないからといって、何者にもなろうともしないというわけではない。絶えず何者かになろうとしていく傾向がある。この何者でもない(本質はない)のだけれど、それでも何者かになろうとする運動があるということが実存主義(の第一原理)なのだ。この何らかの運動、とりわけ時間的運動を見定める必要がある。例えばどんな運動があるだろうか。
われわれは人間がまず先に実存するものだということ、すなわち人間はまず、未来にむかって自らを投げるものであり、未来に自らを投企することを意識するものであることをいおうとするものだからである。人間は・・・まず第一に、主体的に自らを生きる投企なのである。
『実存主義とは何か』42−43頁
人間の実存には時間的運動として未来に向かう運動がある。それがここでは投企〔projet〕という言葉で言い表されているものだ。しかしここでも注意しなくてはならない。これもハイデガー用語なのだ。投企というのは、さしあたり私たちは未来のことをイメージしたり予想したりせずとも、暗黙のうちに未来のことを考え、それらを生きている状況のことを指す。
まず未来に投企しているということと、人間は最初何者でもないという言葉はつながっている。何者かであるためには未来的ではなく、現在的でなければならないからである。つまり投企しているのだから、人間は最初何者でもないのであり、実存しているということがいえる。このように人間はいつでも動いており、不安定な存在なのだ。これこそ実存主義が言いたかったことである。
まとめ
サルトルによる実存主義というのは、このように実存という人間のあり方(絶えず投企していくというあり方)などを基礎にして、人間一般を理解しようとする考え方である。サルトルは『実存主義とはヒューマニズムである』では、そのことを明確に示そうとしている。
ただしよくわかりにくいのは、やはりハイデガーの影響を受けているからだろう。そもそもハイデガー用語も使っており、ハイデガーの『存在と時間』期の哲学を知っていると、よりサルトルの実存主義は理解が深まると思う。
批判
ハイデガーとヒューマニズム(実存主義)
さて、これまではサルトルの実存主義を見てきた。そこでは無神論的実存主義としてハイデガーと自分を一緒の組にしていたのを覚えているだろうか。そんなこんなでフランスでは「ハイデガーって実存主義者なんですか」みたいな雰囲気が深まっていく。そんな中、フランス人のジャン・ボーフレという人が「ヒューマニズム」について1946年にハイデガーに質問状を送ることになる。この時期はもはや現象学という言葉さえ使わなくなっている時であり、ハイデガーはもちろん実存主義に組み入れられることに不満である。そこでその応答を手直しして出版されたのが『ヒューマニズムについて』である。
既に題名が挑戦的で、ドイツ語だとÜber den Humanismus となるのだが、この Über には「・・・を超えて」という意味もあり、「ヒューマニズムについて」でありながら「ヒューマニズムを超えて」という二重の意味を含意している。そしてハイデガーは、『ヒューマニズムについて』でサルトルの立場を批判する。というのもサルトルの哲学は人間を主観とし、他の一切を客観とする主観ー客観関係の形而上学の典型だからである。代わりに、人間の人間性、すなわち人間の実存というのは「存在の光」の中に立っているという「人間の脱存(Ek-sistenz)」こそが人間に固有なものであるとハイデガーは主張することになる。
発展史
実存という言葉について
実存主義はフランス語だと existentialisme と書く。そして「実存」はexistence なのだが、ちょっとややこしいのは、この実存という言葉は実存主義でいわれるような「実存」という意味はなかったということである。実存が人間の実存を指すようになるのは哲学史的にはだいぶ後の話である。
もともとexistentia(ラテン語)は essentia の対義語だった。essentia は「本質」という意味であり、existeintia は「現実存在」と訳される。これは人間に限らず物の現実存在にも使われており、人間に限定されていたわけではない。
それが実存の時代になって、徐々に「人間の現実存在」を指すようになった。またexistenz(ドイツ語)といのは、ex(k)とsistenz という二つの言素から成り立っており、前者には外へという意味が、後者には「存在する」のような意味合いがある。すでに言及しておいたが、人間というのは単なるうちにこもった意識なのではなく、絶えず世界の方へ飛び出していくものだという観念論の乗り越えを図った考え方がハイデガーなどから登場する。するとこの ek は超使えるわけである。つまり、その人間が自らの外へ向かっていく様を表している、というわけだ。というわけで、ek-sistenz みたいにして区切って使用したりする。その場合、「実存」ではなく、その含意を生かすために「脱ー自」とか「脱ー存」とか訳されたりする。ここらへんは翻訳者の力量が試されるところだろう。
参考文献
J-P・サルトル『実存主義とは何か』伊吹武彦/海老坂武/石崎晴己訳、人文書院、1996年。
〈実存主義〉を知るためのおすすめ著作
>>哲学の入門書:哲学初心者向けの人気おすすめ入門書を紹介!
>>哲学書の名著:本格的な人向けおすすめ哲学書を紹介!
>>本記事はこちらで紹介している:哲学の最重要概念を一挙紹介!