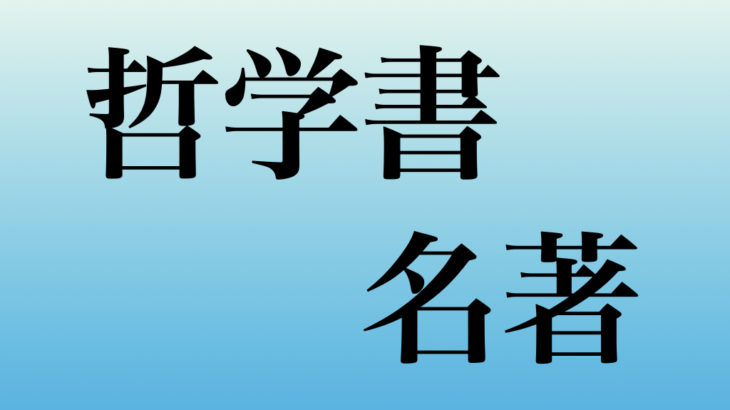- 1. 哲学名著を読もう
- 2. 1位〜5位:5大哲学者の必読名著
- 3. 6位〜10位:死ぬまでに読まねばならない哲学書
- 4. 11位〜20位:一度は読みたい哲学書
- 4.1. 11位:フロイト『ドストエフスキーと父親殺し/不気味なもの』
- 4.2. 12位:ヒューム『人間本性論』(1739年)
- 4.3. 13位:フッサール『イデーンI』(1913年)
- 4.4. 14位:フーコー『監獄の誕生』(1975年)
- 4.5. 15位:マルクス『資本論』(1867年)
- 4.6. 16位:ハンナ・アーレント『活動的生』(1958年)
- 4.7. 17位:ショーペンハウアー『意志と表象としての世界』(1819年)
- 4.8. 18位:ヴィトゲンシュタイン『論理哲学論考』(1921年)
- 4.9. 19位:メルロ=ポンティ『知覚の現象学』(1945年)
- 4.10. 20位:レヴィナス『全体性と無限』(1961年)
- 5. 21位〜32位:できれば読みたい哲学書
- 5.1. 21位:ドゥルーズ『差異と反復』(1968年)
- 5.2. 22位:キルケゴール『死に至る病』(1849年)
- 5.3. 23位:カンタン・メイヤスー『有限性の後で』(2006年)
- 5.4. 24位:スピノザ『エチカ』(1677年)
- 5.5. 25位:ヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術』(1936年)
- 5.6. 26位:サルトル『存在と無』(1943年)
- 5.7. 27位:ルソー『人間不平等起源論』(1755年)
- 5.8. 28位:ジェレミー・ベンサム『道徳および立法の諸原理序説』(1789年)
- 5.9. 29位:ライプニッツ『モナドロジー』(1720年)
- 5.10. 30位:マックス・ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』
- 5.11. 31位:アダム・スミス『国富論』
- 5.12. 32位:クロード・レヴィ=ストロース『野生の思考』
- 6. ほかの哲学書にも挑戦しよう
哲学名著を読もう
哲学は入門書から入るべきか哲学著作から入るべきか。
結論から先に述べておくと、どっちでも良い。哲学への入門の仕方は人それぞれである。入門書から入る人もいれば哲学書から入る人もいる。正解はない。ただし、そのあと入門書だけ読んでるのではダメだし、原著しか読まないのもよくない。哲学書を読んで自分はこういう読みをするという自分なりの読み方を自覚することが哲学書を読むということである。そのためにある程度の相対化も必要で、他の人がどんなことを考えるているのか他の解説書などで知っておくことが重要である。あとは量を重ねていこう。読みまくればなんとなく哲学が分かってくる。
今回「なるほう堂」では、哲学書だったらどれから読めばいいの?と悩んでいるあなたに、その哲学者の主著から選りすぐったものをランキング形式でご紹介。古代に興味があればプラトンから、現代哲学に興味があればデリダなどの著作をまず手に取るのが良い。そこから徐々に哲学書の範囲を広げていこう。教養としても知っておいた方が良い。初学者から大学生まで読んでいて損はない。
1位〜5位:5大哲学者の必読名著
哲学者を5人挙げるとしたら誰?という問いがあって、それに選ばれるのが、プラトン、アウグスティヌス、デカルト、カント、ハイデガーである(諸説あり)。1位から5位まではその五人の哲学者の著作がランクインした。
1位:カント『純粋理性批判』(1781年)
やはり哲学書といったら1位はこれ。大陸合理論とイギリス経験論をつなぎ合わせることで完成したカントの主著『純粋理性批判』。そこで彼は超越論的哲学という主観性の哲学を立ち上げた。
主観というOSが存在するというコペルニクス的転回。しかし、その前提にはアンチノミーの発見があった。ドイツ観念論から思弁的実在論までの哲学の伝統を理解するためには、絶対読まなければならない必読書である。
入門書・解説書紹介:カントを学ぶのにおすすめ入門書・解説書
2位:デカルト『省察』(1641年)
疑いえないものってなんだ?中世神学の時代も過ぎ去り基盤が不確かとなっていった時代に、唯一で絶対確実な真理を打ち立てるのに情熱を注いだのがデカルトである。
そのデカルトの形而上学の全てが詰まっている、それが『省察』だ。あらゆるものを徹底的に疑う方法的懐疑の末に到達した真理とは!これも、その後の哲学史を理解する上で必読書の部類に入る。
入門書・解説書紹介:デカルト哲学を学ぶのにおすすめ入門書・解説書
関連記事:デカルト『省察』超入門|目的、主題、要約、名言、有名な箇所を分かりやすく解説
3位:ハイデガー『存在と時間』(1927年)
20世紀最大の哲学書と呼ばれる『存在と時間』。存在とは何か、ついに新たに存在の意味を問う時代がやってきた。格別な存在者である現存在は、不安に打ち勝ち本来性にまでたどり着くことができるのか。ハイデガー以後の哲学者はほとんどハイデガーの影響を受けている。
なかには、難解なハイデガー用語をそのまま使っている哲学者もおり、『存在と時間』を知らないとよくわからない哲学書もある。それゆえ、堂々の3位ランクイン。
邦訳は今紹介している細谷訳の『存在と時間』(ちくま学芸文庫)が、専門家から最も評価が高い。
入門書・解説書紹介:ハイデガーを学ぶのにおすすめ入門書・解説書
関連記事 :ハイデガー『存在と時間』解説|目的、主題、要約、有名な話題を紹介。
4位:プラトン『国家』
プラトンの中期対話編。副題は「正義について」。国家とは、政治の目指すべきあり方とは。プラトンのイデア思想を個人だけでなく国家にまで貫徹させようとした壮大な哲学体系がここにある。有名な「洞窟の比喩」もこの著作にある。
政治哲学を語る上での古典であり、政治哲学は必ず『国家』を参照する(例えばハンナ・アーレントの著作)。政治哲学を語る上で、避けては通れない書物である。
ちなみに一般に広く知られているのは、『ソクラテスの弁明』の方かもしれない。ソクラテスは「無知の知」で有名で、この本はAudibleで無料で聴くことができる。
入門書・解説書紹介:プラトン哲学を学ぶのにおすすめ入門書・解説書
5位:アウグスティヌス『告白』(397~400)
「取りて読め」。アウグスティヌスは決定的な回心をする。幼少期の過ちと怠惰、青年期の放埒から信仰に目覚めるまでのキリスト教最大の教父、アウグスティヌスの生々しい告白。それでいて時間論などの精密な考察も数多く含まれる。現代哲学の方向性を示した教父哲学の名著である。
時間論が有名で、読んでいて損はない。またフッサールがアウグスティヌスの言葉をさまざまなところで引用しているように、西洋哲学では広く知られた古典的名著である。
入門書・解説書紹介:アウグスティヌスを学ぶのにおすすめの入門書・解説書
6位〜10位:死ぬまでに読まねばならない哲学書
6位:アリストテレス『形而上学』
千年以上にわたって西洋の世界観に決定的な影響を与えたばかりでなく、西洋哲学の枠組みも規定した名著。哲学の最も根本的な問題の探究をめぐってアリストテレスは奮闘する。『形而上学』によって基本的な哲学用語や哲学の命題が決定することになる。哲学の前提知識として読んでおいた方が良い。
邦訳は岩波文庫の『形而上学』(上下2冊)が手軽でおすすめである。
入門書・解説書紹介:アリストテレス哲学を学ぶのにおすすめ入門書・解説書
関連記事:形而上学とは何か|わかりやすく解説
7位:ニーチェ『善悪の彼岸』(1886年)
ニヒリズムやルサンチマン、永劫回帰などの概念を提唱したニーチェの代表作。過去の哲学がキリスト教の道徳的前提を暗黙のうちに受け入れていたことを徹底批判。
本来の哲学はこれら秩序・道徳に対する反対運動でなければならない。善悪を超えて彼岸へ、そこには何が待ち受けているのか。現代思想の源流であるニーチェを読まずして、現代思想を読み解くことはできない。
入門書・解説書紹介:ニーチェを学ぶのにおすすめ入門書・解説書
8位:デリダ『エクリチュールと差異』(1967年)
初期の代表作。痕跡、差延、脱構築などのデリダ的概念がここに展開される。異色の論文集であり、フーコー、レヴィナス、フロイト、バタイユ、レヴィ=ストロースの読解を縦横無尽に駆け巡る。ここからフランス現代思想が始まる。
とりわけフランス現代思想の考え方を知りたい人は、デリダから始めるのが良いだろう。
入門書・解説書紹介:デリダを学ぶのにおすすめ入門書・解説書
9位:ベルクソン『意識に直接あたえられたものについての試論』(1889年)
ベルクソンの博士論文であり主著。感覚や情緒、それらの多様性とそれらが「持続」において展開する有機的組織化の考察を通じて、全く斬新な行為論・自由論が提示される。フランス・スピリチュアリスムの決定的著作。
『時間と自由』という通称でも有名。原著はどちらも同じ著作である。
入門書・解説書紹介:ベルクソンを学ぶのにおすすめ入門書・解説書
10位:ヘーゲル『精神現象学』(1807年)
ヘーゲルの主著。カント、フィヒテ、シェリングを乗り越えてドイツ観念論の最終地点が描かれている。観念論の立場から弁証法を展開し、絶対精神へと至る。
その道程はいかなるものだろうか。後世の哲学とりわけマルクス主義などに決定的な影響を与えた大著である。
入門書・解説書紹介:ヘーゲルを学ぶのにおすすめ入門書・解説書
11位〜20位:一度は読みたい哲学書
11位:フロイト『ドストエフスキーと父親殺し/不気味なもの』
精神分析という新たな学問分野を生んだフロイト。彼が哲学に持ち込んだのは性や死の欲動、無意識というまったく新しいものであった。
本書では、フロイトの重要概念「父殺し」や「不気味なもの」を解説した重要論文を収録。精神分析の核心に迫る。
入門書・解説書紹介:フロイトを学ぶのにおすすめ入門書・解説書
12位:ヒューム『人間本性論』(1739年)
人間本性とはなんだろうか。それを追求したヒュームの代表作が本書『人間本性論』である。ヒュームは徹底した懐疑論者だったのだろうか。ヒュームは自らの懐疑論を「緩和された懐疑主義」と呼んでいる。
ヒュームは懐疑の末に、それを理性に解消するのではなく、緩和したまま残すという態度をとった。そこがヒュームの魅力であり、その魅力が存分に現れているのが本書だ。哲学史を学ぶ上で、カントに決定的に影響を与えたヒュームの思想は見逃せない。
入門書・解説書紹介:ヒューム哲学を学ぶのにおすすめの入門書・解説書
関連記事はこちら:人間本性論の紹介
13位:フッサール『イデーンI』(1913年)
現象学の創始者フッサールの主著である。本書では現象学の根本的な方法、現象学的還元の思想が本格的に導入される。エポケーの先に開かれる現象学的領野はどのようなものなのか。
意識の本質である志向性の解明を軸に、人間の意識の全貌が明らかにされていく。そのほかに間主観性などの概念が登場する。現象学を学ぶなら、まずこの著作からで良いだろう。
入門書・解説書紹介:フッサールの哲学を学ぶのにおすすめの入門書・解説書
14位:フーコー『監獄の誕生』(1975年)
フランス現代思想の一人、フーコによる権力論である。規律・訓練などの概念を使って、権力の発展とその構造について、人間がどのように権力と向き合っているのかを古代から遡って徹底的に解明していく。
現代の政治状況にもつながる話で、権力や政治を理解したい場合に欠かせない一冊。
入門書・解説書紹介:フーコーの哲学を学ぶのにおすすめ入門書・解説書
関連記事:フーコー=デリダ論争とは何か
15位:マルクス『資本論』(1867年)
ドイツの社会学者カール・マルクスによる経済学の書である。ドイツ哲学の集大成とされるヘーゲルの弁証法を批判的に継承した上で、それを経済学に応用し、資本主義的生産様式や資本の運動所法則を明らかにし、唯物論哲学を唱えた。
共産主義の思想に決定的に影響を与えた書物である。
入門書・解説書紹介:マルクスの思想を学ぶのにおすすめ入門書・解説書
関連記事:カラタニその可能性の消尽『力と交換様式』書評・要約・解説
16位:ハンナ・アーレント『活動的生』(1958年)
ユダヤ人哲学者ハンナ・アーレントの哲学的主著『人間の条件』のドイツ語版。アーレント思想の核心をなす現代の古典である。
人間における労働・仕事・活動という三つの能力を切り分けながら、人間の条件を徹底的に考察していく。
入門書・解説書紹介:アーレントの哲学を学ぶのにおすすめ入門書・解説書
17位:ショーペンハウアー『意志と表象としての世界』(1819年)
ヘーゲルと同世代の哲学者であるショーペンハウアーの主著『意志と表象としての世界』カント哲学を引き継ぎながら認識論の世界に意志の力を注ぎ込んだ全く新しい哲学。
ショーペンハウアーの意志優位の哲学が、現代思想の源流の感性優位の哲学の土台を形作る。
入門書・解説書:ショーペンハウアーの哲学を学ぶのにおすすめ入門書・解説書
18位:ヴィトゲンシュタイン『論理哲学論考』(1921年)
言語哲学の基礎を形作ったヴィトゲンシュタイン唯一の生前刊行作『論理哲学論考』。体系的に番号づけられた「命題」からなる本書は、世界を論理空間として形作る。
それでは論理空間の外側は?「語り得ぬものについては沈黙せねばならない」という名言の意味が、この著作で明らかとなる。
入門書・解説書紹介:ウィトゲンシュタインの哲学を学ぶのにおすすめ入門書・解説書
19位:メルロ=ポンティ『知覚の現象学』(1945年)
メルロ=ポンティの二つ目の主著が『知覚の現象学』である。フッサールの還元思想を引き継いだ先に待っていたのは、完全な還元は存在しないということであった。そこから独自の身体の哲学が始まる。揺らぎの中で蠢く身体の運動を哲学的に記述する。
入門書・解説書紹介:メルロ=ポンティを学ぶのにおすすめ入門書・解説書
20位:レヴィナス『全体性と無限』(1961年)
ユダヤ人哲学者レヴィナスの主著。存在論に陥らないようにすればどうすればよいのか。存在論の外部の探究により新たなレヴィナス哲学が開かれる。それは無限という他者の到来を意味するものであった。現代思想の他者論の出発点がここで明らかとなる。
講談社版の『全体性と無限』が新訳である。岩波文庫版よりもこちらをおすすめする。
入門書・解説書紹介:レヴィナスの哲学を学ぶのにおすすめ入門書・解説書
関連記事:レヴィナスにおける他者と責任とは何か
21位〜32位:できれば読みたい哲学書
21位:ドゥルーズ『差異と反復』(1968年)
フランス現代思想の差異の思想がここに。フランスの哲学者ジル・ドゥルーズは本書で同一性の問題に焦点を当て、そこから同一性で処理できないような差異とその反復の過程を明らかにする。
入門書・解説書紹介:ドゥルーズ哲学を学ぶのにおすすめ入門書・解説書
22位:キルケゴール『死に至る病』(1849年)
「死に至る病とは絶望である」。それまでのヘーゲル的な理性主義の哲学を批判し、新たなる実存思想の立場から哲学を開始する。
絶望に陥った人間精神の心理を事細かに描写し考察する様は圧巻である。人間にとって不安とは、そして死とはいったい何なのだろうか。
入門書・解説書紹介:キルケゴールの哲学を学ぶのにおすすめ入門書・解説書
23位:カンタン・メイヤスー『有限性の後で』(2006年)
現代を生きる思想家メイヤスーの主著が『有限性の後で』。カント的な有限性の後に開かれる別の可能性とは一体何なのか。そこに登場するのは別様にいくらでも切り替わる偶然性だった。思弁的実在論の最先端をなすおすすめ著作。
24位:スピノザ『エチカ』(1677年)
ユダヤ教を破門されたスピノザはスコラ哲学とデカルトを徹底的に研究した。そこから新たなる倫理学(エチカ)が開かれる。幾何学的秩序によって論証された本書によって、われわれが今いる場所でどのように住み、どのように生きていくのかを解き明かしていく。
入門書・解説書紹介:スピノザ哲学を学ぶのにおすすめ入門書・解説書
25位:ヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術』(1936年)
巨大な思想家ベンヤミンの刺激あふれる先駆的映像芸術論。映像の世紀である20世紀には写真や映画にどのような可能性が含まれているのか。ベンヤミンが明らかにする。
入門・解説書紹介:ベンヤミンを学ぶのにおすすめ入門書・解説書
26位:サルトル『存在と無』(1943年)
実存思想を切り開いたサルトルの哲学的主著『存在と無』。
現象学にハイデガー由来の存在論にヘーゲル的弁証法を合体させてできた思想は、存在と無の戦いであった。日本で一世を風靡したサルトル独特の存在論へご招待。
入門書・解説書紹介:サルトルを学ぶのにおすすめ入門書・解説書
関連記事:サルトル『嘔吐』なぜ吐き気を催すのか|あらすじ・解説・考察
27位:ルソー『人間不平等起源論』(1755年)
哲学者ジャン=ジャック・ルソーによる政治哲学の著作。題名の通り人間の不平等の起源を考察した著作である。
ルソーによれば原初の状態(自然状態)においては教育・言語・階層もないため不平等は存在しない。それではどのように社会によって不平等が作られているのか。後世にも大きな影響を与えた必読書。
入門書・解説書紹介:ルソーを学ぶのにおすすめ入門書・解説書
28位:ジェレミー・ベンサム『道徳および立法の諸原理序説』(1789年)
刊行より200年以上経っても、倫理学、法哲学、政治思想など広範な分野に圧倒的な影響を与えている名著。最大多数の最大幸福という功利主義の原則はいかにして可能なのか。ベンサムの挑戦が始まる。
入門書・解説書紹介:ベンサムを学ぶのにおすすめ入門書・解説書
29位:ライプニッツ『モナドロジー』(1720年)
ライプニッツの哲学といえばモナドロジーである。モナドとは単純な実体のことで「モナドには窓がない」という言葉が有名だ。まったく他と関係しない単純な実体モナドが、いかにして他のモナドと調和するのか。モナドの表象から神の存在まで、広範な領域を取り扱う。
30位:マックス・ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』
ドイツの社会学者マックス・ヴェーバーによる資本主義の研究。プロテスタントの禁欲主義が逆に資本主義の「精神」に適合しており、近代資本主義の基盤となったことを示した書。
入門書・解説書紹介:ウェーバーを学ぶのにおすすめ入門書・解説書
31位:アダム・スミス『国富論』
近現代経済学の出発点に位置づけられる古典中の古典。それまでの経済思想史や経済政策に関する論究など幅広い研究が登場する。ここから全ての経済理論が始まる。
入門書・解説書紹介:アダム・スミスを学ぶのにおすすめ入門書・解説書
32位:クロード・レヴィ=ストロース『野生の思考』
構造主義の発火点。ここから実存主義を葬り去り、構造主義の歴史が始まった。人類学のデータを元に未開人を探求する。彼らの思考は野蛮な思考ではない。そう、野生の思考なのである。
入門書・解説書紹介:レヴィ=ストロースを学ぶのにおすすめ入門書・解説書
ほかの哲学書にも挑戦しよう
本記事では古今東西の哲学名著を紹介しました。読んだことのない哲学書も多いかとは思いますが、コツコツ読んでいくことが重要です。めげずに頑張りましょう。
哲学の重要概念は「哲学の最重要概念入門」、日本の哲学書のおすすめは「日本の哲学書おすすめ名著」、哲学入門書のおすすめは「哲学初心者向けの人気おすすめ入門書」、フェミニズム入門は「フェミニズムの最新おすすめ入門書」、倫理学の入門書は「倫理学のおすすめ入門書・解説書」、論理学・分析哲学の入門書は「論理学・分析哲学のおすすめ入門書」、プラグマティズムの入門書は「プラグマティズムのおすすめ入門書・解説書」、現象学の入門書は「現象学のおすすめ入門書と専門書」で紹介しています。ぜひこちらもご覧ください。
また文学や映画なども嗜むと、より教養が深まります。挑戦してみましょう。
文学のおすすめに関しては、純文学は「純文学のおすすめ作品」、イギリス文学は「イギリス文学のおすすめ作品」で紹介しています。ぜひこちらもご覧ください。