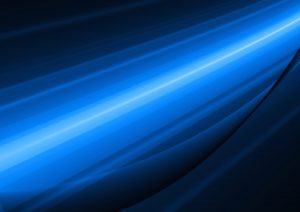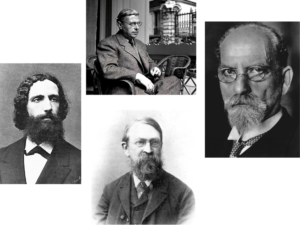永劫回帰の意味
永劫回帰(ewige Wiederkehren)はニーチェの根本思想である。”ewige” が「永遠の」という意味の形容詞、”Wiederkehren”が「再帰」「繰り返し」という意味の名詞である。他に「永遠回帰」とも呼ばれる。
永劫回帰とは、「あらゆる出来事が永遠に繰り返されること」をいう。ニーチェの場合は、そこに歴史意識が加えられている。すべてが永遠に繰り返すということは、歴史において、キリスト教思想が告知したような終わりや始まり(終末論)がないということである。また、ヘーゲルのような弁証法的発展も歴史には存在しない。それ自体目的のない歴史、永遠に繰り返し回帰する歴史、という発想が「永劫回帰」である。
永劫回帰は忌避すべきものなのか?
「永劫回帰」はネガティブな意味に捉えられることが一般的である。「ヨーロッパのニヒリズム」(『ニーチェ全集第9巻』白水社、1984年、278頁)では、永劫回帰を「ニヒリズムの最も極端な形式」と呼んでいる。永遠に同じことが繰り返されるというのは苦痛である。これが一般的な考え方だ。
しかしニーチェは次のようにも言っているのだ。
この作品の根本着想、すなわち永劫回帰思想、およそ到達しうるかぎりの最高のこの肯定の方式は・・・
『この人を見よ』142頁
永劫回帰は本当は「最高の肯定」だというのである。つまり、ここでは非常にポジティブな意味で永劫回帰を捉えている。このようにニーチェの「永劫回帰」という概念の特徴には、一般的にネガティブな意味で捉えられている永劫回帰という観念を、180度ひっくり返して肯定したところにある。その悪戦苦闘の歴史が記されているのが『ツァラトゥストラはこう言った』(以下『ツァラトゥストラ』)となる。
永劫回帰の思想読解
『ツァラトゥストラ』における「永劫回帰」
先ほどの引用の「この作品」とは『ツァラトゥストラ』のことを指す。つまり、『ツァラトゥストラ』は永劫回帰の思想が反映された書物なのだ。読むとわかるが、この書物は、いかに主人公のツァラトゥストラが、永劫回帰のニヒリズムを克服して肯定できるようになるのかを記した書となっている。初めはツァラトゥストラ自身も完全には受け入れられないのだが、徐々に克服して、最後には永劫回帰を教えるものとなる。
永劫回帰について語っている箇所から、重要な箇所をピックアックして解説することにする。
なぜ世界は永劫回帰なのか
永劫回帰という発想がどうして正当化されるのかを記しているのが、『ツァラトゥストラ』第三部「幻影と謎」である。ここでニーチェは永劫回帰という思想を図式化している。
永劫回帰の思想は道に喩えられている。道の間には門があり、両側に道が続いている。この門の名は「瞬間」である。そしてこの「瞬間」の背後には永遠の道が遥々続いている。そのことに関して、ツァラトゥストラは一つの問いを投げかける。
およそ走りうるすべてのものは、すでに一度この道を走ったことがあるのではなかろうか?およそ起こりうるすべてのことは、すでに一度起こり、行なわれ、この道を走ったことがあるのではなかろうか?
『ツァラトゥストラ(下)』21頁。
さらにこの門(瞬間)も過去にすでにあったことにならないだろうか、自分自身もあったことにならないだろうか、とツァラトゥストラは問いかける。
これは「永遠」ということが非常に重要である。過去が有限だったら、出来事が繰り返されるのかは断定できない。しかし過去が永遠、つまり無限だったとしたら、過去には全てがあることになる。それゆえ、過去が無限に続いている以上、永劫回帰が結論づけらるのだ。
観念的な・抽象的な考え方ではあるだろう。また現代においては物理科学の立場から世界の始まり(ex. ビックバーン)について語られるので、過去が無限に続いているというのも信憑性は薄い。しかし、ニーチェは様々な直感から永劫回帰という発想に到達した。
永劫回帰を克服する勇気
この永劫回帰の思想にツァラトゥストラは「恐怖」を感じている。しかしこの節では、この「恐怖」を打ち破るための一つの手段を披露している。それが「勇気」だ。
「勇気はまた同情をも打ち殺す」。これは人生の苦悩に対する同情なのだが、その同情というのはルサンチマンから発生する道徳感情である。つまり、同情は永劫回帰を肯定することはできず、むしろ否定してしまう。逆に「勇気」は永劫回帰に対してどのような態度を取るのか。
進んで攻める勇気、それは死をも打ち殺す。なぜなら勇気はこう言うからだ。「これが生きるということであったのか? よし! もう一度!」
同書、19頁。
死というのは、仮に人生が苦悩とみなされれば、その開放であり救いとなるだろう。しかし、実際は世界は永劫回帰であり、その苦悩がまた再帰することになる。それなら生(苦悩)を肯定するしかないし、肯定するべきなのだ。「よし!もう一度!」、これは永劫回帰をもう一度繰り返すポジティブな決意である。
『ツァラストゥストラ』第四部「酔歌」から読み解く
「概要」でも述べたように、永劫回帰自体は単純なことである。生には始まりも終わりもないということである。目的がないと言い換えてもよい。単に繰り返しているだけである。そんな状況をショーペンハウアー的なペシミズムは肯定できない。彼は、一切は虚しい、と解釈するのである。それゆえ人生は虚しく意味がないので、(形而上学的な意味で)苦痛である。その考えを突き詰めれば、永劫回帰は「ニヒリズムの最も極端な形式」であるという結論に帰着するだろう。
しかし、永劫回帰が真理であるという事実は変わらない。いくら嘆いてもこの事実は変わらない。だからこそこの事実は肯定されるべきだ、とニーチェは考える。この肯定を『ツァラトゥストラ』では「よろこび〔Lust〕」という言葉で言い表している。
よろこびは、しかし、あとを継ぐものを欲しない。子どもたちを欲しない、ーーよろこびは自己自身を欲する。永遠を欲する。回帰を欲する。一切のものの永遠の自己同一を欲する。
『ツァラトゥストラ』第四部 酔歌 9
「よろこび」は厳密に哲学的な概念として使用されている。例えば「あこがれ」と「よろこび」は異なるとニーチェは言う。「あこがれ」はより高いものを目指し、「あとを継ぐもの」を欲し、自分自身を欲しない。「よろこび」はよろこび自身を欲するのだ。すなわち、永劫回帰と自己同一化を欲するのである。この自己同一化というのは、始まりと終わりが一緒という円環を表している。
苦痛はまたよろこびであり、呪いはまた祝福であり、夜はまた太陽なのだ、ーー去る者は去るがいい!そうではないものは学ぶいい、賢者はまた愚者だということを。
『ツァラトゥストラ』第四部 酔歌 10
ここには永劫回帰の円環の思想が反映始まりが苦痛で終わりがよろこびだとしても、始まりと終わりは一致する。ということは苦痛はよろこびなのだ。結局すべてが円環の輪の中で繰り返されるということだろう。
ーーあなたがた永遠の者よ、この世を永遠に、常に、愛しなさい!そして嘆きに対しても言うがいい。「終わってくれ、しかしまた戻ってきてくれ!」と。なぜなら、すべてのよろこびはーー永遠を欲するからだ。
『ツァラトゥストラはこう言った』第四部 酔歌 10
この世が永遠だとしたら、この世には肯定されるべきものしかない。嘆きも肯定する必要がある。なぜなら嘆きもよろこびの一部だからである。円環は輪なのだから、それら嘆きやあこがれ、苦痛もすべてをその円環の中でよろこびへと帰っていくからだ。永劫回帰の肯定とは結局のところすべての肯定である。それはありのままの生の肯定であり、生の事実の肯定である。
補足解説
なぜ永劫回帰が「最高の肯定の形式」とならざるを得ないのか
永劫回帰とは、よくよく考えると、それ自体われわれにとっては普通の考え方ではないだろうか。神は死んだんだ!と訴えられても、まあそうですよね、としか答えられないし、世界は永遠に繰り返されるんだぞ!と切実に訴えられても、それはそれで良くないですか?という感想を抱く人も多いだろうと思う。それなのになぜ永劫回帰という考え方がニーチェの思想にまで発展し、さらにそれを肯定しなければならないんだあ!とツァラトゥストラによって強く訴えられなければならなかったのか。
まず、その考え自体は西洋哲学の伝統の中では珍しいものであったということが挙げられる。ちょっと前の時代に優勢だったのがヘーゲル的な歴史観である。それは弁証法的歴史観であり、それも永劫回帰と同じように生成の歴史観であるが、プラスして発展という構造も持ち合わせていた。つまり何らかの形で始まりと終わりがある。しかしそういった歴史観はもはや信じられない時代がニーチェの時代には到来しており、そこでニーチェが感づいた考えが永劫回帰である。
しかしどうして永劫回帰をことさらに肯定したがるのか。それは一つにそのような状況に対する生へのペシミズムが蔓延していると考えたからだろう。例えばショーペンハウアーから古代ギリシアまで、生きているのは苦痛で良くないことだという価値観があった。ニーチェはショーペンハウアーのような思想をニヒリズムとして批判している。ペシミズムのような否定の思想を拭い去らなければならない。
しかしなぜ拭い去らなければならないのか。仮に生に本当に意味がなくショーペンハウアーのような考えが正しいのなら、それはしょうがないことではないのか。しかし価値とは解釈でしかない。それに対して永劫回帰は事実である。永劫回帰が事実であるということは、それは生の基盤・基礎であり、それを土台として我々人間が生きているということなのだ。哲学的に考えてみよう。ニーチェは生の根源を発見した。永劫回帰は根源である。そしてそれは根源なのだから、哲学的には肯定しなければならないのである。
例えばカントの超越論的観念論やフッサールの現象学的領野を彼ら自身が否定的に扱うことはできないだろう。というのもそれは世界の可能性としての現実でしかないからである。ニーチェの永劫回帰も同じことだろう。
だからこそ、この円環の思想は、同一性ということも語られる。同一性、これは哲学が常に基礎として求めてきたことだった。価値の彼岸に同一性があり、それを基礎とするということはそれこそ古典的な哲学の考え方である。その意味で、ニーチェは古典的な哲学者でもある。ニーチェの思想は難しいが、このように哲学の歴史の中に置き入れてみると(正しいのか正しくないのかは別として)意外とその全貌が見えやすくなるということはある。
〈永劫回帰〉を知りたい人におすすめ著作
関連項目
哲学の入門書:哲学初心者向けの人気おすすめ入門書を紹介!
哲学書の名著:本格的な人向けおすすめ哲学書を紹介!
日本の哲学書の名著:おすすめの日本の哲学書を紹介!
参考文献
須藤訓任編『哲学の歴史第9巻 反哲学と世紀末』中央公論新社、2008年。
ニーチェ『ツァラトゥストラはこう言った(下)』氷上英廣訳、岩波文庫、1970年。