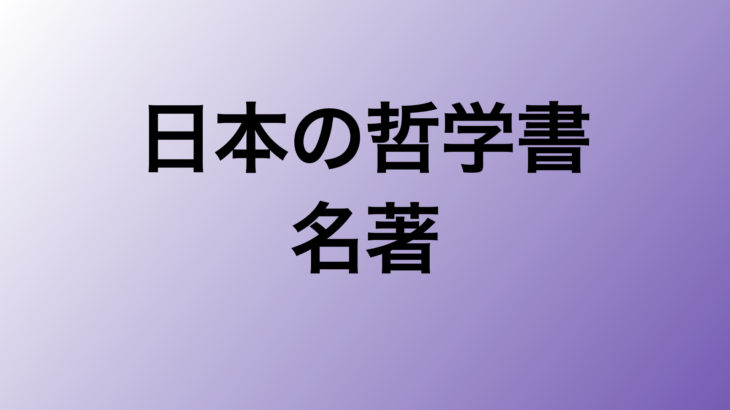- 1. 日本の思想書名著を読もう
- 2. 27〜1位:できれば死ぬまでに読みたい哲学書
- 2.1. 27位:入不二基義『現実性の問題』2020年
- 2.2. 26位:中島義道『不在の哲学』
- 2.3. 25位:村上靖彦『自閉症の現象学』
- 2.4. 24位:鶴見俊輔『戦後日本の大衆文化史 1945〜1980』
- 2.5. 23位:千葉雅也:『意味がない無意味』
- 2.6. 22位:三木清『構想力の論理』1939年
- 2.7. 21位:廣松渉『世界の共同主観的存在構造』
- 2.8. 20位:田邊元『種の論理』
- 2.9. 19位:浅田彰『逃走論ーースキゾ・キッズの冒険』
- 2.10. 18位:斎藤幸平『人新世の資本論』2020年
- 2.11. 17位:坂部恵『仮面の解釈学』
- 2.12. 16位:大森壮蔵『言語・知覚・世界』
- 2.13. 15位:中村雄二郎『共通感覚論』1979年
- 2.14. 14位:森岡正博『無痛文明論』2003年
- 2.15. 13位:吉本隆明『共同幻想論』1968年
- 2.16. 12位:道元『正法眼蔵』
- 2.17. 11位:國分功一郎『中動態の世界』2017年
- 2.18. 10位:鷲田清一『「聴く」ことの力ーー臨床哲学試論』
- 2.19. 9位:九鬼修造『偶然性の問題』
- 2.20. 8位:竹田青嗣『欲望論第1巻「意味」の原理論』
- 2.21. 7位:永井均『存在と時間 哲学探究1』
- 2.22. 6位:(親鸞)『歎異抄』
- 2.23. 5位:木村敏『時間と自己』
- 2.24. 4位:柄谷行人『力と交換様式』2022年
- 2.25. 3位:東浩紀『ゲンロン0 観光客の哲学』2017年
- 2.26. 2位:和辻哲郎『風土 人間学的考察』
- 2.27. 1位:西田幾多郎『善の研究』
- 3. ほかの哲学書にも挑戦しよう
日本の思想書名著を読もう
日本の思想書のどれから読んだら良いか。
日本には思想書と呼ばれるものが幅広く存在します。仏教系の思想書もあれば、現代になって西洋哲学から影響を受けて書かれた思想書(哲学書)もあります。内容もさまざまです。
日本の思想書の場合、それほど歴史を引き継いでいませんので、これだけは読んでおかないと内容が分からない(これだけは読むべき)というものがあまりありません。仏教の影響を受けている思想は仏教系の知識が、現代思想の影響を受けている著作ならハイデガーやデリダ、ドゥルーズの知識が必要かもしれません。とりあえずは興味がある本から読んでみて、そこから興味を広げていくのをお勧めします。まずは難しくても読んでみて、その思想に触れてみるべきです。分からなければ入門書がありますので、そちらを読むのが良いでしょう。
では、どれを呼んだら良いの?と悩んでいるあなたに、その哲学者の主著から選りすぐったものをランキング形式でご紹介しましょう。
27〜1位:できれば死ぬまでに読みたい哲学書
27位:入不二基義『現実性の問題』2020年
『相対主義の極北』など他にも名著がある入不二氏の最新の著作。
離別と死別という二つの体験をもとにして考察を深めていきます。さて、この二つの別離の違いは何なのでしょうか。現実性の問題はここから始まります。
26位:中島義道『不在の哲学』
古来から西洋哲学の中心を占めてきたのは存在論でした。しかしそのような普遍的「実在」を中心に据えるのではなく、逆に「不在」こそが中心概念であるという立場から哲学の難問に取り組みます。
中島哲学をしるにはうってつけの書物です。
25位:村上靖彦『自閉症の現象学』
現象学者の村上靖彦の初期の作品です。
「自閉症」を世界で初めて現象学から読み解きます。現象学によって明らかにされる彼らの世界の形はいかなるものでしょうか。そしてそれは哲学的にどのような意味を帯びるでしょうか。
フッサールの概念などを利用しながら考察を深めていくおすすめの書です。
24位:鶴見俊輔『戦後日本の大衆文化史 1945〜1980』
アメリカのプラグマティズムに影響を受けた鶴見俊輔の日本文化論です。
カナダの大学で学生に向け語られた広い視野からの現代日本思想史前篇となっています。鶴見がとくにこどわったのは日本人の「転向」という側面でした。そのことから日本の精神史を貫く「文化の鎖国性」を読み解きます。日本人論としては必見の書です。
23位:千葉雅也:『意味がない無意味』
今や小説家としても有名な千葉雅也氏の哲学的論考集です。はじめにで語られる書き下ろしの「意味がない無意味ーーあるいは自明性の過剰」でその哲学の大枠が語られます。
〈意味がある無意味〉と〈意味がない無意味〉があり、前者による解釈の増殖をストップさせるのが〈意味がない無意味〉です。そこでは「形態」や「儀礼」「社交」が重要な概念として新たに考えられることになります。
22位:三木清『構想力の論理』1939年
「人生論ノート」などで有名な三木清の主著です。
構想力といえばカテゴリーですが、それを三木清は「否定」やヘーゲルの「弁証法」、ハイデガーの哲学の影響を受けながら、構想力という運動の「論理」として展開します。
戦前の作品としてはかなり完成度の高い作品です。
21位:廣松渉『世界の共同主観的存在構造』
廣松渉が挑んだのは「他者」という哲学的難問です。他者はどのようにして存在するのでしょうか。
廣松がその時焦点を当てたのが身体です。身体では私と他者が共存の次元にいます。そのようにして考察を深めていくと、私の存在を可能にするのに他者が必要であることがわかってきます。それが「共同性の存立構造」です。
20位:田邊元『種の論理』
いわゆる「田邊哲学」と呼ばれるような思考を紡ぎ出すようになったのが、この「種の論理」という呼称されることになる独特な論理です。
「種の論理」は社会に適用されることになります。つまりは種というのは個人のことであり、それと別の個人の関係とはどのような関係か、あるいは国家、民族、人類との関係はどのようなものかが「種の論理」で明らかにされます。
19位:浅田彰『逃走論ーースキゾ・キッズの冒険』
浅田彰といえば他に『構造と力』がありますが今回はこちらを選びました。
本著は、一般紙などに寄稿したエッセイなどを集めた論考集となっています。ここで浅田は、ある見方に固執するパラノイア型と物事に固執しないスキゾフレニア型の二つを提出し、前者から後者への移行を促します。「パラノからスキゾへ」というキャッチフレーズは当時の流行語となりました。
18位:斎藤幸平『人新世の資本論』2020年
SDGsに騙されるな、地球も、人も壊される。センセーショナルな言葉が飛び交う現代社会を考えるための哲学書です。
著者の斎藤幸平はマルクス経済学が専門で、その観点から資本主義が及ぼす様々な問題と未来の危機について抉り出します。この危機の時代に処方箋を見つけることはできるのか。そのヒントがここに埋まっているかもしれません。
17位:坂部恵『仮面の解釈学』
仮面をキータームにした独特な哲学本です。
坂部恵といえば日本語の可能性を最大限に活かした論考と文体で有名ですが、本書では「仮面」を主題にして西洋的な表と裏の二元論を乗り越えようとします。
16位:大森壮蔵『言語・知覚・世界』
自分で考える哲学者であり、永井均など多くの哲学者に影響を与えた大森荘蔵の名著です。
ここではのちに「立ち現れ一元論」へと徹底化されていく立場の始まりを見ることができます。
15位:中村雄二郎『共通感覚論』1979年
パスカルやデカルトの研究から出発した日本を代表する哲学者の一人、中村雄二郎。そして『共通感覚論』は彼の主著となります。
中村は「常識」を意味するセンススコムニス(ラテン語)が、アリストテレス哲学では「共通感覚」を意味していたことに注目します。そしてそこから共通感覚という概念の再構成が試みられることになります。
14位:森岡正博『無痛文明論』2003年
本書で森岡は、現代社会が無痛文明へと向かう危惧しています。快楽を求め、苦痛を避ける方向に向かうことで「生きる意味」も見失っていくのではないか。それが現代文明の行き着く先なのだろうか・・・。
『感じない男』で有名な森岡生命論の代表作です。
13位:吉本隆明『共同幻想論』1968年
吉本隆明の主著『共同幻想論』は幻想としての国家の成立を示した国家論です。
国家が成立するには、吉本によれば共同幻想が必要であると説きます。そしてそこに至るまでの過程を自己幻想・対幻想・共同幻想という三つの枠組みで解明していきます。さてこの共同幻想を解体し、乗り越えることは可能なのでしょうか。本書でその可能性が問われることになります。
12位:道元『正法眼蔵』
禅の奥義を追究した道元の名著『正法眼蔵』。難解でしられる本書の中に、道元の思想の真髄が詰まっている。
入門書・解説書紹介:道元を学ぶのにおすすめ入門書・解説書
11位:國分功一郎『中動態の世界』2017年
能動でも受動でもないアスペクト「中動態」。しかしこの中動態は能動と受動の間の態なのではありません。実は古代ギリシアでは能動の対立概念が中動態だったのです。
中動態の概念を考古学的に掘り崩し、現代における意志と責任の問題に挑みます。果たして意志とは、責任とはなんなのだろうか。
中動態に関する詳しい解説記事はこちらからどうぞ。
10位:鷲田清一『「聴く」ことの力ーー臨床哲学試論』
メルロ=ポンティ研究から出発し新たに臨床哲学という分野を打ち立てた鷲田清一。本書では「聴く」という受け身の営みを通じて広がる哲学の可能性を問い直します。
第三回桑原武夫学芸賞を受賞した良作です。
9位:九鬼修造『偶然性の問題』
『いきの構造』で有名な九鬼修造ですが、主著はといえばこの『偶然性の問題』となります。
偶然性というのは哲学にとって一つの大きなテーマでしたが、九鬼は偶然性を定言的偶然、仮説的偶然、離接的偶然の三つに大別して独特な形而上学的展開を思索します。「偶然と必然」を考える上では必読の書となります。
8位:竹田青嗣『欲望論第1巻「意味」の原理論』
竹田哲学待望の本格的な哲学書。
プラトン、アリストテレスからフッサール、ハイデガーと続く哲学の歴史を通覧し、さらにその先の可能性を開きます。そこではなんと欲望という概念が重要な意味を帯びてくるのです。
7位:永井均『存在と時間 哲学探究1』
「私」を徹底的に考えている哲学者永井均の代表作。
本書ではこれまで覆い隠されてきた〈私〉と〈今〉をめぐる問題の核心に迫ります。ちなみに続編が『世界の独在論的構造ーー哲学探究1』です。
6位:(親鸞)『歎異抄』
浄土真宗の開祖、親鸞の思想が書かれた著作です。伝えたのは弟子の唯円だと言われています。
悪人正機説の思想は、もっともグローバル化した現代、文化や信条に基づく憎しみの連鎖を断ち切る鍵になるかもしれません。現代をと問い直すこともできる一冊です。
入門書・解説書紹介:親鸞・浄土真宗を学ぶのにおすすめ入門書・解説書
5位:木村敏『時間と自己』
「フェストゥム論」で有名な精神科医・木村敏の著作です。
精神病理の研究を基に、自己の根源である時間性について解き明かします。
4位:柄谷行人『力と交換様式』2022年
生産様式から交換様式への移行を告げた『世界史の構造』から10年余り、交換様式から生まれる「力」を軸に、柄谷行人の全思想体系の集大成を示します。
関連記事:カラタニその可能性の消尽『力と交換様式』書評・要約・解説
3位:東浩紀『ゲンロン0 観光客の哲学』2017年
『存在論的、郵便的ーージャック・デリダについて』で華々しくデビューした東浩紀氏による哲学的著作です。
本書では観光客という概念が哲学的概念として扱われています。観光客とは「基本的には特定の共同体に属しつつ、時折別の共同体も訪れる」存在ですが、その「観光客」の意義や理論的な説明が提示され、そこから発展していく様々な可能性が述べられることになります。
第71回毎日出版文化賞受賞。
2位:和辻哲郎『風土 人間学的考察』
『人間の学としての倫理学』と悩みましたが、第2位はこの著作とします。
ハイデガー存在論(『存在と時間』)には空間に関する考察が欠けていることに気付いた著者が風土という独特な概念で人間存在の空間的あり方に挑みます。私たちはその日々の暮らし、環境、天候からどのような影響受けているのでしょうか。「モンスーン型」「砂漠型」「牧場型」という類型はあまりにも有名です。
1位:西田幾多郎『善の研究』
日本の最大の哲学者西田幾多郎の主著。日本で最初の本格的な哲学書である本書では、西洋哲学と対峙しながら、主客身分の「純粋経験」に立ち戻り、新たに経験の根源から真理を探っていきます。
紹介している講談社学術文庫の『善の研究』では《全注釈》がついており、非常にわかりやすい構成となっています。堂々の一位です。
入門書・解説書紹介:西田幾多郎を学ぶのにおすすめ入門書・解説書
ほかの哲学書にも挑戦しよう
本記事では日本の哲学名著を紹介しました。読んだことのない哲学書も多いかとは思いますが、コツコツ読んでいくことが重要です。めげずに頑張りましょう。
また世界の哲学名著は「哲学のおすすめ名著」、哲学の重要概念は「哲学の最重要概念入門」、哲学入門書のおすすめは「哲学初心者向けの人気おすすめ入門書」、フェミニズム入門は「フェミニズムの最新おすすめ入門書」、現象学入門は「現象学のおすすめ入門書と専門書」で紹介しています。ぜひこちらもご覧ください。