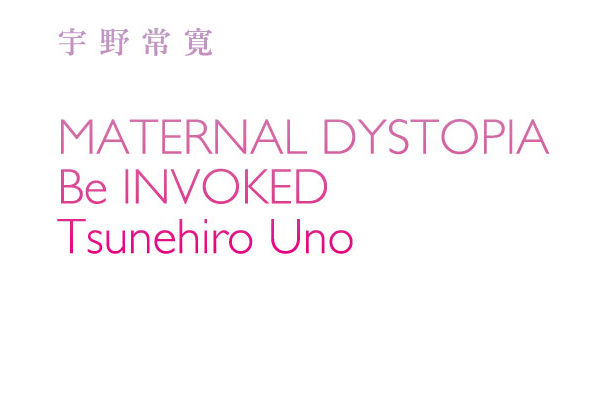母性のディストピアとは何か(解説)
母性のディストピアとは宇野常寛『母性のディストピア』という本の題名であり、この本の骨格をなす概念でもある。はじめに宇野の定義をご紹介しよう。
妻を「母」と錯誤するこの母子相姦的想像力は、配偶者という社会的な契約を、母子関係という非社会的(家族的)に閉じた関係性と同致することで成り立っている。
『母性のディストピア I』45頁
本書では、この母子相姦的な構造を「母性のディストピア」と表現したい。
しかし、どうしてこのような想像力が日本社会では機能しているのだろうか。そこには日本的な成熟像が関係している。
近代社会では人は自立した個人として生きていくことが求められる。この「自立」は性的想像力でいえば、「父性」を背負わされていると言える。この父性でもって自立して生きていくのが普通の成熟の形だ。しかし、戦後日本社会においては父になるために、アイロニカルで歪んだ回路を進んでいかなければいけない。
戦後日本は政治と個人の関係性においてアイロニカルな状況を余儀なくされていた。例えば日本の安全保障体制に関して、一方で憲法9条を改正しようという立場と、他方で憲法9条を断固として守ろうという立場がある。しかし前者ではそれで日本が独立するということではなく、アメリカの後ろ盾を前提とする。後者は、実のところ単なる理想でしかなく、一国平和主義的に血まみれの繁栄を謳歌するという考えが前提としてある。これがアイロニカルな状況である。しかしこの矛盾した構造を知っていながら「あえて」引き受けるというのが、戦後日本的な、歪んだ形ではあるが、成熟(父になること)の形だったのである。
しかしこのように父になるにしても、そこには共犯的な力(想像力)が隠れていると宇野は考える。それが母性である。実のところ、戦後日本において父は自らが父となるためにが妻(母)という共犯者を必要としていた。宇野は江藤淳や村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』に言及しながら、彼らの想像力を指摘する。「江藤/村上の根底にあるのは自分たちは「父」になれない、武器を持てないという諦念である」(『母性 I』43頁)。しかし父になることからは逃れられない。そこで、自分が偽物(虚構)の父であることを自覚しながら(成熟)、父になるために自分の代わりに誰かの犠牲が必要となる。それが基本的には妻的な存在であり、それを母的な存在に組み換えることによって父が成立するのだ。それは母と子という、非常に閉じた公共空間と接続しない関係である。ここに母性のディストピアが爆誕することになる。
『ゼロ年代の想像力』における母性のディストピア
現代において、私たちを縛り付けるのはもはや去勢する父親ではない。そんなものは大きな物語の失効と同時に、とっくに退場している。今、私たちを縛り付けているのはむしろその胎内にすべてを取り込む母親なのだ。
『ゼロ年代の想像力』253−254頁。
母性のディストピアは『母性のディストピア』という著作で正面から論じられるのだが、その概念自体はすでに『ゼロ年代の想像力』に登場している。『ゼロ年代の想像力』第十章「肥大する母性のディストピアーー空転するマチズモと高橋留美子の「重力」」である。
高橋留美子『うる星やつら』では、ラムの母性の暴力/抑圧が描かれる。それを告発したのが押井の映画『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』だ。その作品では夢邪鬼という妖怪が、ヒロイン・ラムの「いつまでもこのメンバーと楽しい学園生活を送りたい」という願望を叶えるため、その世界が夢であるということに気付いたり、ラムの恋敵となる登場人物を次々に石像に変え、その世界から排除していく。その暴力は一般に権力の象徴として描かれる父性からではなく、母性から発せられるのだ。
高橋留美子作品では他でも「凶暴なまでに肥大した母性」描かれる。例えば『めぞん一刻』(1980〜87)である。主人公の五代裕作は、結末でヒロインの管理人・音無響子とめでたく結婚し子供も生まれるが、もと住んでいた一刻館(モラトリアムの象徴)に住み続けることになる。大塚英志はここに「オタク系文化の成熟忌避的な傾向」を読み取ったが、宇野はその母性に注目する。それは「男性の自己実現の回路が女性のテリトリー(胎内)から一歩もはみ出ない範囲で完結することを意味する」(『ゼロ年代』247頁)。ここでは母性のエゴイズムが完全勝利を果たす。
この頃の母性のディストピアは、このように母のノイズを排除するという抑圧・暴力が強調される。
宮崎・富野・押井と母性のディストピア
『ゼロ年代の想像力』で取り扱われた「母性のディストピ」は『母性のディストピア』では、さらに拡張的な概念として扱われる。母性のディストピアは政治と個人、日本の戦後社会の想像力を規定しているのだ。
『母性のディストピア』では3人のクリエイターがその母性のディストピアの観点から取り上げられる。宮崎駿、富野由悠季、押井守である。そのうち宮崎駿はその性的想像力である母性のディストピアを「母性のユートピア」として(つまりディストピアの肯定)、富野は母性のディストピアとして描いた作家として論じられる。
宮崎にとって母的なものは、男性的ロマンティシズム(典型は宮崎作品における飛ぶこと)の追求による自己実現を保証してくれるものであった(ex. 『風立ちぬ』)。つまり母的なものを肯定的に描いたのだ。他方で富野は例えば「少年たちを呪縛し、殺していくディストピアとして描いた」(『母性 I』274頁)。それを最も引き受けたキャラクターがガンダムシリーズに登場するシャアであり、最も色濃く反映させているのが『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』(1988年)である。
押井になると、新たな展開がある。その代表作が『機動警察パトレイバー the Movie』である。『ビューティフル・ドリーマー』から『パトレイバー』への転換について宇野はこう評している。
ここでより重要なのは押井がこれまで構築してきた「夢」の世界から、その世界を呪縛していた少女=母的な登場人物が消失していることだ。そして夢の世界は母胎の比喩ではなく再開発と増殖を機会的に反復する都市ーー東京ーーに置き換わった。この置き換えーーある種の情報論的転回ーーによって押井は世界に対して新しいアプローチを見出すことになった。
『母性 II』55−56頁。
押井の想像力では、母性的なものがもはや登場人物ではなく、そこに登場する都市に置き換わるのである。父を包み込むのは都市なのだ。これを宇野は情報論的転回と呼んでいる。この情報論的転回は現代の情報社会の先取りと見ることもできる。そこで、押井は情報社会という新たな世界におけるモラルを探究したのだが(『パトレイバー2』や『攻殻機動隊』など)、悲しいかな、時代は映像の世紀からネットワークの世紀に移っていく。そこでは押井は「ネットワークの与える全能感に充足しつつ地平する消極的なモラルの提示に」(『母性 II]』176頁)留まっている。映像の世紀の終わりとともに、批判的精神も限界を迎えたのである。
日本的情報社会と母性のディストピアの肥大
戦後といっても、すでに70年以上たった。もうすでにこの国は戦後の文学者が反復してきたアイロニカルな成熟の形を忘れかけている。にもかかわらず「母性」は健在だ。インターネットが新しい「母」として登場したからである。結局母性だけが肥大した。その世界では誰でも簡単に父になることができ(なぜならネット空間がすでに母であり、そこでは見たいものだけを見れるから)、戦後的成熟のためのアイロニー〈あえて〉は必要ない。
映像の世紀で終わりになるはずの母性のディストピアがいまだに肥大している。批判力もないままにである。母性のディストピアは未だに日本社会を覆っている。
>>漫画・イラストレイターを目指すならこちら|アミューズメントメディア総合学院
関連項目
・拡張現実の時代
・シャカイ系
・アトムの命題
・ゴジラの命題
・フェミニズム
・不可能性の時代
・平成転向論
参考文献
宇野常寛『ゼロ年代の想像力』ハヤカワ文庫JA、2011年。
宇野常寛『母性のディストピア I 接触篇』『母性のディストピア II 発動篇』ハヤカワ文庫JA、2019年。