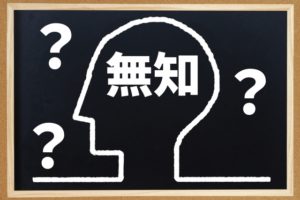意味
方法的懐疑(doute méthodique)とは、ただ疑うだけでなく疑いをさしはさみうるすべてのことに同意しないという方法的態度のことである。
形而上学的な原理を獲得するためにデカルトが提唱した哲学的方法のことであり、単に間違っているから偽というだけでなく、疑わしいものはとりあえず「偽」という形で懐疑を拡張(誇張)しているので、誇張的懐疑とも呼ばれることがある。
主に『方法序説』や『省察』で、その方法論について語っている。
著作読解
『省察』における方法的懐疑
『省察』はデカルトが究極の原理を探究するために方法的懐疑を実践した書物である。『方法序説』にも方法的懐疑の順序は述べられているが、実は『省察』の方がより詳しく語っている。
ここでは、デカルトの方法的懐疑がどのようなものであったのかを『省察』の第一省察から具体的に解説する。
確実に真理といえないものは偽とする
唯一確実な真理を獲得するためにまずどうしたらよいのか。それは真理ではないものを排除していけばよい。しかし、そのためにあらゆる物事を引っ張り出してきて「これは真だ、これは偽だ」といちいち判断を下す必要はない、とデカルトは言う。
むしろ理性がすでに説得しているところによれば、全く確実で疑いえないわけではないものに対しても、明らかに偽であるものに対するのと同じく注意して、同意をさし控えるべきであるので、それらの意見のどれか一つのうちに何か疑う理由が見出されるなら、それだけで、その全てを拒否するのに十分であろう。
『省察』35頁
「無知の知」で有名なソクラテスが、本当は熊だった、と言われたらそれは明らかに偽だろう。しかし、「海は青い」という命題はどうであろう。見方によれば灰色に見えるし、時と場合によってはまた別の色にみえるかもしれない。つまり「海は青い」は「全く確実で疑いえないないわけではないもの」だ。真理値にもグラデーションがある。確実な真理があり、真理っぽいものがあり、疑わしいものがあり、明らかに偽がある。デカルトが言っているのは、このうち確実な真理以外は偽にする、ということである。真理っぽいものも、疑わしいものも、偽の仲間に加えてしまう。それでは少しでも疑わしいものには具体的にどんなものあるだろうか。
感覚も信念も数学も疑わしい
まず、デカルトが検討したのが感覚である。色や形などを私たちは感覚を通して知ることになる。あれは赤色、これは黒色というように。しかし、時にはその認識が間違っていることがあるだろう。ということは感覚は少しでも間違う可能性があるので、感覚は方法的懐疑の原則によって信頼できないことになる。これによって感覚的なもの全てが拒否される。
しかし、感覚は信頼できないといえども、「いま私がここにいること、暖炉のそばに座っていること・・・この紙を手で触れていること・・・この身体全体が私のものであること」(36頁)は疑うことができるのだろうか(ここの文章がフーコーの論文「私の身体、この紙、この炉」という題名の元ネタである)。ここで狂気と夢の例が登場する。夢の中にいるときは、そのようなことも現実だと錯覚しているのではないかというのである(この狂気と夢の解釈について争ったのが「フーコー=デリダ論争」である)。最終的に、今目覚めているのかそれとも眠っているのか、そのことを区別する確実な印がないということで、方法的懐疑の原則により、私がここにいることや、炉ばたに坐っていることも確実に正しいとは言えないという結論になる。なぜならそれは夢かもしれないからである(クリストファー・ノーランの映画『インセプション』であったら、コマを回して現実か夢か判断できるのだが)。
というわけで、感覚も、ここに座っているという素朴な信念も疑わしいということになった。他に信頼しうるものはあるだろうか。そこで。デカルトは「単純で極めて一般的なもの」、すなわち代数学や幾何学を持ち出してくる。眠っていようがいまいが、狂気に陥ってようがいまいが2+3=5だというわけである。では、2+3=5は疑いえない確実な真理となりうるのだろうか。
実はこれもまだ疑わしいところが残っている。というのも欺く神(悪しき霊とも呼ばれる)が存在しているかもしれないからである。この神が私たちに嘘を真実だと信じ込ませている可能性が存在する。つまり、2+3=5は本当は偽なのに、欺く神が正しいと信じ込ませているだけではないか、とデカルトは疑うのである。この可能性は拭い去れない。というわけで、代数学も偽だということになる。
「第一省察」はここまでである。結果、感覚も信念も代数学も疑わしいということになり、唯一確実な真理にはまだ到達できていない。「第二省察」では、さらに方法的懐疑を進めていき、唯一確実な真理を発見することになる。
欺く神がいても疑いえないもの
「第二省察」でも《欺く神》の話が続く。「第一省察」でも述べたように、欺く神が存在するなら、自分が正しいと思っていることは全て偽の可能性があるということだろう。誇張的な方法的懐疑の結果、ほとんど何も信じられないような状況に達したのである。「それゆえ私は、私が見ているものはすべて偽であると想定しよう。あてにならない記憶が表象するものはどれも、何も存在しなかったと信じることにしよう」(44頁)。それでは、方法的懐疑の結果、唯一確実な真理など存在しないという結論になってしまうのだろうか。
しかし、ここでデカルトはある大発見をする。欺く神が私を欺き、私は世界には全く何もないと自らを説得したのだとしたならば、むしろその(欺かれている)私は存在するはずだ、というのである。欺く神が私を欺けば欺くほど私は存在する。
それゆえ、すべてのことを十二分に熟慮したあげく、最後にこう結論しなければならない。「私はある、私は存在する」という命題は、私がそれを言い表すたびごとに、あるいは精神で把握するたびごとに必然的に真である、と。
『省察』45頁。
このようにして、デカルトは「我おもう、ゆえに我あり」という唯一確実な真理を発見した。デカルトの方法的懐疑は、このようにして成功したのである。
発展史
方法的懐疑に影響を受けたフッサール
現象学の創始者であるフッサールはその方法論としてエポケーや現象学的還元を打ち出したことで有名だが、このアイディアは、遡ればデカルトの「方法的懐疑」に由来する。というのも、現象学的還元も真理の場を獲得するために実行される方法だからである。
もちろん違いもある。現象学的還元の場合、確かに真理とはいえないもの(「素朴な信念」と呼ばれる)をエポケーによって一旦排斥するのであるが、それは真理ではないものを抹殺するためではなく、むしろ真理ではないのにどうしてそれを正しいと信じてしまっているのかを知るために排斥するのである。
また全てを現象学的還元の場合、全てを懐疑するわけではないという違いもある。本質(形相)は現象学的還元の場合還元されない。デカルトの方法的懐疑の場合、本質(形相)も懐疑にふされ偽とみなされる。
関連記事:本格的な人向けおすすめ哲学書を紹介!
関連項目
参考文献
ルネ・デカルト『省察』山田弘明訳、ちくま学芸文庫、2006年。