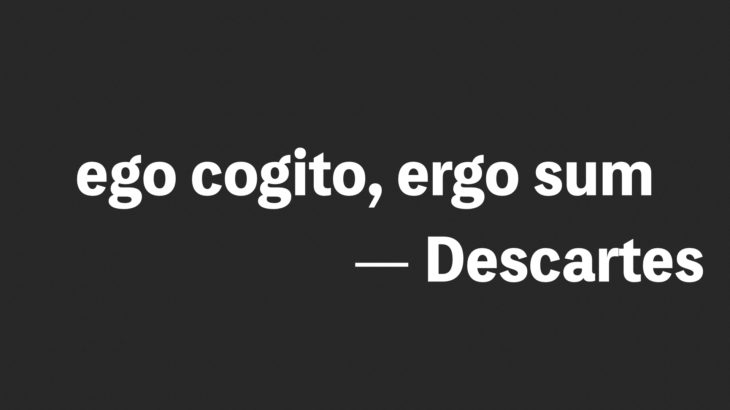我おもう、ゆえに我ありに関する誤解
「我思う、故に我あり」はデカルトの名言とされるが、この言葉に関して割と誤解されていることがある。
・「我おもう、ゆえに我あり」は『方法序説』や『省察』に出てくる言葉である。
皆さんはどうだろうか。実は間違いだ。「我おもう、ゆえに我あり」は『方法序説』や『哲学原理』の中では登場するが、『省察』には出てこない。『省察』はデカルトの形而上学に関する主著なので、この名言が『省察』にも書かれていると普通は思うのだが、なぜが違う表現がなされている。
それでは『省察』では何と書かれているのだろうか。そして『方法序説』や『哲学原理』ではどのように書かれているのだろうか。
『省察』では「私はある、私は存在する」
『省察』は本当は『第一哲学についての省察』という題であり、確実な真理を獲得して、諸々の事柄の基礎づけを行おうとした形而上学に関する書物である。ゆえに哲学者が研究したりするのは主にこの著作だ。内容についていえば、全部で六つの省察がある。一連の省察は山登りみたいなもので、最初に確実な真理に到達するための方法を決めたあと、その方法に沿って考察を進めていく(上り)。そして真理を獲得したあと(頂上)、その真理を基礎として他の事柄について確定していく(下り)。
さてその方法であるが、それが方法的懐疑とよばれるものである。ご存知の方もいるかもしれないが、その方法的懐疑によって得られた真理は「私が存在する」ということであった。その真理を発見した場所をここに引用してみよう。
しかし、私がなにものかであると考えている間は、かれ〔欺く神〕は、私を何ものでもないようにすることは、けっしてできないだろう。それゆえ、すべてのことを十二分に熟慮したあげく、最後にこう結論しなければならない。「私はある、私は存在する」Ego sum, ego existo という命題は、私がそれを言い表すたびごとに、あるいは精神で把握するたびごとに必然的に真である、と。
『省察』第二省察、45頁、〔〕は筆者補足。
ラテン語で Ego は「私」 sum はbe 動詞だから「ある」、existo は「存在する」なので、訳は「私はある、私は存在する」となる。「我おもう、ゆえに我あり」ではないのである。たしかに文脈上、「考えている間は」、私はなにものかである、ということになっているので、結論が「我おもう、ゆえに我あり」でも全然おかしくないのだが、『省察』では「私が存在する」だけが命題として書かれている。
『方法序説』『哲学原理』における「我おもう、ゆえに我あり」
それでは『方法序説』を見ていくことにしよう。どのように書かれているか。
しかしそのすぐ後で、次のことに気がついた。すなわち、このようにすべてを偽と考えようとする間も、そう考えているこのわたしは必然的になにものかでなければならない、と。そして「わたしは考える、ゆえに私は存在する〔ワレ惟ウ、故ニワレ在リ〕〈je pense, donc je suis〉」というこの真理は、懐疑論者たちのどんな途方もない想定といえども揺るがしえないほど堅固で確実なのを認め、この真理を、求めていた哲学の第一原理として、ためらうことなく受け入れられる、と判断した。
『方法序説』第四部、46頁。(〈〉は筆者挿入)
まさしく「我おもう、ゆえに我あり」である。それでは『哲学原理』ではどうか。
神も天空も物体もないと想定することは容易であり、また、われわれ自身が手も足も、さらには身体ももたぬと想定することさえ容易である。しかしながら、だからといって、このようなことを考えているわれわれが無であると想定することはできないのである。なぜなら、考えるものが、考えているまさしくそのときに存在しない、と解するのは矛盾しているからである。したがって「私は考える、ゆえに私はある」ego cogito, ergo sum という認識は、あらゆる認識のうち、順序正しく哲学するものが出会うところの、最初の最も確実な認識である。
『哲学原理』1-7(訳は『省察』171−172頁の翻訳)
ラテン語で cogito は「考える」、ergo は「ゆえに」である。sum の前に ego がないが sum は一人称単数の形でそれを使えば「私はある」という意味なのが分かるので ego は省略できる。実は cogito も一人称単数の形なので、それだけで「私は考える」を意味し、ego がついてなくても良い。「コギト、エルゴ、スム」という言葉で「我おもう、ゆえに我あり」を覚えている人はいないだろうか。ここでエゴがないのは、エゴがなくてもラテン語としてはOKだからである。
内容に関しては三つとも一緒だろう。全てが偽あるいは間違っていると考えても、そのように考えている私は存在している。だから私は存在する、ということである。ただしこの言葉に関しては、これは三段論法であり、大前提(この場合は全て思考するものは存在するという前提)があるのにそれを見逃しているのではないか、とか「私は歩く、ゆえに私はある」ではいけないのかというホッブスの批判など、まだまだ議論になることがたくさんある。そのうち紹介したい。
おまけ。『方法序説』はなぜフランス語か。
「我おもう、ゆえに我あり」についてみてきたが、少し気になる人もいたのではないか。『省察』と『哲学原理』はその該当箇所がラテン語なのに、『方法序説』はフランス語なのである。なぜフランス語なのだろうか。
実はこの『方法序説』は一般教養人を対象にしたものだ。当時、哲学や神学の論文はラテン語で書かれたが、ヨーロッパ貴族の間ではフランス語が使われていた。ヨーロッパ貴族の共通語は当時フランス語だったのである。『方法序説』第6部で、なぜフランス語で書いたかその理由を述べている。
わたしが、自分の国のことばであるフランス語で書いて、わたしの先生たちのことばであるラテン語で書かないのも、自然〔生まれつき〕の理性だけをまったく純粋に働かせる人たちのほうが、古い書物だけしか信じない人たちよりも、いっそう正しくわたしの意見を判断してくれるだろうと期待するからである。そして良識と学識をそなえた人々、かれらだけを私の審判者としたい。
『方法序説』第6部、102頁。
よく分かる話である。新しいことをいうと、それだけで頭のお堅い連中は否定しにくる。でも自分(デカルト)としては、自分の言っていることが正しいかどうか、良識を働かせて判断してほしいということであろう。
また宮廷の貴族の女性にも読んでもらいたかったようだ。1638年2月22日のヴァチエ神父宛ての手紙で、女性たちにも何かを分かっていただきたいためにフランス語で書いた、と述べている。いわゆる論文を書く人たちにこの頃女性はいなかったのだろう。かといって教養のある女性がいなかったわけではなくて、例えばデカルトとの心身問題に関する書簡で有名な王女エリーザーベトや、晩年にデカルトを招待したスウェーデン女王クリスティーナなどデカルトの周りにも教養のある女性がたくさんいた。つまり専門の哲学者というよりも、女性も含めた一般教養人に読んでもらおうとした書物なのである。
>>本記事はこちらで紹介されています:哲学の最重要概念を一挙紹介!
参考文献
ルネ・デカルト『省察』山田弘明訳、ちくま学芸文庫、2006年。
デカルト『方法序説』谷川多佳子訳、岩波文庫、1997年。
デカルト『哲学原理』桂寿一訳、岩波文庫、1964年。
>>哲学の入門書の紹介はこちら:哲学初心者向けの人気おすすめ著作を紹介!
>>本格的な人向け哲学書の紹介はこちら:本格的な人向けおすすめ哲学書を紹介!