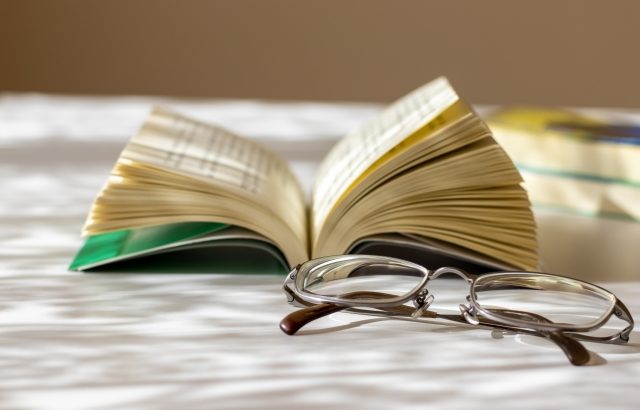純文学とは?
純文学とは「娯楽性より芸術性に重きを置く小説」の総称
純文学の定義は「娯楽性より芸術性に重きを置く小説」の総称で、大衆小説と対を成すジャンルです。
この定義からも分かるように、純文学と大衆小説を分ける明確なラインはありません。その線引きは時代によって変化するものであり、なおかつ、現代ではその線引きも曖昧になりつつあります。
例えば、夏目漱石が純文学作家で、東野圭吾が大衆作家といえば、その線引きは理解しやすいかもしれません。ですが『沈黙』で有名な遠藤周作は純文学作家でありながら一部の作品は大衆小説と評されていますし、『ジョゼと虎と魚たち』で有名な田辺聖子は純文学から大衆小説へと軸足を移しています。
往々にして、純文学好きは大衆小説をバカにし、大衆小説好きは純文学を面白くないと言います。しかし、そのような争いは不毛であるばかりか、(現代・過去・未来の)広義の小説好きにとって有害であることは言うに及びません。
純文学と大衆文学に関して、非常に有名な論争があります。それが芥川・谷崎論争です。論争の経緯について詳しくは触れませんが、芥川龍之介は『文芸的な、余りに文芸的な』(1927年)で物語の面白さと小説の価値は関係ないと主張し、谷崎潤一郎は物語の面白さこそが小説の価値を決めると主張しました。真っ向から対立したこの論争は、日本文学史に残る最大の事件であると同時に、現代でも考えるべき重要な論点を提起しています。そしてこの論争が勃発したちょうど同じ時期に、大衆受けする小説が流行りだしました。それを見かねた芸術性に重きを置く作家たちが、大衆受けの小説から差別化するために、自分たちの小説を「純文学」と呼び始めるのです。つまり、自分たちの小説の正当化のために「純文学」は使われたわけです。やはり「純文学」の始まりからして、この区分けは不毛と言わざるを得ません。
ここでは純文学と広く認められている小説を中心に紹介しますが、場合によっては、大衆小説や古典文学も取り上げていきます。純文学に苦手意識がある人、面白さを感じない人にこそ、純文学を手に取っていただきたい。心に触れる作品に一つでも出会えることを願っています。
純文学はユーモラスで奥深い
ところで、純文学を敬遠している人でも教科書に掲載されている小説を読んで、面白いと感じたことがあったのではないでしょうか。芥川龍之介の『蜘蛛の糸』や夏目漱石の『吾輩は猫である』など、ユーモアに富み素直に笑える作品も少なくありません。
現代まで読み継がれる純文学は、長い年月をかけて吟味されてきた作品ばかりです。その自然淘汰により、面白さや奥深さはかなりの確率で保証されています。時代による淘汰にも負けずに残った傑作だけが、いま手元に存在しているのです。
純文学は面白くて、奥深い!古いもので百年以上前に書かれた小説が、現代を生きる我々の心に、ズシーンと響き、バチーンと想像力を刺激する、このことに素直に驚きます。しかも純文学というジャンルは、いまなお傑作を生み出し続けているのです。
おすすめの基準は、面白さと読みやすさと重厚さに注目
名作は面白いだけでなく、人生について深い洞察を与えてくれます。読み終わったあとに読む前の自分とは世界の見え方が変化する、そんな奇跡のような経験を与えてくれるのも文学作品の特徴の一つです。
とはいえ何から読めばいいかわからないという方も多いと思います。本記事では日本の小説に焦点を当てて、古典的名作から最新の文学まで、純文学から大衆文学よりの小説まで網羅的に紹介します。最近では日本小説が翻訳されて海外で人気を博すことも少なくありません。いまや日本の文学は世界的にも注目が集まっているのです。
そこでこの記事では、読みやすい、面白い、読み応え、の3つの要件にあうおすすめの小説を選びました。ぜひ参考にしてみてください!!古典小説から現代小説まで、純文学から大衆小説まで、多くの作品に触れられることを願っています!
また。意外と多くの純文学がAudibleで聴くか、Kindle Unlimitedで読むことができます。どちらのサービスも30日間の無料期間が設けられているのでご活用してみてください。
→【2023年最新版】Audible(オーディブル)のおすすめ本!ジャンル別に作品紹介
→【2023年最新版】Kindle Unlimitedのおすすめ本!ジャンル別に作品紹介
【1位〜10位】最高傑作と評されるおすすめの純文学
1位 夏目漱石『こころ』(1914年)
小・中学校の教科書にも掲載されていて、一部だけでも目にしたことがあるはず。新潮文庫で最も売れている本で、750万部以上も売り上げています。「先生」と「K」の交流が描かれる「下」が最も有名です。
「K」の「精神的に向上心のない者はばかだ」や、「先生」の「あなたは真面目だから。あなたは真面目に人生そのものから生きた教訓を得たいといったから。」という名言が胸に刺さった人も多いと思います。
平易な文体でありながら、含蓄深く何度読み返しても新たな発見があります。ぜひ一度、通読してみましょう!
夏目漱石はほかに長編『坊っちゃん』『吾輩は猫である』、短編集『夢十夜』、講演「現代日本の開化」などがありどれも面白いです。
関連記事:夏目漱石『こころ』先生の自殺の理由|あらすじ解説・伝えたいこと考察・感想
\Kindle Unlimitedで読める!30日間無料!/
→Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
2位 芥川龍之介『羅生門』(1915年)
長編を通読するのが難しいという方は、芥川龍之介の短編が純文学の導入にうってつけです。
夏目漱石に師事した芥川龍之介は、『鼻』『蜘蛛の糸』『アグニの神様』「河童」など、古典に依拠した数多くの短編を世に送り出しました。芥川の短編は、言葉巧みで教訓に富み、芥川の人間に対する洞察の鋭さが伺えます。
羅生門の上で辿り着いた少年は、そこで死者の衣類を剥ぐ老婆に出会う。正義とは何か、悪人とは何かを問いかける傑作です。
1950年にはこの短編を原作にして、黒澤明が映画化しました。映画はヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞し、現在も世界各国で高く評価される傑作です。人間であるならば、映画好きでなくとも一度は観なくてはならない、必見の作品です。
関連記事:芥川龍之介『羅生門』解説|「下人の行方は誰も知らない」で終わる意味|あらすじ感想|伝えたいこと考察
3位 村上春樹『海辺のカフカ』(2002年)
日本を代表する現代作家、村上春樹の代表作の一つです。長編『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』や『ねじまき島クロニクル』も傑作ですが、それよりも新しい『海辺のカフカ』をお勧めします。テーマもわかりやすく文章も巧みで大変面白いです。
オイディプスと同じ予言を与えられた主人公・カフカが南へ旅する物語です。並行してタナカさんの話も進行し、村上ワールド炸裂の一作になっています。
村上はほかに長編『風の歌を聴け』『1Q84』、短編「神の子どもたちはみな踊る」「かえるくん、東京を救う」などがあります。
関連記事:村上春樹『海辺のカフカ』メタファーとソリッドなもの|あらすじ・解説・考察
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
4位 遠藤周作『沈黙』(1966年)
長い旅路の果てに辿り着いた結末が、衝撃的かつ感動的です。最近はアメリカの映画監督のスコセッシによって映画化されました。
遠藤周作は、戦後のある時期に登場した「第三の新人」という小説家の一群の一人です。「第三の新人」にはほかに小島信夫や安岡章太郎などがいます。
江戸時代初期に日本に訪れたポルトガル人司祭ロドリゴが、キリシタン弾圧下でどのように信仰を貫いたかを描きます。何故イエスは「沈黙」するのか、ロドリゴがだした答えとは!?
遠藤周作はほかに『深い河』『白い人』『海と毒薬』などの傑作があります。
関連記事:遠藤周作『沈黙』今まで誰もしなかった一番辛い愛の行為|あらすじ・解説・考察
\U-NEXTで観れる!31日間無料!/
→U-NEXT(ユーネクスト)とは?料金・サービス内容・注意点を解説
5位 小川洋子『博士の愛した数式』(2003年)
『ことり』や『密やかな結晶』などで有名な小川洋子の代表作の一つ。風変わりの数学者と家政婦とその息子・ルートとの美しい交流が描かれています。
博士は風変わりであるのに加えて、過去の事故によって記憶が60分しか続かないという障害を抱えています。博士と家政婦とルートの交流は、博士の記憶に残ることはありませんが、二人にはゆっくりと積み重なり重みを増していくのです。記憶の話でもあり、愛の話でもあります。映画化もされいまでも多くの人に愛された名作です。
2006年に映画化されて、いくつかの賞を受賞するなど、高く評価されました。
関連記事:小川洋子『博士の愛した数式』美しいつながり|あらすじ・解説・考察
\U-NEXTで観れる!31日間無料!/
→U-NEXT(ユーネクスト)とは?料金・サービス内容・注意点を解説
6位 太宰治『人間失格』(1948年)
多くの人に愛される太宰治。そんな彼の最高傑作の一つが『人間失格』です。新潮文庫の売上部数は、トップの夏目漱石の『こころ』と競い合うほどです。
第一に手記が「恥の多い生涯を送って来ました。」から始まる『人間失格』は、人間存在の本質に迫る内容で、大変読み応えがあります!
太宰は本作の脱稿の1か月後、玉川上水で入水自殺しました。そのため太宰の完結する作品としては、最後の小説ということになります。
太宰にはほかに『走れメロス』『ヴィヨンの妻』『斜陽』など、いくつもの傑作があります。
関連記事:太宰治『人間失格』恥の多い人生だった|あらすじ解説・伝えたいこと考察
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
7位 三島由紀夫『金閣寺』(1956年)
近代日本文学を代表する傑作の一つです。名実ともに三島の地位を決定的にしました。
題材は950年に起きた「金閣寺放火事件」ですが、経緯や人物描写は変更されています。重度な吃音症をもつ主人公が、「美」や「崇高」の象徴である金閣寺を放火してしまうという物語です。
戦後日本のアンビバレントな感情が、重厚な文体で表現されています。海外でも高く評価されていて、兎に角一度は読んでみて損はありません。
三島由紀夫はほかに『仮面の告白』『サド侯爵夫人』『豊饒の海』などが有名です。
8位 今村夏子『こちらあみ子』(2010年)
2010年代にはいり彗星の如く現れた今村夏子。その最初の作品であり代表作が『こちらあみ子』です。清掃のアルバイトをしていた29歳のあるとき、突然小説を描こうと思い立ち誕生したのがこの作品です。
主人公・あみ子の知らないところで渦巻くグログロとした悪意、突然到来する暴力、徐々に壊れいてく人間関係。しかし感情移入の対象であるはずのあみ子は、何を考えているかまったくわからず、言い知れぬ恐ろしさが作品を取り巻いています。「応答せよ。こちらあみ子」の叫びに応える声はあるのか……。
今村の代表作の一つ『星の子』では、宗教2世の子供が描かれていてこちらも傑作です。
また、本作は2022年に映画化されました。完成度は非常に高く、必見です。
\U-NEXTで観れる!31日間無料!/
→U-NEXT(ユーネクスト)とは?料金・サービス内容・注意点を解説
9位 大江健三郎『死者の奢り』(1957年)
日本人でノーベル文学賞をとったのは二人しかいません。そのうちの一人が大江健三郎です。
そんな大江のデビュー作品が短編小説『死者の奢り』です。主人公は大学病院で解剖用の死体を運ぶアルバイトをしているのですが、この設定からしてすでに興味をそそられます。結局この仕事は、無駄だっとわかるという筋なのですが、時代を感じさせる大変な良作です。
大江は『万延元年のフットボール』などの傑作もあるのですが、最初は短編から読むのをお勧めします。面白かったら長編に挑戦しましょう!
大江健三郎はほかに『セヴンティーン』『洪水はわが魂に及び』『新しい人よ眼ざめよ』『叫び声』などの傑作が有名です。
10位 安部公房『砂の女』(1962年)
純文学というと現実世界の話で興味が湧かないという方におすすめです。
主人公が昆虫採集のために海辺の砂浜に訪れると、砂穴の家に閉じ込められてしまいます。脱出を試みるも、次第に主人公の心情にに変化が現れます。
設定からして幻想的です。人間存在の本質と生命力を抉り出す、近代日本小説の傑作の一つです。海外でも高く評価されています。
関連記事:安部公房『砂の女』<希望>はどこにあるのか?|あらすじ・解説・考察
【11位〜20位】現代まで残る名著純文学のおすすめ!
11位 谷崎潤一郎『春琴抄』(1933年)
純文学って刺激が足りないんじゃないの?という方におすすめです。
盲目の三味線奏者である春琴と、献身的に仕えてる佐助の物語。 熱湯をかけられ人に会うことを拒否するようになった春琴にたいして、佐助は思いもやらぬ行動に出ます。
マゾヒズムと美を主題に、生きることの意味を問います。
谷崎潤一郎はほかに『刺青』『痴人の愛』『卍(まんじ)』などがあります。
関連記事:谷崎潤一郎『春琴抄』マゾヒズムと佐助が見たもの|あらすじ解説・考察・感想
12位 梶井基次郎『檸檬』(1925年)
31歳で亡くなった早熟の天才、梶井基次郎。そんな梶井の代表作が『檸檬』です。
「えたいの知れない不吉な塊」に心を押さえつけられていたある男性が主人公。何も楽しめなくなった彼が、八百屋で「檸檬」を見つけると彼の心情に変化が訪れます。
教科書に掲載されることもあります。鮮やかな情景描写と、深い内面描写が特徴的です。短編なので読みやすく、不思議な読後感があります。
梶井基次郎はほかに『kの昇天』『城のある町にて』『のんきな患者』などがあります。
関連記事:梶井基次郎『檸檬』「不吉な塊」に追われて|あらすじ・解説・考察
\Kindle Unlimitedで読める!30日間無料!/
→Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
13位 田辺聖子『ジョゼと虎と魚たち』(1984年)
主演、池脇千鶴と妻夫木聡で映画化もされた田辺聖子の短編恋愛です。
足が不自由で車椅子生活をしているジョゼとそばにいる恒夫の新婚旅行を描いています。ジョゼは天邪鬼で高圧的だったりするのですが非常に繊細な部分もあって、そこと恒夫のいい意味で大雑把でチャランポランな性格がマッチしています。
水族館やラストシーンが美しいです。
関連記事:田辺聖子『ジョゼと虎と魚たち』完全無欠の幸福は死そのものだ|あらすじ・解説・考察
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
14位 川端康成『伊豆の踊子』(1927年)
日本人でノーベル文学賞をとった最初の人が、川端康成です。
ある青年が伊豆へ一人旅にでます。そこで出会った踊子の少女に恋心を抱く物語です。孤独で自我に苦しむ青年と、純粋無垢な少女との交流の過程が描かれます。
日本人に愛され続けた傑作で、吉永小百合や山口百恵などの当時の有名人がヒロインを演じながら、6回も映画化されています。
日本人に愛され続けた傑作で、吉永小百合や山口百恵などの当時の有名人がヒロインを演じながら、6回も映画化されています。
川端の代表作といえば『雪国』ですが、『雪国』が読みきれない場合は、こちらがおすすめです!
川端康成はほかに『千羽鶴』『眠れる美女』『古都』などがあります。
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
15位 山田詠美『ぼくは勉強ができない』(1993年)
数々の賞を受賞した山田詠美の9篇からなる連作小説。1996年には映画化もされています。
地頭のいい主人公・時田秀美が部活やセックス、恋愛に哲学書など様々なものに手を出しながら、学校生活を謳歌する物語です。
秀逸な解説がありますので、こちらとセットで読むと面白さが倍増です。
関連記事:『ぼくは勉強ができない』と散文のロジック|解説・考察
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
16位 井伏鱒二『黒い雨』(1966年)
井伏鱒二は太宰治に大変慕われた作家です。『黒い雨』は戦後小説で特に、広島の原爆を題材にした小説です。
「黒い雨」は、原子力爆弾が投下された後に降る放射線を帯びた雨のことで、それを浴びると原爆症にかかってしまいます。そんな「黒い雨」を浴びて原爆症を発病してしまう人たちの話です。
重い話ですが絶対に読むべき小説です。ぜひご一読を!
井伏鱒二はほかに『山椒魚』などがあります。
17位 志賀直哉『小僧の神様』(1920年)
志賀直哉は明治から昭和にかけて活躍した白樺派を代表する作家です。彼は「小説の神様」と称され、その後の日本文学に多大な影響を与えますが、そう呼ばれるようになったきっかけが短編の「小僧の神様」です。
兎に角寿司を食べたい小僧と、Aという貴族院議員の物語です。
志賀直哉は芥川龍之介との交流も深く、同時代の多くの小説家に影響を与えました。
志賀直哉はほかに『城の崎にて』『暗夜行路』『和解』などがあります。
関連記事:志賀直哉「小僧の神様」神様の誕生|あらすじ解説・伝えたいこと考察・感想
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
18位 森鴎外『舞姫』(1890年)
森鴎外は医者であり小説家でもある、多彩な人物でした。そんな鴎外の代表作が短編『舞姫』です。
19世紀末にドイツに留学していた主人公の太田豊太郎が、そこでの恋愛経験を手記に綴ります。
森鴎外はほかに『雁』『阿部一族』『山椒大夫』があります。
\Kindle Unlimitedで読める!30日間無料!/
→Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
19位 村田沙耶香『コンビニ人間』(2016年)
三島由紀夫賞を受賞しながらコンビニバイトをし続けた作家村田沙耶香の渾身の一作です。
発表当時は日本国内でかなり話題になり、現在は翻訳もでて海外でも人気だそうです。
コンビニで働く30代の古倉恵子視点から、コンビニという小さな世界を描くことで現代をうつしだします。
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
20位 島崎藤村『破戒』(1906年)
19世紀末にフランスのゾラによって、自然の事実を観察しそのまま描写する、自然主義文学という文学運動が起こります。日本で最初期に取り入れたのが島崎藤村の『破戒』 になります。
部落差別と、身分を隠して生きよという父の教え、主人公・瀬川丑松の自我の芽生えを中心に描かれる物語です。
島崎藤村はほかに『春』『家』などがあります。
\Kindle Unlimitedで読める!30日間無料!/
→Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
【21位〜30位】純文学から大衆小説まで読むべき名作
21位 小島信夫『抱擁家族』(1965年)
遠藤周作と同じく「第三の新人」という世代の代表的存在の一人です。『抱擁家族』は第1回谷崎潤一郎賞を受賞しました。
主人公で大学教師の三輪俊介は、あるとき家政婦から、妻・時子がアメリカ兵であるジョージと肉体関係をもったと知らされます。食い違う証言、家出する息子、時子の死、そして……。
これまた傑作の一つです。批評家の江藤淳が『成熟と喪失 “母”の崩壊』で高く評価しました。
小島信夫はほかに『アメリカン・スクール』『別れる理由』などがあります。
22位 乗代雄介 『旅する練習』(2020年)
コロナ以後に書かれた旅と記憶、それに練習を主題とした小説です。
鹿島に歩いて向かう小説家の私とサッカーが得意な姪の亜美。私は風景描写の、亜美はリフティングの練習をしながら旅をします。
風景を描写にこびりつく記憶に、あふれる想いに、涙が止まりません。
関連記事:乗代雄介『旅する練習』コロナ以後の記憶と旅の文学|あらすじ・解説・考察
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
23位 有島武郎『カインの末裔』(1917年)
有島武郎は志賀直哉と同時代の人で、志賀直哉、武者小路実篤などと同人「白樺」を発刊しています。俗にいう白樺派の一人です。
舞台は北海道。主人公で農夫の仁右衛門の生き様を通して、無知と罪というテーマを描きます。
カインの末裔自体は、キリスト教の聖書にでてくるモチーフですね。アダムとイブの子であるカインは、弟のアベルを殺害してしまうのです。そのためカインの末裔は生まれながらに罪深い心をもっているとされます。
有島武郎はほかに『生れ出づる悩み』『或る女』があります。
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
24位 坂口安吾『桜の森の満開の下』(1947年)
日本論である『堕落論』で有名な坂口安吾ですが、小説も傑作多し。その一つが短編小説『桜の森の満開の下』です。
山賊と美しくも残酷な女性との幻想的な物語です。
坂口安吾はほかに『白痴』『不連続殺人事件』などがあります。
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
25位 本谷有希子『本当の旅』(2018年)
本谷 有希子は劇作家で小説家。さらに演出家、女優、声優なども兼ねた、非常に多彩な作家です。
『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』や『生きてるだけで、愛。』で数々の文学賞にノミネート。さらに主宰する劇団「劇団、本谷有希子」で、自作の戯曲を公演するなどの活動をしています。
『静かに、ねえ、静かに』に収録されている『本当の旅』は、SNS時代の旅を描いた小説です。旅行先でもスマホを介して間接的に常時接続する新たな時代に、旅はいかなるものになるのか。新たな時代の旅の形式を否定するのではなく、そこに迫りくる新たな闇を描きます。
関連記事:本谷有希子「本当の旅」新たなる小説の誕生に向けて|あらすじ・解説・考察
26位 宮沢賢治『銀河鉄道の夜』(1934年)
宮沢賢治といえば『雨ニモマケズ』で有名です。宮沢賢治は生前は無名でしたが、死後高く評価されるようになりました。現在では彼の作品が教科書にも掲載されてるようになり、国民的な作家になりました。
『銀河鉄道の夜』は、ジョバンニという孤独な少年と、友人であるカムパネルラが銀河鉄道で旅をする物語です。幻想的な童話小説で、謎多き小説でもあります。
宮沢賢治はほかに『注文の多い料理店』『風の又三郎』などがあります。
\Kindle Unlimitedで読める!30日間無料!/
→Kindle Unlimitedのメリット・デメリット【サービス内容・おすすめ活用方法・評判】
27位 川上弘美『センセイの鞄』(2001年)
『センセイの鞄』は、ツキコさんと元教師のセンセイとの恋愛を描いています。谷崎潤一郎賞を受賞し、15万部超のベストセラーとなりました。
若者の恋とは違い、一風変わった恋愛が落ち着いた雰囲気で繰り広げられます。また料理が美味しそうで旅行の情景が豊かです。
川上弘美はほかに『蛇を踏む』『真鶴』などの小説もおすすめです。
関連記事:川上弘美『センセイの鞄』高年男性と恋愛|あらすじ・解説・考察
28位 江國香織『きらきらひかる』(1992年)
アルコール依存症の笑子と同性愛者の睦月の夫婦。さらに睦月の恋人である紺を加えた三人の奇妙な関係を描いています。
異性愛夫婦とは違う愛の形がここにあります。笑子と睦月の生活が微笑ましいです。
映画化もされた名作です。
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)のメリット・デメリット【おすすめ活用方法・評判】
29位 柳田国男『遠野物語』(1910年)
『遠野物語』は民俗学者の柳田国男が、岩手県遠野地方の伝承を集めたものです。
小説とはいえないのかもしれませんが、言い伝えや説話は面白い!
日本の民俗学の先駆けとも言われていて、学問的観点からみても大変重要な作品です。ぜひご一読を!
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
30位 舞城王太郎『好き好き大好き超愛してる』(2004年)
6つのストーリーから織りなす愛の物語です。芥川賞候補になった本作は、審査員の石原慎太郎に「タイトルを見ただけでうんざりした」と評された問題作。
ですが題名で忌避するのは勿体ない!愛とは何か、文学とは何かという大問題に真剣に取り組んでいます。
関連記事:舞城王太郎『好き好き大好き超愛してる』解説・考察|祈り・物語・愛
【31位〜39位】古典から現代純文学までのおすすめ
31位 いとうせいこう『想像ラジオ』(2013年)
3.11を経験した作家が、震災に応答した小説が『想像ラジオ』です。
死者の言葉を代弁するので物議をかもしましたが、それもフィクションができることの一つだと思います。
震災を題材にした新海誠の『君の名は。』や『天気の子』など、震災に応答した名作が生まれることでしょう。
32位 江戸川乱歩『怪人二十面相』(1936年)
推理小説『怪人二十面相』は、エドガー・アラン・ポーに影響された日本の小説家・江戸川乱歩の傑作小説の一つです。
大怪盗怪人二十面相や、名探偵・明智小五郎など、一度は聞いたことがある名前ばかり。漫画やアニメ、推理小説など、現在でも色濃く影響を与えています。
怪人二十面相と探偵・明智小五郎、さらにその助手・小林少年の推理バトルが繰り広げられます。小林少年がつくる「少年探偵団」は、『名探偵コナン』でもみられますね!
江戸川乱歩はほかに『D坂の殺人事件』『黒蜥蜴』などがあります。
\Kindle Unlimitedで読める!30日間無料!/
→Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
33位 吉田修一『悪人』(2007年)
妻夫木聡と深津絵里が主演で映画化されました。
数々の賞を受賞しベストセラーになりました。殺人を犯した清水祐一と偶然知り合った馬込光代が、共になって逃げていく物語です。なぜ殺人事件が起きたのか、二人の結末は?
吉田修一はほかに『パレード』や『横道世之介』、『怒り』などほかにも面白い作品がたくさんあります。
関連記事:映画『怒り』考察|怒りとは何か|あらすじ・解説・感想|吉田修一|李相日
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
34位 保坂和志『季節の記憶』(1996年)
谷崎潤一郎賞、平林たい子文学賞を受賞した名作です。
穏やかな生活を描くのが特徴の保坂が、さらに子供の視点をくわえて、日常や自然を描きます。
不思議で穏やかな小説です。
35位 三浦綾子 『塩狩峠』(1968年)
実話を基にしていて、自己犠牲や愛、信仰をテーマにした物語です。
鉄道事故で殉職した長野政雄を基に、乗客を救うために自己を犠牲にした鉄道職員の生涯が描かれています。
どっしりと重いテーマで人生について深く考えさせられると思います。
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→【2023年度最新版】Audible(オーディブル)の評判・口コミを徹底解説
36位 ?? 『竹取物語』(平安時代前期)
『竹取物語』は現存する日本最古の物語です。作者不明で成立時期も正確には定まっていないですが、平安時代前期に成立したとされています。
光る竹から生まれた姫と結婚を迫る男性たち、そして姫を連れ戻すために現れた月の使者。
とても豊かな想像力です。日本最古の物語でありながら、現代でもとても面白く読めます。これまた必読の書ですね。
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
37位 中島敦『山月記』(1942年)
『山月記』は中国の唐代の伝奇小説の『人虎伝』を題材にした小説です。
文体は古文調ですが、内面の心理描写は鮮やかであり、決して読みにくいというものではありません。
教科書で取り上げられることも多く馴染み深い作品です。
関連記事:中島敦『山月記』臆病な自尊心と尊大な羞恥心|あらすじ・解説・考察
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
38位 中河与一『天の夕顔』(1954年)
中河与一の代表作で、英、仏、独、中国語など六カ国語に翻訳されています。
〈わたくし〉が愛しつづけた女には夫がいた。学生時代から続く年上の彼女への愛は、20年以上過ぎた日々でも燃えつづけていた。
純粋で狂信的な愛を描き、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』にも並ぶほどの浪漫主義文学の傑作です。
39位 梨木香歩『西の魔女が死んだ』(1994年)
小学生から中学生におすすめできるベストセラー小説です。
亡くなったおばあちゃんの家に向かう間、2年前に1ヶ月一緒に過ごした日々の素晴らしい思い出と後悔を回想する物語。
大号泣したい方は必読書です。
関連記事:『西の魔女が死んだ』解説|自然の在処|あらすじ感想・伝えたいこと解説|梨木香歩
ほかの小説や哲学・批評にも挑戦してみよう
有名で知っている本から、読んだことのない本まであったと思います。どれか一つでも気に入る作品を見つけていただければ嬉しいです。
ほかに「世界文学のおすすめ」、「フランス文学のおすすめ」、「イギリス文学のおすすめ」、「感染症文学のおすすめ」でもおすすめ小説を紹介しています。
ほかに批評理論や哲学などを嗜むと、より一層文学を楽しめると思います。
批評理論のおすすめ本は「批評理論のおすすめ本」、おすすめ批評理論は「批評理論をわかりやすく解説」、おすすめ哲学入門書は「哲学初心者向けの人気おすすめ著作」、おすすめ哲学書は「本格的な人向けおすすめ哲学名著」で紹介しています。