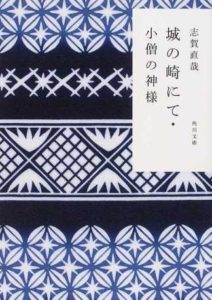概要
『山月記』は、1942年『文學界』に発表された中島敦の短編小説。唐代の伝奇小説「人虎伝」を題材としているため、古文調の文体で書かれている。
文章の美しさや教訓の深さから、長らく中学の国語の教科書に掲載されている。
他人の下で働くことを嫌い山に籠ったが故に虎となってしまった李徴が、旧友の袁傪に自らのうちにある「臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」について語る物語。
小説は他に、ヘッセ「少年の日の思い出」、ワイルド「幸福な王子」、太宰治「走れメロス」、宮沢賢治「注文の多い料理店」「やまなし」、魯迅『故郷』、森見登美彦『夜は短し歩けよ乙女』、辻村深月『ツナグ』などがある。
本作は「日本純文学の最新おすすめ有名小説」で紹介している。
登場人物
李徴(りちょう):詩人の才能に溢れた主人公。しかし、発狂し行方不明になり、袁傪が見つけた時には虎になっていた。
袁傪(えんさん):李徴の友人。監察御史。
名言
共に、我が臆病な自尊心と、尊大な羞恥心との所為である。己の珠に非ざることを惧れるが故に、敢て刻苦して磨こうともせず、又、己の珠なるべきを半ば信ずるが故に、碌々として瓦に伍することも出来なかった。
己の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ。これが己を損い、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては、己の外形をかくの如く、内心にふさわしいものに変えて了ったのだ。
あらすじ・ネタバレ・ストーリー
唐の時代、李徴は若くして科挙に合格する秀才であったが、詩人として名声を得ようとして官職を退いたため困窮する。しかたなく妻子を養うために地方の下級官吏の職に就くが、自尊心の高さゆえに嫌気がさし、しまいには発狂して姿を消す。
翌年李徴の友人であった袁傪が、旅の途上で人食い虎に襲われる。しかし虎が茂みに隠れ「危ないところだった」と人の声で呟く。その声がなんと李徴の声だった。袁傪が問いただすと、その虎は自分は李徴だと答える。李徴はなぜ虎になったのか分からないとするも、だんだんと人間の心が失われていくのを苦しんでいる。
李徴は自分の詩を記録してくれるように袁傪らに頼み、一人朗読する。袁傪はその詩に感嘆しながらも第一流の作品になるにはどこか欠けているところがあると気づく。
そのあとさらに自分が虎になったことを詠んだ詩を詠むと、李徴は虎になった理由には思い当たる節がないこともないと語り始める。それは「臆病な自尊心と尊大な羞恥心」ではなかったかという。これが自分と周りを苦しめた結果、内心に相応しく外見も虎に変えてしまったのではないかと。
最後に頼みとして、妻に自分は死んだと伝えること、その後の生活に困ることがないようして欲しいとお願いする。しかし、もし人間だったなら真っ先にこのことをお願いすべきだったのだ、そんなんだから獣に身を落とすのだ、と自嘲する。
別れの時が来る。李徴は最後に、あの丘に袁傪が登ったら振り返って見てもらいたいとお願いする。お互い涙しながら別れる。袁傪が丘にたどり着き振り返ると、1匹の虎が草の茂みから道の上に躍り出たのを見る。そして二声三声咆哮したかと思うとまた草むらに戻っていき、再びその姿をみることはなかった。
\Audibleで聴ける!30日間無料!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
解説
題材となった『人虎伝』との相違点
『山月記』は、唐代の伝奇小説「人虎伝」を題材とした中島敦のデビュー作である。彼の家系が代々漢学者であったおかげで、中島は漢学の素養を身につけ「人虎伝」を題材に小説を書くことができた。ちなみに古典に依拠して小説を書いた作家は、中島だけではない。芥川龍之介の「鼻」や「芋粥」などの名作も、日本の古典を題材にしている。
中島敦のその非凡な才を大いに発揮し、「人虎伝」を大幅に改変して完成したのが『山月記』である。中国古典を題材にしているため文体は古文調ではあるが、内面の心理描写が鮮やかであり、大変読みやすい。
題材となった「人虎伝」は、李徴が因果応報により虎になる怪奇譚である。李徴はある娼婦との逢瀬を楽しんでいたが、ある一家に邪魔される。その妨害に怒った李徴は、一家を焼き殺してしまい、その因果応報として虎に変身してしまう。この伝奇小説では、欲望のために人を殺したことが、虎に変身した理由になっている。
それに対して『山月記』では、変身の理由が李徴の繊細な内面性に求められる。彼は「臆病な自尊心」や「尊大な羞恥心」といった実存的な悩みを告白し、その内面の臆病さが外見を作り出したと吐露するのだ。この繊細な内面描写と実存的悩みこそが、本作の魅力であり傑作と呼ばれる所以である。
「臆病な自尊心と尊大な羞恥心」とは何か
なぜ李徴は虎に変身してしまったのだろうか。
人間は誰でも猛獣使であり、その猛獣に当るのが、各人の性情だという。己の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった。
虎となった李徴が語るには、「臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」に原因がある。人は誰しもが生まれつき猛獣のような性質を内に秘めている。李徴の場合、飼い慣らさなくてはならない性情(性質)は、「臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」であった。
では、臆病な自尊心と尊大な羞恥心とは、何を意味しているのだろうか。
結論から先に述べよう。臆病な自尊心とは、強すぎる自尊心を傷つけないように行動する臆病な心のことであり、尊大な羞恥心とは、強すぎる羞恥心を悟られないように尊大にみせようとする心のことである。
李徴は詩の才能があり自信があったが、一方でそれは中途半端な自信であった。才能はあるけれども自分より上がいるということにビビってしまったため、自分の才能のなさが世間にバレないように、あえて仲間と切磋琢磨せずに孤独にいた。これが「臆病な自尊心」である。「自尊心」とは、自分は天才であるという自負のことで、「臆病」とは、自分は才能がないのかもしれないという懸念のことである。
他方で、それでも才能があると信じていたため、凡才の群れにも加わらなかった。これが「尊大な羞恥心」である。「尊大」とは、才能があるという考え方自体のことで、「羞恥心」とは、凡人のように生きるのは恥ずかしいという感情を意味する。
本来ならば、尊大は自尊心と、臆病は羞恥心と結びつくべきである。しかしそうならないのは、李徴の精神が二つに分裂し屈折しているからだ。その分裂と屈折が、本来くっつく筈のない臆病と自尊心、尊大と羞恥心を結びつけてしまったのである。
李徴の精神は中島敦の心の表れ
その結果、李徴はどうなったか。
彼は「臆病な自尊心」のために詩を続けることも、「尊大な羞恥心」のために詩を諦めることもできなかった。仲間との切磋琢磨を怠った李徴は、高官になった仲間に敵うはずがない。だが詩を諦めれば、凡百の人間と同列になってしまう。彼は「臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」のために、どちらも耐えられなかったのだ。そして内面に抱えた「尊大な羞恥心」が、外見を虎に変えてしまった。虎はその外見によって相手を威嚇するが、それ故に孤独な存在でもある。その姿まるで「臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」そのものだ。李徴の外面は、変身によって、内面と一致することになった。
実は李徴には、中島自身の心が反映されている。中島敦は喘息のために33歳でこの世を去った。『山月記』は彼のデビュー作であるが、死の年に書かれたものでもある。それが雑誌で発表されるまでは、なかなか注目されてこなかった。豊かな教養を持ち合わせ、自分の才能にいささか自信もあったであろう中島は、その元々の性格である厭世主義もあいまって、芸術に対する不安と孤独の中で生活していた。しかも病気がちで死の予感もあったであろう。死の予感と芸術に対する孤独感は、焦燥感を掻き立てたに違いない。当時抱いていたその焦燥感は、そのまま李徴に反映されているのである。
\Kindle Unlimitedで読める!30日間無料!/
→Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
考察・感想
伝えたいことは「才能の有無が問題ではない」ということ
さて、本書を丁寧に読み解くと、李徴が自分の才能の有無に拘っていることがわかる。彼はそうこう悩んでいる内に、「臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」が肥大化して、変わり果てた姿になってしまったのである。
だが、李徴は成功した人間についても語っている。
己よりも遥かに乏しい才能でありながら、それを専一に磨いたがために、堂々たる詩家となった者が幾らでもいるのだ。
青空文庫(https://www.aozora.gr.jp/cards/000119/files/624_14544.html)
李徴はこの人たちを「己よりもはるかに乏しい才能」だと断言している。乏しい才能の持ち主が、李徴を差し置いて、堂々たる詩家になれたのは何故か。
大成した者と李徴の違いは、才能の有無に拘らなかったところにある。彼らは才能が乏しかろうと、師を仰ぎ仲間と切磋琢磨して、詩の技術を磨いてきた。その反面、李徴は自分の才能の有無ばかり気にして、どっちつかずの態度をとった。少しの自信から才能の乏しい者を馬鹿にする一方で、他を圧倒するような自信がないために作品を世に問うこともできなかった。才能で存在を認めさせることのできない李徴は、コツコツ努力する道も歩まなかったのである。
そう考えると、李徴に足りなかったのは、シンプルな向上心だと分かる。もちろん向上心があればうまくいくというわけではない。だが、才能の有無にかかわらず、向上心がないと成功しないのだ。そしてそれこそが作者の中島敦が伝えたいことでもある。才能があることは、成功の絶対条件ではない。才能が乏しくともコツコツと努力して大成した李徴の仲間を見よ。向上心や己を磨き続ける力の方が、上達のための絶対条件なのだ。
李徴は「我々自身」である。だから李徴の言葉は我々の心に響く
物語の終盤で李徴は、虎になった自分の気持ちは誰一人分かってくれないと述べる。そしてそのことの虚しさを吐露した後、自分の弱さを告白する。
人間だった頃、己の傷つき易い内心を誰も理解してくれなかったように。己の毛皮の濡れたのは、夜露のためばかりではない。
17頁
いくら才能に溢れていようとも、人間の心は弱く傷つきやすい。李徴のように「尊大だ」と評される人物でもそうなのだ。虎の毛皮ですら自らの涙で濡れたように、外見は全くあてにならない。
李徴は特殊な人間だろうか。むしろ李徴のように「臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」を抱えた人間が沢山いるのではないか。まずは胸に手を当てて内省してみるといい。自分は頭がいい、明日になればできると自信を持ちながら、自分の作品や才能の一端ですら示せない。そこに「臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」が存在してはいないか。わたしたちは皆、自分の才能のなさを人に知らされたくないという「臆病な自尊心」と、才能のない人間に成り下がりたくないという「尊大な羞恥心」を持っているのだ。
中島敦だけでない、誰もがこの不安の中で悩んでいる。だからこそ、李徴の言葉は心に響く。解決策は簡潔で、それ故難しい。内に潜む「臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」を見つめること、そしてコツコツ努力すること、ここにしか成功の道はない。
そして成功した者や才能があると一目置かれる者ですら、傷つきやすい弱い人間であることも、『山月記』は教えてくれる。李徴の臆病さを他人が理解してあげていれば、彼は虎にならなかったかもしれない。しかし殻に閉じこもった人間の内面を、理解することは難しい。ここには解き難いジレンマがある。『山月記』はこのジレンマによる孤独と根本的な寂しさも見事に描いている。
関連作品
Audible・Kindle Unlimitedでの配信状況
| Kindle Unlimited | Audible | |
|---|---|---|
| 配信状況 | ○ | ○ |
| 無料期間 | 30日間 | 30日間 |
| 月額料金 | 980円 | 1,500円 |
文学作品を読む方法は紙の本だけではない。邪魔になったり重かったりする紙の本とは違い、電子書籍や朗読のサービスは、いつでもどこでも持っていけるため、近年多くの人に人気を博している。現在日本では、電子書籍や朗読が読み・聴き放題になるサブスクリプションサービスが多数存在している。ここでは、その中でも最も利用されているAudibleとKindle Unlimitedを紹介する。
AudibleはKindleと同じくAmazonが運営する書籍の聴き放題サービス。プロの声優や俳優の朗読で、多くの文学作品を聴くことができる。意外なサービスだと思われるが、聴き心地が良く多くの人が愛用している。無料お試しはこちら。
関連記事:Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
関連記事:【2023年最新版】Audible(オーディブル)のおすすめ本!ジャンル別に作品紹介
Kindle UnlimitedはAmazonが運営する電子書籍の読み放題サービス。様々なジャンルの電子書籍が200万冊以上も読めるため、多くの人に愛用されている。30日間の無料期間があるので、試し読みしたい本を無料で読むことができる。無料お試しはこちら。
関連記事:Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
関連記事:【2023年最新版】Kindle Unlimitedのおすすめ本!ジャンル別に作品紹介
参考文献
中島敦『李陵・山月記』新潮文庫、2003年。