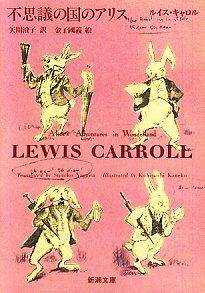概要
『砂の女』は、1962年に刊行された安部公房の長編小説。1963年に読売文学賞を受賞。1964年に勅使河原宏監督により映画化。日本を代表する不条理文学の一つ。不条理文学はカミュ『異邦人』、カフカ『変身』などが有名である。
現代日本文学を代表する傑作であり、世界各国で翻訳され海外でも高く評価されている。1968年にフランスで最優秀外国文学賞を受賞。
昆虫採取のために海辺の砂丘を訪れた男が、砂の穴に閉じ込められそこに住む女と生活しながら、脱出を試みる物語。
純文学はほかに谷崎潤一郎『春琴抄』、太宰治『人間失格』、芥川龍之介「河童」、村田沙耶香『コンビニ人間』などがある。
本作は「日本純文学の最新おすすめ有名小説」で紹介している。
登場人物
男:仁木順平。教師。31歳。身長158センチ、体重54キロ。視力は右0.8、左1.0。血液型はAB型。趣味は昆虫採集のために海辺の砂丘を訪れたら、女が住む砂の穴に閉じ込められてしまう。
女:30歳前後。色白で愛嬌のある小柄の女。去年、夫と中学生の一人娘を大風で亡くす。男と生活しながら、砂を運びだす作業をしている。
村人たち:砂の穴の外にいる。配給品の配達、砂の移動などをしている。男の要求に融通を利かせる場面もあるが、作業をしないと水の配給を止めるなどの強硬姿勢を示す。
老人:村長らしき男。
名言
罪がなければ、逃げるたのしみもない(p.4)
そう……十何年か前の、あの廃墟の時代には、誰もがこぞって、歩かないですむ自由を求めて狂奔したものだった。それでは、いま、はたして歩かないですむ自由に食傷したと言いきれるかどうか?(p.85)
納得がいかなかったんだ……まあいずれ、人生なんて、納得ずくで行くものじゃないだろう……しかし、あの生活や、この生活があって、向こうの方が、ちょっぴりましに見えたりする……このまま暮らしていって、それで何うなるんだと思うのが、一番たまらないんだな……(p.198)
べつに、あわてて逃げだしたりする必要はないのだ。いま、彼の手のなかの往復切符には、行き先も、戻る場所も、本人の自由に書きこめる余白になって空いている。(p.227)
あらすじ・内容
昭和30年(1955年)8月のある日、男が一人行方不明になった。彼は休暇に電車で海岸に向かったきり帰ってこなかった。旅の目的は昆虫採集で、それ以前に逃亡をほのめかすようなこともなく、事件解決は困難を極めた。その7年後、民法30条の規定により、死亡認定を受けることになった。
ある8月の午後、男は新種のハンミョウを採集するために、汽車とバスを乗り継いで海岸近くの砂丘に向かった。海岸に近づくにつれ砂丘は高くなり、砂の穴に建てられた家は相対的に低くなっていく。そこに漁師らしき老人が現れた。彼ははじめ男を市の役人かと疑っていたが、一般市民であることを確認すると、部落にある民家で泊まるよう案内される。
その家には寡婦が一人で住んでいた。彼女は日々積もり続ける砂を、穴の外に運び出す作業に明け暮れていた。砂の穴と外の出入りは縄梯子のみで、外にいる村人に砂を渡し、村人からは物資が補給される。彼は男がこれからも砂の穴で生活することが前提となっているような彼女の言い回しに疑問を覚えるが、昆虫採集のことを考えて寝てしまう。
一夜明けると、縄梯子が取り外され、男は砂の穴に閉じ込められていた。失踪届が提出され役人が探しに来ると脅してみたり、怪我をしたと偽ってみたりするが全く効果がない。その間、女は家が潰れないように日々砂を外に運び出していた。そこで男はその作業を手伝い従順なふりをして、脱出の機会を探る。
ある日、女を拘束し砂を運ば仕事をやめ、外にでられるよう村人と交渉する。しかし村人は一向に動かず、男は水分不足で苦痛に喘ぐ。結局男は根負けし女の拘束を解く。それ以来、砂運びの仕事を再開し、脱出の機会をうかがう。
村人が寝静まったタイミングを見計らい、自作の縄で脱出を試みる。しかし村人が起きる前に村の外へ行けないばかりか、方向を誤り海辺の近くまで来ていた。村人に追われて危険地帯に入ってしまい、砂に溺れてかけたところを村人に助けられる。そして男はまた砂の穴に戻され、女との生活を再開する。
次第に女との生活にも慣れ、夫婦のようになる。烏を捕まえる装置を作ったところ、その装置の下に水が溜まっているのを発見し、誰にも知られないように溜水装置の研究をする。
3月になり、女が妊娠した。その2ヶ月後、子宮が妊娠で町の病院に運ばれる。そのとき使った縄梯子はそのままになっていた。男は縄梯子に登り脱出しようとする。しかし溜池装置のことを誰かに伝えたいという衝動がこみ上げ砂の穴に戻る。逃げる手立ては翌日に考えればいいことである。
\30日間無料!解約も簡単!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
解説
『砂の女』の評価と批評の概略
『砂の女』は安部公房の代表作にして、現代日本文学の傑作の一つに数え上げられる。また20ヵ国語以上に翻訳され、海外でも高い評価を得ている。刊行されたのは1962年で、安部の中期の作品にあたる。
昆虫採取に海辺に向かった男が、砂の穴に閉じ込められ、女との共同生活を余儀なくされる、というのが物語の筋である。基本的には、砂の穴の生活からの脱出の試みと、女との交流と労働が描かれるが、途中で会社員時代の生活やある男性との会話などが挿入される。幾度かの脱出の試みが失敗し次第に砂の穴の生活に順応した男が、外に出るための縄梯子を前にして、開発した溜池装置を誰かに知らせたいという想いから砂の穴に戻るというのが結末である。
小説家の大佛次郎は本書を「新しいイソップ物語りとして愛読した」と述べている(大佛次郎「選評(第14回・1962年度読売文学賞)」)。大佛の言う通り、砂の穴での女との共同生活という奇抜さと砂丘や溜池装置などの描かれ方は如何にも寓話的である。だが本書から何を受け取るのかは意外にも難しい。
物語の複数の解釈
例えば、男が砂の生活に意外にも馴染んでいく様子を重視して、どのような環境でも順応し、如何なる生活でも力強く肯定できるという物語にもとれる。男が作り上げた鴉を捕獲する装置である<希望>の底に発見した水から、溜水装置を作り上げるその創意工夫と環境適応の柔軟さは見習うところが大きい。
また、砂の穴からの脱出を試みては失敗しその度に絶望しながら、それでも脱出の意思を最後まで失わなかったという点も注目すべきだろう。彼は一度二度の失敗ではへこたれず、仮病、立て籠り作戦、縄を用いた脱出、鴉を捕獲する装置である<希望>、など挑戦を諦めることはない。それは脱出を諦めたと考えられる最後の場面、「逃げるてだては、またその翌日にでも考えればいいことである」(p.228)でも示されている。つまり、砂の穴に戻ったあとでも見方によっては脱出の挑戦を捨てたわけではない。
砂の穴に戻った男の決断を重視し、男の自己変革の物語にもとれる。女を病院に運ぶために使われた縄梯子がそのまま残されてるのをみて、男は一度はそれに登るも、溜水装置を村の人に見せるために砂の穴に戻る。この心情の変化は、脱出から共住へ、とまとめることができるだろう。この荒涼とした砂漠から湧き出る水の存在は、男の精神を潤すだけでなく、村全体の恵みの水になる可能性がある。強制されたこの生活にどっぷりと浸かることで、自己のみならず村全体の変革の予兆を発見するのである。
\30日間無料!解約も簡単!/
→Kindle Unlimitedとは?料金・サービス内容・注意点を解説
考察・感想
資本主義からの逃走
別の観点から考えてみよう。
本書が刊行されたのは1962年で、舞台はその7年前の1955年、死亡届がでるのが1962年の7月だから、安部は執筆当時から7年前に舞台を設定したことになる。その頃の日本といえば、まず高度経済成長期であることを指摘せずにはいられない。高度経済成長期とは、1954年12月の第一次鳩山一郎内閣から、1973年11月の第2次田中角栄内閣までの、約19年間も続く長い長い好景気のことで、1955年は実質的な始まりの年である。
働けば働くほど報酬が得られた時代。今日よりも明日、明日よりも明後日と過ぎていけば、生活の質が向上すると素朴に信じられた時代。男が生活しているのはそのような希望にあふれた日本社会なのである。ところが本書にはそのような明るい雰囲気が見られない。都会から離れた海辺近くの砂丘が舞台になっているのだから、そのことは当然のようにも思われるかもしれないが、過去の回想や会社員時代の同僚との会話でも陰鬱な雰囲気が漂っている。
この点を重要視するならば、本書が輝かしい高度経済成長期の裏面、都会や資本主義から阻害された人物を描いているとも考えられる。
一人前の大人になって、いまさら昆虫採集などという役にも立たないことに熱中できるのは、それ自体がすでに精神の欠陥を示す証拠だというわけだ。(p.6)
これは彼の同僚が、男の趣味の昆虫採集に注目して、失踪の理由に厭世自殺を言い出した場面である。真実は砂の穴に閉じ込められたのだからこの説は間違っていたわけだが、しかし昆虫採集の熱心さは目を惹かれるところがある。「役にも立たないことに熱中」する原因は、少なからず当時の環境と、砂を求める男の精神に関係しているだろう。新種の昆虫の発見意欲が昂じ、「以来、彼は、砂地に関心を示し始め」(p.12)、それは独立した興味へと変容し、「流動する砂のイメージは、彼に言いようのない衝撃と、興奮をあたえ」(p.16)ることになる。彼は砂の流動性のイメージに取り憑かれている。
たしかに、砂は、生存には適していない。しかし、定着が、生存にとって、絶対不可欠なものかどうか。定着に固執しようとするからこそ、あのいとわしい競争も始まるのではなかろうか?(p.16)
彼はこのとき明らかに、「あのいとわしい競争」の原因を「定着」にみて、そこから逃れる術としての「流動する砂」に惹かれている。「強い適応能力を利用して、競争圏外に逃れた生き物たちだ。たとえば、彼のハンミョウ属のように……」(p.16)は、まるで砂の穴に適応する彼の将来を予見しているかのようである。生存に適していない砂丘に住むハンミョウ属を追う男は、いつの間にか男はハンミョウ属のように環境に適応する。彼は「自分自身が流動しはじめているような錯覚にとらわれさえ」(p.16)している。
求めた自由は外部にない。<<脱出>の先にある脱出>の先にある……
反対にこの村の住人、特に若者は、「若い人たちは、なかなか、居ついてくれませんのですよ……どうしたって、町場のほうが、給金もいいし、映画館や食堂だって、毎日店を開けているんでしょう……」(p.113-114)と言われれるように、村から出て町場のほうに向かってしまう。「映画館や食堂」は発展し成長する街の象徴であり、若者はそこで割りの良い「給金」を貰いながら資本主義のシステムに入っていく。
これに対比的に描かれるのが、砂丘の村で展開されるある種の社会主義的な経済システムだろう。女と男の砂掻きという労働は何も生産せず、報酬は内職の微々たるもので、食糧や必需品は村から分配される。生産や競争とは無縁の砂掻きという労働は、文字通り生きるために行われる。男が告白するように街の労働には、「義務のわずらわしさ」がこべりついてた。
そこまで義務を負ういわれはない。そうでなくても、負わなければならない義務は、すでにあり余るほどなのだ。こうして、砂と昆虫にひかれてやって来たのも、結局はそうした義務のわずらわしさと無為から、ほんのいっとき逃れるためにほかならなかったのだから……(p.41)
男にとって想定外だったのは「ほんのいっとき逃れるため」に訪れた砂丘に半永久的に閉じ込められただけではなく、そこでの生活が決して義務からの解放を意味していなかったことだ。競争から逃れた先にある生きるための労働に男は不自由を感じ、元の生活に戻る気持ちを抑えられない。そしてこの窮屈な砂の穴の生活を強制される女に、「自由」を手に入れたくはないのかと問わずにはいられない。
「歩けばいい!」
「歩くって……?」
「そうさ、歩くんだよ……ただ、歩きまわるだけで、充分じゃないか……そういう、あんただって僕がここに来る前は、自由に出歩いていたんでしょう?」(p.84)
物資は配給制で、毎日砂を掻き出すだけの生活。この無欲な生活を強制されている女に、せめて外を歩きたいと言ってほしい。そして強制されているという意味で同じ土俵に立っていることを確認し、「自由」を共に手に入れたい。ところが驚くべきことに、彼女は自由を望むことはおろか、この生活を強制すらされていない。
「歩きましたよ……」ふと、女は、殻を閉ざした二枚貝のような抑揚のない声で、「本当に、さんざん、歩かされたものですよ……ここに来るまで……子供をかかえて、ながいこと……もう、ほとほと、歩きくたびれてしまいました……」
男は、不意をつかれる。まったく、妙な言いがかりもあったものだ。そうひらきなおられると、彼にも言い返す自信はない。
そう……十何年か前の、あの廃墟の時代には、誰もがこぞって、歩かないですむ自由を求めて狂奔したものだった。それでは、いま、はたして歩かないですむ自由に食傷したと言いきれるかどうか?現に、おまえだって、そんな幻想相手の鬼ごっこに疲れはてたばかりに、こんな砂丘あたりにさそい出されて来たのではなかったか……砂……(p.85)
不意を突かれた彼女の答えに、自分も歩き疲れていたことを、だからこそ砂丘に誘い出されたことを思い出す。男は強制的に歩かされていたのだ。彼はその強制(=義務)から逃れるために砂丘を訪れ、いまや閉じ込められていること(=義務)に不満を抱き、「自由」を求めている。ここに彼の行動の矛盾と、外部に解放を求めることの不可能性が明瞭になる。では一体、どこに<希望>があるというのだろうか?
伝えたいこと——希望は渇き切った砂の底にある
男は鴉を捕まえる装置を作り<希望>と名付ける。脱出の試みが失敗した彼は、捕まえた鴉に手紙をくくりつけ飛ばす作戦を思いついたのだが、<希望>に鴉がひっかかる様子はみられない。それに「男はひどく慎重になっていた」(p.201)。彼は息を潜め、村人の意識から消え去るために、「生活の単純な反復のなかに融けこ」もうとする。
この<希望>という仰々しい名前にもかかわらず、脱出への意思に絶対的なものがみられないのは、諦めにも似た感情に侵食されたからだけではない。それに加えて反復の生活の中で彼に変化が起こり始めている。恐怖に身を引きつらせた亡者たちがひしめき合う孤独地獄という銅版画の写真を、当初は「どういうわけで、これが孤独地獄なのだろう?題をつけ違えたのではないかと」も思ったが、「いまならはっきり、理解できる(p.203)」と言う。
孤独とは、幻を求めて満たされない、渇きのことなのである。(p.203)
これは水分を吸収し枯渇させる砂であると同時に、義務を逃れ砂丘に昆虫に何かを求めた過去の自分のことでもある。そのことを悟ったのも、彼が日々繰り返されるここの生活に「あるささやかな充足を感じていた」からである。
ある日、男は<希望>の下に水が溜まっているのを発見する。これまで彼を魅了しながら苦しめてきた渇き切った砂は、地下に潤沢な水を蓄えていた。そしてそのヒントは意外にもこれまでの日常に隠れていた。「朝夕、砂浜が吐き出す、あの膨大な量の霧も、壁や柱にこべりついて、材木を腐らせていくあの異常な湿度のことも、全て容易に説明がつくわけだ」(p.222)。これまでの生活において負の効果しか与えてこなかった湿度と霧、この見えていたはずなのに透明だった水の存在が、砂の底で希望へと変わる。脱出への希望を灯す恵の水は、渇き切った砂の底に、当て付けのようにつけられた<希望>の下に、誰にも知られず存在していたのだ。
二人は念願だったラジオを手に入れる。それは資本に踊らせた結果でも、義務にかられたものでもなく、日々の内職で少しずつ貯めた金で買ったささやかな喜びである。そのような生活が続いたある日、子宮外妊娠を疑われた女が病院に運ばれる。女が運ばれた後、縄梯子がそのままになっている。男にとっては待ち望んでいたチャンスである。彼はその縄梯子を一度は登るも、溜池装置が壊れているのを発見して、砂の穴に戻る。
べつに、あわてて逃げだしたりする必要はないのだ。いま、彼の手のなかの往復切符には、行き先も、戻る場所も、本人の自由に書きこめる余白になって空いている。——中略——
逃げるてだては、またその翌日にでも考えればいいことである。(p.328)
彼はもはや砂の穴を出る必要はない。何故なら、いまここではない外部のどこかに「幻を求め」ることが「満たされない」と悟り、そして、絶望的に渇き切った砂の下に水が存在していることを、つまり逃げ出したくなるようないまここの生活の足元に、希望への端緒が開かれていることを発見したからだ。村の人は往復切符の行き先に街を戻り先に砂の穴を、男は行き先に砂の穴を戻り先に街を書き込むが、そこはいまや「余白になって空いている」。義務から遠ざかり生活から逃げるという偽りの自由を捨て、彼は本当の「自由」を手に入れた。どこに行ってもいい。何をしてもいい。ただ答えは、透明な霧の存在に、渇き切った砂の下に、すでに存在している。
補遺——『砂の女』とほかの作家への影響
『夢十夜』や『こころ』で有名な夏目漱石は『草枕』の冒頭で、外部に救いがないことを的確に表現している。
ただの人が作った人の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい。あれば人でなしの国へ行くばかりだ。人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう。
男は人の世を逃れるために砂丘に来たのだが、実際「人でなしの国」である砂の穴は大層住みにくかったであろう。だから人の世のほうを住みやすくしよう、というのが夏目の提言であるが、とはいえそれは、砂の穴にきたからこそ気づけたことでもある。「人でなしの国」とはここでは砂の穴であるわけだが、ここはある意味で日本を表象してもいる。遠藤周作は『沈黙』のある部分で、「この国はすべてのものを腐らせていく沼だ」と書いているが、『砂の女』の砂のイメージはこれに通ずるものがある。日々家に積もり腐らせる砂は、彼らに生きる基盤を与えない。したがって、男の脱出の信念を腐らせ、女の歩き疲れたという諦念に変化させるという見方もできなくもない。
ところで「人でなしの国」との接触というモチーフは、その後も綿綿と受け継がれている。代表的なのは村上春樹である(村上には「かえるくん、東京を救う」「神の子どもたちはみな踊る」などがある)。彼の作品には「異界」との接触というモチーフが溢れている。『街とその不確かな壁』ではこの現実世界とは異なる「街」の生活があり、『海辺のカフカ』ではラストに死後の世界のような空間へと接続され、『1Q84』では巨大な力を持つ善悪不明の存在「リトル・ピープル」によって月が2つある1Q84の世界が現れる。そしてこの「異界」との関係と責任を真摯に考え抜いたのが『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』である。この作品では主人公が、脳内世界と考えれれる「世界の終わり」に残ることを決意する。ある観点からいえば、その結末は『砂の女』と類似しているわけだが、その場に残る決意の理由は異なるようだ。
村上に影響を受けたアニメ作家の新海誠は、数多くの作品で「死の世界」との接触を描く。『星を追う子ども』のアガルタや、『君の名は。』の御神体を祀る山頂がそれだ。そして「異界」との接触を描いた『天気の子』は、村上とは異なり「異界」からの脱出をはかる。
このように「異界」のモチーフは、姿形を変え現代まで綿々と受け継がれてながら、各々の作家がそれとの接触に異なる想いをのせ、それぞれの回答を提出してきた。そのことに注目すると、受け継がれてきたものの大きさとフィクションの歴史の重みを感じるだろう。そして現代のフィクションの作り手は、小説家だけでなくアニメ作家や映画監督も、近代小説の影響を少なからず受けており、そこで提出された問いの答えを探している。
関連作品
参考文献
安部公房『砂の女』新潮社、1981年