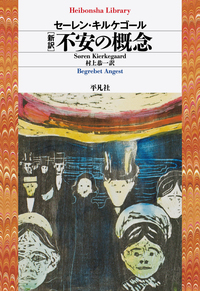ハイデガーとキルケゴールとヘーゲル
ハイデガーの『存在と時間』には「不安」という気分に関する記述がある。複雑で難解な哲学的議論の最中に「不安」の概念がいささか唐突に挿入されるため驚いた読者も多いかと思われるが、実はハイデガーが「不安」を考察するにあたり依拠した先行研究がある。それがキルケゴールの『不安の概念』だ。
ハイデガーは1889年にドイツに生まれて、キルケゴールは1813年にデンマークに生まれた。『死に至る病』で有名なキルケゴールは、ほかにも『不安の概念』や『あれか、これか』などの重要な著作が多数ある。キルケゴールはキリスト教徒であり哲学的著作は宗教色が強いため難解なのだが、実存主義の創始者でもあり後世に多大な影響を与えた重要な哲学者である。
キルケゴールの時代の哲学的背景を概観しておこう。キルケゴールに先行する人にゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルという大物哲学者がいる。ヘーゲルといえば「弁証法」が有名で、最近では東京都知事の小池氏が「アウフヘーベン(止揚)」なる概念を用いていたが、何を隠そう「アウフヘーベン」はヘーゲルが鍛え上げた弁証法の用語なのだ。東京都知事だけではなく、現代の哲学者、例えばジジェク(否定性や現実界などで有名)やジュディス・バトラーもヘーゲル哲学に多大な影響を受けている。
では、約200年前、キルケゴールの時代はどうだったのだろうか。実はキルケゴールの時代のほうが現在よりもずっとヘーゲルの威光が輝いていた。大学ではヘーゲル哲学が跋扈していたのだ。ヘーゲル哲学の権威があまりに強かったため、後続の世代はヘーゲル哲学を乗り越える形で自らの哲学を打ち立てねばならなかった。その中心がマルクス、ニーチェ(ニヒリズムやルサンチマン、永劫回帰などの概念が有名)、そしてキルケゴールである。キルケゴールは考えた、ヘーゲルの哲学は合理主義で主観的な考察に欠けていると。そしてでてきのが「実存」の問題である。
キルケゴールの不安(=めまい)
『不安の概念』は1844年に出版された。キルケゴールの著作は神との関係が問われることが多く、キリスト教の知識が必要な場面がある。まず目次を見てみよう。
1. 原罪の前提としての不安
2. 原罪の結果としての不安
3. 罪意識を欠く罪の結果としての不安
4. 罪の不安、あるいは個体における罪の結果としての不安
5. 信仰による救いの手としての不安
さっそくでてきた「原罪」はキリスト教において重要な概念だ。かいつまんでいうと、アダムとイブという無垢な存在が神の言いつけを破り木の実を食べたという罪で、人類最初の罪ということになる。この罪はアダムとイブを媒介にして、人類全体に侵入してしまったので我々も生まれながらにして原罪を負うことになる。個別の罪(アダムとイブ)が普遍の罪(人類)にそしてまた個別の罪(我々個人)へと転換されてしまうのだ。この個別と普遍のごっちゃ感がキリスト教を分からなくさせているところでありまた面白いところでもある。
目次をもう一度見てみよう。不安には「原罪の前提としての不安」と「〇〇の結果としての不安」の二つがある。罪を発生させる不安と、罪から生じる不安があるというのだ。ここでも重要なのは原罪の概念だ。人類が原罪を背負う前後を見てみよう。原罪以前、楽園にいたアダムとイブは性も善悪も罪の意識もない無垢の存在だった。しかしなぜか禁忌の木の実を食べてしまう(後述するが禁忌の木の実を食べてしまう理由こそが不安だとキルケゴールは主張している)。原罪以後になってようやく性や善悪や罪の意識をさらには主観と客観の区別を持つようになる。ここで原罪以前の不安は罪を発生させる不安に対応し、原罪以後の不安は罪から生じる不安に対応する。
原罪以後の不安からみてみよう。二章に有名で端的に不安の概念が語られている箇所がある。
不安はたとえて言えば「目まい」 (Svimmelhed)のようなものである。仮にある人がふと自分の眼で大口をひらいた深淵をのぞき込んだとすると、その人は目まいを覚えるであろう。
キルケゴール 『不安の概念』村上恭一訳、平凡社、2019年、111頁
この後すぐに深淵は自由と言い換えられる。
自由が自己自身の可能性(の底)をのぞき込み、しかもその際わが身を支えるために有限性に手を差しのべるときに、不安が自由のめまいとなって起こるのである。
キルケゴール 『不安の概念』村上恭一訳、平凡社、2019年、111頁
我々の前には可能性が広がっていて、その可能性の中で我々は自由である。しかし自由を覗き込むと不安(=めまい)を起こしてしまう。ここで重要なのは不安の対象が存在しないことだ。明日のプレゼンをどうしようとか試験でいい点取れるかなあというように、対象を持つ場合はキルケゴールが論じている不安ではない。不安は無に対して漠然とおこるものなのである。
原罪以前の不安
原罪以後の不安に似ているのだが、原罪以前の不安についてもみてみよう。原罪以前というのはキリスト教の中の話であって我々には関係ないのではないか、と思われるかもしれない。しかし案外そうでもない(ように読める)。なぜなら原罪以前というのは善悪がない状態=子供の状態ともとれるからだ。そして我々だって常に善悪の意識があるわけではない。意外と何も考えていない(擬似的な原罪以前の)状態で生活をしていたりもするのだ。
わかりやすいように原罪以前の不安を「アダムとイブがなぜ罪を犯したか」という別の角度の問いから明らかにしてみよう。こう問われた場合、蛇が誘惑したからだ、といいたくなるかもしれない。しかしアダムとイブが原罪以前の状態だということを忘れてはならない。無垢な状態では誘惑は誘惑にならない。なぜなら魅力的という観念すらないからだ。
驚くべきことに、「蛇の誘惑は誘惑ではない」ということと同じことが、神の禁止にもいえてしまう。アダムとイブにとって「木の実を食べるな」は禁止の意にとられていのだ。だから「アダムとイブがなぜ罪を犯したか」という問いの罪は罪ではない。所詮は原罪以後からみたときにのみ生じる罪でしかないのである。ここらへんを取り違うなとキルケゴールは再三注意する。
神がアダムに対して、「しかし善悪を知る木から取って食べてはならない」と告げられたとのことだが、実のところアダムがこの言葉を理解しなかったことは確かに当然のことである。どうしてアダムがこの善悪の区別を理解するはずがあろうか。
キルケゴール 『不安の概念』村上恭一訳、平凡社、2019年、81頁
では神の禁止は無意味かといえばそうではない。神の禁止には禁止の意味はないが、それゆえになしうるという意味での自由を目覚めさせるのである。
禁断がアダムのうちに自由の可能性を目覚めさせたからである。
キルケゴール 『不安の概念』村上恭一訳、平凡社、2019年、82頁
そしてそこにこそ以下で定義されるような不安が生まれる。
恐怖やそれに類似した諸概念は、恐怖とか何かある特定のものに関係しているが、これに対して不安は、可能性に先立つ(それ以前の)可能性としての自由の現実(性)なのである。
キルケゴール 『不安の概念』村上恭一訳、平凡社、2019年、77頁
神の禁止は禁止としての役割はないのだが、禁止が発せられることで可能性としての自由が与えられてそれが現実性を帯びたとき不安にかられる。そして「禁断の木の実」を食べるや否や事後的に罪の概念が人類に入ってくるのである。
>>本記事はこちらで紹介されています:哲学の最重要概念を一挙紹介!
関連項目
・他者(レヴィナス)
・良心(ハイデガー)
・自由(メルロ=ポンティ)
・ルサンチマン
・実存主義
・形而上学
・方法的懐疑
参考文献
キルケゴール 『不安の概念』村上恭一訳、平凡社、2019年
>>哲学の入門書の紹介はこちら:哲学初心者向けの人気おすすめ著作を紹介!
>>本格的な人向け哲学書の紹介はこちら:本格的な人向けおすすめ哲学書を紹介!