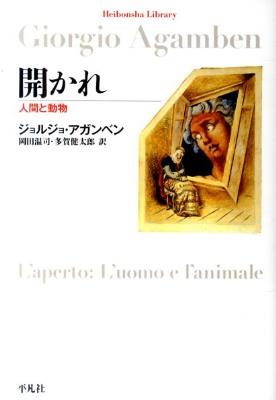シジュウカラは「言葉」を操る?――導入
近年、シジュウカラ(鳥類の一種)の発する「言葉」に迫った鈴木俊貴氏の研究が、専門分野内外でにわかに注目を集めている。鈴木氏の研究によれば、シジュウカラは複数の鳴き声(音声)を「単語」として組み合わせて「文」を構成しており、その構成にはいわゆる「語順」の概念があるのだという。2017年に発表された研究成果では、同種や他種の鳴き声を素材にした人口的な音列であっても、正しい「語順」に則っていればシジュウカラはその意味を理解できることが明らかにされた(京都大学HP「文法を操るシジュウカラは初めて聞いた文章も正しく理解できる」)。シジュウカラは「文法」を持っている。これを実証した鈴木氏の研究は、テレビ番組やネットのオンライン記事でよく取り上げられており、[1] 動物行動学という専門領域を超えて、動物に必ずしも特別の関心を抱いていない一般の人々にも大きなインパクトを与えている。
この研究が広範な反響を呼び起こしているのは、「言葉」という要素が、人々の認識において人間と動物のあいだの暗黙の線引きであったからかもしれない――「言葉を自在に操る能力は人間にのみ与えられた特権である。動物が音声をはじめとした何かしらのサインで、個体間のコミュニケーションを行っているのは明らかであるとしても、言語というよりむしろ特定の刺激に対する本能的反応に過ぎないようにも見える動物の「言葉」は、依然として人間と動物の埋まらない溝を表すものではないのか」・・・といったような認識である。エヴァ・メイヤー著『言葉を使う動物たち』(2020年)に見られるように、言語における人間の特権性に再考を促す言説も新たに注目を浴びつつあるが、「言葉」を操る能力を以って人間と動物の分水嶺とする見方は、根強く浸透しているようだ。
人文学の領域においては、人間と動物の弁別の基準を探ろうとする哲学的・思索的試みが、これまでに数多くなされてきた。動物の言語的「劣等性」に着目するような見方もまさにその一例である。ただしデリダが述べるように、人間と動物の線引きとなる動物の固有性を突き止めようと伝統的に立てられてきた問いの数々は、多岐にわたり、枚挙にいとまがない。
「動物は考えるか?」「動物は表象を持つか?」「私」を、「想像力」を、それとしての将来への関係を持つか? 動物は、記号だけでなく、言語も持つか、そしてそれはどんな言語なのか? 動物は死ぬか? 笑うか? 泣くか? 喪に服すか? 退屈するか? 嘘をつくか? 赦すか? 歌うか? 発明するか? 音楽を発明するか? 音楽を演奏するか? 遊ぶか? 歓待を差し出すか? そもそも差し出すのか? 贈与するのか? 手を、目を持つのか? 等々。羞恥は? 服は? そして、鏡は?……これらの問いのすべて、そしてそれらに依拠する他の多数の問い、それらは動物の固有なものについての問いである。それらは、その歴史、諸前提、争点の複雑さのために、膨大なものである。
(デリダ 120頁)
こういった問いの多くは、大抵の場合、修辞疑問として帰結してきた。つまり、これらの問いに否定形で答えることで、人間と動物の差異は考察されてきた。[2] 人は、己の持つ種々の能力を動物のうちに見出さないことによって、動物の「本質」を規定するための手がかりをつかもうとしてきたのである。[3]
人間の「退屈」と動物の「とらわれ」――ハイデガー
デリダが挙げたキーワードはさまざまだが、人文学における現代の動物理論を知るうえでなかでも重要なのは、「退屈」をめぐるハイデガーの哲学的思索だろう。これは『開かれ――人間と動物』において、アガンベンが人間と動物の閾(=境界)を探るうえで詳細に取り上げた議論でもあった。
ハイデガーによれば(ハイデッガー 303頁)、無生物、そして動物と人間を分かつ境界線は次の三つのテーゼに集約される。
- 石は無世界的である[4]
- 動物は世界貧乏的である
- 人間は世界形成的である
それぞれ確認していくと、まず石はほかに存在する事物に対し、積極的・能動的に関わることがないという点で世界をもたない。つぎに動物はほかの存在物と関わりながら生きているが、しかし付き合う対象物の範囲は限定的であり、さらには目の前にある関係対象を客観的かつ抽象的に「~として」把握することはできない。恣意的な例を出して言ってしまえば、たとえばサケが一生のなかで関わるのは、川や海で遭遇する存在物に限られるし(わざわざ陸地に赴いて陸上生物との交流を探し求めはしない)、アザラシなど天敵に出くわした場合には本能に衝き動かされて逃げるだけで、自らの逃避行動をメタ的に認知することもないし、「アザラシ」という存在を抽象的な仕方で把握することもない。世界との関わりにおけるこういった「貧しさ」をもとに、ハイデガーは動物を「世界貧乏的」と言い表した。
その一方で、人間は現存在(自らが世界に存在していることを自覚する存在)として、自らが付き合う対象物を思うがまま増やしていくことができ、さらにはその世界を世界として認識し、言語を駆使して意味を抽出することさえできる。事実、いまや私たちは陸や海だけでなく、宇宙にまでも進出して関係対象を無数に増やしているし、先に例に出したアザラシにしても、多様なコンテクストにおいて自在に関わっていくことが可能だ(アザラシをアザラシとして一歩距離を置いて捉え、観察・愛玩の対象、もしくは食用にするにせよ、さまざまな仕方で関わることができる)。ハイデガーの見るところ、世界と主体的かつ自在に関わることができる人間は、「世界形成的」な存在なのであり、動物の「世界貧乏」性とは対照をなしている。
こうした視座からすれば、人間は動物よりもはるかに「自由」な存在である。私たちはもはや、特定の外的刺激に(あるいは、個を超えた「使命」のようなものにも)必ずしも没入することなく生きることができる。目の前には数多の選択肢がある。ただし、「とらわれ」ることなく人生の無限の可能性を認知できるからこそ、「生きる意味とは何か?」とふと考えてしまう余地が生まれうる。そうした空虚な気持ちに苛まれ、人はしばしば膨大な時間を持て余しているような思いを抱く。
「自由」であるからこそ、人間は「退屈」しうる。この退屈という心的状態こそ、現存在の本質を成す根本気分であるとハイデガーは見なした。そしてハイデガーの議論において、最も度合いの強い退屈とされるのが、「なんとなく退屈だ」(ハイデッガー 225頁、傍点原文)と感じる状態のことである。「なんとなく退屈だ」については「全体として言うことを聴かない有るもの[=存在者]へと現有[=現存在]が引き渡されていること」(ハイデッガー 234頁、傍点原文)と説明されている。独特な言い回しのせいもあり、やや理解に手間取るが、要するに、現存在の深い退屈を根底から一掃してくれるようなものを存在者が提供してくれないことを指すと考えていいだろう。これは、勉強や仕事、あるいは娯楽といった日常で従事するあらゆるものがみな、ふと長い人生の暇つぶしに思えてしまう虚無感に近い。だが、深い退屈状態にある人間は、それにも拘らずそうした「言うことを聴かない」存在者と関係を結ばざるを――「引き渡され」ざるを――得ない。自らが放置され、閉じ込められている空虚な広域を抜け出すことができていないからこそ、人は退屈する。國分功一郎氏がハイデガーを読み解きながら簡潔に言い表すように、自由と退屈は表裏一体の関係にあるのである――「私たちは退屈する。自由であるが故に退屈する。退屈するということは、自由であるということだ」(國分 228頁)。
では、人間ほどの自由を持たない「世界貧乏」の動物に固有の存在様式とは何か?それは「とらわれ」である。[5] ハイデガーは、ミツバチが蜜を吸っている最中に腹部を切断しても、そのミツバチは吸い続ける動作を止めないといった(ホントかウソか疑わしくも思える)実験を例に出しているが(ハイデッガー 384頁)、つまり動物は世界を「~として」認識する能力が欠如しているがゆえに、目の前にエサが現れたら条件反射的に飛びついてそれに夢中になるし、天敵が現れれば本能のまま逃避行動に没入する。特定の外的刺激に衝き動かされ、思考を挟む間もなく、それに導かれるまま否応なしに行動させられざるをえないのだ。こういった存在様式をハイデガーは「とらわれ」と呼び、「動物性の本質」(ハイデッガー 393頁)をなすものだと論じた。
こうした議論に基づき、デリダが例の一つに挙げた「動物は退屈するのか?」という問いに立ち返れば、動物は(少なくとも人間が抱くような)「退屈」を感じえない点に特徴があると言える。ハイデガーによれば、動物(的)であることは「とらわれ」の主体であることを意味する。「とらわれ」ているからこそ「退屈」しないということになる。
「動物」の呼び方には要注意?――デリダ
ただし、ハイデガーの論述にしても、あるいはそのほかの動物哲学にしても言えることだが、議論で持ち出される「動物」という単語が、具体的にどのような種類の動物を想定しているのか、という疑問はここで当然生じてくるだろう。もし動物論の論者が人間を除く動物全般を包括的に扱っている場合、千差万別な動物を――脊椎動物であれば哺乳類に始まり爬虫類や両生類など、無脊椎動物であれば節足動物や軟体動物などを――すべて一緒くたにし、人間以外の生き物を「動物」とまとめ上げて論じることには問題はないのだろうか?本来多種多様であるはずの動物一般を人間と安易に対比させて二項対立を導き出す思考には、人間の傲慢が見え隠れしないだろうか?
デリダが『動物を追う、ゆえに私は〈動物で〉ある』で強調したことの一つは、まさにそうした点だった。動物をめぐるこれまで哲学の言説に「「人間」に対する「動物」という大きなカテゴリーのもとにあらゆる動物種を混同する傾向」を見て取るデリダは(デリダ 114頁、傍点原文)、まず「動物」の新たな呼び方を提案する。定冠詞付きの単数形 l’animal(英語の the animal に対応、動物を人間と対比して抽象的・総称的に表す言い方)の代わりとなるよう、animal の mal を mot(英語の wordに対応)に付け替えた l’animot という造語である。動物を言い表すのに mot を接尾辞として用いるのは、いわゆる「動物」一般が実体のない言語上の概念にすぎないことを強調する目的もあるが、そのほか animot の発音のうちに、フランス語のanimal の複数形 animaux の音を響かせる狙いもあった。
単数形のなかに動物たちという複数形 le pluriel d’animaux を私は聞かせたい。一般的単数形の動物なるものはないからである、分割不可能な唯一の限界で人間から分け隔てられているようなものは。「生けるものたち」がいるということ、そしてその複数性は、人間性に単純に対立させられた動物性という唯一の形象に集約されるがままにはならないということに考えを及ぼさなくてはならない。
(デリダ 91頁)
この世界に存在するのは、単数形の動物ではなく、あくまで複数形の動物(たち)にほかならない。いわゆる「動物」の途方もない複数性・多様性にも拘らず、あらゆる種の動物を形而上学的な一つのカテゴリーに押し込めて語ることは、複数形の動物(たち)に対する始源の暴力になりうることをデリダは示唆する。
繰り返すが、なすべきことは、異質な限界と構造の多様性を考察に組み入れることだろう。人間ならざるものたちのあいだには、そして人間なるものたちから分離したところには、単数定冠詞付きの動物とか動物性一般と呼ばれるカテゴリーのもとに、暴力と利害がらみの誤認による以外、何があろうと均質化されない他の生けるものたちの膨大な多様性がある。ただちに複数不定冠詞付きの動物たちが、そして言うなれば〈アニモ〉がいるのである。動物という共通にして一般的なカテゴリーのもとに人間ならざるすべての生けるものたちを混同することは、思考の要請、注意深さや賢明さ、経験の権威に対する過誤であるばかりではない。それはまた罪でもある。それこそ、動物性に対する罪ではない。そうではなく、複数定冠詞つきの動物たち、複数不定冠詞つきの動物たちに対する第一の罪なのである。
(デリダ 91-92頁)
デリダは(「人間」に対比された)「動物」という形而上学的カテゴリーに疑義を呈することを皮切りに、〈人間〉と〈動物〉を截然と分割しようとする伝統的な動物哲学に批判的検討を加えていく。〈人間〉と〈動物〉のあいだに横わたる境界の存在自体を否定はしないものの、デリダはその境界を次のように捉えなおそうとする――「これから私が言うことのすべては、限界を抹消することではけっしてない。そうではなく、限界の形象を増加させ、線を複雑に、厚くするもの、脱線状化するもの、それを折り曲げ、分割するものである、まさしくそれを、成長させ、増殖させることによって」(デリダ 62頁)。ここでの言い回しは曖昧でやや難解だが、デリダにとっては、少なくとも〈人間〉と〈動物〉の境界はたんなる一本線ではない。二者のあいだの境界にあるのは、増大しうる流動的な空間なのである。[6]
「人類学機械」の停止に向けて――アガンベン
また、アガンベンにしてみても、ハイデガーの議論を踏まえたうえで力点を置いたのは、人間の退屈(=倦怠)と動物のとらわれ(=放心)の間に見出される共通項であった。その共通項に着目したとき、人間と動物のあいだの線引きは宙づりにされ、一時的に停止される。
しかし、だからこそ倦怠は、現存在と動物との思いがけない近似性を明るみに出す。「現存在」は、退屈することによって、現存在から拒まれている何かへと引き渡される(ausgeliefert)のであり、まさしく放心における動物のように、露顕されざるもののうちに曝される(hinausgesetzt)のである。
(アガンベン 116-17頁、傍点原文)
世界貧乏な動物にとって、エサや天敵などの外的刺激は没入を余儀なくされる対象であるが、動物にはそれらを「~として」抽象的に認識する能力がない。つまり、「目の前にいるこの存在は何だろう?」という問いを立てることもできないし、それゆえにその「正体」も決して開示されることがない。にも拘らず、そうした対象に「とらわれ」たまま関係性を続けることを動物は否応なく強いられる。これを指してアガンベンは「露顕されざるもののうちに曝される」ことと表現し、さらには端的に「非暴露性への開かれ」(アガンベン 104頁)とパラフレーズした。この場合、「開かれ」とは「否応なく向き合わされること」と理解するとわかりやすいかもしれない。
だが、実はこの「非暴露性への開かれ」は、人間の根底にある退屈の気分においても通底する概念であった――「人間の倦怠[=退屈]も動物の放心[=とらわれ]とともに、もっとも本来的な身振りにおいては、閉ざされに開かれている」(アガンベン 117頁、傍点原文)。動物性の本質が「とらわれ」なら、人間は人生の根底をなす退屈という「とらわれ」を潜在的に苦しみながら自覚しつつも、そこから決して逃避できない動物にすぎない。要は、動物は自らの環境世界から逃げ出すことができないが、実は人間も退屈という根本的な気分に閉じ込められていて、そこから抜け出すことができていない。その意味で言えば、「閉ざされへの開かれ」にある己の主体を認知し、自分が閉ざされていることに気づくことで動物は「人間」化する。「退屈することを習得した動物、自己の放心から自己の放心へと覚醒した動物」(アガンベン126頁、傍点原文)こそが人間なのである。
動物のとらわれと人間の退屈のアナロジーを論じることでアガンベンが意図するのは、人間と動物の線引きを宙づりにし、二者のあいだの不分明な閾の存在を暴き出すことにほかならない。現代に至るまで人間と動物を区別してきたさまざまな言説をアガンベンは「人類学機械」と呼ぶが、[7] その閾とはまさに、人類学機械が例外的に停止される場なのである。
人文学の動物理論は、動物の解放に寄与できるか?――結びに代えて
このように、〈人間〉の優位性を裏打ちしてしまうような〈人間〉と〈動物〉の安易な線引きに対し、脱人間中心主義的な眼差しを向けるところにこそ、デリダを中心としたポストモダン的動物論の特徴の一つがあると言っていい。現在、動物倫理および動物福祉の分野においては、ピーター・シンガーが『動物の解放』において提起した動物への道徳的配慮の基準――苦痛を感じる能力があるかどうか――に導かれる形で、人が動物に与える苦痛の最小化に力が注がれている。実際、動物福祉への関心が高い欧州では、2021年、鶏などの家畜動物のケージ飼育を2027年までに段階的に廃止する方針がEUによって発表されたことも記憶に新しい。だが、ポストモダニズムの動物論者はしばしば、そういった動物倫理・福祉のアプローチに潜在する人間中心主義的な暴力性をも浮き彫りにする。たとえばオーストラリアの人権・社会法学者ディネシュ・J・ワディウェルは、人間の動物に対する暴力的支配関係を徹底的に糾弾した著書『現代思想からの動物論――戦争・主権・生政治』(原題は The War against Animals)において次のように述べている。
ベンサムの問い――「かれらが苦しみを感じるかどうか」 は、人間と動物の関係を扱う非常に多くの倫理研究で中核をなしている感があり、ピーター・シンガーの『動物の解放』もその一例をなす。ある意味、苦しみの問いは既に、他存在の苦しみが現実かを問う大権保有者の人間主体と、苦しむ能力が疑問に付される人外の主体とを構造化している。今日では動物の苦しみをめぐる哲学的問いが科学と関係し合い、魚は痛みを感じるか、その痛みは人間と同じかなどを調べる現代科学の研究が政治的な比重を増すに至った。そうした探究は、当の苦しみに問われる余地があると想定し、かつその問いは苦しみの存在と状態を調べる人間の大権によってのみ答えられると想定することで、初めから構造を設けている。苦しみをめぐる問いの答は、人間が利用する数百億の動物たちの福祉、ひいては利用の倫理に大きく影響する。しかし正当を期すなら、そもそもなぜこの苦しみを問う権利が私たちにあるのか、そして私たちに利用される生きものらの苦しみの有無を問う権利は、それ自体が私たちの利用行為を通して形づくられたものなのではないかを考えねばならない。苦しみを問う権利が利用行為の産物であるとしたら、倫理は支配に後続もしくは追随することとなる。峡谷に響くこだまのごとく、倫理は支配の反響となる。主権を前提に置く倫理は、先述した認識的暴力に結び付きかねない。
(ワディウェル 52-53頁)
このような現代思想の影響色濃い人文学系の動物論については、動物福祉に向けて実際に活動する人々の足を引っ張りかねないといった批判もあるかもしれない。事実、アメリカの道徳哲学者Gary Steiner(ゲイリー・シュタイナー)は、Animals and the Limits of Postmodernism(『動物とポストモダニズムの限界』)において、デリダを始めとしたポストモダンの動物理論が取り組んでいるのは “feel-good ethics”(「自己満足のための倫理」)であるとその思弁性を手厳しく批判した。シュタイナー曰く、理論家たちは安全地帯に留まっているだけで、動物の抑圧を改善するための具体的な手はずを示せていない――“The tragedy of postmodernism as regards animals is that it comes so close to embracing a notion of human-animal continuity and kinship but fails to advance so much as one clear principle regarding our treatment of animals”(「動物にまつわるポストモダニズムの悲劇は、人間と動物の連続性や親族関係の概念をほぼ受け入れているのに、私たちが動物に接するにあたっての明確な原則を一つでさえ提示できていないということである」)(Steiner p. 3, 6、拙訳)。
しかし、それでもなお、脱人間中心主義的な仕方で人々に徹底した内省を促すという点で、動物をめぐるポストモダンの理論的成果が一定の意義を持つことはたしかだろう。むしろ、現在工場式畜産や動物実験における動物の管理が生政治(民衆の生に権力的に介入して管理・統制する政治支配体制)的な様相を帯びている以上、フーコーやアガンベンの議論は動物の置かれた現状を理解するのに必須であるかもしれない――「工場式畜産や動物実験においては、動物たちの生は常に例外空間[=法の効力が宙づりにされて主権者の暴力に曝されるという、アガンベンが論じた空間概念]に囚われる。それを明確に物語るのは差別的な法の行使で、動物虐待防止法は常に科学や食品産業に利用される動物を法の対象外としてきた」(ワディウェル 117頁)。
動物論はいまや領域横断的に広く論じられている学問であるが、人文学における動物理論は、文学作品における動物(的)表象の解釈に一役買うのみならず、現実社会で人間が動物に行使する支配体制に切り込む糸口になりうるという点でも興味深いものになっている。
引用文献
Steiner, Gary. Animals and the Limits of Postmodernism. Columbia UP, 2013.
Weil, Kari. Thinking Animals: Why Animal Studies Now? Columbia UP, 2012.
アガンベン、ジョルジョ『開かれ』岡田温司・多賀健太郎訳、平凡社、2011年。
京都大学「文法を操るシジュウカラは初めて聞いた文章も正しく理解できる」京都大学HP 文法を操るシジュウカラは初めて聞いた文章も正しく理解できる | 京都大学 (kyoto-u.ac.jp) Accessed 07/06/2022
國分功一郎『暇と退屈の倫理学』新潮文庫、2021年。
ジャケ、シャンタル『匂いの哲学-香りたつ美と芸術の世界』岩崎陽子監訳、晃洋書房、2015年。
シンガー、ピーター『動物の解放』戸田清訳、人文書院、2011 年。
デリダ、ジャック『動物を追う、ゆえに私は(動物で)ある』マリ=ルイーズ・マレ編、鵜飼哲訳、筑摩書房、2014。
ハイデッガー、マルティン『形而上学の根本諸概念』ハイデッガー全集第29/30巻 川原栄峰・セヴェリン・ミュラー訳、創文社、1998年。
フロイト『幻想の未来/文化への不満』中山元訳、光文社古典新訳文庫、2007年。
メイヤー、エヴァ『言葉を使う動物たち』安部恵子訳、柏書房、2020年。
ワディウェル、ディネシュJ.『現代思想からの動物論――戦争・主権・生政治』井上太一訳、人文書院、2019年。
[1] 東大の助教を辞め、5年任期の教員に…シジュウカラにすべてを捧げる「小鳥博士」の壮大すぎる野望 「僕は、シジュウカラという動物を世界で一番見てるんで」 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) / 世界初! 「鳥の言葉」を証明した“スゴい研究”の「中身」(サイエンスZERO) | 現代ビジネス | 講談社(1/6) (ismedia.jp)
[2] たとえば、精神分析の知見が教えるところでは、「動物は嘘をつくか?」や「動物は恥を感じるか?」といった問いを突き詰めると、人間と動物のあいだの差異に行き当たる。
ラカンに従って言えば、そもそも嘘をつく行為、すなわち相手を欺く行為というのは二段階に峻別される。それらは、第一段階の「(戦略的)偽装」と第二段階の「〈発話〉の欺瞞」であり、まず前者の「偽装」とは、数多くの動物に関して特定の条件下で見られる反射的な「反応」行為のことを指す。 そして、第二段階の「欺瞞」については、ラカンの議論を要約しつつデリダが以下のように説明している。
だが、より正確に言えば、欺瞞とは、他者を惑わすために、真実とは別のことを他者に信じさせるために真実を言うという代補的な可能性を、真実を約束することで含むかぎりでの嘘なのである(フロイトが語りラカンがしばしば引用するユダヤの物語はよく知られている。「なぜきみは Xに行くなどとぼくに言うのか、ほんとうは X に行くくせに、 Yに行くのだとぼくに思わせようとして?」)
(デリダ 236頁)
ここで着目される「欺瞞」とは、ただ単に虚偽の発言をするというだけではなく、相手を騙すためにあえて本当のことを言う 「偽装の偽装」であり、これは人間にのみ可能な行為である。もちろん、動物はカモフラージュなど「偽装」の形をとって、天敵などに「嘘」をつくことはできる。すなわち、現象に対する反射的な「反応」で相手を欺くことはできる。しかし、〈真理〉の次元、ないし証人としての〈他者〉を前提とする「偽装の偽装」は動物には行えない。その意味で言えば、「偽装の偽装」をなしえないところにこそ、動物の固有性があるということになる。
また、Kari Weil(カリ・ヴェイユ)は精神分析的文脈に依拠しながら、「恥」の感覚は人間と動物を分かつ境界線として機能すること、さらに己に潜む忌避すべき動物性が「恥」の感覚の前提になることを述べている――“The feeling of shame, according to Freud and Lacan, is what separates humans and animals, but shame is experienced, Kuzniar suggests, at the moment we act most naturally or most ‘animal like’”(「フロイトとラカンによれば、恥の感覚は人間と動物を分かつ性質であるが、クズニアルが示唆するように、恥ずかしいと感じるのは、私たちが最も自然のままに、言い換えれば最も「動物的に」行動したときである」)(Weil 63頁、拙訳)。人間は恥を知るが、動物は恥を知らない。そして、「恥」の感覚は、本能的な欲求に衝き動かされてしまった、換言すれば、「動物のように」振る舞ってしまった、と自覚したときに生じる。ここでは、「私」となるもののうちに棲みつく「恥」を知らない〈他者〉として動物性が位置づけられており、その動物性を自覚して恥じる人間的主体とのあいだにある種階層的な関係が導入されている。
[3] または、これと表裏一体の見方として、人間が持たない、あるいは進化の過程で失った能力を動物に見出すことによっても、動物性はしばしば措定される。たとえば、「鼻がきく」と言えば、しばしば「犬」と結び付けられるように、嗅覚の鋭さは動物を象徴する要素の最も卑近な一例かもしれない。もともと西洋哲学の伝統において、視覚が審美的意識や人間の知性と結びつけられるのとは対照的に、いわゆる「低級」な感覚である嗅覚は、人間の知的精神や文化に逆行するもの、すなわち「人間の内に存在する動物性の残滓」(ジャケ 18頁)として考えられてきた。フロイトは『文化への不満』の中で、「人類にとって決定的な意味をもつ文化プロセスの端緒は、直立歩行にあった」と述べ(フロイト198)、直立歩行への移行、嗅覚が持つ意義の衰退、それに代わる視覚刺激の価値の向上が、連続した進化の過程であったと述べている。したがって、「人間が直立歩行するようになるとともに、嗅覚の価値が低くなった」と考えるフロイトに従うならば(フロイト212頁)、かつての鋭敏な嗅覚を取り戻すことは、人類の進化の流れに逆らい、失われた動物性へと回帰していくことを意味しうる。「嗅覚の弱さは、動物に対して知性において優勢にたつ人間の力の証拠」とされてきたからである(ジャケ 18頁)。
[4] ハイデガーは、ここで述べられる「世界」の意味合いについて、「そのつど接近通路可能な有るもの、付き合い可能な有るもの、のことであり、それは接近通路可能であり、それとの或る付き合いが可能であり、また、有るものの有の様式にとってはそれとの付き合いが必然的であるような、そのようなもの」と定義している(ハイデッガー 319頁)。
[5] 『形而上学の根本諸概念』では「とらわれ」と訳されているが、『開かれ』では「放心」という日本語訳が与えられている。
[6] デリダの言葉を用いてこの空間を言い表せば、複数的かつ脱線的で分割可能、そして自己増殖する「〈リミトロフィ〉」(デリダ 62頁、傍点原文)である。
[7] アガンベンの言葉を使って言えば、「人間と動物の境界線を画定するということが、たんに哲学者、神学者、科学者、政治家が論じているさまざまな問題中のひとつにとどまるというのではなく、むしろ、そこにおいてはじめて「人間」のようなものが規定され産出されるような、根本的に形而上学的かつ政治的な、ひとつの操作」である(アガンベン 43-44頁)。
こちらは哲学用語特集 – 〇〇とは何か – に収録されています。こちらもぜひご覧ください。