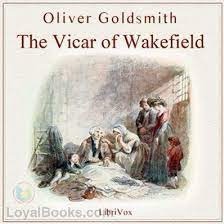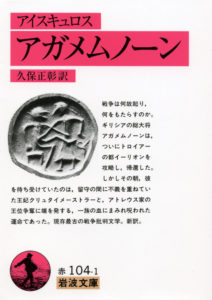小説の誕生から成熟へ
イギリス小説最初期の作家ヘンリー・フィールディングやジョナサン・スターンと、19世紀初頭に活躍するジェイン・オースティンとの中間に位置する1766年に出版された作品である。現代の目から見て作品単体でおもしろいかどうかは微妙だが、文学史的に考えてみると色々と興味深いところが多い。
作品の内容には、フィールディングなどに典型的なピカレスク的冒険、ゴールドスミス自身がその尺者でもあった風習喜劇的な登場人物(放蕩、結婚など)、「感傷(センチメンタリー)」と呼ばれるブルジョワ的市民道徳(中流階級の道徳観を礼讃するような一節も見られる)、当時人気だった変装というモチーフなど、この時代、あるいはそれ以前の時代に顕著な要素がふんだんに盛り込まれている。これらの要素が混ぜ合わされている雑多さがまさに小説的で、とりわけピカレスク・ロマンの枠組み(特に作品後半)をもとにしながら風習喜劇的な筋を展開させている点は注目される。
同時に、あとの時代の作品との共通点も目につく。特に最初の数章に強く見られる、子供たちの結婚にお節介を焼く牧師の妻の言動、ソーンヒル氏の第一印象の悪さとその後の印象の改善(もっとも彼は最終的に悪人だということになるので厳密には異なるが)などは、オースティンの『高慢と偏見』などの作品を思い起こさせる。また、バーチェル氏が実際にはサー・ウィリアム・ソーンヒルという高貴な人物だったと判明する展開は、ディケンズの『大いなる遺産』などイギリス的な「遺産相続」型教養小説を先取りしているといえる。この作品がドイツのゲーテに愛されたという逸話はよく知られており、ある種の小説群に影響を与えた作品であることは間違いない。
心理描写の萌芽
基本的に登場人物の心理に重きが置かれていないことは、現代から見ると物足りなさや違和感を感じるかもしれないが、それはそれでこの時代の作品の味わいどころではある。一人称で語られた作品でありながら、牧師の感情は基本的に問題にならないか、描かれたとしてもきわめて定型的なものであり、次々と災難に突き当たる牧師の内的葛藤を解明しようという態度はこの作品にはみられない。
しかしその一方で、やがて訪れるロマン主義的感性の萌芽が見られるように感じられる場面もある。例えば第十章にある次のような一節。
そこで土曜日の午前中に私が気をつけていると、妻と娘たちがひそひそと相談をしては私のほうをちらちら見ている。その顔からは、何か陰謀をたくらんでいることがはっきり見てとれた。(89頁)
このように語り手が家族の他のメンバーから疎外されていると感じる場面は、前半を中心にしていくつか見られるのだが、大げさにいえば世界との不調和を感じるこうした心性はロマン主義的な価値観の萌芽と見做すこともできる。もちろんこうした心理はこれ以上探求されることはないが、目の前に迫る18世紀末という時代の気配を、こうした箇所に感じ取ることができる。
この観点からすると、バーチェル氏(サー・ウィリアム・ソーンヒル)とジェンキンソンという二人の脇役がおもしろい。彼らがこの小説においては珍しく、人間的深みを感じさせるような台詞を口にする人物だからである。この二人に共通するのは両者とも世間に身分を偽って生きていた経験を持つことであり、その意味では彼らこそ登場人物中もっとも世界との隔絶を感じている人間だ。18世紀的変装から、19世紀的な世界との葛藤へ。やがて主人公の資格を得ることになる人物が、『ウェイクフィールド』ではおどけながら脇役としてふるまっている。
関連記事:イギリス文学のおすすめ紹介