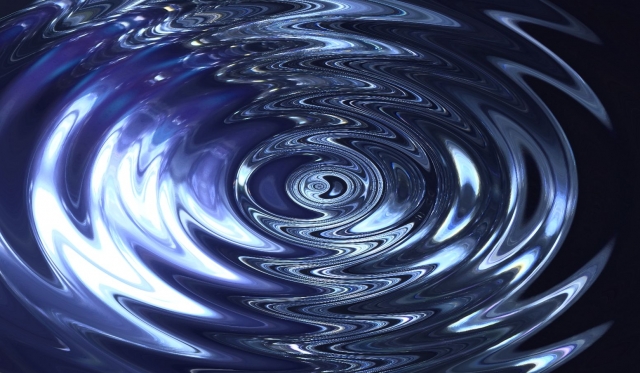ヒュームの因果論 前編:帰納法の問題
ヒューム哲学ほど、研究してみると通俗的な紹介とのギャップを感じる哲学はない、と思う。というのも、書店に並んでいる哲学入門的な本の多くは、ヒュームを紹介していても、その懐疑論の帰結部分だけを紹介するか、もっと言えば本来ヒュームの論じていない懐疑論を紹介しているためだ。例えば、ヒュームは因果性の存在を否定したであるとか、自我は知覚の束に過ぎない、などのようなフレーズを聞いたことがあるかもしれない。そうしたフレーズから、しばしばヒュームは法外な懐疑主義者として語られてきたのである。
確かに、ヒュームを法外な懐疑主義者として位置づけることは、近世哲学における経験主義の論理的帰結としての破綻と、カントや近代哲学への転換点として哲学史を物語る上では好都合であるかもしれない。しかし、今日的なヒューム研究の視点からすると、そうした見方はヒューム哲学を歪めてしまうだけである。そのため、まずヒュームがこれまでにどう解釈されてきたのかを述べた後に、今日的なヒューム研究の視点からその因果論を紹介した上で、私の感想を述べていきたい。そうしなければ、書店に並ぶ哲学の入門書でヒュームを勉強したことのある人ほど、私が何か感想を述べても困惑してしまうであろう。
上述した中で、とりわけヒューム哲学を歪めて広める要因になってしまったのが、「帰納法の問題」と呼ばれる懐疑論であろう。これはヒュームの因果論が紹介される際には必ずといっていいほど語られる懐疑論である。確かに、帰納法の問題自体もまた議論の尽きない面白いテーマではあるだろう。しかしながら、今日のヒューム研究からすると、この問題はヒュームが論じたかった問題ではない。そもそも、今日のヒューム研究者の間では『人間本性論』で帰納法の問題が論じられていると考えられてきた箇所は、懐疑論とさえ考えられていないのである。そこで今回は、ヒュームに対する誤解の解消に向けて、この帰納法の問題について紹介することに努めよう。
さて、帰納法の問題とは、帰納法が前提とする「自然の斉一性」が、論理的な証明によっても、蓋然的論証(帰納的推論)によっても、正当な根拠を持たないことを示すことで、経験的知識に関する推論一般の非合理性を暴くという懐疑論である。ここで、自然の斉一性という言葉は、聞き馴染みのない人もいるかもしれないため、説明しておこう。自然の斉一性とは、簡単に言ってしまうと、これまで自然に見出されてきた規則性は、条件が変わらなければ、これからも一様であり続けるという原理のことである。例として、ヒュームによる自然の斉一性の定義を紹介しておこう。
“経験されたことのない事例は経験されたことのある事例に類似していなくてはならず、自然の過程はつねに斉一的に同じであり続ける、という原理”
(Treatise.p.62)
この原理に基づく推論の具体例をあげれば、次のようになる。これまで私は、手に持っているマグカップを離せば、下に落ちるということを経験してきた。それ故に、明日や明後日、あるいは別の場所でもいいが、同じ条件のもとマグカップから手を離してみれば、同じように下に落ちるだろう、というものだ。もし、この原理を否定するのであれば、明日同じ条件でマグカップから手を離せば、マグカップが浮くだろうだとかマグカップがどこかへ消えるだろうだとか、無数の可能性を、それもどの可能性も同じようにあり得ることとして考えなければならなくなる。
ファンタジーやSFといった想像力の世界について考えるならば話は別だが(この想像力の世界での思考可能性が重要でもあるのだが)、日常生活における事実の範囲に限定するならば、この原理から逸脱した推論を大真面目にしている人は、狂人か、もしくはまだ世界について経験をしたことのないタブラ・ラサ的状態の人として扱われてしまうだろう。
また、自然科学も、基本的にこの原理を前提としていると言って差し支えないように思う。自然科学の手法における「再現性」について考えてみてほしい。自然の中に見いだせる規則(たとえそれが確率的な事象であったとしても、それは確率的な規則性を持っている)が、時間・空間的に一様でないならば、再現性の有無を確認することには何の意味もなくなってしまうだろう。昨日出来たことが、今日再現できなくても、それは当然のことだ。なぜなら、昨日と今日とでは自然法則が違うからだ、と言われたら困惑するしかない。
このように、自然の斉一性は私達の素朴な生活にせよ、知性的に考えるときにせよ、常に意識的であれ無意識的であれ、前提としている原理であると言える。しかし、この原理を前提とすることには理性的な根拠が見出だせない、というのが懐疑論の主張だ。
このことは極めて単純な論理によって示すことができる。自然の斉一性が理性的に正当化されるためには、それが論理的な証明か、蓋然的な論証(帰納的推論)によらなければならないだろう。まず、論理的な証明はどうか。自然の斉一性は、その否定が矛盾を含むわけではない。これまでは、マグカップから手を離すと地面に落ちてきたが、明日同じことをしたら浮くだろう、という命題は、事実を思考する私達にとっては違和感こそあれど、論理的な矛盾は含まない。つまり、自然の斉一性の原理は論理的に真なる命題ではなく、必然的でない。次に、帰納的推論による証明はどうか。この場合、証明しようとしている命題を前提として推論することになるため、循環論法に陥る。つまり、帰納的推論によって論証しようとするならば、これまで自然の規則性は一様だったから、これからも自然の規則性は一様であり続けるだろうと推論しなければならないが、この推論は自然の斉一性を前提にしているわけである。従って、自然の斉一性は論理的にも蓋然的にも論証出来ず、従って理性的な根拠がないということが帰結する。
以上が、帰納法の問題の論理である。通俗的なヒューム紹介においては、このようにヒュームは経験的知識に関する推論は、全て理性的な基礎を持たないことを示したとされる。そして、帰納法または因果推論は単なる想像力の「習慣」に過ぎないとし、人間知性の非合理性を暴いたであるとか、経験主義を突き詰めた結果、法外な懐疑に陥ったであるとか語られてきた。この帰納法の問題は、とりわけ20世紀初頭の英米系哲学の実証主義者達の間で盛んに取り上げられ、その解決や解消が試みられていた。そして、実証主義者らの問題設定を、ヒューム哲学の内に読み込むことで作り上げられた懐疑論が巷に広まったのである。実証主義者らのヒューム解釈や批判が気になる人は、バートランド・ラッセルの『西洋哲学史』のヒュームの項や『哲学入門』、カール・ポパーの『推測と反駁』などどれでもいいが、実証主義の潮流に数え入れられる哲学者の著作を読んでみることを勧める。英米系の哲学者でヒュームの影響を受けていない人はいないと言っても過言ではない。
さて、最後にもう一つ付け加えておくことがある。今回の記事のタイトルがヒュームの「因果論」となっているのにも関わらず、因果性というワードが出てこないじゃないかと思っている読者もいることだろう。もしくは、因果性の概念を受け入れるなら、そもそも帰納法の問題など考える必要がないとも思われるかもしれない。確かにそうである。帰納法の問題を紹介するためにとばしてしまったのだが、そもそも因果性の概念に問題がなければ、このような懐疑論は出てこないはずである。なぜならば、ある原因が存在すれば、「必ず」その結果が生じるだとか、逆に、ある結果が存在するのであれば、「必ず」その原因が存在するというように、原因と結果の関係に「必然性」があれば、私達は推論するまでもなく、世界が因果の連鎖に貫かれていることを前提と出来るであろうからである。
しかし、ヒューム自身、経験主義の原理に基づいて因果性を分析することで、その定義に含まれていると考えられる「必然性」が、見出だせないことを述べている。今回、ヒュームの議論の前後を入れ替えてしまったが、ヒュームの論述の順序に従えば、この因果性の必然性に関する議論があって、その後、その必然性が見出せないがゆえに、わざわざ帰納法の問題と考えられてきた先程の議論へと迂回することで因果性に関する考察を深めていくという道筋になっている。繰り返しになるが、因果関係の「必然性」、もしくはヒュームの言葉で言い換えれば「必然的結合」を巡る議論や、先程紹介した帰納法の問題とされる議論において、しばしばヒュームは因果性の存在を否定したと語られてきた。しかし、ヒュームの本来の因果論は、そういう懐疑論ではない。では、ヒュームは因果論において、何を語っていたのだろうか。
今回の記事はここまでにしよう。今回は、実証主義的な問題設定の枠組み内で再構成されたとも言えるヒュームの因果論の一端を紹介した。話の本題に入る前の導入的な感じになってしまったので、物足りない人もいるかもしれないが、覚えておいてほしいことは、帰納法の問題が、経験的知識に関する推論の正当性を問う「根拠問題」だという点である。ヒュームの因果論は、同じことを語っていても、その問題意識が、合理的根拠を問うような知識の正当化には向けられていない。その問題設定の違いを理解して読むと、ヒュームの因果論は全く別の様相を呈するのだ。次回は、ヒューム自身の因果論が今日どのように考えられているのか、つまり帰納法の問題と呼ばれてきた箇所がどのような性質の議論で、因果論がその後どのような考察へと深められていくのかを論じていく予定である。
参考文献
・Hume.D, A Treatise of Human Nature(1739-40), edited by David Fate Norton and Mary J.Norton(New York: Oxford university press, 2000)