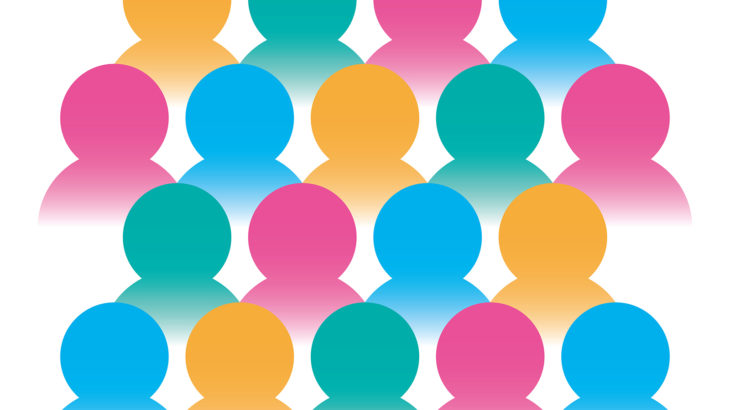世人(ダス・マン)の意味
世人は『存在と時間』に登場するハイデガーの哲学用語。das Man というドイツ語の訳である。世人と訳すのはどちらかというと珍しく、「ひと」と訳す方が多い。そのままドイツ語読みで「ダス・マン」と言ってしまうこともある。
ドイツ語の man は非人称主語と呼ばれ、漠然と世間の人のことを指す。それに冠詞(das)をつけて大文字にしたのが das Man である。没個性的な人の状態を指す言葉であり、日常の不特定多数のひとりとして生きている現存在のことである。これはハイデガーからすれば現存在の非本来的な在り方に分類される在り方であり、そこから逆に本来的な在り方がどういうものかが考察されることになる。
*『存在と時間』の解説はこちら→『存在と時間』解説・入門
著作読解
『存在と時間』における世人
日常において現存在であるのは誰なのか
『存在と時間』169頁(SZ. 114)
私たちは普段どう暮らしているだろうか。ハイデガーの場合、その問いは現存在は普段どう暮らしているのだろうかと言い換えられる。朝起きて、散歩したり、人と話ししたり、働いたり、寝たりしている。これが普段の私たちの在り方であり、日常的な在り方である。そのうち、人と共に暮らしているという点を日常性において協調する。私たちは一人で生きているわけではないのだ。その存在をハイデガーは共同存在(Mitsein)あるいは共同現存在(Mitdasein)と呼ぶ。
そして他の人と暮らしていく様を分析することで日常性というものが垣間見えるようになる。では普段人と共に暮らしている時に、現存在はどのような生き方をしているのか。
日常的な自己存在の様態は、この共同現存在という在り方に根差しており、この様態を解明すれば、私たちが日常性の「主体」と呼ぶもの、すなわち「ひと〔das Man〕」というものが見えてくる。
同書、同頁(SZ. 114)
そう、現存在は「世人」という生き方をしている。つまり「日常において現存在である」のは世人なのだ。それでは世人というのはどのような生き方なのか。
*高田珠樹訳『存在と時間』ではdas Man は「ひと」と訳されており、筆者もそちらの方が良い訳に思われるので、引用に関してはあえて訳を変えていない。なので「ひと」= 世人 と解釈してもらって大丈夫である。
世人の特徴
ハイデガーは世人の特徴をいくつか記述している。それをいくつか見ていこう。
まず世人というのは、他の現存在との間に埋没している在り方であるという。つまり現存在が世人である時、それは他の現存在と区別がつかない。みんながみんな世人という同じ在り方をしているからである。そのことをハイデガーは次のように表現している。
日常的な現存在が「誰なのか」と言えば、それは特定の誰かではなく、またそのひと自身でもなく、何人かの人たちとか、すべてのひとの総計というものでもない。その「誰なのか」は、特になんという特徴のない中性名詞としての「ひと」である。
同書、188頁(SZ. 126)
「特になんという特徴のない」というのがポイントである。例えば人間には個性というものがある。スポーツができる、勉強ができる、絵が得意、虫が苦手等々。しかし世人にはそういった特徴はない、つまりありていに言えば没個性的だということである。世人には個性がない。言い換えれば、それは人並み、平均的、平坦であるということである。どこまで行っても世人は他の人と同じなのだ。
以上私たちは、距離を測りがちであること、人並みであろうとする平均性、平坦化、公共性、存在の負担の軽減、迎合といった日常的に互いのあいだに在ることの存在性格の諸相を取り出してきた。
同書、190頁(SZ. 128)
距離を測りがちであること、存在の負担の軽減、迎合に関しては『存在と時間』本文を読んでもらうことにしたい。平均性(Durchschnittlichkeit)、平坦化(Einebnung)、公共性(Öffentlichkeit)、とにかく全てが抜きん出ていない。テストで例えるならば、全ての科目のテストが平均点だということであり、どの科目も得意でも不得意でもない。これが世人なのである。
このあとさらに付け加えて面白いことをいう。このような世人としての自己を本来的な自己と区別するというのである。この本来的というのは、『存在と時間』では非本来的の対義語で、つまり世人は非本来的な自己だということである。ここで非本来的ということは自己自身に向き直っていないということになる。この自己自身というのは実存している自己自身、つまりある意味では個性を持っている自己自身のことであり、ということは自己自身に向き直っていないということは、そういった個性的な部分に目を向けていないということである。なぜ目を向けないかというと、そういった部分に目を向けることは不安であり、ハイデガーによれば目を背けたい部分なのである。それではどのようにして目を背けるのか。
世人の開示性:おしゃべり、好奇心、曖昧さ
自分自身に目を向けないためにはどうすれば良いのか。目を瞑るのではなく、別のところに目を向ければ良いのである。それでは現存在は世人の時どこに目を向けているのか。それは世界である。その世界に目を向けることを世人の開示性というが、それはそうすることによって世界が開示されるからである。
さて、その開示の仕方には大きく分けて三つある、おしゃべりと好奇心と曖昧さである。それぞれ見ていこう。
おしゃべり
おしゃべり(Gerede)とはその名の通り、人とお話しすることを意味するが、ハイデガーは狭義的に世人における語り様態として使用している。「巷談」と訳される場合もある。おしゃべりする場合、それは語る内容を相手に伝えることが前提とされており、そのうちではおしゃべりする他者が暗黙のうちに前提とされている。つまり、他者が開示されているわけである。
注目すべきなのは、そこには日常的な現存在(世人)の存在様態である平均性が備わっているということである。というのもいわゆる共通理解のようなものがないと、他者に伝達事項が通じないからである。語りが平均的な傾向を帯びれば帯びるほど、それは「おしゃべり」となる。
おしゃべりの場合、伝達ということで人に伝える事柄があるにせよ、そのこと自体はすでに相手は知ってしまっている。というのも共通理解の上を動いているからである。ある意味で「おしゃべり」の場合、誰かと話しているようで話していない。それは現存在Aと現存在Bとの会話ではなくて、世人と世人との会話なのである。
ということで、これは何かを開示する作用であると同時に閉ざす作用でもある。
巷談とは、語りが取り上げるものの地盤に立ち返るのを怠るという、そのそもそもの特性からして、ひとつの閉ざす作用なのである。
同書、253頁(SZ. 169)
実はおしゃべりとは、究極的には存在論的に自分に関心を向けないようにしているということなのである。
好奇心
人は何かに好奇心(Neugier)がある。例えば学問、運動、虫とか雲とか何でも。好奇心の向かう先を私たちは日常的に「見よう」とする(ハイデガー的には、この「見る」の様態は存在論的様態であり、物理的な視覚以上の意味が込められている)。しかし日常性における好奇心は少し特殊だ。ハイデガーによれば存在論的な好奇心は、その興味の対象を理解するために向けられるものではないという。
自由になった好奇心がいろいろ見ようと配慮するのは、自分の見たものを理解するため、つまり、それとなんらかのかたちで関わりあう在り方に立ち至るためではなく、ただひたすら見るためである。
同書、257頁(SZ. 172)
その目的は何だろうか。それはおしゃべりとほとんど同じである。ただひたすら好奇心のある対象を「見る」のは、気晴らしや気散じのため、自らに目を向け返さないためである。この好奇心には、ハイデガーは「絶えず自分の根を失うという日常的な現存在の新たな在りようが露呈している」(258頁)という。好奇心も世人の在り方なのである。
曖昧さ
第三の現象が曖昧さ(Zweideutigkeit)である。どういうことかというと、未来の事柄、これからやらなくてはいけないこと、やってなければいけないこと、やるはずのことを曖昧なままにしておくということである。それとなく感じているが決定的なことは行わない。そういった曖昧さがあればこそ、そこに好奇心が生まれるし、それが語る内容、つまり「おしゃべり」の内容にもなるとハイデガーはいう。曖昧なままにしておくこと世人の日常的なありようなのである。
世人の根本的なありよう:頽落
さて先ほどの三つおしゃべり、好奇心、曖昧さという日常性的な現存在の在り方を考えてみると、そこに共通点のようなものが見出せる。それが「頽落(Verfallen)」というあり方である。
これはハイデガーが何度も述べていることだが、頽落ということで現存在の日常的な在り方にケチをつけたり、否定的な評価を下しているのではない。この在り方が世人の在り方だ、というだけの話である。それでは頽落とは具体的にどのような在り方なのか。
この名称は何か否定的な評価を表現しているのではなく、現存在がさしあたってたいていは、自分が配慮する「世界」のもとに在ってそれにかかずらっているのを言い表そうとするものである。
同書、262頁(SZ. 175)
この「世界」のもとにかかずりあっている在り方が最終的に非本来的なあり方とされる。「世界」ではなく「自己」の方に目を向けなければ存在論的に真理には辿り着けない。そこで本来性へと至るために、自らに目を向けて、不安の中で死へと向かう存在であること意識しながら良心の声を聞き決断することが必要となるのである。
参考文献
マルティン・ハイデガー『存在と時間』高田珠樹訳、作品社、2013年。