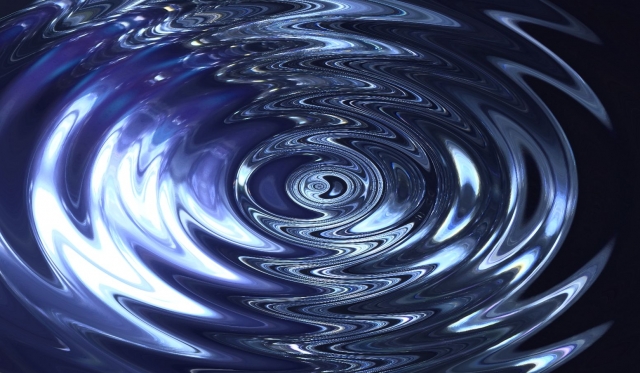いざ、懐疑の底なし沼に沈みゆかん
私は3年ほど前まで大学院でヒュームについて研究していた。今回は、なぜ自分がヒュームを研究していたのかという思い出話を通じて、『人間本性論』の感想を書いてみたい。
「何がしたいんだろう…?」
ヒュームの『人間本性論』の第一部「知性について」を学部生の頃に初めて読んだ時の感想だ。私は困惑しかなかった。議論の理屈は分かる。しかし、結局何が言いたいのかさっぱり分からない。それがヒュームとの初対面だった。当時、私はプラトンや近世哲学を勉強し、そしてカントの『純粋理性批判』を読み終えた後に、初めてヒュームに触れたため、とにかく哲学に対して荘厳な建築物のような体系的思想を期待していた。しかし、ヒュームは一見すると、その真逆を行く。経験論的な知識論を展開したかと思えば、懐疑、懐疑、懐疑に続く懐疑…。とにかく近世哲学がその拠り所にしてきた知の基礎を破壊しまくるのである。そのあとに一体何が残るのだろうか?デカルトは方法的に懐疑はすれど、神の観念を梃子に「cogito,ergo sum」を引き出し、理性的な世界を回復したが、ヒュームにおいてはそうはいかない。ヒュームの懐疑はひとたびはまるとまるで底なし沼にはまったように抜け出せないまま、そのまま先へと進まねばならないタイプの懐疑なのである。それゆえに、出版当初から百年くらい経っても、ヒュームは単に法外な懐疑主義者とさえ考えられていた程である。まぁ、今となっては古い研究ではあるが、20世紀初頭にノーマン・ケンプスミスという研究者によって、単なる法外な懐疑主義者という見方がヒュームに対する不当な評価だと退けられ、新たな展開を見せるのではあるが…。なにはともあれ、まだ研究書など読んだことのなかった私には、懐疑の理屈は分かるけれども、そこから何を引き出したいのか、はたまた懐疑するだけで読者を煙に巻き、困惑する姿を傍から見てほくそ笑んでいるだけなのか分からなかった。面白いのは、ヒューム自身、『人間本性論』第一部「知性について」の終わりで、知性に対する絶望的な心境を語っているところだ。ここでその一節を見てみよう。ヒュームは知性について論じ終え、その結論部の冒頭で、これまでの知性論を土台に探求の場を広げていこうという時に、以前の議論を振り返って、次のように語っている。
「思うに、私は、小さな入江を通り抜けるのに、多くの障害物にぶつかり、かろうじて難破するのを免れてきながら、まだ向こう見ずにも同じ漏れ穴のある風雨に晒されたボロ船で海へと漕ぎ出そうとし、それにも関わらず、それらの不利な状況下で、ついには地球を周航しようと考えるに至るほどに野心を抱きさえする、そうした人のようなものだ。私の過去の誤りと困惑は、未来に対する私の自信を無くさせる。私の探求において使用しなければならない諸能力の窮状、弱さ、混乱は、私の懸念を増やす。それらの能力を修正し、正すことが不可能であることは、私をほとんど絶望させる。そして、思い切って広大に広がっている果てしない海へと乗り出すよりも、いっそのこと今いる不毛な岩の上で死んでしまおうかと決心させる。この突然の自分の危機的光景が、私を憂鬱にさせるのだ。そして、この情念が、他のどの感情よりも、それ自身に耽溺することはよくあることであるので、私は、今の主題が私にあのように豊富に供する落胆させるあらゆる反省と共に、私の絶望が肥え太ることを抑えることが出来ない。」
“A Treatise of Human Nature” (p.172)
『人間本性論』の邦訳が手元に無かったため、3、4年ぶりに原文を翻訳してみた。訳のぎこちなさについてはご容赦願いたいが、間違いがあれば指摘して頂きたい。さて、それはともかくとして、私はこの知性に対する絶望感をどうしたものかというモヤモヤ感から、ヒューム研究へと駆り立てられたのであった。以上が、私のしがないヒュームとの出会いの思い出である。この思い出は、何やら知性に対してただただ悲観的な雰囲気を持つヒューム像を抱かせるであろう。もちろん、それは当時の私の無知ゆえであることは付言しておきたい。ヒュームは懐疑を理性によっては解決しないが、屈するわけでも、無碍にするわけでもない。ヒュームは懐疑の沼にはまった後に脱出しようとしないのである。そうではなく、あえて沈むがままに任せ、放置する。つまり、懐疑によって知性の場を更地にした後に、「自然に任せる」のだ。自然に任せてみると何が起こるのか、これこそが「Human Nature」を探求するときの肝なのだ。強いて言うなれば、理性によっては回復できないところまで懐疑を深め、それから自然に身を任せてみるのがヒュームの方法と言ってもいいのではないだろうか。自然に任せてみたらどうなるのだろう?懐疑の沼に沈んだ先に「底」はあるのだろうか?あるとしたら、それは人間の知性を支えるに足るものなのだろうか?その答えは、読者の解釈に委ねられている。
さて、今回、ただの思い出をつらつらと気取った感じで書いてみた。しかし、思い出をこれ以上語るのは蛇足になると思うのでここでやめよう。私にとってヒュームは最初「謎」だったという感想を言いたかっただけなのだ。今度はしっかりとヒュームの書物に対する直接的な感想を投稿してみたい。
参考文献
Hume.D, A Treatise of Human Nature(1739-40), edited by David Fate Norton and Mary J.Norton(New York: Oxford university press, 2000)
おすすめ記事
・「意味がない無意味––あるいは自明性の過剰」箇条書き的読解(千葉雅也『意味がない無意味』)
・不気味なものとは何か – フロイト
・『声と現象』における時間論について
・第三者の審級とは何か – 大澤真幸