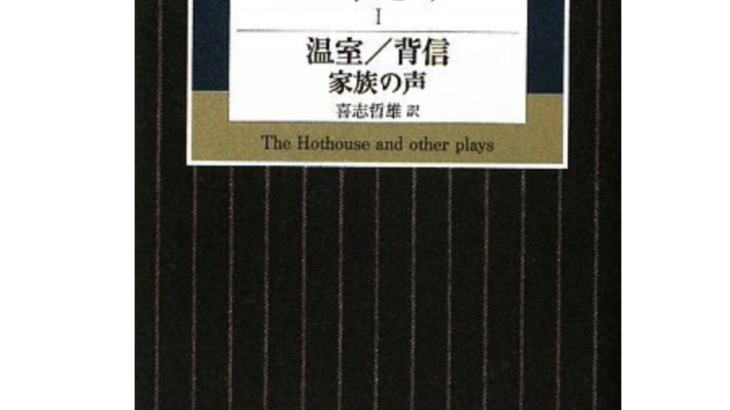概要
ハロルド・ピンター(Harold Pinter, 1930-2008)は、20世紀イギリスを代表する劇作家。ノーベル文学賞受賞。『背信』(Betrayal, 1978)はピンターの代表作のひとつ。本作が描き出す七年間にわたる情事は、作家の1962年から1969年にわたる実際の経験をもとにしているとされる。
中心にいるのはエマ、ロバート、ジェリーという三人の人物だが、舞台には登場しないケイシーという人物とエマの不倫関係が匂わされたり、ロバートも過去に不倫を繰り返している様子だったりと、作品のタイトル『背信』はさまざまな意味合いをふくんでいる。
海外文学はほかにヘッセ『少年の日の思い出』、カズオ・イシグロ『日の名残り』、キャロル『不思議の国のアリス』、サン=テグジュペリ『星の王子さま』、フロベール『ボヴァリー夫人』、ポー『黒猫』『モルグ街の殺人』『ウィリアム・ウィルソン』、サルトル『嘔吐』、チャペック『白い病』、カルヴィーノ『木のぼり男爵』『パロマー』、プリーストリー『夜の来訪者』、ボルヘス『隠れた奇跡』などがある。
>>関連記事:イギリス文学のおすすめ有名小説
\30日間無料!解約も簡単!/
→Kindle Unlimitedのサービス内容とメリット・デメリット
登場人物
エマ(Emma) ロバートの妻
ジェリー(Jerry) ロバートの親友でありエマの不倫相手。ジュディスという名の妻がいる。
ロバート(Robert) エマの夫
給仕
あらすじ
1968年から1977年の間に起こった出来事が、時系列を反転させて演じられる。以下は時系列順。
エマは1968年にジェリーと出会い、以後5年間、互いの配偶者に知られることなく不倫関係を結ぶ。1973年、ジェリーがエマに宛てた恋文をロバートが発見したことをきっかけに、「背信」が発覚。しかしロバートはその後もジェリーと友人関係を続ける。1975年、ジェリーとエマは別れる。
1977年、ジェリーとエマは二年ぶりに再会し、エマは現在ケイシーという別の男と不倫をしていること、ロバートもまた多くの女性と不倫をしていたこと、そして、かつてのジェリーとの関係をロバートに明かしたことを伝える。その日ジェリーはロバートと会い、このことについて話す。ロバートは妻と友人の「背信」を四年前から知っていたことを告げる。
\30日間無料!解約も簡単!/
→Audible(オーディブル)とは?サービス内容・料金・注意点
解説・考察
逆行する時間
本作の形式上の特徴は、何といっても時間の逆行である。エマが元不倫相手のジェリーと約二年ぶりの再会を果たした1977年の春から作品はスタートし、一部の例外を除いて場ごとに時間を遡りながら、最終的には1968年、エマとジェリーとの不倫が始まる地点にまで行きつく。
こうした構成は、作品にどのような効果を生んでいるのか。通常の物語では、出来事は「旧」から「新」へ、原因から結果へという流れをたどる。しかし『背信』では逆に、結果=「新」がまず提示され、それがどのような原因や経緯をもつのか、それがどのような意味合いをもつのかということが、次第に明らかになっていく。
例えば、ジェリーがエマのまだ「ひどく軽かった」娘シャーロットを、「君[=エマ]の亭主、僕の女房、子供たちもみんな」がいるなかで、「君[=エマ]の家の台所」にて「抱き上げて、ほうり上げては受けとめた」ことが、第一場で回想される(183-84頁)。これと同じ場面が第六場(1973年夏)で繰り返されるのだが、第一場と同じ状況が演じられたあとに、「あなたがあの子をほうり上げても構わないじゃない?」というエマの台詞が付け加わる(263頁)。読者はその直前までの回想を既視感をもって読むだけにこの一行に新鮮な驚きを覚えながら、第一幕の(観客の経験からすれば過去、時系列的には未来の)場面の印象を書き換えることになる。ジェリーがシャーロットを「ほうり上げる」エピソードは二人にとって、愛情がまだ現実だったころの幸せな夢想をふくんだものだったのだ。
出会いで終わる——期待の不可能性について
ジェリーとエマの関係のスタートに行きつく最終九幕の終わり方は印象的である。ロバート、エマ、ジェリーの三人の場面で、ジェリーが部屋から出て行くと、ジェリーはエマの「腕をつか」み、「彼女は立停」り、「二人は見つめ合いながら、じっと立っている」(299-300頁)。あらたなロマンチックな関係への期待にみちた場面でありながら、この先にページは続かず、読者も役者もこののちの二人に思うような未来はないことを知っている。二人が「見つめ合」うその視線の先にあるのは、舞台の時間からいっても物語内の時間からいっても空白だけである。
このアイロニカルな哀愁をもって舞台は幕を閉じるのだが、ピンター作品特有の「沈黙」、「間」には、根本的なところでこのエンディングの雰囲気と共通するところがある。
二十世紀演劇は、待望されるゴドーがついに舞台に現れないという空虚によって幕を開けたが、ピンターにいたってその空虚はもはや「待望」という時間性が成立しないところまで進んでいる。ただたんに欲しいものが手に入らない、欲しいものが存在しないかもしれないというのではなく、すべてが(しかも喪失が)先取られ「欲しい」という欲望すら自分のものにならないという空虚が、新たな関係への期待に満ちあふれた『背信』の二人の頭上にぽっかりと口を開けている。